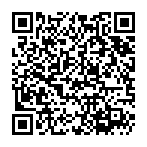破和合僧
2023年8月22日(未掲載)
五老僧は破和合僧
<正師に違背した五老僧>
さて、大聖人御入滅(一二八二年)から大石寺開創(一二九〇年)に至る八年間の日興上人の御振る舞いを拝するとき、それは大聖人の正法を「断絶」せんとする内外の魔軍との、まさに生命を賭されての戦いの御姿であられた。ここで、その一端を拝しておきたい。
大聖人は御入滅を前に、日興上人に唯授一人の付嘱をされ、その証として「二箇相承」を認したためられている。
すなわち、まず「日蓮一期弘法付嘱書」(弘安五年九月)において、大聖人が御一代に弘法なされた法体、つまり三大秘法の一切を、日興上人に相承されたことを示されている。
そして「身延山付嘱書」(弘安五年十月十三日)において、身延山久遠寺の別当職を譲られた。
大聖人は、この「二箇相承」で、それぞれ「就中我が門弟等此の状を守るべきなり」、「背く在家出家どもの輩は非法の衆たるべきなり」と仰せになっている。
「非法の衆」とは、仏法にはずれた者で、大聖人の門下ではない、との意であり、唯授一人血脈付法の日興上人を中心として、滅後の法戦にあたっていくことは、門下一同に対する大聖人の絶対の御遺誡であられた。
いうまでもなく、日昭、日朗、日向、日頂、日持の五老僧とて、この大聖人の厳命の例外ではない。いな、誰よりも、日興上人を守り、支えていくべき立場にあった。
ところで「五老僧」の立場を、現代の私達に分かりやすくいえば「方面長」とでもいえる存在であろうか。
すなわち
日昭は相模(神奈川)の鎌倉、
日朗は鎌倉と武蔵(東京)の池上、
日向は上総(千葉)の藻原、
日頂は下総(千葉)の真間、
日持は駿河(静岡)の松野
の各地を中心に担当し、弘教にあたっていた。
この五人の方面責任者が、
日興上人を中心に心を合わせ、
団結していったならば、
早くから他の既成宗教をしのぐ
正宗の発展がなされたかもしれない。
大聖人は、御遺言の中に「六人香華当番」と仰せである。すなわち六老僧が、大聖人の御墓所を当番制で交代に守護していくべきことを示されていた。
ここからも、各地に散りゆく五老僧が、大聖人の墓所の設けられる身延を定期的に訪れては、日興上人を中心に、互いに連携を取りながら「異体同心」で進んでいくようにとの、大聖人の深き御心が拝される。
こうして、大聖人の御心を体して、皆の合意をもって、六老僧を中心に主な門下十八人が、交代で御墓所を守っていく「墓所輪番制」が定められたが、五老僧はこれを守ろうとはしなかった。五老僧は、あれこれと理由をつけては、身延の大聖人の墓所をお守りしようともせず、日興上人のもとを訪れようとしなくなった。
なかでも日昭と日朗は、
身延での大聖人の第百箇日忌法要が終了して下山する際、
墓所の傍かたわらに安置されていた「註法華経」を日昭が、
「釈尊の一体像」を日朗が、
それぞれ奪い去っていった。
そして、当然、彼らは身延に二度と来ることはなかった。
この「註法華経」と「一体像」は、どちらも大聖人が御生前に、随身されていたもので、日昭と日朗は、この遺品を自分達の権威づけに利用しようとした。彼らは、その所持をもって、自らを大聖人の正統とさえ称したのである。しかし、もとより大聖人の法門の本質から、見る人が見ればまことに滑稽な二人の姿であった。
ともあれ、日昭も日朗も、入門順からいえば日興上人の先輩格にあたる。年齢も、日昭が二十五歳、日朗が一歳、日興上人より年長となる。しかも、大聖人とゆかりの深い鎌倉、池上方面の草創からの中心者である。″自分のほうが格が上だ。日興上人につく必要はない″と、日興上人を軽んじ、見下そうとする心の動きは容易に想像できる。
それが世間的次元のことであれば、自身の感情のままに行動することも、当人の自由であるかもしれない。
しかし、
ことは仏法上の根本問題である。
自らの増上慢の心に流され、
正法から離れてしまえば、
最も決定的な悪となる。
そして、
最も戒めるべき破和合僧へと通じてしまう。
しかも、
指導的立場にある中心者の狂いは、
その人についている多くの人々をも迷わせてしまう。
これ以上の不幸はない。
たとえ、
本人に罪はなくとも、
信心の濁った中心者につけば、
その人たちの信心も濁流に染まっていってしまう。
それほど仏法は厳しく、
信心は厳格に見なくてはならない。
ゆえに、日昭、日朗ら五老僧についた信徒には、
信心の厳しき目からみれば、功徳はない。
第六天の魔王の眷属となった者は、
絶対に成仏はできないのである。
退転、反逆の者の本質は結局は、
いやしく、醜い自分の心が魔の働きにからめとられ、
悪の道へと引っ張られていったにすぎない。
そうした悪の心をはらんだ生命を、
どう正しい方向へもっていくか、
いかに正しき信心の軌道から外れないようにしていくか、
これが指導であり、
同志の厳しくも温かな励ましである。
ともあれ、
日昭も日朗も、自らの増上慢の心に、ついに勝てなかった。
彼らは、日興上人を妬み、
そして対抗への歩みをはじめる。
日昭も、日朗も、それぞれの方面で、
″我こそ大聖人の直弟子である″と、
傲おごり、たかぶっていた。
俗にいう「お山の大将」的存在になっていた――。
しかし彼らは大聖人の御遺誡に背いて、
後継の正師・日興上人から離れてしまった。
そこには、もはや大聖人の仏法の血脈は流れ通っていない。
五老僧は自分のエゴと慢心が中心となり、
正師を見失った。
″心を師とする″姿に堕ちたのである。
そうした本性は、
いかにとりつくろい、飾ろうとも、隠しおおせるものではない。
必ずや一生涯のうちに赤裸々に現れてしまう。
大聖人御入滅後三年の弘安八年(一二八五年)には、鎌倉を中心に幕府の迫害が起こった。幕府は大聖人一門の住坊(寺)を破壊すると脅迫してきた。この時、日昭と日朗はともに申状を当局に提出する。それは、自らを「天台沙門」すなわち″天台の弟子″と称し、さらに幕府のために祈祷いたしますと申し出る卑屈なものであった。
「天台の弟子」なら、当時、公認された権威がある。ゆえに迫害を避けるために、「大聖人の弟子」と名乗らなかった。憶病にも、厳格な折伏の正道を捨て去り、幕府の権力に迎合して難を免かれたのである。
これは日興上人が、後世のために「五人所破抄」や「富士一跡門徒存知の事」また「弟子分本尊目録」に、しるされている通り、厳然たる歴史の事実である。
また日昭、日朗だけでなく五老僧の全員が、同様の醜態を示した。たった一人、日興上人だけが、微動だにもなされなかった。厳として大聖人の正法正義を主張し通された。
多数決でいうなら、五対一で五老僧に分があるように見えるかもしれない。しかし仏法の上からは、師の心に生きる「一人」にこそ正義はあった。
戸田先生も、よく、こうした五老僧の姿を通して、信徒の立場から広布の未来への戒めを話してくださった。
「私がいる間はよい。
私がすべて守っている。
しかし、私の死んだ後、
権力でひどい迫害を加えられるかもしれない。
マスコミからも、社会からも、
様々な圧迫があるだろう。
その時、いったい何人の人が『私は学会員だ』と、
毅然として誇り高く言いきれるか。
『いや私は自分だけ信仰しているのです』とか
『広宣流布なんて考えておりません』とか
言い出さないとも限らない」と、
真剣な姿で語っておられたことが忘れられない。
その言葉通り、
これまでにも、何か起こるたびに、
動揺して去っていく人間がいた。
先日も″名の通った、立場のある人間ほど、
いざという時に弱い″というお話をしたが、
幹部や社会的有名人ほど、もろい場合が多い。
反対に、
名もなく貧しく、地位もない、
何もない庶民は、″さあ、何でもこい!″と
開き直って立ち向かえる利点がある。
また女性の方が、いざという時には、
ハラがすわっている場合が多いようだ。
五老僧は権力に迎合した。
我が身を守るために、強い者に迎合し、
癒着するのは離反者の常である。
その根底は「憶病」だからだ。
現代にも信念なく、
さまざまな権威や勢力と野合を繰り返し、
広布を阻もうとする輩もいる。
五老僧に通じる、
同じ方程式の心理と行動といってよい。
さて「天台沙門」と名乗った時、
日昭は六十五歳、日朗は四十一歳。
日昭は、この前年に、鎌倉に一寺を創建したばかりであった。
日昭には自分の寺が大事で大事でならなかった。
せっかく得た安住の寺と財産を失いたくなかった。
もはや
「法のために」
「広宣流布のために」また
「民衆のため、仏子のために」という心ではなかった。
ただ我が身かわいさの一心であった。
そこには難と戦いゆく崇高な精神など微塵もない。
民衆への慈悲もない。
保身と策略の心しかなかった。
ちなみに先日、四月の第三回本部幹部会の席上、「両人御中御書」(御書1101㌻)を拝して、お話しした。この御書には、年老いた日昭の住坊のことにまで、大聖人が最大に心をくだかれていた御様子が示されている。
そうした大聖人の御慈愛を受けながら、大聖人の正義を裏切った彼らの忘恩の姿は、無慙であり、あわれという以外にない。
そもそもいったい、
誰のおかげで、その住坊を持てたのか。
全部、大聖人の大恩で出来上がったものである。
そう受け止めるならば、
いわば大聖人からお預かりした住坊である。
したがって、
この大法ゆえに住坊を取り上げられるというならば、
喜んでそうするのが本来の正しき姿であるといってよい。
ともあれ、
大聖人の仏法は
「立正安国論に始まり、立正安国論に終わる」といわれる。
この立正安国の精神こそ、
大聖人門下としての根幹である。
その根本精神を彼らは捨て去った。
保身のために大恩ある師の正義を曲げた、
憶病にして卑怯な姿こそ、
日興上人に随順しなかった日昭らの本質であった。
こうした、彼らのわびしき末路を、
将来の広布の指導者である青年部の諸君は、
鋭く見極めねばならない。
弘安七年(一二八四年)十月、大聖人の三回忌の折にも、五老僧は誰一人として墓参にもこなかった。あまりにも不知恩の姿である。
理屈はいくらでもつくれる。しかし、現実の姿が雄弁に真実を語っている。いかなる理由をあげるにせよ、墓参にもこぬ姿を弁解することはできない。
このように、
離反者は、何より一人の「人間として」まともでない。
現代の″五老僧の眷属″ともいうべき退転者たちも、
まず人間として、ひんしゅくを買う行動が余りにも多かった。
また五老僧と同様に、
大事な時にこないで、
陰で正体不明のことをしている人間は
必ず後でおかしくなっている。
私をはじめ、(中略)多田総合婦人部長らは、いつもながらの、そういう人間たちのやり方を手にとるように分かっている。皆、何とか正道に戻してあげたいと思い、また守ってきた。その包容をよいことに、勝手なことを言っている姿は笑止というか、こっけいというか、本当にお話にならない。
この三回忌の直後、日興上人は上総(千葉県)の美作房日保という一人の門下に御手紙を書かれている。
その末尾には「当時こそ寒気の比ころにて候へば叶かなわず候とも、明年二月の末三月の間に、あたみ湯治の次でには如何が有るべく候らん」(編年体御書1730㌻)――今(旧暦十月)は寒い時期なので、こちら(身延)へはこられないかもしれませんが、明春の二月の末から三月の間には熱海の湯治かたがた、おこしになってはいかがでしょうか――と仰せになっておられる。
もとより日興上人は、正法を護持されゆくためには、それはそれは厳格であられた。と同時に、この御文からもうかがえるように、身延を訪れようとしない一人一人まで最大に包容され、こまやかにして温かい心配りをなされていた。
何とか正しい信心を全うさせてあげたい。
最高の人生の総仕上げをさせてあげたいとの
大慈悲の心であられたと拝される。
身延離山の背景に波木井実長の変節
日興上人は正応二年(一二八九年)春、ついに身延を離山される。その背景に、地頭・波木井実長の重大な違背・謗法があったことは、ご存じの通りである。
しかし日興上人は離山されたのちも、何とか実長を改心させたいとの御心から、戒めの御手紙まで送られる。だが、そうした日興上人の御慈愛に対して、実長は傲岸不遜の返事を突きつけてきた。
信心が狂ってしまえば、もはや手のつけようがない。列車や飛行機が、動いている途中で故障してしまうようなものだ。暴走や墜落を止めることは困難である。
また多くの乗員が、それに巻き込まれてしまうように、
背信は本人ばかりか、
一族、子孫末代までも苦しめてしまう。
大聖人が仰せのごとく、
信心は「信順」を第一義としなければならない。
実長が日興上人にあてた師敵対の手紙。
彼の忘恩の心根を万代にまで証言する、
この書簡が現代にまで伝えられている。
その一部を紹介したい。
すなわち「かねてより怨まいらする仔細の候あいだ間仰に従ひて、さ然うけ給はりぬと申す御事恐れ入り候」――かねてから、あなた(日興上人)に対して恨んでいる事柄があるから、あなたの言われる通りにしたがい、承服することができないことは、痛みいります――と。
実長は何かについて、日興上人を逆うらみする感情をもっていた。
また「実に仏道成候時は、障碍の候なれども、此は障碍には成るべからず候」――まことに成仏を遂ようとする時は、様々な障害がありますが、(あなたが私に注意している)このことは、別に成仏の障害にはならない――。
つまり″よけいな心配は無用である″との言葉である。
「日円は故聖人の御弟子にて候なり申せば老僧たち達も同じ同胞にてこそ渡らせ給ひ候に、無道に師匠の御墓を棄てまいらせて咎な無き日円を御不審候はんは何で仏意にも相叶はせ給ひ候べき」――日円(実長)は、故・大聖人の弟子である。だから、いうならば、あなた方、老僧方とも同じ兄弟弟子であります。それなのに、道理もなく、(あなた方が)師匠である大聖人の墓を捨てたうえ、罪のない私を責め、謗法よばわりすることが、どうして仏意にかなうでしょうか――。
彼は、自分の謗法をタナに上げたばかりか、それが要因となった日興上人の身延離山をも、大聖人の墓を捨てたと逆に非難している。
「師匠の御愍を被り候し事恐らくは劣りまいらせず候、前後の差別計こそ候へ」――大聖人の慈愛を受けたことは、おそらく、あなた方にも劣らないと思っております。ただ入信が前か後かのちがいがあるだけではありませんか――との暴言である。
日興上人の御指導に従わないばかりか、″仏意に背く″等とかえって攻撃している。増上慢もきわまれりというほかない。自分が、わがまま勝手にしたいために、邪魔になる日興上人を排撃し、″同じ大聖人の弟子ではないか″と、理屈にもならぬ妄言を吐いている。
次元はもとより異なるが、これまで、事件を起こしたり、自分勝手なわがままができなくなった人間は、″自分は戸田会長の弟子である″と必ず言い出す。
戸田会長の弟子であるならば、戸田会長の指導通り、学会とともに広宣流布に進むべきである。先生は「団結していけよ」と仰せで、「破和合僧せよ」とは、おっしゃっていない。そんな論理は、まことに、こっけいな落語みたいなものだ。
さて、実長が、こうした手紙の五年前、弘安七年(一二八四年)に同じく日興上人に送った手紙も残っている。
それには「渡せ給ひ候ことは偏に聖人の渡せ給ひ候と思まいらせ候に候」――(日興上人が、身延へ)いらっしゃったことは、ひとえに大聖人がいらっしゃったと同じと思っております――と、日興上人の御入山を最大に歓迎している。
それが、この豹変ぶりである。日亨上人は、次のように慨嘆しておられる。
「わずか五年のあいだに、かくも情感の反覆(ひっくりかえること)するものか。親愛が仇敵に変じ、師弟が同輩に下落する事のあさましさよ」(「富士日興上人詳伝」)。
親愛の言が五年のうちに、″仇敵″に対する絶交の手紙となり、師匠と仰いだ心が″同輩″のように見下す傲慢となる変心を嘆いておられる。
なお日亨上人は、それとともに、中国・唐の大詩人、白楽天(七七二―八四六年)の詩の一節を引いておられる。
「行路難 水に在あらず 山に在らず 只人情反覆の間に在り」と。
すなわち、わが行く道の本当の難所――それは逆さか巻く河にあるのでもない。険しい山にあるのでもない。ただ人々の心の頼みがたさ、心のうつろいの激しさにある、との詠嘆である。
この詩句は、私の人生行路に照らしてみても、まさにその通りだと実感する。
今の退転者たちも、ついこの間まで、
「学会と池田先生の大恩は山よりも高い」、
「生涯かけて、ご恩返しをいたします」等と、
自らすすんで書いてきた。
私が嘆くのは、忘恩うんぬんではない。
そうした変節の徒は、
自分自身の、かけがえのない″生命の法器″を自ら破壊してしまう。
ただ、そのことが、かわいそうでならないだけである。
これからの諸君の、
広布の大遠征においても、
幾多の「裏切り」や「反逆」、
「憎悪」「策謀」等に遭遇することがあるにちがいない。
しかし決して″感傷″になってはならない。
弱々しい″人間不信″に陥ってはならない。
常に朗らかに、また朗らかに、
堂々と前進していくことだ。
十界互具・一念三千の大法という高き次元から、
すべてを悠然と見おろし、
乗り越えながら、
いかなる時も、
限りない希望の虹を、
自ら大きくつくり出していける
勇者であってほしい。
そうした大ロマンにあふれた、
信仰王者の人生を私は諸君に期待する。
「悪知識」となった日向の卑劣な存在
ところで、もともと日興上人の教化によって大聖人の門下となり、また日興上人を敬い仰いでもいた波木井実長が、なぜこれほどまでに違背・謗法の道を一気に転落してしまったのか――。ここに、いわゆる「悪知識」の恐ろしさがある。
日興上人は次のように仰せである。
「此の事共は入道殿の御失にては渡らせ給い候はず、偏に諂曲したる法師の過あやまちにて候」(編年体御書1733㌻)
――これらのこと(さまざまな謗法)は、入道殿(実長)のせいではない。ひとえにへつらい、心の曲がった法師の罪であると――。
すなわち、
実長にへつらい、取り入りながら、
ついには日興上人へ反逆の矢を射させた
悪法師の存在があったのである。
それは誰か――。
五老僧の一人、
日向である。
日向は日興上人より七歳年下で、少年時代から大聖人に帰依していた。彼は学識豊かで多才であった。また弁舌に長じ、社交性にも富んでいたようだ。大聖人のかつての師・道善房の死去にさいしては、大聖人の命により「報恩抄」を、その墓前で奉読するほどの存在であった。また、大聖人の法華経講義を受講し、「御講聞書」もまとめている。
しかし
日向は、
大聖人の御葬送や第百箇日忌法要など、
肝要な時には姿を見せていない。
ここに、彼の「忘恩」の心根がうかがえる。
その日向が弘安八年(一二八五年)の春ごろ、突然、身延に登山してきた。日興上人は日向の心根を危惧されながらも、五老僧の中でただ一人自ら登山してきた彼を包容し、身延山の学頭という要職に任ぜられた。
だが――。その翌年の末ごろから、
日向による撹乱が始まる。
日向は言葉巧に実長に取り入っていく。
やがて実長は、″自分の師匠は、厳しい日興上人ではなく、
親切な日向である″と思うまでに日向に心を奪われ、
信心をすっかり狂わされてしまった。
日向はその実長を教唆して、
次々に重大な謗法を犯させていく。
日興上人が厳重に訓誡されても、
日向は逆に″日興上人は外典読みに偏っていて、
法門の極意が分かっていない″などと
的はずれの批判をしてくる始末であった。
こうして、
ついに日興上人は身延離山を決意される。
まさに現代的にいえば、
日向による実に悪辣な
″乗っ取り″の手口であったといえるかもしれない。
正応元年(一二八八年)厳寒の十二月、日興上人は身延離山を前に一通の御手紙を記された。今からちょうど七百年前のことである。それは、波木井一族のなかにありながらも、日興上人に対して変わらぬ″師弟の誓い″を立てた若き門下へあてたものであった。
「原殿御返事」と呼ばれるこの御手紙を通し、日興上人は、身延離山にいたるいきさつ、また御自身の御心情を、信頼する若き門下に対して諄々と語りかけておられる。
すなわち、「彼民部阿闍梨、世間の欲心深くしてへつらひ諂曲したる僧、聖人の御法門を立つるまでは思いも寄らず大いに破らんずる仁よと、此の二三年見つめ候いて、さりながら折折は法門説法の曲りける事を謂れ無き由よしを申し候いつれども、敢用いず候」(編年体御書1732㌻)――かの民部日向は世俗の欲心が深く、(波木井実長殿に)こびへつらう僧であるから、大聖人の建立された御法門を守り弘め通すとはとても考えられない。むしろ大いに破る人であろうと、この二、三年見つめながら、折々に法門を誤って説法している点を注意していたが、一向に改める様子がなかった――と。
このように、日興上人は、日向の本性を厳しく断罪された。
これは、波木井一族の門下に対する、
″あなた方の主を誑惑した
悪知識の正体をしっかりと見破っていきなさい″
″つくべき師を絶対に間違ってはならない″
との御心からであったと拝されよう。
このような日興上人の御心中を拝察するとき、
″これまでは何とか立ち直らせたいと包容し指導もしてきた。
しかし結局、
正法を破り和合僧を破壊していく存在であることが明白となった以上、
私は断固として戦っていくつもりである。
若き門下の者たちよ、
このことをよく知っておきなさい″
との毅然たる御心情が偲しのばれてならない。
″青春の誓い″に生涯走り抜け
さて、
昭和二十五年、戸田先生が第二代会長に就任される前年のことである。
先生の事業は最大の苦難に直面していた。
それは単に一事業の危機で済まされるものではなく、
誕生まもない「創価学会」が断絶するかどうかという瀬戸際であった。
戸田先生の人生もこれで終わりかもしれない――そんな苦衷のさなかにあった。
当時、私は二十二歳。まさに″戸田先生と学会を守り抜きたい″との覚悟で戦う一日一日だった。その夏のある雷雨の日の日記に、私は次のように記した。
「先生の、激励に応え、再び、世紀の鐘を、私が鳴らそう。先生より、離れる者は、離れろ。若き戦士となり、若き闘士となって、先生の意志を、私が実現するのだ……」と。
この青春の誓いを、私は敢然と貫き果たしてきたつもりであるし、そのことを最大の誇りと思っている。
そして、時は移り、
二十一世紀に向かわんとする今日、
次の新しき″世紀の鐘″を鳴らすのは青年部の諸君以外にない。
だからこそ私は、
諸君を最大に激励したい。
信じていきたい。
偉大なる人生と広布に連なりゆく
「共戦の歴史」をともどもにつづっていきたい
――という思いでいっぱいである。
戸田先生のもと開かれた毎月の本部幹部会は、主に東京・豊島公会堂を会場として、広布の前進の歴史を刻む大切な会合であった。
私は、その折々の戸田先生の師子吼のごとき雄叫を忘れることはできない。
昭和二十九年二月の本部幹部会では、戸田先生は次のように指導された。
「わが学会は、和合して、広布へ、日蓮大聖人様の教えを、日蓮大聖人様の指導通りにやろうというのであるから、これを破ろうとするものは、かならず仏法の大きな罰をうける。もし破ろうとするものあるならば、やってみたまえ。内から外からやってみたまえ。絶対にできぬ。
われわれは和合僧なりと、心から叫ぶ団体である。幹部は結束してこれにあたっている。そして破るものも悪いが、これらのもののみだけではなく、破られたほうにも(罪が)ある。これはみなさんの心に、深く気に留とめなければならぬ。確固不動の信心を求めるしだいである」と。
さらに、逝去せいきょの一年ほど前の本部幹部会の席上、
戸田先生は、「ほんとうに、信心なら戸田と太刀打ちしても負けるものかという相手なら、私も受けましょう。私はなにも、金にも驚かない、権力にも驚かぬ。だが信心だけはこわい。だが、私は、信心には自信がある。私に反抗してやれるものなら、やってごらん。不肖な私だけれども、日蓮大聖人様のお使いとして、七百年後の今日きたのでありますから、創価学会なんてインチキだ、でたらめだというなら、いわしてやろうではありませんか。どんな結果になるか、断じて負けません、私は。三年かからずに、かならず結果をみせてあげる」と述べられた。
そして「これが信心というものです。金でもなければ、権力でもない。学会の位置をつかって、金のことや権力の行動をしたなら、かならず罰をうけるということを、きょうは宣言して、私の話を終わります」と結ばれている。
まことに深い意味を含んだ、今日また未来への戒めともいえる言葉だと思う。
信心のない人間が、
肩書とか権力とか学歴とか、
そんなものでいくら表面を飾っても虚しいだけである。
無名の一青年や一婦人であっても信心のある人にはかなわない
――すなわち、限りない強さ、深さ、輝きをもっているからだ。
これが、私の四十年間の信心の体験からいえる実感でもある。
どうか諸君は、
″断じて負けない″との「確固不動」の信念に立って、
(中略)学会の清き信心の流れを、
どこまでも守り抜いていく一人一人であっていただきたい、
と心から念願し、記念のスピーチとさせていただく。
第四回全国青年部幹部会 破和合僧 1988.5.28
スピーチ(1988.5〜)(池田大作全集第71巻
2023.8.23整理
2022年9月15日
第2102回
同志の怨嫉は、破和合僧となる
<『己心の内』に法を求める仏法者の生き方を!>
「皆さん一人ひとりが、
燦然たる最高の仏です。
かけがえのない大使命の人です。
人と比べるのではなく、
自分を大事にし、
ありのままの自分を磨いていくことです。
また、自分が仏であるように、
周囲の人もかけがえのない仏です。
だから、同志を最高に敬い、
大事にするんです。
それが、創価学会の団結の極意なんです」
日蓮大聖人は、
「忘れても法華経を持つ者をば
互に毀るべからざるか、
其故は法華経を持つ者は必ず皆仏なり
仏を毀りては罪を得るなり」
(新1988㌻、全1382㌻)と仰せである。
さらに、同志の怨嫉は、破和合僧となり、
仏意仏勅の団体である創価学会の組織に亀裂を生じさせ、
広宣流布を内部から破壊する魔の働きとなる。
伸一は、愛する同志を、
決して不幸になどさせたくなかった。
ゆえに、
厳しく怨嫉を戒めておきたかったのである。
「学会のリーダーは、
人格、見識、指導力等々も優れ、
誰からも尊敬、信頼される人になるべきであり、
皆、そのために努力するのは当然です。
しかし、互いに凡夫であり、
人間革命途上であるがゆえに、
丁寧さに欠けるものの言い方をする人や、
配慮不足の幹部もいるでしょう。
いやな思いをさせられることもあるかもしれない。
そうであっても、
恨んだり、憎んだりするならば、
怨嫉になってしまう。
〝どう見ても、これはおかしい〟と思うことがあれば、
率直に意見を言うべきですし、
最高幹部にも相談してください。
もし、幹部に不正等の問題があれば、
学会として厳格に対処していきます。
また、リーダーの短所が災いして、
皆が団結できず、
活動が停滞しているような場合には、
その事態を打開するために、
自分に何ができるのかを考えていくんです。
他人事のように思ったり、
リーダーを批判したりするのではなく、
応援していくんです。
それが『己心の内』に法を求める仏法者の生き方です。
末法という濁世にあって、
未完成な人間同士が広宣流布を進めていくんですから、
意見の対立による感情のぶつかり合いもあるでしょう。
でも、人間の海で荒波に揉まれてこそ、
人間革命できる。
人間関係で悩む時こそ、
自分を成長させる好機ととらえ、
真剣に唱題し、
すべてを前進の燃料に変えていってください。
何があっても、
滝のごとく清らかな、
勢いのある信心を貫いていくんです」
<新・人間革命> 第29巻 力走 162㌻~163㌻
2022月9月14日(未掲載)
松野殿御返事(十四誹謗の事)
新版(374)松野殿御返事(十四誹謗の事)
建治2年(ʼ76)12月9日 55歳
松野六郎左衛門
(前略)
御文に云わく
「この経を持ち申して後、
退転なく十如是・自我偈を読み奉り、
題目を唱え申し候なり。
ただし、
聖人の唱えさせ給う題目の功徳と、
我らが唱え申す題目の功徳と、
いか程の多少候べきや」と云々。
さらに勝劣あるべからず候。
その故は、
愚者の持ちたる金も
智者の持ちたる金も、
愚者の然せる火も
智者の然せる火も、
その差別なきなり。
ただし、
この経の心に背いて唱えば、
その差別有るべきなり。
この経の修行に重々のしなあり。
その大概を申さば、
記の五に云わく
「悪の数を明かすとは、
今の文には説・不説を云うのみ。
ある人これを分かちて云わく、
先に悪因を列ね、
次に悪果を列ぬ。
悪因に十四あり。
一に憍慢、二に懈怠、三に計我、
四に浅識、五に著欲、六に不解、
七に不信、八に顰蹙、九に疑惑、
十に誹謗、十一に軽善、十二に憎善、
十三に嫉善、十四に恨善なり」。
この十四誹謗は在家・出家に亘るべし。
恐るべし、恐るべし。
過去の不軽菩薩は、
「一切衆生に仏性あり。
法華経を持てば必ず成仏すべし。
彼を軽んじては仏を軽んずるになるべし」とて、
礼拝の行をば立てさせ給いしなり。
法華経を持たざる者をさえ、
「もし持ちやせんずらん、仏性あり」とて、
かくのごとく礼拝し給う。
いかにいわんや、
持てる在家・出家の者をや。
この経の四の巻には
「もしは在家にてもあれ、出家にてもあれ、
法華経を持ち説く者を一言にても毀ることあらば、
その罪多きこと、
釈迦仏を一劫の間直ちに毀り奉る罪には勝れたり」と見えたり。
あるいは
「もしは実にもあれ、
もしは不実にもあれ」とも説かれたり。
これをもってこれを思うに、
忘れても
法華経を持つ者をば互いに毀るべからざるか。
その故は、法華経を持つ者は必ず皆仏なり、
仏を毀っては罪を得るなり。
かように心得て唱うる題目の功徳は、
釈尊の御功徳と等しかるべし。
(後略)
(新1987㌻~同1988㌻、全1381㌻~同1382㌻)
2022年7月11日
第2050回
破和合僧
団結を破壊する破和合僧は大罪
(5)
釈尊が厳しく戒めた罪に、「両舌」がある。
「二枚舌」のことである。
告げ口などによって人々の間を裂き、
離れさせ、争わせるので、
「離間語りけんご」とも言う。
″不和を助長し、
不和を楽しみ、
不和を喜ぶ″卑劣な人間であり、
″和合の破壊者″である。
(前掲『南伝大蔵経』42、前掲著作集16、参照)
釈尊は、
「愚人よ、汝らは、なぜ争いを起こすのか」
(前掲『南伝大蔵経』2、参照)と呵責し、離間語を罰した。
創価の世界は、
仏子の集いであり、善の力の「結合」である。
心と心を「和合させる言葉」を生み出す人々の集まりである。
断じて、「分断」の動きに食い破られてはならない。
日蓮大聖人の時代に、
優れた弟子であったにもかかわらず、
退転した三位房という弟子がいた。
大聖人はその不幸な死を書き記し、
「鏡のために申す」(御書1191㌻)
――後世のために言っておく、とつづられている。
私たちの広布の歴史もまた、
正義と極悪との戦いの真実を、厳格に刻みゆく。
わが学会は、
どこまでも真剣な祈りを根本に、
ともに励ましあい、
永遠の和合僧団として前進してまいりたい。
2005.8.4全国最高協議会(7)
2022年7月9日
第2048回
破和合僧
団結を破壊する破和合僧は大罪
(4)
釈尊は「破和合僧」を厳しく戒めた
仏典には、
仏道修行者の集まりを破壊する動きへの
戒めが説かれている。
そのいくつかを紹介しておきたい。
初期の仏教教団においても、
教団の規模が大きくなると、
怠惰、傲慢、嫉妬などにとらわれ、
悪事を犯し、
その悪事を隠す者が増えたようだ。
ある長老は、
そうした様子を次のように語った。
「会議(sangha)に際しては、
たとい徳がなくとも、
巧みにいいまくる
饒舌無学の輩が有力となるであろう」
「会議に際しては、
たとい徳がそなわり、
恥を知り、欲念のない人々が、
道理に従って陳述しても、
力が弱いだろう」
(『原始仏教の成立』、『中村元選集〔決定版〕』14所収、春秋社)
また、堕落した者の特徴として、
″師の言葉をないがしろにする″点があげられている。
(「たがいに相敬うことなく、あたかも荒れ馬が馭者に対するがごとく、師の言に注意することがないだろう」〈同前〉)
和合僧を分裂させようとし、
諌められたにもかかわらず、
その企てを捨てなかった者や、
首謀者を助けた者たちには、
厳しい処罰が科せられた。
皆の前で、
みずから犯した罪を白状し悔い改めることを誓う。
謹慎生活や「別住」を課される、等の罰である。
(『平川彰著作集』11、春秋社、参照)
「和合僧を破す者は一劫、地獄にて煮らる」
(『南伝大蔵経』22、大正新脩大蔵経刊行会)
とも説かれている。
間断なき苦しみの生命となる。
反逆者の提婆達多が
釈尊の教団を破壊しようとしたとき、
その動きを助けた者たちは、
「分派の加担者」
「破和合僧の随順者」等と厳しく戒められた。
(前掲著作集14、参照)
また、戒律を破った罪のある比丘(男性の出家)は、
比丘が全員出席する集まりに参加することを禁じられた。
出席を禁じられた者のなかには、
「破和合僧」を犯した者も、
「破和合僧」を企んだ者も含まれる。
罪のある比丘が
自身の罪を隠して出席した場合、
他の比丘には、
その比丘の出席をさえぎる権利があった。
もし、戒を犯した者が入り込んだ場合、
その集まりで決定されたことは無効になった。
(同前)
(つづく)
2022年7月8日
第2047回
破和合僧
団結を破壊する破和合僧は大罪
(3)
先生は、学会に迷惑をかけた邪悪な人間について、
「性根の腐った者は、
どこまでいっても始末が悪い」と憤りを込めて言われた。
極悪とは、断じて戦わねばならない。
知恵を尽くして、徹底的に責めぬくことである。
また、こうも語っておられた。
「自分の命も大事だが、それよりも、
広宣流布に戦っていく人、
広宣流布の組織で戦っている人がいちばん大事なのだ」
そのとおりである。なかんずく、リーダーが同志を大切にする姿勢にいちだんと徹すれば、学会はさらに発展していく。
戸田先生は、幹部に対しては本当に厳しかった。
「信心の基本を忘却した幹部ほど哀れなものはない」
「見かけは有能に見えても、
信心の基本を欠いたら、
信心は即座に崩れ去る」
信心の「基本」とは、言うまでもなく「信・行・学」の実践に尽きる。
どこまでも基本に徹して、
皆から慕われるリーダーであっていただきたい。
牧口先生の時代には、軍部政府の弾圧によって、
ほとんどの幹部が退転していった。
戦後、一人で学会の再建に立ち上がった戸田先生。
その時代も、難を恐れ、臆病にも、退転していった人間がいた。
広宣流布に進む以上、三障四魔が起こるのは当然である。
恐ろしいのは、正法を知りながら裏切り、
清らかな師弟の世界、
異体同心の世界を壊そうとする「破和合僧」の存在である。
学会員の皆さんは、人がいい。
温かい心の持ち主が多い。
決して、悪心を持つ輩にだまされたり、
広布の団結を乱されてはならない。
悪を滅する戦いを忘れてしまえば、善は生じない。
これが仏法の原理である。
学会では、
「現実に戦っている人」を最大に讃えるのである。
(つづく)
2022年7月7日
第2046回
破和合僧
団結を破壊する破和合僧は大罪
(2)
釈尊の在世において、
提婆達多は教団の乗っ取りと分裂を画策した。
提婆達多の邪悪な本性を見破った釈尊は、
厳しく言った。
「提婆達多がなすところの事は、
もはや仏法僧の事ではない。
ただ提婆達多の所作なのである」
(「四分律」、『国訳一切経』〈大東出版社〉を参照)
もはや提婆達多の言動は、
仏法者のものではない、と言明したのである。
提婆の人生は破綻した。
頼りにしていた権力者の阿闍世王からも、
見放された。
その悪行も世間の知るところとなり、
人々から憎まれた。
最後は大地が割れ、
生きながら無間地獄に真っ逆さまに堕ちていったとも、
経典には記されている。
インドのアショーカ大王が残した法勅には、″僧伽(仏道修行をする人々の集団)を破壊する者は、追放されねばならない。なぜならば、私が願うのは、和合した僧伽を永続させることだからである″と刻まれている。(塚本啓梓『アショーカ王碑文』第三文明社、参照)
このアショーカ大王の法勅については、現代インドを代表する大哲学者であるロケッシュ・チヤンドラ博士との対談でも、話題になった。博士は、現代の「和合僧」というべきSGIの人間主義運動に、大きな期待を寄せてくださっている。
インドだけではない。今や全世界の心ある知性が、創価の和合の前進に、「共生と平和の未来」への希望を見いだしているのである。
大聖人は仰せである。
「悪を滅するを功と云い善を生ずるを徳と云うなり」(御書762㌻)
生命の悪、生命の無明の消滅が即、功徳である。
「悪を砕く」大闘争にこそ、その大功徳が輝く。
大発展の道がある。
邪悪な「破和合僧」の輩を断固として打ち破るたびに、
学会は、いよいよ威光勢力を増していく。
その闘争があったからこそ、
百九十カ国・地域に広がる創価の和合の大連帯が築かれたのである。
2005.7.16各部合同協議会
2022年7月6日
第2045回
破和合僧
団結を破壊する破和合僧は大罪
(1)
仏法を行じ、弘めゆく人々の団結を破壊せんとする「破和合僧」の罪は、仏法上、たいへんに重いとされる。
「破和合僧」は「五逆罪」の一つとして説かれている。(五逆罪の内容は、仏典等により諸説ある)
御聖訓には仰せである。
「大阿鼻地獄(無間地獄)の業因をいえば、五逆罪をつくる人が、この地獄に堕ちるのである。
五逆罪とは、
一に父を殺すこと、
二に母を殺すこと、
三に阿羅漢(小乗の悟りを得た聖者)を殺すこと、
四に仏の身を傷つけて血を出させること、
五に破和合僧である」(御書447㌻、通解)
また、「佐渡御書」で中国の不惜身命の僧として言及されている慧遠は、『大乗義章』で論じている
″破和合僧は、正法に違背し、人々を悩ませ、成仏への道を閉ざしてしまう。ゆえに、五逆罪の中でもっとも罪が重い″
さらに、こう断じている。
″破和合僧は、
貧嫉の心から起こる。
貧りの心、
名聞を求める心、
嫉妬心のゆえに和合僧を破壊するのである″
遠くは、日蓮大聖人、日興上人の御在世においても、
近くは、牧口先生、戸田先生の時代においても、
破和合僧の反逆者たちの性根は皆、同じであった。
その本質は、今も変わらない。
「和合僧」を破壊することは、
正しき仏法を断絶させることに通じる。
ゆえに、破和合僧の悪人を、絶対に許してはならない。
あいまいな態度で妥協してはならない。
こうした人間を放置すれば、
仏法の命脈が絶たれてしまうからだ。
また、悪行を徹して責めぬいてこそ、
その人を目覚めさせ、救うこともできる。
「破和合僧」の輩と戦いゆく
学会の「破邪顕正」の言論闘争は、
仏法の法理の上から見て、
正しい行動なのである。
(つづく)
 日めくり人間革命
日めくり人間革命