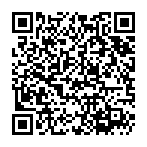死刑制度の廃止
死刑制度廃止マップ
◆死刑廃止について◆
「二十一世紀への対話」
アーノルド・トインビー
◆死刑廃止への賛否◆
「社会と宗教」
ブライアン・ウィルソン
◆第七章 「死」の実体に迫る仏法の眼◆
「宇宙と仏法を語る」
◆死刑廃止論◆
「私はこう思う」「私の人生観」「私の提言」
◆貧人繋珠の譬え◆
「随筆 人間革命」「私の履歴書」「つれずれ随想」
◆第四章 現代の目標◆
「文明・西と東」
クーデンホーフ・カレルギー
◆死刑廃止について◆
「平和への選択」ヨハン・ガルトゥング
◆死刑廃止について◆
「二十一世紀への対話」
アーノルド・トインビー
(池田大作全集第3巻)
<本文>
池田 イギリスでは死刑制度は廃止されていますが、日本も含めて世界の大部分の国々では、まだ死刑が行われています。
イギリスがどのように死刑廃上に踏みきったかは、非常に興味のある問題です。博士は、イギリスの死刑廃止について、どのような見解をもっておられますか。
トインビー イギリスで死刑が廃止されたことを、私は非常に喜ばしいと感じています。しかし、この廃止も決して驚くべきことではないのです。イギリスでは、かつてこの処置がとられるずっと以前から、警察と犯罪人たちの間に、ある暗黙の了解がありました。それは、双方とも武器を使用しないだけでなく、携帯することも差し控えようということでした。といっても、犯罪者たちが説得されて強盗などの犯罪をやめた、というわけではありません。ただ、警察側が犯罪者に対して暴力の行使を避けたので、その限りにおいて、彼らもなるべく暴力を用いずに犯行をしようとしたのです。そこで共通にめざされたことは、暴力は最小限に抑えようということでした。したがって、論理上は、死刑の廃止はそうした人道的な方向に沿う、大きな一歩前進となるはずだったのです。つまり、これに対する犯罪者側の反応としては、殺人を一切やめるということでなければならなかったはずです。
ところが不幸なことに、イギリスでは、死刑廃止に続いて起こったのは、職務上犯人の逮捕にあたった警官たちが次々と殺害されるということでした。すでに死刑が廃止された今日では、犯人としては次のような計算が成り立つのでしょう。つまり、自分が警官に逮捕されてしまったらそれまでで、その犯した罪が重ければ、長期間の禁固刑に服さなければならない。そこで、いっそのことその警官を殺してしまえば、その後逮捕されたとしても、最悪の場合でせいぜいもっと長期間の服役をすれば、それですんでしまう。あるいは、自分を逮捕しかけている警官を殺してしまえば、まつたく捕らわれずにすむ可能性も出てくる――と。こんなところに、犯人たちが警官を殺害しようとする動機がひそんでいるわけです。
こうした新しい事態が生じたことによって、警察の仕事は以前よりも危険になりました。そこで警察側としては、公務執行中の警官が犠牲となった殺人事件の場合は、それに対する刑罰として死刑を復活すべきであると提案しているのです。
池田 私は、そうしたイギリス警察の考えは、無理もないとは考えます。しかし、それでは死刑を復活させれば警官の犠牲はなくなるかというと、そうでもないことは、諸外国の例をみれば明らかです。私はあくまでも死刑は廃止されるべきだと考えます。
死刑廃止論を唱える人は
「人が人を裁き、その生命を奪うことは許されない」というヒューマニズムの精神か、
または「死刑を廃止しても犯罪は決して増加しない」という根拠に基づいています。
一方、死刑の存続を主張する人は、
死刑が犯罪の抑止力になるという効果を説いています。しかし、死刑に犯罪の抑止力という効果があるにしても、そういう考えには、殺されたことへの報復という思想や、生命を奪うことによって他への見せしめにしようという思想があるように思われます。
報復は必ず新たな報復を招き、悪循環をもたらすものです。また、見せしめという点についていえば、私は、絶対的に尊厳である生命を、生命以外のもののために手段化するのは、断じて許されないことだと考えます。生命の尊厳は、それ自体目的であり、したがって、もし何らかの社会的な犯罪抑止力が必要ならば、死刑以外の方法を考えるべきです。
見せしめのための死刑というのは、
人間社会につきまとってきた残忍性のあらわれであり、現代において、ますますその傾向は強まっています。現代における生命軽視の風潮はそのあらわれであり、そのような風潮を生み出している最大のものは戦争です。戦争は、多くの場合、国家がその利益のために人間生命を手段化し、犠牲にするもので、これ以上の罪悪はありません。これを許しているかぎり、凶悪な犯罪の温床は広がり、深まる一方です。
トインビー 私は、あらゆる国々で、死刑が廃止されるよう望みます。それには、二つの説得力ある理由があります。
その第一は、どんな人間にも他人の生命を奪う権利は、道義上まったくないということです。おっしゃる通り、死刑廃止は、同時に戦争の放棄を必要とします。一方では、ある人間が他人や人間社会に対して何らかの重罪、たとえば殺人を犯した場合、このたった一人の人間を、できるかぎり非人道性の少ない方法で死刑に処すことさえ私たちの権限にないとしておきながら、他方、戦争にあっては、最も残酷で最も野蛮な手段をもって、無数の人間を殺傷することが正当視されるというのでは、それこそ非論理的な話です。しかも兵士たちは、個人的には何の私怨ももたないいわゆる敵兵を、命を賭しても殺すよう強制されるまでは、かつて人間同胞に何の罪を犯したこともなかったのです。戦争は、人々を殺すだけでなく、人間を無理やり殺人者に仕立てあげます。そして、この二つの罪悪を、個人の次元だけでなく、集団的に犯させるのです。
死刑と戦争を廃止すべき、
第二の説得力ある理由とは、一度殺してしまった生命は、再び元へ一戻すことができないということです。たとえその人が度重なる重罪を犯した人であっても、生命あるかぎりは、道徳的に更生する可能性があるものです。
池田 死刑廃止には、それと同時に戦争放棄が必要だという点で、私たちの意見はすでに一致しています。この戦争放棄ということに含まれますが、とくに私が主張したいのは、核兵器を使用することだけは断じて許されないという点です。もし死刑が許されるものとするならば、戦争を起こし、核兵器を使用する魔性の人こそ、死刑に処せられるべきでしょう。といっても、私が死刑を認めるというのでないことは、よくおわかりいただけると思います。私は、人々が、核兵器による大量殺人という、最大の罪悪を抹消すべき強い姿勢に立ち、その根を断ち切るべきだといいたいのです。
私は、現在、死刑廃上の方向が各国で模索されているのは、非常によい傾向だと思っています。しかし、もう一歩、死刑に値するような犯罪を生まない社会を築いていく努力が、続けられなくてはなりません。そのためには、どうすれば今日の生命軽視の風潮が抜本的に改められるかを、考えることが先決でしょう。
ただ、現実の問題としては、いわゆる凶悪犯に対していかなる姿勢で臨むかということも、考えなければなりません。これについては、私は、どんな犯罪者に対しても、忍耐強くその良心を呼び覚ましていく努力が必要だと思います。この努力をせずに、国家が凶悪犯を死刑に処すならば、国家自体が殺人を行っていることになりましょう。どうしても社会的制裁が必要な場合でも、死刑以外の手段が講じられるべきだと考えます。
トインビー ある国で死刑が廃止されたからといつて、では、有罪と決まった犯人にも十分な個人的自由が与えられてよいかというと、決してそんなことはありません。何の罪科もない一般市民が道義的・法的な権利としてもっていると同じだけの自由が、犯罪者に与えられてよいはずはないのです。殺人犯にも生き続ける権利があるというのであれば、同じく無辜の隣人たちには、殺人犯によって殺される危険から保護される権利がある、といわなければなりません。したがって、殺人犯として服役中の者は、釈放しても他の人間に害を加える恐れが、もはやまったくないと思われるまでは、刑期を解くべきではありません。ただし、この場合、あくまでもその恐れがないと思われる、ということであって、そこに確実性はないわけです。
犯罪者を刑に服させることの目的は、報復をめざすものであってはなりません。むしろ、どこまでも犯罪の予防をその目的とすべきであり、さらにこの消極的な目的を超えて、積極的に教育し、更生させることをめざすべきです。刑務所は、できうるかぎり、犯罪者に自力更生の道を教える、学校のような存在にすべきです。しかし、これは、はたしてどこまで可能なものでしょうか。教育の効果は、自発性の度合いに比例するものです。他の人間関係と同様、教育にあっても、強制は抵抗を生みがちです。刑務所という名の学校も、やはり客観的にみて、また服役者自身の意識からいって、強制が最大限行われ、強制がもたらす怒りが極限に達している学校なのです。
池田 あらゆる刑は報復的なものでなく、予防を目的とするものでなければならないとする博士のご意見に、私も賛成です。また、服役者の教育は強制をともなうゆえに、効果を生むことはむずかしいというご指摘も、まことにその通りであると思います。この囚人教育がもっている限界を乗り越える唯一の道は、教育者の並々ならぬ情熱と慈愛であり、そこから、服役者との間に真に人間的な心のつながりをつちかうことではないでしょうか。
ともあれ、死刑の廃止、死刑を必要としない社会を実現させるには、仏教で説く″慈悲″の精神がすべての人々に行きわたり、確立されることが望まれます。それによって初めて、人間が真の意味での生命の重みを認識し、生命の尊厳に目覚めることができると信ずるからです。
◆死刑廃止への賛否◆
「社会と宗教」
ブライアン・ウィルソン
(池田大作全集第6巻)
<本文>
死刑廃止への賛否
池田 イギリスでは死刑制度は廃止されていると聞きますが、日本や他の多くの国では、まだ死刑が行われております。
日本でも、死刑廃止か存続かを巡ってしばしば論議があり、死刑廃止論者は、その根拠として、人間が人間を裁き、その生命を奪う権利はないとするヒューマニズムを訴え、また死刑を廃止しても犯罪は増加しないといいます。一方、存続論者は、死刑には犯罪への抑止力があると主張します。
教授は、死刑に対して、どのような意見を持っておられますか。
私は生命は尊厳なものであって、誰びともこれを奪う権利はないとの信念から、死刑は廃止すべきであると考えています。尊厳なる生命を、生命以外のもののために手段化すべきではありません。
もし、死刑に犯罪の抑止力があるというのであれば――私はこの意見に賛成できませんが――犯罪の抑止のためには、死刑以外の方法を講ずべきでしょう。
また死刑には、殺されたことへの報復の思想や、他者への見せしめの思想があるように思います。私はこのような思想には、断固として反対します。
ウィルソン 現在の死刑賛成論の大半は、犯罪抑止力への期待に基づいているようです。しかし、そうした抑止力を実際に証明するとなると、これは評価が難しくなってきます。
たしかに、激情から生じる犯罪は、刑罰の軽重に関係なく発生しているようです。これに対して、不法な利得を得ようとして犯される罪は、刑罰の軽重によって影響されるかもしれません。
たとえば、強盗が、逮捕されたときに武器を持っていなければ罪が軽くなることを知っている、といった場合が、これにあたります。刑の軽重がもつ影響性という一点だけから、殺人の統計を判断することは、残念ながら困難です。しかし、押しなべてみれば、たとえ逮捕される可能性がさほどない場合であっても、逮捕されるかもしれないという心配のほうが、どんな刑罰よりも大きな抑止力になっていることは、疑いのないところです。
報復的な処罰という考え方は、西欧諸国では、知的に受け入れられなくなってきています。西欧では、死刑の問題についての公の論議に参画している人々の大半は、洗練された感覚の持ち主で、彼らにとって報復という概念は魅力的でないことは確かであり、ときには理解しがたいものです。彼らは、現代文明はすでに懲罰の必要性をほぼ超越した段階に達していると信じたい気持ちをもっており、私もそれにはかなりの共感を覚えております。しかし、私は、一般大衆の間では、報復的処罰への要求がまだかなり強いのではないかと思います。したがって、私自身は、法的判決の適切な基礎として、復讐的動機を支持することはしませんが、こうした大衆の感情をまったく無視することもできないと思っています。
西欧諸国では、理論上は、民衆の意志が政治家によって実行されるという、民主主義体制が機能していますが、多くの問題があまりにも専門的すぎて、大衆の意志が正確に反映されにくいということがあります。
しかし、死刑の問題の場合は、論点をかなり簡略化できますし、国民投票に付すことも容易でしょう。私は、民主主義の価値を主張する人々ならば、この種の問題について大衆の意見を考慮に入れる義務を、そう簡単に無視することはできないと思います。それは、たとえ彼らが、死刑の問題に対する態度について、大衆に再考を促す教育を推進しようとしたとしても、同じことでしょう。
池田 たしかに、大衆の意志が看過されることがあってはなりません。また、同じ殺人といっても、同情すべき状況の中で犯したという場合もあれば、まったく同情の余地のない殺人もあります。私も一個の人間として、特に最近、日本でも多くなっている凶悪犯罪のニュースを聞くにつけ、そのなかには死刑にされてもやむをえないと思う例も少なくありません。
しかし、死刑にするかしないかは、国の法律に照らし、司法機関によって定められるわけですが、法律を定めるのも、判決を下すのも、死刑を執行するのも、生きている人間です。裁判には誤りもありえますし、死刑執行者は、現実に人の命を絶つ行為をさせられるのです。どんなに憎んでも憎み足りない凶悪犯であっても、その生命を絶つ仕事をさせられるのは、人間として嫌なものであろうと思います。
のみならず、人間は、一時的な衝動によるだけでなく、誤解や間違った考え方のために罪を犯し、後になって後悔することもあります。若いころ凶悪な犯罪人であっても、年を取ってからは悔い改める人もいます。たとえ獄からは出られなくとも、悔い改めた人が、その人生を罪の償いと社会への貢献のために費やしうる機会が与えられることが、私は望ましいと考えます。
だからといって、すべての人が私と同意見になるべきだというわけではありませんし、まして家族や知り合いが殺されたとき、殺人者に対して抱く憎しみの心は、私もよく分かるつもりです。ただ、憎しみの心をどう克服するかということも、私は人間の課題であると思います。
ウィルソン 殺人者に対する死刑賛成論は、たぶん二つの要因から強まっているのだと思います。一つには、今日、刑務所は犯罪者にとって、しだいに居心地のよい場所になっていると、多くの人が思っていることです。新聞記事は、牢獄での生活が、多くの大衆がこうあるべきだと考えているほど苛酷でないことを、定期的に報道しています。
またもう一つには、近年、西欧諸国で、身の毛もよだつような、非道な殺人の異常事件がいくつか起きていることが挙げられます。アメリカでは、まったくのサディスティックな動機によるものや、または異常な性行為に関連した大量殺人事件が、いくつか起きています。
イギリスでも、数人の幼い子供たちを、共謀して殺害した連中が、現在、投獄されています。現にいま、私がこうして執筆している最中にも、野蛮かつ残忍な手口で数人の若い女性を殺害し、五十万市民を(注1)恐怖に陥れたある男を、警察が探索中です。その他にも、カネのために殺人を請け負う殺し屋がいて、何の罪もない人たちを殺害しています。そのなかには「仕事の邪魔になる」というだけの理由で殺された子供さえいるのです。
また、何の罪もない人々の生命が絶たれることには目もくれず、たんなる政治上の宣伝のために、爆弾を爆発させた多くのテロリストもいます。彼らは、たんに自分たちの目的だけのために、無謀にも罪なき生命を犠牲にしたのです。このようなタイプの犯罪すべてに対して、イギリスの世論は、何年か前に廃止された死刑の復活を、おそらく圧倒的に期待しているものと思われます。
池田 大事なことは、生命の尊厳に対する意識が、どのように、あらゆる人々の心の中に定着するかです。死刑廃止が実現されても、民衆全般の中に生命を軽視する風潮が強まれば、死刑にならないことを悪用して、残忍な犯罪が頻発することになります。
日本では、九世紀から十一世紀まで約三百年間にわたって、死刑が行われなかった時代がありました。その背景には、仏教の信仰があり、殺人を犯した報いとして地獄に堕ちることの恐ろしさが、広く人々の意識に定着していたのです。もとより、この時代も殺人がなかったわけではありませんし、戦闘もいくつかはありました。しかし、社会の支配的立場を占めたのは、教養と文化を重んじた宮廷貴族であり、武士は、彼らに仕える立場でした。都の京都は「平安京」と名づけられ、優雅さが何よりも喜ばれていました。
残念ながら、やがて仏教は煩瑣な儀礼と迷信に堕落し、それとともに、生命を尊ぶ風潮は廃れて、争いを事とするようになり、それにつれて武士階級が主役になり、殺伐とした犯罪や謀反が続発するのに対応して、刑罰も残虐化していったのです。ここには、まさに悪が悪を呼び、残忍な犯罪が残虐な刑罰を求めるという、悪循環の様相があります。
この悪の連鎖を断ち切って、平安の世を実現するには、その土壌として、生命を尊ぶ思想、生命の尊厳を重んずる精神が、あらゆる人々の中に確立されなければなりません。ただちに平安の社会を実現することはできないとしても、こうした努力は、必ずこれまでに見られなかったような、健康的な社会を現出させていくものと信じます。
◆第七章 「死」の実体に迫る仏法の眼◆
「宇宙と仏法を語る」(池田大作全集第10巻)
<本文>
死刑には反対する仏法の立場
木口 死刑制度の是非論が盛んですが、これは世界的な問題ですね。この点は、どうお考えでしょうか。
池田 死刑は反対です。
釈尊の仏法が広まった、一つの象徴的な例として有名な阿育大王の時代がありました。
阿育大王は、ほとんどインド全域に及ぶ統一を最初に成し遂げた王で、慈悲を根底とした善政を施したことで知られています。
彼は、寛刑主義をとっており、死刑は行いませんでした。外国と多くの友好交流にも努めている。また、文化の興隆に最大の力をそそいでいます。
仏法に帰依した彼が、絶対平和主義を標榜したことは、たいへんに有名です。
木口 なるほど。すると極悪人に対しては、どうみますか。
池田 よく戸田先生も言っておられましたが、極悪人の場合でも、「無期刑」でよいのではないか、と……。
私も、そうせざるをえないと思うし、また、それでいいのではないでしょうか。
これは罪人とはまったく別の話ですが、鎌倉時代、蒙古襲来のさい、「元」の使者を、幕府が斬首したことについて、「科なき蒙古の使の頚を刎られ候ける事こそ不便に候へ」(「蒙古使御書」)と、日蓮大聖人は斬ってはいけなかったとおっしゃっている。
ともかく仏法は、この世に生をうけたものは、この人生をどう意義あらしめるか、価値あるものとしていくかを教えている。その最高の価値ある人生が成仏であることは当然として、この人生を「所願満足」「衆生所遊楽」と説かれているように、最大の喜びと充実しきった人生にしていくことが大事なのです。
「死」は人生の総決算
―― さきほど、ルーマニアでも『源氏物語』が話題になったということでしたが、この物語にも、たしか「死」についてのくだりがありましたね。
池田 『源氏物語』では、一次元からとらえるならば「生老病死」ということが、全体のモチーフになっているともとれる感がありますね。
平安時代の作品とはいえ、紫式部の『源氏物語』は、多くの文学の原点といえるでしょう。「死」の姿に対する表現として、四つの描写が記憶にあります。
木口 そうですか。
池田 紫式部は、光源氏を中心として近親や、最愛の人々の死の姿を描いて、
「淡のごとく消えゆく……」
「露の消えるがごとく……」
「枯葉が散るごとく……」
「灯が消えるがごとく……」
というような表現をしています。
―― そのとおりですね。
池田 そこで紫式部は、多くの「死」の場面を、必ずといってよいほど「秋」に設定している。
まあ、何人かの女人に対しては、恋慕の情すてがたく、春に死なせていますが。また早く、生に流転させようという作者の情愛がそうさせたのでしょう。
木口 なるほど、おもしろいですね。
池田 ともかく仏法では、人生の総決算が、「死」という瞬間の場面に集約されると説かれている。
木口 非常に厳しいものですね。
池田 そうです。
しかし、そうでなければ刹那主義、快楽主義に陥って、なんの進歩もなくなってしまうでしょう。時代の進歩もなくなってしまう。また人生、あまりにもふざけ半分になってしまう。
それでは、自己を律すること、人々への善意、社会への貢献などというものは、忘れ去られてしまうでしょう。
―― 同感です。
池田 「秘とはきびしきなり三千羅列なり」――と仏法では説かれています。
つまり作々発々、瞬間、瞬間の生命活動に対して、網の目も許されないほどの厳しき因果律が、厳然として積み重ねられていくわけです。
そこで「女人成仏抄」という御書には、「されば経文には一人一日の中に八億四千念あり」といわれ、その念々が、ことごとく業因になっていくと述べられております。
―― 漠然としていれば、なにもわからないですむように、社会にも、また自身に対してさえも、傍観的な生き方はできるかもしれない。しかし、それなりの厳しき因果律は、どうしようもないと思います。
池田 日蓮大聖人は、「先臨終の事を習うて後に他事を習うべし」と説かれています。
他事――政治、経済ということも、もちろん大切であるが、まず、この「生死」という根本命題に挑戦し、解明しゆかんとすることが、人生の最大の課題であるということだと思います。
いまの世界の人々の志向性は、政治優先、科学優先、経済優先で一見、賢明のようであるが、じつは、本末転倒していると言わざるをえない。
―― まったく、そのとおりですね。ところで、人間は、いつ自分が死ぬかということがわかるわけにはいかないのでしょうか。(笑い)
池田 われわれ、凡夫にはわからない。(笑い)
ただ病人が死の直前になって、なんとなく、自分は、もはや余命いくばくもないという察知は、あるようです。
ある医師が語っていたことですが、病人が「もうこのへんだと思います」とか「これまで、ありがとうございました」などの言葉を口にすると、必ず二十四時間以内には死んでいくといいます。
しかし、何年、何月、何日、何時ごろ、死ぬかというようなことは、当然、わからないと思う。
生命は生死の永遠の連続
木口 仏さまは、どうなのでしょうか。
池田 覚者であられるから、知っておられる。
その証拠として、釈尊も、日蓮大聖人も、きちっと、一つの仏法上の原理を自ら示されています。
木口 それはどういうことですか。
池田 釈尊は、霊鷲山において仏法を説き、霊鷲山の東北にあたる跋提河のほとりの沙羅林で入滅している。そこは純陀という大工さんの家でした。
大聖人は、身延山で妙法を講誦し、やはり東北にあたる現在の多摩川、当時は「たはがわ」といっておりましたが……、そのほとりの池上にて御入滅されている。また、池上家は鎌倉幕府の建築奉行でした。
釈尊も、大聖人もわれわれでは考えられない、ひとつの同じ儀式というものをふまえられておられるのです。
木口 なるほど。不思議な一致ですね。
池田 ですから、日蓮大聖人は「委細に三世を知るを聖人と云う」とも仰せなのです。
木口 なるほど。なるほど。
池田 近きをもって遠きを推す、また一事が万事である。ゆえに、私どもは「仏」を信ずることができるのです。
―― ただいまの脱益の仏である釈尊と、下種益の仏である日蓮大聖人の御入滅の符合というものは、まことに不思議ですね。
池田 これらのことについて、さきほども触れましたが「如来は如実に、三界の相を知見す」と「法華経」では説かれています。
つまり仏法とは、「悟り」の哲学であり、この現実世界の姿をありのままに知見したものなのです。
それに比して、いわゆるマルクス、ヘーゲル、カントといったギリシャ哲学に端を発した西洋哲学、思想というものは、いまだ、そこに到達しえない途中の段階にある。ここに、抜本的な違いがあることを知らなければならない。
―― そのとおりですね。西洋の哲学は科学の発達、時代の進歩、社会構造の変化といった、いわゆる人間生活の営み、文明といったものを客観視した次元においては、大きな功績を示してきたといえます。
しかし、いわゆる客観視だけでは、人間というもののすべてを、とらえることができない……。
池田 人間そのもの、生命それ自体をとらえるには、そこにどうしても、主観視していくいき方が必要になってくる。
それが、絶対性の追究であり、宗教、信仰へとつながっていくわけです。
木口 なるほど。人間を主観視すれば生命、客観視すると生活であり、社会であるということもわかるような気がします。
池田 私の人生の師である戸田先生は、死の問題について、興味ぶかいことをよく言われていた。それは――。もし、自分が昭和何年何月何日に死ぬということが、みなわかってしまったら、これほどおもしろくないことはない。むしろ苦痛である。こんなわびしいことはない。
むしろ凡夫は、わからないほうが幸せに生きられるものであるということで、そのことを仏さまは残してくれたのかもしれない……と。(笑い)
木口 おもしろい話ですね。
池田 ともあれ、以前にも申し上げましたように、生命というものは永遠である。これが仏法の大原則論となっているところです。
八万法蔵という膨大な法門の魂というべき「法華経」の「寿量品」には「方便現涅槃」と説かれている。
これは、一日にたとえてみるならば、朝日が昇り目をさます。「生」である。そして昨日の「生」の延長として一日の行動が始まる。一日の行動を終えて、疲れを癒すために家路につく。夜、あすの「生」のために休息の床につく。これすなわち、一日の「死」である。
これと同じように、一生の価値ある活動を終え、新たな活力ある生命力を得るために、「死」という方便の姿を示すというのです。
この生死を、三世永遠に繰り返しゆくのが十界にわたる「生命の実相」であるという意義だと思います。
太陽、月そして地球の寿命は
―― ところで木口さん、星も生まれては死んでいくわけですが、星の寿命は、どういうふうになっているのでしょうか。
木口 そうですね。
星には、それぞれ寿命がありますが、まえにもお話ししたように、星は回転するガス雲からできます。
それが、固まるときの質量の大きさによって、一生の長さが決まってしまいます。
池田 質量の大きい星ほど短命であるといわれていますが、それだけ行動が大きく、活発ですから、エネルギーを早く使い果たしてしまうのでしょうか。
木口 そのとおりです。質量の小さい星は、逆に、あまりエネルギーを使いませんから長命です。
―― われわれの地球の寿命は、どれぐらいなんでしょうか。
木口 地球は現在、約四十五億歳といわれます。あと何年、寿命が残っているかは、当然、太陽と密接な関係があるわけです。
池田 太陽は、あと約五十億年から六十億年で、自らのエネルギーを使い果たし、崩壊が始まるといわれていますね。
木口 ええ、太陽の現在の年齢は約四十五億歳、つまり太陽の寿命は、ほぼ百億年となります。
―― どうやって寿命を計算するのですか。
木口 簡単に言えば、太陽は、水素が核融合し、ヘリウムとなって、エネルギーを光として放出しています。
そこで、太陽から地球に届く光の熱量と太陽との距離から、太陽が時間あたりいくら熱量を出しているかを測り、太陽の重さから燃料の量をもとめて寿命を計算します。
―― 地球の年齢は、どうやってわかるのですか。
木口 地球上の鉱物のなかの放射線を出す物質の量から計算します。
―― 月はどうですか。
木口 詳しくは、まだ分析されていませんが、ただ地球と同時期の誕生ということは間違いありません。
池田 太陽が約四十五億歳。地球も月も同じく約四十五億歳。この三者に、密接な関連性が見いだせるわけですね。
木口 そのとおりです。
―― その他の天体はどうですか。
木口 太陽系内の他の惑星については、残念ながらデータ不足ですが、ほとんど地球の年齢と同じであると信じられています。
ところで太陽の年齢が経って、この水素が少なくなると、太陽はどんどん膨張を始めます。
―― すると地球上にも、重大な変化が起こりますね。
池田 温度は急上昇し、あらゆる生態的バランスがくずれ、ついにはすべてが焼き尽くされてしまいますね。
木口 そのとおりです。太陽は、現在の大きさの百倍から二百倍にもふくれあがり、水星、金星、そして、おそらく地球をものみこんで、一緒に燃えてしまいます。
これを、「赤色巨星」といいます。こうした星の終末は、他の天体で、実際に観測されています。
―― その後は、どうなるのですか。
木口 太陽の膨張は、約二十億年つづき、その後、逆に急速に収縮していきます。そして、ついには大爆発を遂げて、太陽の外層部をガスや塵として宇宙にバラまき惑星状星雲をつくります。残った部分は「白色矮星」という、ごく小さな星となってしまいます。
すべてに「成住壊空」のリズムが
池田 そうですか。まことに壮大で劇的な、われわれの想像を絶した太陽の「死」ということになりますね。
太陽も、月も、そして地球も、すべてが、仏法の説く「成住壊空」の法則のうえにのっとって運行している。
まえにも述べたように、宇宙それ自体もいま膨張期にある。この膨張期こそ妙法が広まっていく大前提になるわけです。
ともあれ森羅万象、いかなるものといえども、「成住壊空」のリズムにのっとっている。その点を、厳しく見極めたのが仏法なのです。
この「四劫」で、人生をとらえてみるならば、
「成」とは、誕生。青年期。
「住」とは、壮年期。
「壊」とは、老年期であり、
「空」とは、死である。
―― そうなるでしょうね。
池田 また、「一日」にもたとえられる。
朝は「成」。
昼は「住」。
夕方、夜は「壊」。
深夜は「空」。
木口 なるほど、そういう流れになるでしょうね。
池田 ですから、今度は「一年」としてとらえてみれば、
春は「成」、
夏は「住」、
秋は「壊」、
冬は「空」、
とも考えられる場合もあるでしょう。
―― よくわかります。
池田 ここで、西洋哲学と対比して、いちだん深く、実在論の思索をしていかなければならないことがある。
それは、少々むずかしいのですが、いわゆる「空」という問題です。ここに大乗仏教の真髄がある。
「有る」といえば有る。「無い」といえば無い。しかし、厳然と実在する存在としての「空」。
それを、仏法では「中道一実」、「我」と説いております。
この「我」という存在が、なんらかの具体的な一つの生命に発現され、誕生しゆくことが「成」である。それが「住」「壊」「空」というリズムに流転していくのです。
―― 最近は、天文学者のなかでも、星の誕生から消滅までが、仏法で説く「成住壊空」の原理に、非常に近いという人が少なくないようですね。
また先日も、「日本経済新聞」の論説に、「成住壊空」の原理に「近代科学の宇宙像が奇妙に、似通っている」と、載っていました。
近代天文学の発見と仏法の宇宙観
木口 たしかに、不思議なくらい近代天文学の発見と、仏法の説く宇宙観とは相通ずることが多いと思います。現象面での星の誕生・消滅と、それを貫く重力の法則は、物質面の次元にすぎませんが、さきほど話題になった「客観」と「主観」ですね。
―― そうですね。
「主観」と「客観」という立場については、今世紀最大の科学者の一人といわれたドイツのハイゼンベルクの志向性も同じであるといえるのではないでしょうか。
池田 彼の「不確定性原理」は、よく知られていますが、とくにノーベル賞を受けて以来の、ハイゼンベルクの思想の傾向は、急速に“万物の合一性”についての考え方を強めてきた。
木口 そのとおりです。「不確定性原理」という理論は、二十世紀の科学を前世紀までの科学と峻別する大原理なのです。この原理によってニュートンの機械論も、ダーウィンの進化論も破産してしまいました。これによって、人間の主観が物理学に復権したといえます。
池田 たとえば、ハイゼンベルクは、「われわれが観測しているのは、自然そのものではなく、われわれの探究方法に映し出された自然の姿である」という意味のことを言っている。
木口 ええ、ハイゼンベルクが、デンマークの物理学者、ボーア博士と共同提唱した「観測される系」(客体)と「観測する系」(主体)が密接に結び付いているという主張です。
ボーア博士は、世界的学者を多く育てたノーベル賞学者として著名です。
ハイゼンベルクたちのこの見解を、量子物理学では、「コペンハーゲン解釈」といっており、二十世紀の前半の西洋哲学の出発点となっています。たとえば、イギリスの哲学者、ホワイトヘッドの形而上学(『過程と実在 1』平林康之訳、みすず書房刊)もそうですし、アメリカの哲学者、ライヘンバッハやカルナップの実証主義もそうです。
しかし、物理学者はこれらの哲学に、どうしても満足できませんでした。
―― ボーアもハイゼンベルクも、晩年は仏教に関心をいだくようになっていた、というのは有名な話ですね。
池田 そうですね。まえにも何回か述べてきましたが、偉大な科学者は、必ずといってよいほど、宗教を志向している。そのなかでも、とくに仏法を志向していることは不思議ですね。
―― そうですね。どうやら、現代科学の志向性も仏法の世界に入っていますね。
池田 仏法では、環境としての「依報」と、主体としての「正報」が、二にして不二であるととらえます。
「瑞相御書」という御書には、「夫十方は依報なり・衆生は正報なり譬へば依報は影のごとし正報は体のごとし」とありますが、人間と環境社会との関連性を鋭くとらえております。
木口 「二にして不二」ですか。まさに卓見ですね。
科学の世界では、長い間、「環境」は「環境」、「主体」は「主体」として分離して考えられてきました。
それゆえに、科学は長足の進歩を遂げましたが、進歩すればするほど、じつは袋小路に迷い込んでいるということは事実といえます。
―― なるほど、そうですか。
◆死刑廃止論◆
「私はこう思う」
「私の人生観」
「私の提言」
(池田大作全集第18巻)
<本文>
今日なお行われている死刑制度に対しては、こうした観点からも深い疑惑をいだかざるをえないのである。しかしながら私の主張したい中心眼目は、そのことではない。裁判がどんなに厳正公平に行われたとしても、死刑に処するということ自体が、根本的に間違っていると言いたいのだ。
生命の尊厳と簡単にいうが、尊厳とは他の何ものによっても代えられないし、いかなる権力も侵すことができないということを意味する。もとより、その人が社会に悪をおよぼす場合、社会の人々の尊厳を守るためにその自由を抑制することはできるし、むしろ、せねばならぬといってもよい。しかし、その生命自体を断つことは、絶対に許されるべきでない。
この生命の尊厳を単なる観念ではなく、事実の行動原理として具現したときには、戦争もまったく根絶するにちがいなかろう。個人の意思は、容易に左右できるものではないが、それが国家ないし社会の行動と密接に結びついていることも事実である。したがってまず、国家が、生命の尊厳観にたって、死刑や戦争といった殺人権を放棄することである。個人的な凶悪犯罪を一掃する道もそこから開けると私には思えてならない。
私の知るかぎり、死刑がまったく廃止された社会は、歴史上、二つある。一つは、古代インドのマウリヤ王朝時代の、特にアショカ王の治世である。もう一つは、わが国の平安朝時代である。特に後者は、三百数十年にわたって、一切の死刑の行われなかった期間がつづいたといわれる。
この二例に共通するものは、仏教が興隆し仏教思想が為政者に甚大な影響をおよぼしたという点である。政治の原理は慈悲に求められ、人々は、生命を断つということに対して、地位や権力を超えて深い畏れをいだいた。犯罪は激減し、平和な日々がつづいた。アショカ大王の名は、今日なおインドおよび東南アジアの民衆の渇仰の的となっているようである。
元来、仏教は、生命の哲理を徹底的に究明し、生命の尊厳をこの世界に樹立しようとした教えなのである。キリスト教やイスラム教などにおいては、一切、神の意思によるとするが、仏教は、おのおのの生命の因果の法によるとする。主体は、あくまで現実に生き、働き、悩んでいる人間生命それ自体である。
その生死を決定するものもまた、神などという抽象的、観念的な他者ではなく、因果の理法によって動く、自己自身にほかならない。そこには“代理人”などという、あいまいな権力のつけいる隙間がない。絶対的なものは、自己自身の内にあるからである。
しからば、死刑を廃止すれば、犯罪が増えるのではないか等といった議論が出る。それは、この絶対的なものを、あくまで外に求める観念から、脱却できないでいるからだと私は考える。
内なる生命に眼を開き、そこに逃れようとしても絶対に逃れることのできない“生命の法”があることを知ったとき、犯罪がいかに恐るべきかは、なにも刑罰で脅かさなくとも生命の奥底から瞭然とするはずである。
◆貧人繋珠の譬え◆
「随筆 人間革命」
「私の履歴書」
「つれずれ随想」
(池田大作全集第22巻)
<本文>
死刑は廃止すべきである、と私はつねづね思っている。たしかに、世の中が一定の秩序を保っていくには、法による裁きは、欠かすことができない。しかし、その裁きが円滑に運用されていくには、根底に、人間への信頼感がなければならないと思うからだ。
日蓮大聖人の御遺文集に「無顧の悪人も猶妻子を慈愛す菩薩界の一分なり」と仰せのように、いかなる悪人でも、心の底には人を愛し、人を慈しむ心根を秘めているものである。その点への信頼なくして、どんなに法による規制を強めても、結局は、空転を免れない。ところが、死刑制度は、そうした人間の可能性を、いっさい閉ざしてしまう。人間不信の産物であると思わざるをえないのである。
だれもが、極悪人でさえもがもっている菩薩の心、さらには仏の心。この点について、法華経には“貧人繋珠の譬え”という譬喩が説かれている。 ──昔、あるところに一人の男がいた。彼には、役人をしている裕福な友人がいる。ある日、男は、その親友の家に遊びに行き、酒や料理のもてなしを受けた。そして、すっかり酒に酔いつぶれてしまう。ところが、親友は急に公用ができて、旅立たなければならなくなる。やむなく親友は、酔いつぶれた男の服の裏に、どんな願いでもかなえられる“無価の宝珠”を縫いこんでおく。眠りこけている男への最高の贈り物をしたのであった。しかし、男は親友から宝珠を贈られたことも知らず、やがて諸国を放浪する身となる。永い歳月が過ぎる。すっかり貧しい身なりで、彼は親友と再会した。驚いた親友に教えられて、彼は初めて自分が、素晴らしい宝珠を持っていたことを知ったのである。
これは、仏界という尊極の生命の開発を忘れ、低い悟りに満足していた釈尊の弟子たちが、愚かさを反省しつつ語った物語である。
この尊極無上の生命を“宝珠”もろとも消し去ってしまう権利はだれにもない。しかし死刑においては、あたかも当然の権利であるかのように、国家権力の名のもとにそれが正当化される。その傲慢さゆえに、私は、死刑は無意味である、と主張するのである。
“貧人繋珠の譬え”を、さらに広く、そして日常的に解してみたい。たとえば“きめつけ”である。子どもの些細な失敗をとらえ、ただ「ダメな子ね」ときめつける。大人同士でも、ちょっとした諍いから、きのうまで談笑していた隣人が仇のように憎くなったりする。きのう親しき隣人が真実の彼(女)であるのか、それとも、きょうの彼(女)の姿が真実なのであろうか。そんなことはおかまいなしに、感情的なきめつけに走る。売り言葉に買い言葉で、相手もそれに応ずる。“宝珠”の存在などどこへやら、低次元のやりとりを繰り返し、お互いに傷つけ合う。そうした事例は想像以上に多いものだ。
相手の“宝珠”が見えないのは、自分自身の“宝珠”に気づいていないということだ。──ゆえに、互いにこの一点を凝視すべきだと思えてならない。
子どもや隣人は、ある意味では、自分を映し出す鏡であるといってよい。相手が悪いときめつけてみても、その悪は相手の実像とは関係なく、みずからの命の影の部分であることが意外に多い場合がある。
吉川英治の『宮本武蔵』(講談社)のなかで、武蔵が少年・伊織に、富士山を眺めながら、次のように語っている。
「あれになろう、これに成ろうと焦心るより、富士のように、黙って、自分を動かないものに作りあげろ。世間へ媚びずに、世間から仰がれるようになれば、自然と自分の値うちは世の人が極めてくれる」
私はこの富士山のようにどっしりと、悠々自適の日々を送っている年配の婦人を数多く知っている。彼女たちの笑顔は、例外なくさまざまな風雪をとおして磨き抜かれた“宝珠”の輝きを放っているものだ。
◆第四章 現代の目標◆
「文明・西と東」クーデンホーフ・カレルギー(全集102)
<本文>
生命の尊重
池田 今日、強大な国家権力は、国民の生命に対して、生殺与奪の権利をもっています。それは戦争と死刑の二つです。
戦争については、これまでいろいろ論じてきましたので、さしおくとして、死刑という問題について考えてみたいと思います。
私は、生命の尊厳という理念を貫くからには、死刑も当然、廃止されなければならないと考えます。
クーデンホーフ 私も死刑には反対です。しかし結局、人間は、みんな死刑を宣告されているようなものです。所詮、人が人の命を奪うことはできません。ただ、人の命を縮めるにすぎません。
しかし、私は、非人道的な不法・不当な理由で殺人を犯した人を死刑に処すことには、なんら反対しません。
池田 私は、裁判が仮にどれほど厳正公平に行われたとしても、死刑というのは、根本的に誤りであると思うのです。
どれほど科学主義・合理主義が強調されても、人間は所詮、不合理な存在で、日常生活においても多かれ少なかれ、およそ過ちを犯さない人間などというものはありません。つまり、人間を誤った裁判によって誤って死にいたらしめたならば、それは殺人罪と同じことになります。
あなたが言われるように、確かに人間は、生まれながらにして死刑の宣告を受けているようなもので、いつかは死ななければなりません。死刑は、ただそれを早めるだけかもしれませんが、そうした早めさせる権利は、だれももっていないはずです。
生命を縮めさせること、死を早めさせることが軽い意味しかもたないとしたら、殺人行為についても同じことになり、もはや大した罪ではなくなってしまうでしょう。
自分の定まった人生を他人に妨げられないで生きる権利、つまり、生存の権利はこのうえない尊いものです。もし、一人一人の生存権が至上のものであるならば、これを侵すことは、どのような大義名分があるにせよ、罪悪とならざるをえません。
生命の尊厳とは、他の何ものによっても代えられない、いかなる権力をもってしても侵すことができない、ということを意味すると思います。
人間社会は、生命の尊厳を、もはや動かすことのできない、根本原理として認めながらも、国家に対しては、生命の尊厳を侵す権利を与えつづけているというのが現実ではないでしょうか。これこそ現代における最大の誤りであり、ここに一切の矛盾と悪の根源があると私は考えます。
こうした観点からも、今日行われている死刑制度について、深い疑惑をいだかざるをえないのです。
この生命の尊厳観に立って、国家は、死刑のみならず、さらに戦争という重大殺人権を放棄すべきだと、私は主張しております。個人による凶悪犯罪を一掃する道も、あるいはそこから開けるのではないかと、私は思うのです。
一般に、死刑を廃止すれば、犯罪が曽えるのではないかといった議論もありますが、それは、人間の本性を″悪″と決めて、それを抑制するには権力以外にないという考え方、あるいは死刑という恐怖の処置によって犯罪を防ぐ以外にないという考え方の表れだと思います。
しかし、人間の心は″悪″のみでもなければ、脅かしによってしか抑制できないような愚かな存在でもありません。人間は、本来、善悪の両面をそなえていますし、それを自制できる英知もそなえています。
一人一人が、生命の尊厳に目を開き、そこに因果律にもとづいた″生命の法則″が厳然とあることを知ったとき、犯罪がいかに恐ろしいことであるかは、刑罰で脅かさなくとも生命の奥底から判然とするはずだと思います。
クーデンホーフ 私は、死刑よりもむしろ拷問に強く反対します。
第二次大戦中、私はあやうくナチの手を逃れて、スイス、イギリス、アメリカヘと亡命しましたが、私自身は、ナチの手で殺されることは恐れませんでした。しかし、ナチの拷問は恐れました。この恐ろしい拷問はなくしたいものだと思います。
ナポレオンとビスマルクの時代、約百年にわたって、拷問が禁上になったことがあります。しかし、二十世紀に入ってから、ふたたび復活しました。多くの人が死刑には反対しますが、拷問はしかたがないと受けとめているようです。日本がそういう国にならないことを望みます。
池田 話は変わりますが、生命の尊厳の問題に関連して、先進国における爆発的なモータリゼーションは、たとえば、日本では″交通戦争″とか″走る凶器″という言葉まで生みだしています。
日本で、一九六九年の交通事故の死者が、一万六千七百人に達し、今や、物質文明に支配された人間性喪失時代を象徴している感があります。その解決策について、ご意見がありますか。
クーデンホーフ 年間交通事故死が一万六千人以上というのは恐るべき数字ですね。
一つの案として、日本は富める国になったわけですから、とくに、歩行者の人命を守るために地下道や歩道橋などの安全施設をたくさんつくるべきだと思います。
現在、ヨーロッパでは、このような対策が大規模に行われていますが、歩行者よりも、まだ車のほうが優先されている傾向があります。
パリのエトワール広場には地下道があって、ここはかつて、人身事故でひどいところでしたが、ようやく歩行者の安全が保証されるようになりました。中央・地方の政府、議会は、歩行者を守るための安全施設を最優先で増やしていくべきだと思います。
人間性喪失とコンピューター
池田 現代文明の直面しているさまざまな問題をつきつめていくと、結局、人間性の喪失という問題に集約されると思います。科学技術、産業が発達し、社会が高度に発展すればするほど、人間のかけがえのなさ、尊さというものが失われていく傾向があります。
本来、文明が人間から出発したものである以上、人間に帰着すべきものです。
ところが、物質的豊かさとか、カネとか、権力とかいったものが中心になってしまって、人間はそれらの目的に奉仕する下僕になりさがってしまった感があります。
私は、人間をふたたび文明の中心に位置づけして、学問も、技術も、政治も、経済も、産業も、まったく新しく立て直す必要があるのではないかと考えております。
先にあなたは、第一次技術革命に対して、新たに第二次技術革命が行われなければならないと言われましたが、それは、どのような形で行われるべきだとお考えですか。
クーデンホーフ 人間性の喪失こそ人類の直面している最大の危機である、というご意見には、私もまったく同感です。産業や科学技術は、ますます発達していくことでしょう。
しかしこうした発達の結果が、すべて人間性の喪失に結びつくとは考えません。私は人間の英知を信じます。
また、よく″古き良き時代″と言いますが、これは金持ちにとっての古き良き時代だったのであって、貧しい人にとっては″古き悪しき時代″だったと思います。
池田 同じく人間性の問題ですが、コンピューターの登場によって、将来の国家は国民一人一人に関する、あらゆる情報を集めることができ、しかも、容易に抽出したり、活用したりできるようになるだろうと言われています。
これは、かつてない強力な中央集権的な統治機構の出現を意味するわけです。そうなれば、個人のプライバシー、人間の尊厳、主体性に対して非常な脅威になると思います。この点あなたのお考えはいかがでしょうか。
クーデンホーフ コンピューターは人間の自由にとって大きな脅威となるでしょう。もしも超全体主義国家によってフルに活用されるところとなれば、その強力な手先となることは間違いありません。
つまり、国家によって、すべての人間が完全に掌握され、国家がある種の全体的人格をもつようなことになれば、これは、人間から、あらゆる自由を奪うことになり、すべての人間の尊厳が完全にそこなわれることになります。
池田 それは恐るべき非人間的な社会と言わねばなりません。
われわれは科学の進歩が与えてくれる便利さとか、能率の良さなどによって、それが無条件に人間の幸福生活にプラスするものと思いがちですが、便利さや能率の良さが、われわれを支配するために悪用される危険性を秘めていることに、気づかねばなりませんね。
クーデンホーフ この点をさらに掘り下げて考えてみますと、こういった事態は宗教と道徳的基盤が危機にさらされた結果、起きるものとも言えましょう。
もし、すべての宗教が行き詰まり、それに代わるべき新しい宗教も、新しい道徳的原理も生まれてこないとしたら、こうした事態が現実となり、その結果は、コンピューターや唯物思想によって、すべての社会がならず者の集団と化してしまうでしょう。
万一、そんなことになれば、この世界には、二つの階級――武装した少数派と、武器を持たない市民の多数派――だけしか存在しなくなってしまうことになります。これは軍事的独裁、軍事国家、警察国家を意味します。
一つの国で、無政府主義と専制主義のいずれを選択するかということになれば、無秩序の社会というものは本来、成り立ちえませんから、結局、専制主義になり、独裁者を出現させることになるでしょう。
仮に無政府主義が、現代の産業化社会を支配したならば、ただちに、あらゆる生産や流通に破壊と混乱を与え、集団飢餓状態にまで追い込むことは必至です。したがって、人々は、無政府主義よりも、むしろ専制主義のほうをとるという結果になるのです。
池田 人間の尊厳を脅かすものは、結局、人間自身です。では、その人間をそうさせていくものは何か――帰するところ、思想であると言えます。逆に言うと、人間性の確立に向かわせていくものも、やはり、思想ということになりますね。
クーデンホーフ 私の考えでは、唯物主義は、あらゆる倫理的価値の基盤を破壊し、専制、武力統治、軍事的独裁、全体主義国家へと、直線的に結びつきます。
自由は、市民が自由の権利を享受するに値するとき、初めて生きてくるものです。自由の権利に対して資格のある市民ならば、警察の取り締まりがなくとも、法律を遵守し、互いに自制しあって治安を保つことができます。しかし、ならず者の世界では、自由は蹂躙され、死滅するしかありません。
スイスは小国ですが、その自由の理想の伝統のもとに、自由な人々が、平和と繁栄のうちに生活しており、民主主義国の一つの立派な模範と言えます。
真理と価値
池田 現代文明に人間性喪失をもたらした原因を考えるとき、私は人々の行動の基準である価値観に問題があるように思います。
価値観とは、人々の日常的な行動における判断の基準であり、あらゆる文化的、学問的探究や創造的活動の方向を決める″ものさし″とも言えるでしょう。
従来、ヨーロッパの伝統的な唯心哲学の価値観では、カントの説いた真・善・美が人間の求めるべき価値の内容とされてきたように思います。
近代以後、真理を探究する科学が大きな比重を占めるようになり、しかもその科学によってもたらされた″真理の発見″が、人類の運命をも支配するにいたりました。
真理の発見は、確かに幾多の恩恵をもたらしましたが、しかし、同時に、取り返しのつかないマイナスにもなってしまった、というのが現代文明の実情ではないかと思います。
これを、よく考えてみますと、真理は元来、認識の対象であって、評価の対象ではない、ということを無視したのが原因とは言えないでしょうか。
もちろん、正しく評価するために、真理を知る必要がありますが、真理そのものはプラスの価値にもなれば、マイナスの価値にもなります。それを単純に、真理をそのままプラスの価値としてきたことが、人類に不幸をもたらす原因の一つとなったと思いますが、この点あなたのご意見はいかがでしょうか。
クーデンホーフ ヨーロッパにおいて、真理の価値が過大評価されてきた、というあなたの批判には、私も、まったく同感です。真理は科学にとっては、非常に重要ですが、芸術にとっては、ほとんど意味がなく、ましてや道徳にとっては重要ではありません。
ヨーロッパでは、どの宗教にも、ほかの宗教にはない真理があると信じられています。預言者の説いた教えだけが、唯一の真理であって、他の教えはことごとく誤りである、ということです。
だから人々は、あるいは偽りであるかもしれない真理のために、みずからの生命を犠牲にしたり、他人をも殺したりするわけです。
中世ヨーロッパのカトリックでは、聖書によって真理とされたことがらに異議を唱えるものに対して拷問が行われました。
しかし、カトリックだけを責めるのは不公平でしょう。プロテスタントの創始者の一人であるカルヴァンは、三位一体説を否定したというだけの理由で、スペイン人セルヴェトを死刑に処しました。真理への盲信のために西洋は狂信と不寛容に走ったのです。
池田 私どもも、教義のことについては、まったく同じ考え方をもっております。ただ、あえて言うなら、宗教が教義上の問題で潔癖を貫くのは当然のことでしょう。
しかし、それはあくまで教義自体についてであって、人間や個人の尊厳に対しては、最大に寛容でなければならないと考えます。その点、アジアの仏教や儒教は、この寛容さを非常に大事にしてきたと言えるのではないでしょうか。
クーデンホーフ 私は、日本の仏教と神道が、狂信的にならず、互いに寺社を共有してきた事実を、高く評価してきました。
ギリシャの賢者ソクラテスは、真理に対して別の見方をしていました。「私が知っている唯一のことは、私が何も知らないということである。しかし、人々は、このことすら知らない」と言っております。
キリスト教徒は、たいてい、シナイ山上の十戒の一つが「汝嘘をつくなかれ」であると信じていますが、じつは間違った解釈です。この戒律の正しい読み方は「汝謗るなかれ」ということで、別のものです。
嘘のない人生なんて、およそ耐えられないでしょう。もし、今日、超大国の首脳が会議を開き、それぞれが真実であると考えていることを、そのまま語ったとしたら、明日にでも世界大戦が始まるかもしれません。しかし、幸か不幸か、外交は真実ではなく「ていねいな嘘」を前提としています。
もちろん真実を愛する人が、道徳的に嘘つきよりも優れているのは当然です。人間にとって、誠実は偉大な徳性です。しかし、真理や真実が美と同じように徳性であると考えるのは誤りです。
この点からも、真理を最高の価値の一つとするヨーロッパの偏見を、あなたが指摘されたことは正しいと思います。
池田 多くの人が、真実という問題について迷うことは、つねに、真実を話すべきかどうかということだと思います。この点、あなたは、どう考えますか。
クーデンホーフ 私は、だれしも自分自身に対しては誠実であるべきであり、また臆病にかられて、人を中傷したり、嘘をついたりしてはならないと思います。しかし真実を話すと、相手を傷つけることになる場合もあり、やむをえず嘘をつかなければならないこともあります。
われわれは、社会生活において、真実と偽善、または真実と礼儀、というように、二者択一を決めなければならない場合にぶつかります。こういうような場合に、つねに本当のことをしゃべってしまう人は、男女を問わず、じつは、人間に値しないのではないでしょうか。
幸福と平和
池田 次に、幸福ということについてですが、人間は、だれしも幸福を求めて生きていると言えます。
そこで、いかなる状態を幸福というか、幸福とはいったい何かということについては、種々の議論があります。あなたの幸福論をうかがえませんか。
クーデンホーフ 私は、調和こそ幸福の主な源泉であると考えています。調和は数学や、幾何学、音楽などにおいて大切な要素とされており、また均衡、対称という概念とも密接なつながりがあります。
調和は第一に、美の基本的な要素であり、さまざまな幸福を創り出します。われわれ自身の中の調和、家族や友人との間の調和、社会環境との調和、食欲と食物との調和、身体の調和そのものである健康、職業と経済生活との調和、そして平和と繁栄による国際的な調和などです。
調和とは、われわれの生活が恐怖政治によって支配されていないことを意味します。
しかし、調和は幸福の唯一の形態ではありません。それは、どちらかといえば、女性的な価値で、むしろ勝利と支配を求める男性の本能とは対照的なものです。
ライオンはカモシカを殺したときに幸せを感じ、英雄は敵を倒したときに幸せを感ずるでしょう。これらは、男性的な幸福と言えるようです。
しかし、ここで考えねばならないことは、幸福は善に結びつかないかぎり、それだけでは道徳的価値とはならないということです。幸福は生活の価値の一つであり、われわれにとって行動の原動力となるものです。
池田 人間は、これまで科学技術が発達すれば、より幸福になると考えられてきました。しかし、科学技術の発達が必ずしも人間の幸福に結びついているとは言えません。この問題については、どうお考えですか。
クーデンホーフ 先に、私は、科学技術や産業の発達が、人間性を失わせるとは考えない、との意見を述べましたが、それは、こういうことです。現代は、百年前に比べれば、いろいろな面で条件が良くなっていると思います。
第一に、近代産業と科学技術の発達は、多くの″手″を重労働から解放しました。人力車を引くより、タクシーを運転するほうが容易であり、能率的です。
第二に、人々は科学の発達によって、かつてないほど多くの自由な時間をもてるようになりましたが、さらに、今後の技術革命はたんなる生産力第一主義でなしに、公害を制圧し、労働をできるだけ快適なものにし、人間の尊厳と幸福を高めるものでなければならないと考えます。
機械が行うことのできる作業は、できるだけ機械に任せます。しかし、どうしても労働によらなければならない仕事や、必ずしも快適ではない仕事にたずさわらなければならない人たちには、余分に自由な時間を与えて、その苦労をおぎなってやるべきでしょう。そうしてやれば、たとえ仕事自体は楽しくなくても、余分のレジャー・タイムでつぐなわれるでしょう。
第二次技術革命は、もちろん″公害に対する戦い″となるべきもので、そのために必要とあれば、生産を抑えることもやむをえないでしょう。なぜなら、生産自体は最終目的ではなく、美と幸福をもたらすための手段なのですから。
池田 幸福に関連して、次に平和ということについて、ご意見をうかがいたいと思います。
人間の世界、ひいては生あるものの世界は、一面では一切が戦いの歴史であるとも言えると思います。人間のこの社会も、武器による戦いではなくとも、経済の戦争、思想の戦争がつづいています。平和といっても、いかなる状態をもって平和とするかは、きわめてむずかしい問題だと思います。
私は、生命の尊厳がすべてに優先する状態、すなわち、いかなる目的のためにも生命が犠牲にされることのない状態が″平和″というものではないかと思いますが、いかがでしょうか。
クーデンホーフ 平和とは何かという問題に答えるのは、幸福とは何かという問題に答えるのと同じようにむずかしいことです。平和とか幸福とかいうような基本的な価値は、論理や頭では説明できないもので、心によって感じとる以外にないと思います。
生活とは、つねに闘争です。人間同士の間でも、動物の世界でも生命が存続するかぎり、闘争がつづきます。この事実を遺憾だとする理由は何もありません。
闘争は、あらゆる競争の根底にあるものであり、完成への道程です。最も強いものが勝ち、最も美しいものが生き残ることが、進歩と繁栄の秘訣です。
闘争は、騎士精神でもあります。日本の武士道は、闘争を演劇にまで高めました。男は皆戦わなければなりません。唯一の問題があるとすれば「騎士のごとく戦うか、悪人として戦うか」でしょう。闘争を美化するのは、フェアプレーのみです。
池田 私は思うのですが、宗教だけが、真の世界平和を保証することができるのではないでしょうか。
クーデンホーフ そのとおりです。政治ではありません。
私は、正当防衛のための行為が犯罪であるとは思いません。
これまでも、侵略戦争は別として、防衛戦争は必ずしも非道義的とはみなされておりません。この侵略戦争をすべて絶滅するために国際政治は努力をすべきです。
長期にわたって平和を維持することが、決してたんなる理想ではないという証拠に、スイスとスウェーデンの例があります。しかし、真に世界平和を保証する唯一の道は結局、宗教以外にはないと思います。
宗教ないし道徳的な価値というものをもたない人々は、恐怖政治によって飼いならされてしまうことになるでしょう。聖職者は警察官によって取って代わられ、自己統御が警察統制によって取って代わられてしまいます。私は、人類の将来は、まさに、宗教の興亡いかんにかかっていると思います。
女性と政治
池田 あなたは、女性こそ平和の母体である、と言われていますが、私もまったく同感です。しかし、その女性の特質は、今日必ずしも十分に発揮されているとは言えません。日には男女平等が叫ばれても、現実は、両性の地位にあまりにも大きなギャップがあるからです。
その原因は、第一に、それを支える理念の欠如にあり、第二に女性の特質についての認識の欠如にあると思います。
私は、その意味からも、男性と女性がそれぞれの特質を理解しあい、とくに女性に対して、もっと社会的に進出する機会が与えられるべきだと考えます。
クーデンホーフ 私の持論は、女性がより大きな役割を果たす機会が与えられれば、それだけ世界が平和になるということです。なぜなら、女性は本来、平和主義者だからです。
子どもを見ても、女の子は、皆人形で遊びますが、男の子の遊びは、どこでも戦争ごっこです。世界中、どこの国でも、男性が興味をもつことは、相手を負かすことです。
これは映画を見てもわかるとおり、最近の映画の二つのテーマは殺人とセックスです。スパイ映画やアクションものでも、興味をわかせるのは殺人の場面です。これは何千年も前から、男性の殺伐な欲求でした。野獣を殺し、敵を倒して、家族と自分を守るのが男性の役割だったのです。
だから男性が、すべて生まれながらの闘士であるというのは、きわめて自然な姿です。男性とは、立派であればあるほど、ますます戦士であるわけです。
男性は頭の中では平和主義者でも、心ではやはり戦士のままです。だから、男性の支配がつづくかぎり、地球上の平和はありえないでしょう。
池田 男性と女性の特質がともに十分に発揮されて、本来の調和が保たれていくことになるわけで、それが真の意味の平等だと私は思います。そこから、女性の具体的な役割も出てくるわけでしょう。
クーデンホーフ そうです。女性は男性よりも、はるかに誠実な平和主義者です。
女性は生命をはぐくみ育てるのが本能であって、殺戮を望みません。それは、自然が女性に、男性にはできない使命を与えたためです。たとえば、世界中どこでも、婦人運動はつねに、平和運動と密接につながっているはずです。
池田 いつの時代でも、戦争で最も苦しむのは女性の側です。私も、長兄の戦死の知らせがきたとき、悲しみにじっと耐えていた母親の姿をいまだに忘れることができません。
そこで私が強調したいことは、女性の幸、不幸の姿こそ、一つの社会、一つの国が安泰であり、健全であるかどうかの具体的な表れだということです。そして、これこそ、人類の未来にとって重要な道標となるものだと思います。
さらに言えば、女性の幸福を保証できる指導者や為政者こそ、本物の指導者・為政者だというべきでしよう。
クーデンホーフ 私は、女性がいっそう政治に力をもつようになることを願っています。政治面で女性に開放されている仕事はたった一つ、女王という任務だけだと言われ、政治家、官吏、外交官など、いかなる政治上の仕事からも、概して女性は除外されてきました。
今日なお、多くの男性は、女性に政治能力がないと考えていますが、歴史はまさにその逆であることを示しています。
数こそ少ないですが、ヨーロッパを支配した女王たちは、いずれの国においても、最も優れておりました。
オーストリアの、最も偉大な国王は、マリア・テレサ女王で、その前にも後にも、彼女の右に出る国王はでていません。また、イギリスでは、エリザベス一世女王、ロシアでは、キャサリン女帝、スペインではイザベラ女王が、それぞれ最も偉大な国王でした。
女王のほうが優れていたことは、このように歴史の示すところです。したがって、女性が政治家として、また指導者として劣るという考え方は、まったく偏見です。私は、反対に女権拡張運動こそ重要な世界平和への運動であると信じています。
池田 現実に、インドのI・ガンジー首相、セイロン(=現スリランカ)のバンダラナイケ首相、イスラエルのメイア首相など、優れた婦人政治家が現れてきているのは喜ばしいことですね。
女性こそ、本来生命をはぐくむ特性をもった平和の担い手であり、だからこそ女性は、その特性をもって、積極的に社会に進出していくべきだ、とのご意見には、私も賛成です。
しかし、そのためには、女性のみならず、男性も認識を変え、意識を改めていかなければならないと思います。それには、どうしたら良いか、何か具体案がありますか。
クーデンホーフ 私は、女性のみによる政党結成を提案したいと思います。世界平和のために、女性だけが立候補できる政党です。
女性の有権者に対しては、当然、最優先で投票するよう呼びかけます。もちろん、男の有権者も女性候補者に投票できます。地球上の女性は、男性より数が多いわけですから、そうなれば、女性が国会や内閣で過半数を占めることも、決して不可能ではないでしょう。
池田 私もそう思います。それには、やはり私は、今日、男女ともにいだいている――女性には、政治的才能がもともと欠けている――という先入観を、きっばり捨てることだと思います。
そのかわり、政治の場に立つ女性は、その自覚に立つと同時に、みずからも思うぞんぶんに女性らしい持ち味を発揮して、その声を政治に反映していけるようであってほしいと思います。
女性の役割
池田 ところで、女性は、互いに力を合わせるという面が非常に苦手だと、しばしば指摘されるところです。あなたがおっしゃる女性の力をこの社会に反映していくためには、女性の団結ということが大事になってくると思います。
利害の打算、醜い憎悪や嫉妬の感情に汚されない、女性同士の美しい団結の花を咲かせ、人間関係の不信と憎悪の世界を、信頼と調和のリズムで包容し、転換していくこと、これは女性の団結に対する私の希望でもあるのですが……。
今、女性は平和の担い手として、力強く、歴史の主役を演じなければならない時を迎えています。
本来、平和主義者としての女性の面目をいかんなく発揮するためには、決して自分中心の狭い世界にとどまっていてはならないと思います。そして、男女双方の特性があいまって、初めて調和ある世界が築けるわけです。
本性的に生命の尊厳を知っている女性こそ、現代という生命軽視の風潮の時代にあって、よりいっそう、社会の諸活動に参加して、強いリーダーシップをもっていかなければなりません。
そのためには、女性は、もっと社会的自覚と責任に立つべきだと考えます。
歴史を振り返ってみても、たとえば戦争の絶滅という問題について、女性の声が力強く反映されたとは言えないのではないでしょうか。
それは、男性と同じような権利が与えられていなかったことにもよりますが、女性の側にも責任があったと思います。つまり、女性が、それぞれの小さな殻に閉じこもっていて、積極的に社会への視野を広げなかったことにも原因があるのではないで
しょうか。
女性も、あくまでも主体的に、社会の諸問題に取り組んでいく姿勢が、今後ますます大事だと思います。
クーデンホーフ 女性が戦争を憎む一方で、強き者、戦士を愛するというのは、おもしろいパラドックス(逆説)です。
女性が強き者を愛するのは、男性の保護のもとにありたいという本来の願いから出たものでしょう。ですから、女性はえてして平和主義者よりも、英雄的な戦士を選ぶという危険があります。
このことから考えると、私が提唱した女性のみによる政党ができたら、女性の有権者は同性の候補のみを選ぶようにしたら良いと思いますね。
いずれにしても、女性が参政権を得たことは、恒久平和に向かっての決定的なステップとなったと言えましょう。
池田 最近のいちじるしい傾向に、婦人の家事労働の軽減があります。こうした傾向は、さらに進むでしょう。そこで、自由時間が増えてきたという新事態に、女性はいかに対処すべきか。また、社会は婦人のエネルギーをどのように吸収すべきかということが重要な問題となってきます。
そこで、女性の権利と力について、ご意見をうかがいたいと思います。
クーデンホーフ 私は、二つの事実の認識の上に立たなければならないと思います。
第一に、男性と女性とは極端に違うということです。たとえば、日本人の男女の違いは日本人の男性とヨーロッパ人の男性の違いよりも大きいと言えます。
男女は互いにかけ離れた二つの世界に属しています。自然は別々の責任や義務を課しているわけですから、本来、両性は同じ責任・義務を果たすことができません。
女性の主な仕事は、子どもを産み、育て、その一生の初めの大切な時期に教育を与えることです。
しかし、子どもが成長してしまうと、時間に余裕ができてきて、あとはせいぜい孫の子守りをするぐらいしかやることがなくなってしまいます。こうした婦人たちこそ、男性を助け、アドバイスを与え、政治的活動に入っていくべきです。
私は、世界中で女性が議会と政府の半分を占めるようになれば、世界平和は盤石になるだろうと考えております。
第二に、男性が女性よりも知性的だというのは、大変根の深い偏見だということです。この偏見は打ち破らなければなりません。女性より男性のほうが、有名人が多いのは事実です。しかし、それは女性に教育の権利と機会が平等に与えられていなかったことによるものです。
もしも、ラジウムの発見者キュリー夫人が、もう百年早く生まれていたとしたら、おそらく勉学する機会が与えられなかったことでしょう。またもし仮に、ニュートンが女性であったとすれば、せいぜい料理上手の一介の主婦で終わっていたかもしれません。
しかし、今や多数の国において女性は勉学する権利と機会を享受しているわけですから、女性は知性においても男性と平等であると認められるべきです。現実には、しかし、まだ政府、議会、企業など男性支配が一般的です。
ただし、一つ例外があります。それは秘書の仕事です。ヨーロッパでは、過去二十年の間、秘書の仕事も男性によって占められていましたが、今日では、女性がこの仕事を征服しています。
もう一つの興味ぶかいことは、自動車が普及し始めたころのことですが、女性に運転を許すべきではない、という議論がありました。ところが、自動車事故の統計によれば、女性のほうが男性より事故が少ないことが明らかとなっています。
スウェーデンでは、女性の事故率が大変低いことから、自動車保険料が男性よりも一〇パーセントも割り安だということです。
池田 女性の秘められていた力がしだいに開発されてき、また、そのことについて男性も認識し始めたということでしょう。ともかく、固定した枠をもうけて、人間をそこに押しこめてしまうことは、非常に危険なことだと思います。
◆死刑廃止について◆
「平和への選択」ヨハン・ガルトゥング(池田大作全集第104巻)
池田 ところで、死刑制度の是非については、長い間、賛否両論
から言えば、私は、仏法者の立場から死刑制度には反対です。何と言っても、死刑は
<本文>
池田 ところで、死刑制度の是非については、長い間、賛否両論がかわされています。結論から言えば、私は、仏法者の立場から死刑制度には反対です。何と言っても、死刑は国家権力による暴力の一つの極限的あらわれであるからです。
また一般に死刑廃止反対論者が主張するように、はたして、悪質な犯罪を抑止することができるかどうかには疑問があります。統計的にも、死刑のない社会に凶悪犯罪が多いとは言えないようです。また、裁判における誤判がありうるのも事実です。何よりも、人為的に生命を奪う権利は、何人にも、どのような理由によってもありえないことと私は考えます。文豪ヴィクトル・ユゴーは、あの動乱の時代においてさえ死刑廃止を強く主張しました。彼は死刑囚にこう言わせます。「おちつきはらって、儀式ばって、よいこととして、私を殺す。ああ!」(ヴィクトル・ユゴー『死刑囚最後の日』豊島与志雄訳、岩波書店)。ユゴーは、終身刑でことたりるとしています。また、囚人の無辜なる家族を地獄におとすことなども、問題点としてあげています。
たしかに、ゲーテが「社会が死刑の法律を廃止すれば、すぐまた一種の正当防衛がはじまる。すなわち、仇討ちの復活である」(『ゲーテ全集』10、大山定一訳、人文書院)と述べているように、因果応報への欲求は、人間に本然的なものです。しかし、人間が人間を裁くという情念をつきぬけた、ある種の強者の境涯――ガンジーが「敵を赦すことは敵を罰するより雄々しい」と語っているような境地を想定し得ずして、非暴力を論ずることはできないと思うのです。
ガルトゥング いやしくも“文明社会”の名に値する社会であるならば、そこでは死刑という蛮行をほしいままに行うようなことはないでしょう。この重要なテーマについては、犯罪と刑罰という一般論の枠組みの中で考えてみれば、あるいは得るところがあるのではないかと思われます。何よりも重要なことは、この問題を「水平的」にあつかうか、「垂直的」にあつかうかです。前者の場合は、悪事を働いた者が自分の犯罪行為を正面から直視して、何が間違っていたのか、またどうすれば将来のためにカルマ(業)を改善できるかを見いだそうとします。罪を犯した側は、その罪を償うために、盗んだ金を返す、負わせた傷を癒してやる等の行為をしなければなりません。実際に、世の中の悪事というものは、見かけよりも多くの場合、このような形で解決されているものです。この「水平的」なアプローチは、和解と自己改善を結び合わせた、成熟した方法です。ところが現行の法体系は、そのようにはなっていないのです。
この「水平的」なアプローチは、だれでも対処できるというものではありません。強姦された女性、あるいは殺害された人の遺族に、加害者を許すよう求めるのは、あまりにも過大な要求となります。これらの人たちが、復讐を望むのも無理からぬことです。事実、「禁固」の目的は、犯罪者を拘禁という形で罰するとともに、復讐を望む人間が近づけないようにして、さらなる犯罪を防ぐことにもあります。「垂直的」な犯罪処理法は死刑においてその極に達しますが、この制度によって、神の属性としての生殺与奪権が国家に与えられるのです。
あなたと同じく、私も死刑に反対です。それは、だれ人にも生命を破壊する権利はないと信じるからです。さらに言えば、死刑は殺人を合法化するがゆえに、私は死刑に反対です。おっしゃるとおり、死刑は犯罪を防ぐどころか、むしろ助長しているように思われます。そのうえ、国内で生命を奪うことを容認するような国は、国外ではさらに躊躇なく生命を奪うことでしょう。アメリカが犯してきた何百回もの軍事介入は、私が言わんとしていることの適例なのです。
◆「原水爆禁止宣言」に思う◆
2001.9.7 随筆 新・人間革命4 (池田大作全集第132巻) の尊厳を第一義とする仏法者として、死刑制度には絶対反対であった。それでも、あ
<本文>
ウィーゼンタール氏が、若者たちに警鐘を鳴らした言葉に、「文化と文明はごく薄い表皮でしかなく、その下には相変わらず私たちのなかの野獣が隙あらばと機会をうかがっている」(前掲『ナチ犯罪人を追う』)とある。
四十四年前、台風一過の天高く、爽やかな風が吹き渡るなか、戸田会長は、五万の同志を前に、「遺訓の第ことして、原水爆の禁止を宣言され、この思想を世界に広めよと青年に託された。
その宣言の核心は、原水爆を使おうとする発想の背後に隠された「爪」、すなわち、人間のなかに巣くう”魔性の生命″に、鋭くメスを入れられたところにある。
ウィーゼンタール氏の言う「私たちのなかの野獣」とはまさにこのことであろう。
さらに、先生は言われた。
「われわれ世界の民衆は、生存の権利をもっております。その権利をおびやかすものは、これ魔ものであり、サタンであり、怪物であります。
それを、この人間社会、たとえ一国が原子爆弾を使って勝ったとしても、勝者でも、それを使用したものは、ことごとく死刑にされねばならんということを、私は主張するものであります」
”原爆使用者を死刑に!″――もとより先生は、生命の尊厳を第一義とする仏法者として、死刑制度には絶対反対であった。それでも、あえて「死刑に」と叫ばれた。
それは、原水爆を保有し、使用したいという人間の己心の魔性それ自体に、朽ちざる楔を打ち込むためであった。
原水爆を「絶対悪」として断罪する思想を、いわば「防非止悪」の堤防として、人類の胸中深くに打ち立てようとされたのである。
「生」を守るために、その対極の「死」という言葉で、サタンの魔性の働きを砕き尽くさんと――。生命厳護という絶対の正義を実現する、信念の行動であったのだ。
6 当時、戸田先生の先駆的な「宣言」は、一般には少しも顧みられることはなかった。
しかし、その不滅の光は、四十四年を経て、今や大光となり、新世紀の世界を煌々と照らし始めた。
アメリカの「核時代平和財団」のクリーガー所長も、原水爆禁止宣言について、「今日もなお極めて重要である」と明言している。
私と所長とは、この夏、対談集『希望の選択』を出版した。そのなかで、所長は言われた。
「青年は『未来』です。青年は自分が受け継いでいく世界に、当然、発言権があります。核の脅威をなくすには、青年たちが大いに活躍しなければなりません」
青年よ、正義をさらに強く、広く叫べ!
そして、新世紀の創価の青年よ、永遠の平和への連帯を、断固と世界へ、未来へ結べ!
◆宣言◆
小説「人間革命」11-12巻 (池田大作全集第149巻) 死刑に」と叫んだのは、決して、彼が死刑制度を肯定していたからではない。彼は、
<本文>
彼は、悠然としてマイクの前に立っと、力強い声で語り始めた。
「天竜も諸君らの熱誠に応えてか、昨日までの嵐は、あとかたもなく、天気晴朗のこの日を迎え、学会魂を思う存分に発揮せられた諸君ら、また、それに応えるとの大観衆の心を、心から喜ばしく思うものであります。
さて、今日の喜ばしさにひきかえて、今後とも、難があるかも知らん。あるいは、身にいかなる攻撃を受けようかと思うが、諸君らに、今後、遺訓すベき第一のものを、本日は発表いたします」
五万余の観衆は、思ってもいなかった戸田の言葉に、耳をそばだてた。弟子たちは、「遺訓」という言葉に、何かただならぬものを感じた。しかも、それは、「難」と「攻撃」を受けることを予告したあとに、「遺訓すべき第一のもの」を発表すると、続いているのである。
歓喜につつまれた「若人の祭典」の終了にあたって、戸田が語ろうとする遺言とは何かを思い、人びとは固唾をのんで、次の言葉を待った。会場の空気は一変していた。
「前々から申しているように、次の時代は、青年によって担われるのである。広宣流布は、われわれの使命であることは申すまでもないことであり、これは、ぜひともやらなければならぬことであるが、今、世に騒がれている核実験、原水爆実験に対する私の態度を、本日、はっきりと声明したいと思うものであります。いやしくも私の弟子であるならば、私の今日の声明を継いで、全世界にこの意味を浸透させてもらいたいと思うのであります」
人びとは、ここで″原水爆のことか″と思った。
相次ぎ繰り返される近年の原水爆実験について、誰もが不安と怯えとをいだいていたことは確かであったが、多くの同志は、広宣流布という使命に立って、寂光土の建設を第一としていけば、それでよいのだという思いでいたことも事実であった。寂光土の建設がなされれば、原水爆などといった核兵器が存立するはずはないというのが、大多数の同志の確信であったのである。
しかし、広宣流布の道はいまだ遠く、その道程にあって、核の脅威が、日ごとに高まりつつあることは、誰もが実感していた。
そして、もし、原水爆が使用される事態になれば、広宣流布の道もまた、一瞬にして破壊されかねないという無残な予感に、心を痛めている人もいた。あの広島、長崎の悲惨な記憶が、いやがうえにも、不吉な予感を駆り立てるのであった。
原水爆の問題は、学会員にとって、避けがたい問題であったが、事が事だけに、自らの思考ではもてあまし、漠然とした不安に怯えながら、いかにすべきかを模索していたといってよい。
それを、今、戸田城聖は、核実験、原水爆に対して、彼の態度を明らかにし、声明を宣言しようというのである。しかも、その宣言を、彼の遺訓の第一のものとし、それを受け継いで、全世界に浸透させてほしいというのだ。
戸田は、毅然としていた。強い気迫のこもった言葉が、マイクを通して陸上競技場の隅々にまで轟いた。
「それは、核あるいは原子爆弾の実験禁止運動が、今、世界に起こっているが、私は、その奥に隠されているところの爪をもぎ取りたいと思う。
それは、もし原水爆を、いずこの国であろうと、それが勝っても負けても、それを使用したものは、ことごとく死刑にすべきであるということを主張するものであります。
なぜかならば、われわれ世界の民衆は、生存の権利をもっております。その権利を脅かすものは、これ魔ものであり、サタンであり、怪物であります。
それを、この人間社会、たとえ一国が原子爆弾を使って勝ったとしても、勝者でも、それを使用したものは、ことごとく死刑にされねばならんということを、私は主張するものであります」
戸田城聖は、まず、核兵器を、今世紀最大のの産物としてとらえた。「魔」とは、サンスクリットの「マーラ」の音訳であり、「殺者」「能奪命者」「破壊」等と訳されている。つまり、人間の心を惑わし、衆生の心を悩乱させ、生命を奪い、智慧を破壊する働きといってよい。
そして、この「魔」の頂点に立つものこそ、第六天の魔王であり、それは、他化自在天王といわれるように、他を支配し、隷属化させようとする欲望をその本質とする。
この観点に立つ時、人間の恐怖心を前提にして、大量殺裁をもたらす核兵器の保有を正当化する核抑止論という考え方自体、第六天の魔王の働きを具現化したものといってよい。
彼の原水爆禁止宣言の特質は、深く人間の生命に潜んでいる「魔」を、打ち砕かんとするところにあった。
当時、原水爆禁止運動は、日本国内にあっても、大きな広がりをみせていたが、戸田城聖は、核兵器を「魔」の産物ととらえ、「絶対悪」として、その存在自体を否定する思想の確立こそが急務であると考えたのである。それなくしては、原水爆の奥に潜む魔性の爪をもぎ取ることはできないというのが、彼の結論であった。
それは、いかなるイデオロギーにも、国家、民族にも偏ることなく、普遍的在人間という次元から、核兵器、及びその使用を断罪するものであった。そこに、この原水爆禁止宣言の卓抜さがあり、それが、年とともに不滅の輝きを増すゆえんでもある。
戸田が、原水爆禁止宣言のなかで、原水爆を使用した者は「ととごとく死刑に」と叫んだのは、決して、彼が死刑制度を肯定していたからではない。
彼は、九年前の四八年(同二十三年)に、極東国際軍事裁判(東京裁判)で、A級戦犯のうち東条英機ら七人が、絞首刑の判決を受けた時、次のように述べている。
「あの裁判には、二つの間違いがある。第一に、死刑は絶対によくない。無期が妥当だろう。もう一つは、原子爆弾を落とした者も、同罪であるべきだ。なぜならば、人が人を殺す死刑は、仏法から見て、断じて許されぬことだからだ」
また、彼は、しばしば、「本来、生命の因果律を根本とする仏法には、人が人を裁くという考え方はない」とも語っていた。
では、その戸田が、なぜ、あえて「死刑」という言葉を用いたのだろうか。戸田は、原水爆の使用者に対する死刑の執行を、法制化することを訴えようとしたのではない。彼の眼目は、一言すれば、原水爆を使用し、人類の生存の権利を奪うことは、「絶対悪」であると断ずる思想の確立にあった。
そして、その「思想」を、各国の指導者をはじめ、民衆一人ひとりの心の奥深く浸透させ、内的な規範を打ち立てることによって、原水爆の使用を防ごうとしたのである。
原水爆の使用という「絶対悪」を犯した罪に相当する罰があるとするなら、それは、極刑である「死刑」以外にはあるまい。もし、戸田が、原水爆を使用した者は「魔もの」「サタン」「怪物」であると断じただけにとどまったならば、この宣言は極めて抽象的なものとなり、原水爆の使用を「絶対悪」とする彼の思想は、十分に表現されなかったにちがいない。
彼は、「死刑」をあえて明言することによって、原水爆の使用を正当化しようとする人間の心を、打ち砕とうとしたのである。いわば、生命の魔性への「死刑宣告」ともいえよう。
当時は、東西冷戦の時代であり、原水爆についても、東西いずれかのイデオロギーに立つての主張が大半を占めていた。戸田のこの宣言は、それを根底から覆し、人間という最も根本的な次元から、原水爆をとらえ、悪として裁断するものであった。
宣言を述べる戸田の声は、一段と迫力を増していった。
「たとえ、ある国が原子爆弾を用いて世界を征服しようとも、その民族、それを使用したものは悪魔であり、魔ものであるという思想を全世界に弘めることこそ、全日本青年男女の使命であると信ずるものであります。
願わくは、今日の体育大会における意気をもって、この私の第一回の声明を全世界に広めてもらいたいことを切望して、今日の訓示に代える次第であります」
宣言は終わった。大拍手が湧き起こった。感動の渦が場内に広がっていった。
戸田城聖が、この原水爆禁止宣言をもって、第一の遺訓とした意味は深い。日蓮大聖人の仏法が、人間のための宗教である限り、「立正」という宗教的使命の遂行は、「安国」という平和社会の建設、すなわち人間としての社会的使命の成就によって完結するからである。
戸田は、原水爆の背後に隠された爪こそ、人間に宿る魔性の生命であることを熟知していた。そして、その魔性の力に打ち勝つものは、仏性の力でしかないことを痛感していたのである。
原水爆をつくりだしたのも人間なら、その廃絶を可能にするのも、また人間である。人間に仏性がある限り、核廃絶の道も必ず開かれることを、戸田は確信していた。
その人間の仏性を信じ、仏性に語りかけ、原水爆が「絶対悪」であることを知らしめる生命の触発作業を、彼は遺訓として託したのである。
以来、この宣言は、創価学会の平和運動の原点となっていった。
三ツ沢の陸上競技場に集った五万余の参加者のうち、子どもたちを除けば、戦争にかかわりのなかった人は、一人としていなかった。それだけに、原水爆実験の果てに、いつまた、あの戦争が勃発するかもしれないという強い不安に苛まれていたといってよい。
しかも、これから起こる戦争では、広島、長崎に投下された原爆を、はるかにしのぐ、大きな破壊力をもっ核兵器が使用されようとしているのである。もし、世界戦争が起これば、日本はもとより、世界中が廃墟となるであろうことは間違いない。
″もう、戦争はごめんだ″との悲願こそ、人びとの共通の感情であったが、そのために、学会員として、また、一人の人間として、何をなすべきかは、わからなかった。しかし、戸田のとの声明は、暗夜の海に輝く灯台のように、進むべき進路を照らし出したのである。
青年たちの胸には、この時、人類が直面した未曾有の危機を克服する、新たな使命の火がともされたといってよい。だが、それはまだ、小さな灯であった。その火が、人びとの心から心へと、燃え広がり、平和のまばゆい光彩となって、世界をつつむことを実感できた人は、皆無に等しかったにちがいない。
山本伸一は、戸田城聖の原水爆禁止宣言を、打ち震える思いで聞いていた。彼は、この師の遺訓を、必ず果たさなければならないと、自らに言い聞かせた。そして、戸田の思想を、いかにして全世界に浸透させていくかを、彼は、この時から、真剣に模索し始めたのである。
伸一の胸には、数々の構想が広がっていった。しかし、彼は、はやる心を抑えた。それが、創価学会の広範な平和運動として結実していくには、まだ、長い歳月を待たねばならなかった。
三ツ沢の陸上競技場での東日本体育大会に続いて、九月二十二日には、西日本の体育大会が、大阪市立運動場で開催された。
山本伸一は、戸田城聖と共に、との体育大会に出席し、翌二十三日を大阪で過ごし、帰途、総登山の輸送会議に臨んだ。翌年三月、総本山の大講堂の竣工を記念して、総登山が実施されることになっており、その輸送の打ち合わせが行われたのである。
伸一は、二十五日夕刻、本部に戻り、戸田に総登山の輸送計画について報告すると、直ちに葛飾に向かった。この日の夜、伸一が総ブロック長に就任した、葛飾総ブロックの結成大会が行われたのである。
葛飾区は、東京二十三区の北東部に位置し、江戸川と荒川に挟まれて、大小の河川が流れる「東京の水郷」ともいうべき地域である。区内には、家内工業を中心とした小さな企業が多く、人びとには、気取りのない下町気質があった。
伸一は、人情味に富み、庶民の温もりが漂い、のどかな田園風景が広がる、この葛飾が好きであった。
彼は、車窓から景色を眺めながら、葛飾の未来に思いをめぐらしていた。
″時代の流れは、やがて、これらの水田を一大住宅地に変えてしまうであろうが、それだけに限りない未来性を秘めた地域といえる。二十年後、三十年後には、東京の広宣流布を決する心臓部となるだろう″
伸一は、東京の、また、日本の広宣流布の未来のために、この葛飾に、全国に先駆けて模範のブロックをつくろうと、固く決意していた。
学会にブロック制が敷かれたのは、一九五五年(昭和三十年)の五月であったが、折伏による人のつながりのうえに成り立つタテ線組織に比べると、ブロックは組織も脆弱であり、連携も希薄であった。
しかも、月のうち、ブロック活動にあてられる日は数日にすぎないところから、会員への指導の手も十分には差し伸べられず、各支部や地区の幹部も、ブロックの活動となると、あまり熱が入らないのが実情といえた。
しかし、広宣流布の未来を考えるならば、人びとの生活の場である地域社会に密着したブロック組織の強化は、不可欠な課題であった。そのために、八月二十八日の本部幹部会で、都内各区に総ブロック制を敷くとともに、組織の刷新が図られたのである。今後は、総ブロックのもとに、大ブロック、ブロック、小ブロックの布陣が整えられていくことに地域に花開いた信心即生活の実証は、人びとを幸福へと誘う道標となろう。また、地域に築かれた同志のスクラムは、新たな社会建設の基盤となろう。
山本伸一は、この本部幹部会で葛飾総ブロック長の任命を受けると、まず、大ブロック、ブロックの組織づくりに入った。
伸一は、その組織案の作成を、西山国昭・キヨ夫妻をはじめ、葛飾区に居住するタテ線の支部幹部たちに委ねた。
彼らは、自分たちのつくる組織案が、今後の葛飾の組織の骨格になるのだと思うと、いたく緊張し、唱題に励みながら、深夜まで検討を重ねていった。
まず、区内に住むタテ線の地区幹部以上の幹部を網羅し、居住地域を調べ、区内の地域割りをしながら、大ブロック、ブロックの責任者を選定していったのである。
しかし、それぞれタテ線の支部が異なり、交流もあまりないところから、一人ひとりの詳しい実態はわかりかねた。そこで、人づてに活動状況を聞いたり、電話で連携を取るなどして、ようやく各大ブロック、ブロックの組織案が出来上がった。
彼らは、それを組織表にして、学会本部を訪ね、山本伸一に見せた。
「皆で、検討いたしまして、できれば、この案でいきたいと思いますが……」
西山国昭が、こう言って組織表を差し出すと、伸一は、「ありがとう」と言いながら、丹念に目を通した。そして、表に記載された一人ひとりについて尋ねていった
「このブロック長候補の方の仕事は何ですか」
「仕事ですか。仕事は……」
西山は、同行した幹部に答えを促すように、顔を見回したが、誰も首をかしげて、口をつぐんだままだった。
「ちょっと、仕事はわかりません」
伸一は、重ねて尋ねた。
「では、この方の奥さんの信心状態は?」
「ええと、奥さんは……」
今度も、誰も答えることができなかった。
伸一は、さらに組織表の隣の行を指さしながら、質問を発した。
「この婦人部の方に、お子さんは何人いるんですか」
この問いにも、皆、互いに顔を見合わせ、口ごもってしまった。
伸一は、テーブルの上に組織表を置くと、厳しい調で言った。
「この組織表は、死んでいるようなものです」
「はぁ……」
西山国昭は、伸の言葉の意味がよくわからなかった。
伸一は、戸惑いの表情で彼を見入る西山たちに語っていった。
「いいですか。組織といっても、それを良くしていくのも、悪くしていくのも、人間の一念であり、戦いなんです。ですから、その組織の責任者となる幹部については、本当にこの人が適任なのかどうかを、あらゆる面から、慎重に検討しなければなりません。そのためには、その人のことを、どれだけ知っているかが大事です」
伸一は、噛んで含めるように語った。
「それぞれの組織の中心者を決定する場合には――その人の家はどこにあり、角から何軒目なのか。また、平屋か二階屋か、家族は何人いるのか――こうしたことも、すべて知らなくてはなりません。なぜかというと、役職につけば、その家に、人も出入りするようになります。そうなっても問題はないかどうかも、考える必要があるからです。
さらに、どこに勤めているのか。会社では、どんな立場にあるのかなども、考慮しなくてはなりません。仕事が多忙を極め、活動の時間が十分にとれない人の場合は、それを補佐できる人を付けることも、考えなくてはならないからです。また、その人がどんな性格なのかも、的確につかんでいなければ、人間を生かすことはできません。
一人ひとりのことが、自分の手のひらにあるように、何でもわかっていなければなりません。そして、組織表を見ただけで、その組織の活動の様子までが目に浮かぶようでなければ、生きた組織表とはいえないのです。ただ事務的に組織を編成し、人を当てはめ、それで組織が出来上がると思ったら、大きな間違いです。今のように、皆さんが何も説明できないような組織表では、戦いにはなりません」
西山国昭たちは、伸一の鋭い指摘に、深く反省せざるを得なかった。
「私が皆さんに、こういうことを言うのは、よく戸田先生が、『学会の組織は、戸田の命よりも大切だ』と、おっしゃっているからなんです。
先生がそう言われたのは、仏意仏勅を賜った創価学会の組織が盤石であれば、必ず広宣流布はできるし、逆に、いい加減な組織になってしまえば、広宣流布も破壊されてしまうからです。
今回、組織の検討を皆さんにやってもらっていますが、大切な学会の組織をつくるんですから、本当によく考え抜いた的確な人事であると、頷けるものをつくってください」
伸一に励まされ、彼らは、その組織表を持ち帰り、もう一度、再検討することにしたのである。そして、一軒一軒、家庭訪問するところから始めていった。伸一の指摘を念頭に置きながら訪問を続けていくと、確かに多くの新たな発見があった。
家庭訪問の結果を持ち寄りながら、連日にわたって、慎重な検討が繰り返された。組織表は、当初の案から、大幅な修正を余儀なくされた。
こうしてつくられた新たな組織表をもって、西山たちは、再び伸一を訪ねた。
「一人ひとりのことを、よく知ったうえでつくられた案ですね」
伸一は、彼らの顔を見回し、確認した。そして、組織表に目を通すと、力強く言った。
「それでは、この案でいきましょう」
九月二十五日夕刻、東京・葛飾区亀有の、葛飾総ブロック結成大会の会場には、三々五々と学会員が集ってきた。刈り入れを待つ稲穂が風にそよぐ、日暮れの田んぼ道を行く同志の表情は、喜々としていた。
山本伸一が到着した時には、会場は千数百人の人であふれでいた。午後七時、結成大会は開会となった。
開会宣言、各部の代表決意などに続いて、葛飾総ブロックの総ブロック委員になった西山キヨがあいさつに立った。彼女は、タテ線では向島支部の常任委員をしていた。幾分、緊張した面持ちで語り始めた。
西山キヨは、学会の一切の企画を立て、活動を推進する、青年部の室長である山本伸一を総ブロック長に迎えた今、いよいよ葛飾の新しい出発の時が来たことを述べ、広宣流布のために、身を粉にして戦っていきたいと、抱負を語った。
そして、「山本総ブロック長のもと、全員が一丸となって頑張りましょう!」と呼びかけて話を結んだ。期せずして雷鳴のような拍手が湧き起こった。伸一が、総ブロック長として葛飾に来たということは、この葛飾から広宣流布の新しいうねりが起こることであると、誰もが確信していた。
参加者は、伸一が、蒲田支部で、文京支部で、また、あの大阪の地で、広宣流布の新たな突破口を開き、常に未聞の金字塔を打ち立ててきたことを、よく知っていた。その確信が決意となり、万雷の拍手となって、響き渡ったのだ。
幹部のあいさつが続いたあと、総ブロック長・山本伸一の登壇となった。大拍手と歓声が場内をつつんだ。人垣の後方に立っていた人たちは、背伸びをし、爪先立ちになって、伸一の姿を見ようとした。
彼は、笑顔を場内に向けると、静かに、しかし、力強い声で語った。
「私が葛飾に来たのは、ただ任命を受けたからではありません。私はこの葛飾に、全国に先駆けて、模範的なブロックをつくるために来ました。戸田先生は、常に葛飾の皆さんのことを考えられ、そして、私に、『今度は葛飾だ』と言われて、派遣されたんです。
それは、ブロックの模範を、皆さんと共に、葛飾につくりなさいという意味にほかなりません。戸田先生は、葛飾の皆さんなら、必ずそれができると信じて、私を派遣されたんです。私も、模範のブロックをつくる方々は、皆さんしかいないと確信しております」
伸一は、葛飾の同志に満腔の敬意を寄せ、心から賞讃した。仏子を大切にし、讃えることは、仏法者の当然の行為にほかならない。彼は、下町の、素朴で、人間味、人情味のあふれる地域性は、堅固な人間組織をつくりあげるための、最大の要件であると考えていた。
伸一は、力強く呼びかけた。
「ブロックの模範をつくるということは、幸せの模範をつくるということです。この葛飾を、皆で力を合わせ、東京一、いな、日本一の、幸せあふれる地域にしていこうではありませんか!」
彼は、こう訴えながら、この愛する庶民の町を、全国に先駆けて、幸せの花園にしようと、固く心に誓っていた。
庶民の幸せのない社会の繁栄は、虚構の繁栄にすぎないといえよう。
また、学会の組織の伸展といっても、その目的は、どこまでも一人ひとりの幸福境涯の確立にある。
場内は熱気に満ち、壇上に立つ伸一の顔には、汗が噴き出ていた。
「では、模範のブロックをつくるには、どうしたらよいか。
まず、全会員が、しっかり勤行できるようにすることです。柔道にも、剣道にも、基本があります
が、幸せになるための信心の基本は、勤行にあります。日々、真剣に勤行し、唱題を重ねた人と、いい加減な人とでは、表面は同じように見えても、三年、五年、七年とたっていった時には、歴然たる開きが出てきます。
宿業の転換といっても、人間革命といっても、その一切の源泉は、勤行・唱題にほかなりません。
ですから、日蓮大聖人は、『深く信心を発して日夜朝暮に又懈らず磨くべし何様にしてか磨くべき只南無妙法蓮華経と唱へたてまつるを是をみがくとは云うなり』と仰せになっているんです。
また、勤行の姿勢が、その人の生き方に表れます。弱々しい勤行の人は、生命力も乏しく、どうしても弱々しい生き方になっていくし、義務的な勤行であれば、信心の歓喜はなかなか得られません。お互いに、白馬が天空を駆けるような、リズム感あふれる、すがすがしい勤行をしていきましょう。
そして、真剣な祈りを込め、大宇宙をも動かしゆくような、力強い、最高の勤行を、日々、めざしていこうではありませんか。
その意味から、私は、わが葛飾総ブロックは、『朝晩の勤行をやりきる』ということをスローガンに掲げて、前進したいと思いますが、皆さん、いかがでしょうか!」
学会の飛躍的な発展の源泉は、一人ひとりの会員に、勤行の実践を徹底して教えてきたことにあった。また、そこに偉大なる宗教革命もあったのである。およそ経文とは無縁な民衆に、勤行を教えることは、想像を絶する労作業であったが、それゆえに仏法を、民衆の手に取り戻すことができたといってよい。
人びとは、経文を知らないがために、経を読む職業宗教屋をありがたく思う。それが、宗教の権威に盲従する精神の土壌をつくりあげる根本要因となっていった。また、それが、僧侶を傲慢にさせ、民衆を蔑視する風潮をつくっていったともいえよう。
山本伸一は、会場の参加者を見渡した。ぎっしりと場内を埋めた人びとの目は輝き、求道の息吹が感じられた。
彼は、腕時計を見た。時間は、まだ、たっぷりあった。
「私が話すだけでは、十分な意思の疎通は図れませんから、今日は質問会にしたいと思います。聞きたいことがあれば、なんでも聞いてください」
場内から大きな拍手が湧き起こった。
「壇上だと、皆さんから遠くて、質問が聞こえないので、私が下に行きます」
こう言うと伸一は、壇上を降り、会場の中央に進んでいった。男子部の役員が、すぐに机とイスを用意し、伸一を会場中の人びとが取り囲むようにして、質問会が行われた。
勢いよく、何人かの参加者の手があがった。経済苦の問題、病気の悩み、夫婦仲のことなど、どれも深刻な問題であった。
悩み、苦しみ、その活路を仏法に求めて、健気に信仰に励もうとする同志に、伸一は全精魂を傾けて、勇気と励ましの指導を続けた。この人たちを苦悩から救い、断じて幸せにしてみせるとの、熱き思いをたぎらせて。
皆、無名の庶民である。しかし、広宣流布の使命を担うために出現した、尊き地涌の仏子なのだ。
彼は、一言一言に愛情を込め、誠実を込め、責任を込めて、一期一会の思いで語っていった。
四、五問の質問を受けたあと、伸一は、会場の同志に促すように言った。
「今日は、葛飾総ブロックの出発となりましたが、組織といっても、人間と人間のつながりです。タテ線に比べて、これまで、なぜブロックの組織が弱かったかといえば、それは、人間関係が希薄であったからです。互いに悩みを分かち合い、喜びを分かち合いながら、広宣流布をめざす、麗しく強い、人の和こそが、組織の強さです。
創価学会といっても、それは皆さんを離れてはありません。皆さんの大ブロックが、ブロックが、そのまま創価学会です。そこが歓喜にあふれでいるか、功徳に満ちているか、温かい人間の交流があるか――それ以外に広宣流布の実像はありません。創価学会も、広宣流布も、どこか別の遠い世界にあるのではない。それは、皆さんの日々の活動のなかに、さらに言えば、皆さん自身の生き方のなかにあります。
どうか、『私が創価学会の代表です』と言える一人ひとりになってください。また、最高のブロック、大ブロックをつくってください。自分の担った分野で、最高のものをつくりあげていく――それが、戸田先生との共戦の姿であり、弟子としての戦いです。やろうじゃありませんか!」
伸一の指導は、参加者を奮い立たせていった。割烹着姿の婦人も、油の染みついた作業服の青年も、どの顔も紅潮していた。そして、決意に輝いていた。
「最後に、私たちが戦いを起こすうえで、最も大切なものは何かを述べておきたいと思います。それは勇気です。朝起きるにも、勤行をするにも勇気が必要です。また、悪いことを悪いと言い切るにも、折伏をするにも、勇気がいります。人生も、広宣流布も、すべては勇気の二字で決まってしまう。
信心とは、勇気の異名です。どうか、勇気をもって、自分の弱さに勝ち、宿命に打ち勝ってください。そして、『私は、こんなに幸せだ』と言える境涯になろうではありませんか。それが、戸田先生の願望です」
心に染み渡るような指導であった。
「それでは、元気いっぱいに戦って、また、お会いしましょう!」
伸一は、こう話を結んだ
葛飾総ブロック結成大会は、喜びのなかにその幕を閉じた。会場を後にする人びとの足取りは軽く、胸には、希望のかがり火が赤々と燃えていた。葛飾にブロックの模範を――これが、その日以来、葛飾の同志の合言葉となったのである。
伸一は、青年部の室長として、全国各地を東奔西走しながら、月数回のブロックの日には、勇んで葛飾にやって来た。
当時、ブロックの日は、毎週水曜日になっていた。伸一は、そのつど、指導会、座談会、御書講義と、全力で奔走した。時には、自転車を借りて、駆け巡ることもあった。
彼は、言うのであった。
「私は、皆さんにとっては、『水曜日の男』だね。水曜には葛飾で元気を取り戻して、また、タテ線に行って、力いっぱい頑張ろうよ」
また、伸一は、会合のあとには、必ずといってよいほど、家庭指導に回った。家庭を訪ねれば、その人の生活の様子がわかる。家庭内の深刻な悩みを知ることもできよう。また、会合では見ることのできなかった、人間の素顔を見ることもできる。それらを知らずしては、一人ひとりに対する適切な指導の手を差し伸べることはできない。
この家庭指導を重ねていくなかから、心と心が解け合い、結ばれ、創価の同志の金剛不壊の絆が固く結ばれていく。ゆえに、家庭指導のない組織には、真の団結も生まれることはない。
伸一は、仕事や家族のことなどを尋ねながら、十分に相手の話を聞いた。そして、悩める人には勇気を、迷える人には確信を与え、全精力を注いで激励していった。
また、幹部の家を訪問した時は、家族に、ねぎらいと励ましの言葉をかけることを忘れなかった。幹部としての存分な活躍ができるのは、家族の協力が必要だからである。特に妻が幹部である場合には、夫に丁重に礼を述べ、心から感謝の意を表した。
仏法が人の振る舞いを説くものである限り、感謝の心をもち、礼儀と常識をわきまえることは、信仰者の必須の要件であり、そこから共感の輪も広がっていく。
伸一は、自ら家庭指導を実践し、範を示しながら、その大切さを訴えていった。
「会合に出席している人だけが学会員ではありません。出たくとも、仕事など、さまざまな事情で参加できない人もいる。
また、悩みをかかえて悶々として、信心の喜びさえも失せ、会合に出席する気力さえ、なくなってしまった人もいるかもしれない。
その人たちにこそ、最も温かい真剣な励ましが必要なんです。
もし、会合の参加者にのみ焦点を合わせ、組織が運営されていくなら、本来、指導の手を差し伸べるべき多くの人を、見落としてしまうことになる。
ひとたび、組織の責任者の任命を受けたということは、戸田先生の大事な弟子を、先生からお預かりしたということです。その人たちを悲しませたり、退転させてしまうようなことがあっては、絶対になりません」
伸一の意識は、むしろ、会合に参加できなかった人に向けられていたといってよい。彼は、会合終了後の家庭指導こそが、勝負であると心に決めていた。そして、同志が元気になり、希望と勇気をもてるためには、どんなことでもした。共に記念のカメラに納まるととも、色紙に励ましの言葉を揮毫して贈るとともあった。さらに、寸暇を惜しんで、激励の手紙を書いた。
信心とは希望である。同志である会員に、大いなる希望を与えてこそ、真実の仏法のリーダーといえる。
同志は、一歩、社会に出れば、冷たく厳しい世間の風にさらされながら、必死に生き、戦っている。そうであればあるほど、学会は、兄弟、姉妹、家族以上の思いやりにあふれた、温かい同志愛の世界でなければならないと、伸一は思った。
彼の行くところ、どこでも明るい対話の花が咲いた。その対話のなかから、新たな創意工夫が生まれていった。
たとえば、勤行の正しい仕方を教えられていない会員が数多くいることを語り合ううちに、勤行の仕方を書いた手引を、印刷して配布するという案が出され、直ちに実行に移された。
一人ひとりの心に兆した強い責任感は、智慧を生み、創意と工夫とを育んでいくにちがいない。
伸一は、懸命に動いた。自分が動いた分だけが、広宣流布の前進につながるというのが、これまでの戦いを通して、彼がつかんだ確信であった。
会合終了後、家庭指導をして、自宅に帰ると、深夜になることも少なくなかった。葛飾区内といっても、場所によっては、大田区の自宅まで、二時間近くを要したのである。
しかし、彼は、丈夫ではない自らの体をかばおうとも、労を惜しもうともしなかった。広宣流布の新時代の幕を開くために、この葛飾に、ブロックの模範を築き上げることが、自分に課せられた使命であると、強く、深く、決意していたからである。
山本伸一が、葛飾の同志と語り合うなかで実感したことは、戸田城聖や本部を身近に感じている人が、極めて少ないということであった。何かあれば本部へ、という雰囲気が之しいのである。
葛飾は、東京二十三区のなかでは、地理的にも学会本部から遠いことは確かである。しかし、問題は決してそれだけではなかった。同志の多くは、自分たちの上には、支部長や地区部長など、幾重にも幹部がいるのだから、直接、本部を訪ねたりするのは、恐れ多いことであり、控えるべきであるとの思いをいだいてきた。
つまり、会員と本部とを隔てる、心の壁ができているのである。支部中心のタテ線の活動が定着していくにつれて、いつの間にか、一人ひとりが本部に直結していくという意識が、薄らいでいってしまったのであろうか。
もし、幹部が会員の上に君臨して組織を私物化し、会員が、師を求めて、本部に行くことも樺るような組織であれば、戸田の精神とは、全くかけ離れた、硬直化した官僚組織であり、広宣流布を阻害するものとなってしまう。
学会の広宣流布への原動力は、一九五一年(昭和二十六年)五月三日、戸田城聖が第二代会長に就任した日の、あの七十五万世帯への大師子吼にほかならない。「七十五万世帯の折伏は、私の手でいたします」と、一人立った戸田の決意と確信に触れ、全同志がそれに相呼応することによって、広宣流布の未曾有の伸展があったのである。
つまり、戸田城聖の広宣流布への一念こそが、学会の戦いの電源であり、それにつながることによって、戦いの歯車は、勢いよく回転してきたといってよい。
伸一は、同志の心に立ちはだかる壁を、まず、取り除かなければならないと思った。
彼は、懇談のたびごとに訴えていった。
「組織を図に表す時には、便宜上、ピラミッド型にしますが、それは精神の在り方を示すものではありません。学会の組織の本義からいえば、戸田先生を中心にした円形組織といえます。皆さんと戸田先生との間には、なんの隔たりもありません。皆さん方一人ひとりが、その精神においては、本来、先生と直結しているんです。
戸田先生は、『会員は会長のためにいるのではない。会長が会員のためにいるのだ。幹部もまた同じである』とよく言われますが、皆さんのために先生はいらっしゃる。
ですから、ブロック長の皆さんであれば、月々のブロックの活動を、お手紙で報告してもよいでしょうし、自分自身のことや、家庭のことを報告することもかまいません。誰にも遠慮などする必要はないんです。皆さんは、戸田先生の弟子ではありませんか。
また、私も、なるべく本部に行っているようにしますから、私を訪ねて、どんどん本部に来てください。幹部のための本部ではなく、会員のための、皆さんのための本部なんですから」
伸一は、それから、幹部の在り方について、語っていった。
「皆さん方一人ひとりを、直接、指導してさしあげたいというのが、戸田先生のお気持ちです。しかし、時間的にも、それは不可能なので、先生のパイプ役として、私が葛飾に来ているんです。
ですから、皆さんのことは、逐一、戸田先生にご報告し、一つ一つ私が指導を受けております。幹部は、どこまでも、先生と会員をつなぐパイプなんです。
したがって、幹部は、同志を自分に付けようとするのではなく、先生にどうすれば近づけられるかを、常に考えていくことです」
伸一自身、そのために、戸田の了解を得て、学会本部で葛飾の大ブロック長会を開くなど、ありとあらゆる努力を払っていったのである。
学会の強さは、戸田城聖と一人ひとりの同志との精神の結合にこそあった。広宣流布の大願に生きる、戸田との共戦の気概が脈打っていない組織であれば、それは、もはや、烏合の衆に等しいといえよう。
葛飾の同志は、次第に戸田を、そして、本部を身近に感じ始めるようになった。彼らは自らの心のなかに、戸田城聖の息づかいを感じ、戸田の指導を、自分に対する指導であると、思えるようになっていった。そして、一人、また一人と、己心の戸田に誓い、その誓いを果たすべく、自発的に戦いを開始したのである。
伸一の戦いは、時間との戦いでもあった
限られたブロック活動の日を使って、一人でも多くの会員と会い、信心の覚醒を促すことは容易ではなかった。
しかも、そのうえ伸一は、そのころ、『大白蓮華』誌上に七回にわたって「男子青年部の歩み」を執筆していた。画板を携えて歩き、活動のなかで、わずかな時間を見つけては、画板を机代わりに原稿を書いた。そして、さらに夜更けに、自宅で原稿用紙に向かう日が続いていた。
青年部の室長としての激務のうえに加わった葛飾での戦いは、彼の疲労をいたく募らせ、微熱にさいなまれた。
しかし、伸一は、ますます闘志を燃やし、祈りには一段と力がこもった。
活動から拠点に戻ると、彼は真っ先に仏壇の前に座り、唱題に励んだ。同志のトラックに乗せてもらい、会場から会場に移動する間さえも、心のなかで題目を唱え続けたのである。一分一秒の時間を惜しんでの唱題であった。
葛飾の総ブロック長としての伸一の戦いは、戸田城聖が逝去し、伸一が会長に就任する前年の五九年(同三十四年)七月まで続けられた。
伸一によって、一人ひとりの同志に植えられた信心の苗は、幹を伸ばし、大きく枝を茂らせ、葛飾は六〇年(同三十五年)の十二月、三総ブロックに発展している。
山本伸一が、葛飾総ブロック長として活動を開始し始めて間もないある日、戸田城聖は伸一に言った。
「伸一、また、君の朝の授業を始めよう。将来のために、私は、もっと多くのことを教えておかなければならないと思っている。君を、世界一流の大指導者に育て上げるのが、私の責任だからな」
戸田は、彼の事業が不振に陥り、その再建のために、伸一が夜学に通うことを断念せざるを得なかった五〇年(同二十五年)ごろから、ほぼ毎朝、伸一のために、さまざまな分野の学問の講義を続けてきた。しかし、ここしばらく、朝の授業は中断されていた。広宣流布の伸展にともない、会長として、戸田のなすべきことが激増し、伸一への講義の時間が取れなくなったためである。
今も、戸田の忙しさは、決して変わってはいなかった。しかも、彼の肉体は、間違いなく衰弱しつつあった。その戸田が、また再び、朝の講義を行おうというのである。
「しかし、それでは先生のお体が……」
伸一が言うと、戸田は答えた。
「そんなことは、君の心配することではない」
驚くほど厳しい口調であった。
それから戸田は静かに、胸の思いを吐露するように言うのだった。
「伸一、私は人間をつくらなければならないのだよ。広宣流布を成し遂げる本当の後継者を。命をかけても、私は、それをしなければならぬ。伸一、学べ。すべてを学んでいくんだよ」
烈々たる気迫のこもる言葉であった。
伸一は、「はい!」と言うと、深く頭を垂れた。
戸田の限りなく大きな慈愛に胸が締めつけられる思いがし、目頭が熱くなった。
真剣勝負の朝の授業が再び始まった。
戸田は、死力を振り絞るようにして、講義を続けていった。彼の授業は、歴史の話から政治、経済、文学へと広がり、哲学にいたり、さらに、仏法の眼から、それらの事象をいかにとらえるかに及んだ。縦横無尽な広がりをもち、それでいて深遠な講義であった。
日ごと、戸田は伸一の顔を見ると、「昨日は何の本を読んだか」と、厳しく尋ねた。
窓から差し込む朝の光のなかで、師は一人の愛弟子に、自らの知識と、智慧と、思想と、魂とを注いでいった。
伸一は、師の白熱の慈愛を浴びる思いで、感動に打ち震えながら、一心不乱に学びに学んだ。戸田は、彼の後継の、分身ともいうべき山本伸一の大成の総仕上げのために、命を削るようにして、最後の薫陶を開始したのである。
◆3 核時代と「原水爆禁止宣言」◆
「希望の選択」ディビッド・クリーガー(池田大作全集第110巻) むろん、戸田会長は仏法者であり、「死刑制度」には反対でした。あえて「死刑」と
<本文>
核兵器は魔性の産物
クリーガー 戸田城聖氏をはじめ、多くの人が要請したように、「尊い生命を全滅させる」という核兵器の悪との闘いは、「生命を守る闘い」です。「人間の品性、尊厳、そして生命それ自体を守る闘い」です。この闘いは人間精神を高貴にする活動です。
池田 そのとおりです。クリーガー所長は、核兵器を「人間精神のもっとも深い闇の反映」と言われましたが、戸田第二代会長が「原水爆禁止宣言」で強く訴えた点も、そこにありました。
クリーガー 核廃絶の闘いは、人間性を物質主義よりも高みに置き、精神性を、頭で考えた言い訳よりも高みに置くものです。それは、抑止力理論につきものの知性の落とし穴である、「安全保障は、国々を『すべて焼きつくすぞ』と脅かすことで達成される」と信じる愚かさを明らかにしていきます。そのような考えは、安全保障ではありません。人間精神のどうしようもない堕落です。精神性を知性の下におくことの危険を、示しているにすぎません。
池田 核兵器とは、「生存の権利」を脅かす「絶対悪」であり、核廃絶なき「平和」は虚構です。この核兵器の本質を、民族でもイデオロギーでもなく、人間の「生命」という地平に立つことによって明らかにしたのが、一九五七年(昭和三十二年)九月八日の「原水爆禁止宣言」だったのです。
「もし原水爆を、いずこの国であろうと、それが勝っても負けても、それを使用したものは、ことごとく死刑にすべきであるということを主張するものであります。なぜかならば、われわれ世界の民衆は、生存の権利をもっております。その権利をおびやかすものは、これ魔ものであり、サタンであり、怪物であります」(『戸田城聖全集』4)と。
むろん、戸田会長は仏法者であり、「死刑制度」には反対でした。あえて「死刑」という言葉を使ったのは、原水爆を持ちたいという人間の「魔の衝動」に、楔を打ち込み、原水爆を使用しようとする魔を絶滅させたかったからにほかなりません。「死」という言葉の対極にある「生」を確かなものとするためです。
クリーガー 「われわれ世界の民衆は、生存の権利をもつ」との戸田城聖氏の宣言は、シンプルな智慧の表現です。戸田氏は、「死」よりも「生」を価値あるものとし、普遍的な「生存の権利」があることを強調しておられますが、この権利は世界人権宣言の中に謳われているもっとも重要な権利なのです。
シンプルさゆえに、その智慧の深さは、すぐには理解されないかもしれませんが、そもそも智慧とはつねに、シンプルなものです。
池田 師はいつも、物事の本質をずばりと、しかもだれにでもわかる平易な言葉で語りました。傑出した民衆指導者でした。
「宣言」でいう「魔もの」を簡単に説明すると、こういうことです。仏法では、人々の生命を奪い、智慧を破壊する働きを「魔」とし、その頂点として「第六天の魔王」
の存在を説きます。「第六天の魔王」とは「他化自在天」とも言い、他を支配し隷属させようとする、人間の内なる強い欲望のことです。戸田会長は、核兵器をこの「第六天の魔王」の産物と喝破したのです。「核兵器」は、「科学の進歩」によってもたらされましたが、本源的には人間の生命の「負」の衝動が生みだしたもの、ととらえたわけです。この核兵器の「正体」を見抜き、戦い抜けと訴えたのです。
クリーガー 私は「第六天の魔王」については詳しく存じあげませんが、その魔王が生命を奪い、智慧を葬ることを喜びとする存在ならば、それは人類の味方ではありません。なぜ核兵器を、この「魔王の産物」だと戸田氏が呼ばれたのか、私はよくわかります。まさに核兵器は生命を奪い、智慧を葬る手段です。
池田 「魔」とは古代サンスクリットの「マーラ(魔羅)」に由来し、「殺者」「能奪命者」などとも訳します。魔王とは、生命の外にあるものではなく、「万人の心」に備わる働きです。ゆえに「万人の心」に呼びかける精神闘争が、核廃絶には不可欠なのです。
さて、「原水爆禁止宣言」から四十年以上が経ちました。核兵器を取り巻く世界はどう変わったでしょうか。
冷戦が終結した時、世界の人々は「平和の到来」を期待しました。核廃絶の客観的条件は、大きく改善されました。事実、南アフリカは核武装を放棄しましたし、NPT(核拡散防止条約)の延長、CTBT(包括的核実験禁止条約)の採択など、核軍縮への歩みは、それなりに前進しました。
しかし、保有国が「核抑止力」に固執し、核廃絶への誠意を示さないうちに、とうとうインド、パキスタン両国が地下核実験に踏み切ってしまいました。私は訴えたいのです。今こそ、核兵器の本質に迫った「原水爆禁止宣言」を真剣に問い直すべきであると。
「原水爆禁止宣言」の継承を
クリーガー 今、核廃絶運動は、岐路に立っています。冷戦が終結して十年以上が経ちましたが、核保有諸国の安全保障政策の根本には何の劇的変化もありません。相変わらず、核兵器に依存した安全保障が続いています。もはやだれのためになるのか明言できないにもかかわらず、いまだに核抑止理論があてにされています。一方、こうした現状に対する反対も世界で強まっていますが、核保有国の政府は今のところ、むしろ反対運動を妨げることに力を注いでいます。
しかし、現状の無期限な持続は、核による破滅に終わりかねないのです。ゆえに私は、戸田城聖氏の「原水爆禁止宣言」は、今日もなおきわめて重要であると思います。広くSGIの青年部が戸田氏の思想を絶えることなく継承していくよう、池田会長が努力しておられることを、心強く思っています。
戸田氏の宣言から四十周年の折に、SGI青年部の国際的な集会(九七年九月十三日、東京で開催されたSGI世界青年平和会議)で、講演の機会をいただいたことは、本当に大きな喜びでした。
池田 ありがとうございます。多くの青年たちから、所長の講演に対する感銘の声を、私は聞きました。
クリーガー 戸田氏は青年部に大きな期待を寄せ、氏の宣言も青年たちに向けられていました。青年への思いは、私も同じです。
池田 魯迅に「血の一滴一滴をたらして、他の人を育てるのは、自分が痩せ衰えるのが自覚されても、楽しいことである」(石一歌『魯迅の生涯』金子二郎・大原信一訳、東方書店)という言葉があります。
私に接してくださる師の姿が、まさしくそうでした。弟子である私もまた、同じ決意で青年の育成に命を削ってきたつもりです。
クリーガー 青年は「未来」です。青年は自分が受け継いでいく世界に、当然、発言権があります。核の脅威をなくすには、青年たちが大いに活躍しなければなりません。
SGI青年部への講演の後、「アボリション(廃絶)二〇〇〇」への署名運動を、創価学会の青年部が日本全国で開始されました。私は心から感動し、励まされました。
そして、わずか二、三カ月のうちに、千三百万人の署名を達成された。劇的な努力です。この署名簿はすでに、核拡散防止条約の各国代表と国連の事務総長に手渡されました。「アボリション」へ世論を向かわせ、全世界の政治的意志を形成していくには、この署名運動のような劇的な努力が、もっと必要です。もう一つ、私の期待として申し上げますが、この千三百万人の署名を、日本のなかでもっと活用し、日本の政府が核兵器廃絶の強力な主唱者となるよう、影響力をおよぼしていければと思います。世界のすべての国の中でも、日本の政府がもっとも、核兵器廃絶を主張する必要を認識しているべきなのに、こう申し上げねばならないのは、ある意味で残念なことですが。
池田 おっしゃるとおり、唯一の被爆国である日本が核廃絶の先頭に立つことは、人類への義務とさえ言えます。
クリーガー 今までは、日本の政治の指導者は、アメリカの核の傘から脱し、真の核兵器反対の立場を表明しようという勇気がありませんでした。これから日本の民衆が政治指導者に強く要求していかないかぎり、これは変わらないのではないかと思います。
池田 ご指摘は、ごもっともです。「平和」を追求していく以外に、日本の活路はありません。ともあれ、私たち創価学会は、政治の状況がどうであれ、仏法者として、核廃絶のその日まで行動をやめません。永遠に「平和勢力」です。
師の遺訓である「核兵器は絶対悪」との精神を、いっそう、力強く叫んでいく決意です。
◆第29巻 「源流」◆
小説「新・人間革命」 す!」と力強い声が響いた。二人は、死刑制度の是非などについて論じ合い、多くの
<本文>
源流(53)
ナラヤンは、すべての階層の人びとの向上をめざして運動を展開し、社会、経済、政治、文化、思想等の総体革命(トータル・レボリューション)を主張してきた。山本伸一も、総体革命を提唱・推進してきた者として、その革命の機軸はどこに定めるべきかを訴えた。
「私は、結局は一人ひとりの人間革命がその基本になり、そこから教育・文化など、各分野への発展、変革へと広がっていくと思っています。いかなる社会にせよ、それをつくり上げてきたのは人間です。つまり一切の根源となる人間の革命を機軸にしてこそ、総体革命もあるのではないでしょうか」
「全く同感です!」と力強い声が響いた。
二人は、死刑制度の是非などについて論じ合い、多くの点で意見の一致をみた。
対談を終えた伸一は、夕刻、ガンジス川のほとりに立った。インド初訪問以来、十八年ぶりである。対岸は遥か遠くかすみ、日没前の天空に、既に丸い月天子が白く輝いていた。空は刻一刻と闇に覆われ、月は金色に変わり、川面に光の帯を広げていく。
伸一は、戸田城聖の生誕の日に、恩師が広布旅を夢見たインドの、ガンジス河畔に立っていることが不思議な気がした。戸田と並んで月を仰いでいるように感じられた。また、広宣流布の険路をひたすら歩み続けた一つの到達点に、今、立ったようにも思えるのだ。
戸田の後を継いで
第三代会長に就任してからの十九年、
さまざまな事態に遭遇してきた。
いかにして難局を乗り越え、
新しい創価の大道を開くか、
悩みに悩み、
眠れぬ夜を過ごしたこともあった。
疲労困憊し、
身を起こしていることさえ辛いこともあった。
そんな時も、いつも戸田は彼の心にいた。
そして、厳愛の叱咤を響かせた。
“大難は怒濤のごとく押し寄せてくる。
それが広宣流布の道だ。
恐れるな。
戸田の弟子ではないか!
地涌の菩薩ではないか!
おまえが広布の旗を掲げずして誰が掲げるのか!
立て!
師子ならば立て!
人間勝利の歴史を、
広布の大ドラマを創るのだ!”
源流(54)
ガンジスの河畔には、点々と炎が上がり、その周囲に幾人もの人影が見える。故人を荼毘に付しているのだ。
灰となって“聖なるガンジス”に還る──永遠なる別離の厳粛な儀式である。
生と死と──永劫に生死流転する無常なる生命。しかし、その深奥に常住不変の大法を覚知した一人の聖者がいた。釈尊である。菩提樹の下、暁の明星がきらめくなか、生命の真理を開悟した彼は、苦悩する民衆の救済に決然と立ち上がった。
その胸中の泉からほとばしる清冽なる智水は、仏法の源流となってインドの大地を潤していった。釈尊の教えは、月光のごとく心の暗夜を照らして東南アジア各地へと広がり、北は中央アジアからシルクロードを通って、中国、韓・朝鮮半島を経て日本へと達した。
彼の教えの精髄は法華経として示されるが、末法の五濁の闇に釈尊の仏法が滅せんとする時、日本に日蓮大聖人が出現。法華経に説かれた、宇宙と生命に内在する根本の法こそ、南無妙法蓮華経であることを明らかにされた。そして、その大法を、御本仏の大生命を、末法の一切衆生のために、御本尊として御図顕されたのである。
「日蓮がたましひ魂をすみ墨にそめながして・かきて候ぞ信じさせ給へ、仏の御意は法華経なり日蓮が・たましひは南無妙法蓮華経に・すぎたるはなし」
また、「爰ここに日蓮いかなる不思議にてや候らん竜樹りゅうじゅ天親等・天台妙楽等だにも顕し給はざる大曼荼羅を・末法二百余年の比はじめて法華弘通のはた旌じるしとして顕し奉るなり」と。
大聖人は、濁世末法にあって、地涌の菩薩の先駆けとして、ただ一人、妙法流布の戦いを起こされ、世界広宣流布を末弟に託されている。以来七百年、創価学会が出現し、広布の大法戦が始まったのである。
それは、「日蓮と同意ならば地涌の菩薩たらんか」と仰せのように、現代における地涌の菩薩の出現であった。
源流(55)
日蓮大聖人は、「観心本尊抄」において、地涌の菩薩は、「末法の初に出で給わざる可きか」と明言され、その出現の具体的な様相について、「当に知るべし此の四菩薩折伏を現ずる時は賢王と成つて愚王を誡責し」と述べられている。
地涌の菩薩が末法において「折伏」を行ずる時には、「賢王」すなわち在家の賢明なる指導者となって、荒れ狂う激動の社会に出現するのだ。
「愚王を誡責」するとは、社会に君臨し、民衆を不幸にしている権威、権力の誤りを正していくことである。主権在民の今日では、各界の指導者をはじめ、全民衆の胸中に正法を打ち立て、仏法の生命尊厳の哲理、慈悲の精神を根底にした社会の改革、建設に取り組むことを意味していよう。
つまり、立正安国の実現である。弘教という広宣流布の活動は、立正安国をもって完結する。個人の内面の変革に始まり、現実の苦悩から人びとを解放し、幸福社会を築き上げていくことに折伏の目的もある。
しかし、それは困難極まりない労作業といえよう。山本伸一は、末法の仏法流布を実現しゆく創価学会の重大な使命を、深く、強く、自覚していた。
初代会長・牧口常三郎は、軍部政府が国家神道を精神の支柱にして戦争を遂行していくなかで、その誤りを破折し、神札を祭ることを敢然と拒否して逮捕された。取り調べの場にあっても、日蓮仏法の正義を語り説いた。
まさに「愚王を誡責」して獄死し、殉教の生涯を閉じたのである。また、共に軍部政府と戦い、獄中闘争を展開した第二代会長・戸田城聖は、会員七十五万世帯の大折伏を敢行し、広宣流布の基盤をつくり、民衆による社会変革の運動を進め、立正安国への第一歩を踏み出したのである。
戸田は、学会を「創価学会仏」と表現した。そこには、濁世末法に出現し、現実の社会にあって、広宣流布即立正安国の戦いを勝ち開いていく学会の尊き大使命が示されている。
源流(56)
山本伸一は、ガンジスのほとりに立って空を仰いだ。既に夜の帳につつまれ、月天子は皓々と輝きを増していた。
一陣の風が、川面に吹き渡った。
伸一の眼に、東洋広布を願い続けた恩師・戸田城聖の顔が浮かび、月の姿と重なった。
彼は、心で叫んでいた。
“先生! 伸一は征きます。先生がおっしゃった、わが舞台である世界の広宣流布の大道を開き続けてまいります! 弟子の敢闘をご覧ください”
月が微笑んだ。
その夜、宿舎のホテルで伸一は、妻の峯子と共に、戸田の遺影に向かい、新しき広布の大闘争を誓ったのである。
翌十二日、伸一たち訪印団一行はナーランダーの仏教遺跡をめざした。パトナから車で二時間余りをかけ、この壮大な遺跡に立ったのは、午後二時過ぎであった。
鮮やかな芝生の緑の中に、歴史の堆積されたレンガ造りの遺跡が続いていた。回廊が延び、階段があり、水をたたえた井戸がある。学僧が居住し、学んだ僧房が並ぶ。
紀元五世紀、グプタ朝の時代にクマーラグプタ一世によって僧院として創建され、次々に増築拡大されていったという。そして、ハルシャ朝、パーラ朝と、十二世紀末まで七百年の長きにわたって繁栄を続け、仏教研学の大学となってきたのだ。
案内者の話では、ナーランダーの「ナーラン」は知識の象徴である「蓮」を、「ダー」は「授ける」を意味するという。
ここには、インドのみならず、アジアの各地から学僧が訪れ、最盛時には一万人の学僧と千人もの教授がいて、仏法の研鑽が行われていた。計算上では教授一人に対して学僧は十人となり、小人数での授業が行われていたことが推察できる。
師弟間の対話を通して、一人ひとりと魂の触発を図る――そこにこそ、人間教育の原点がある。また、それによって、仏法の法理は世界に広がっていったのだ。
源流(57)
ナーランダー遺跡の案内者が説明した。
「僧院では、入学一年目の学僧は、個室をもち、寝具、机が与えられます。しかし、研学が進むにつれて共同での使用となり、卒業時には、真理にのみ生きる人間として巣立っていったといいます」
つまり、精神の鍛錬がなされ、モノなどに惑わされることなく、一心に法を求め抜く人格が確立されていったということである。
人格の錬磨がなされなければ、いかに知識を身につけても、真に教育を受けたとはいえない。
戸田城聖は、創価学会を「校舎なき総合大学」と表現した。仏法の法理を学び、人間の道を探究する学会の組織は、幸福と平和を創造する民衆大学といえよう。山本伸一は、この「校舎なき総合大学」は、人間教育の園として、時とともに、ますます大きな輝きを放っていくにちがいないと確信していた。
ナーランダーの仏教遺跡を見学した一行は、パトナへの帰途、休憩所に立ち寄った。腕時計を見ると、午後五時半である。
口ヒゲをはやした休憩所の主が、どこから来たのかと尋ねた。年は四十前後だろうか。
伸一が、日本からであると伝えると、主は両手を広げて驚きの仕草をした。
「それなら、ぜひ、わが家に寄っていってください。この目の前です」
「ご厚意はありがたいのですが、夕食の時間も迫っているので、ご家族の皆さんにご迷惑をかけてしまいます」
「いいえ、家族も大歓迎します。インドでは、お客さんと教師と母親は神様といわれているんです。ですから、こうして歓迎することは、神様を敬うことにつながるんです」
バジパイ外相を訪ねた折にも、聞かされた話である。こうした考え方がなければ、初対面の人を自宅に招いたりはしないだろうし、あえて関わろうとはしないにちがいない。
伸一は、宗教が人びとの精神、生活に、深く根付いていることを実感した。宗教をもつことは、生き方の哲学をもつことである。
源流(58)
休憩所の主に請われて、山本伸一たちは、好意に甘え、自宅に伺うことにした。
家は石造りであった。主は、庭を案内し、井戸の使い方も丹念に説明してくれた。
中庭で懇談が始まった。一行が最初に紹介されたのは主の母であった。インドの家庭では、年長者への尊敬心が厚いようだ。
家族総出で、紅茶と菓子を振る舞ってくれた。一行のために、今、木の実の料理も作っているという。
伸一は、ぶしつけなお願いとは思ったが、その様子を見せてほしいと頼んだ。人びとの暮らしを知っておきたかったのである。快く台所に案内してくれた。
二人の娘が、土間の片隅にしゃがみ込んで、七輪のようなコンロで、ミルクや湯を沸かしたり、木の実を炒めたりしていた。
水道も、ガスも、立派な調理台もあるわけではない。しかし、土間にはきれいに水が打たれ、清潔な感じがした。
出された菓子は、すべて自家製である。また、クッションなどのカバーや子どもの服など、多くが手作りであった。モノは、決して豊富とはいえないが、一つ一つの品に愛着があふれ、人間的な温かさ、心の豊かさが感じられた。日本など、先進諸国が失いつつあるものが、ここにはあった。
紅茶をすすりながら、語らいは弾んだ。
伸一は、「家族は何人ですか」と尋ねた。
主は「七人、いや八人です」と言うと、にこにこして、一匹の大きな犬を抱えてきた。
「この犬も、家族の一員ですから」
主の表情には、“家族”であるとの思いがあふれていた。単なるペットではなく、仕事の役割も担う共同生活者なのであろう。
三十分ほどの訪問であったが、伸一たちと家族は、すっかり打ち解けた。帰りがけに伸一が記念の品を渡すと、主は、「必ず、また来てください」と言って、何度も彼の手を握り締めた。出会いを大切にし、対話を交わすことから、心は触れ合い、人間の絆が育まれていく。国境も、民族の壁をも超えて。
◆小説<人間革命> 第12巻 宣言 135頁~137頁◆
戸田が、原水爆禁止宣言のなかで、原水爆を使用した者は「ことごとく死刑に」と叫んだのは、決して、彼が死刑制度を肯定していたからではない。 彼は、九年前の四八年(昭和二十三年)に、極東国際軍事裁判(東京裁判)で、A級戦犯のうち東条英機ら七人が、絞首刑の判決を受けた時、次のように述べている。
「あの裁判には、二つの間違いがある。第一に、死刑は絶対によくない。無期が妥当だろう。もう一つは、原子爆弾を落とした者も、同罪であるべきだ。なぜならば、人が人を殺す死刑は、仏法から見て、断じて許されぬことだからだ」
また、彼は、しばしば、「本来、生命の因果律を根本とする仏法には、人が人を裁くという考え方はない」とも語っていた。
では、その戸田が、なぜ、あえて「死刑」という言葉を用いたのだろうか。戸田は、原水爆の使用者に対する死刑の執行を、法制化することを訴えようとしたのではない。彼の眼目は、一言すれば、原水爆を使用し、人類の生存の権利を奪うことは、「絶対悪」であると断ずる思想の確立にあった。
そして、その「思想」を、各国の指導者をはじめ、民衆一人ひとりの心の奥深く浸透させ、内的な規範を打ち立てることによって、原水爆の使用を防ごうとしたのである。
原水爆の使用という「絶対悪」を犯した罪に相当する罰があるとするなら、それは、極刑である「死刑」以外にはあるまい。もし、戸田が、原水爆を使用した者は「魔もの」「サタン」「怪物」であると断じただけにとどまったならば、この宣言は極めて抽象的なものとなり、原水爆の使用を「絶対悪」とする彼の思想は、十分に表現されなかったにちがいない。
彼は、「死刑」をあえて明言することによって、原水爆の使用を正当化しようとする人間の心を、打ち砕こうとしたのである。いわば、生命の魔性への「死刑宣告」ともいえよう。
小説<人間革命> 第12巻 宣言 135頁~137頁
 日めくり人間革命
日めくり人間革命