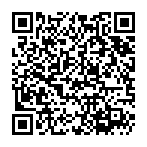日めくり一週間2022
2022年12月24日~26日
第2165回
だから戦うのである
<悪徳と戦い、その根を切らねばならない>
スウェーデンの作家ストリンドベリは、
「ひどい目にあわされた方が黙っていると、
悪漢の方が正しいことになってしまうのである」
(『戯曲論』千田是也訳、早川書房)と述べている。
だから戦うのである。
ひどい目にあった場合、
断じて黙っていてはならない。
学会もこの精神である。
大聖人の教えとも共鳴する。
古代ローマの哲学者セネカは、
「悪徳はすべて、
それが起こったときに押し潰してしまわないと、
その根を深く下ろします」
(『道徳論集』茂手木元蔵訳、東海大学出版会)と指摘した。
2005.12.8第五十五回本部幹部会、全国青年部幹部会
2022年12月21日~23日
第2164回
本物の戦う師子が必要である
<広宣流布のために一切を捧げようとする、
本物の信仰者をつくれるかどうか>
「信心は日蓮大聖人の時代に還れ!」
――これが戸田先生の叫びであった。
何があっても揺るがない、
本物の信仰者を育成する。
この一点に心血を注がれていた。
それは、戦時中、軍部権力の弾圧によって、
ほとんどの幹部が退転したという歴然たる事実があったからだった。
「広宣流布のために一切を捧げようとする、
本物の信仰者をつくれるかどうか」
――ここに、戦後の創価学会の再建の焦点があった。
臆病な羊の群れであっては、
ほんの小さな弾圧でもあれば、
すぐに動揺し、崩れ去ってしまう。
そう考えておられたのである。
広布に進めば「三類の強敵」が必ず現れる。
御書に照らし、経文に照らして、それは明らかである。
戸田先生の時代、
私は、学会に対するデマや中傷に対して、
真っ向から戦った。
卑劣な嘘を、絶対に許さなかった。
どんな相手に対しても、
たとえ自分一人であっても、
堂々と正義を訴え、
認識を正していった。
正義ゆえの迫害は、
学会が御聖訓どおりの前進をしている証拠である。
だからといって、そうしたデマを放置してはならない。
新入会の友や、何の知識も持たない人が、
嘘の情報にたぶらかされてしまうからだ。
また、将来にも禍根を残してしまう。
皆が安心して信心に励めるよう、
正義という筋道は、
きちっと、厳然と示していかねばならない。
″嘘も百回言えば真実になる″という言葉があるが、
それが悪の常套手段である。
正義を攻撃するには、
「嘘」しか方法がないからである。
卑劣な宣伝に、決して負けてはならない。
私は何十年もの間、つねに迫害の矢面に立ってきた。
私が今、厳然と学会を守っているからといって、
決してそれに甘えてはならない。
今こそ、本物の戦う師子が必要である。
一人立つ勇者がいなければ、
まじめに学会活動に励む会員が、かわいそうである。
広布のために勇敢に戦えば、
その大福徳は、子孫末代にまで行き渡る。
永遠にわが身を荘厳し、一家一族を守っていく。
それが仏法の法理である。
このことを忘れてはならない。
私は、皆さん一人一人の健康、
皆さんのご家族の健康を、
毎日、真剣に祈っている。
どうか、健康であっていただきたい。
自分のため、
人のため、
一家のため、
世界のために!
聡明に自己を律し、
賢明な生活を心がけ、
自分自身の健康を勝ち取っていただきたい。
健康をたもっているということ、
それ自体が、勝利である。
健康で、広布のために戦える。
何はなくとも、それこそが、
最大最高の幸福な人生ではなかろうか。
どうか、風邪などひかれないように!
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月20日
第2163回
新しい組織の出発に当たり、
大切な点は何か
<「核」をしっかりとつくる>
新しい組織の出発に当たり、大切な点は何か。
ある幹部に聞くと
「団結です。ただちに闘争を開始することです」と答えてくれた。
またある人は、「人材育成です」と言った。
またある人は、「最初の三カ月問、全力で第一線を駆けめぐることです」と言った。
どれも大事なポイントだと思う。
新しい組織。新しい陣列。
理想の団結を築いていくには、
「核」をしっかりとつくることである。
まず自分自身が、
広宣流布のために、強く、深い決意を固める。
そして、誓いを共にする同志を一人、また一人と糾合する。
安心して何でも言い合い、
激励し合える仲間をつくっていくのである。
組織がすでにあるからといって、
すべてが順調にうまくいくわけではない。
そんなに簡単なものではない。
できあがった組織にあぐらをかくような
リーダーであってはならない。
自分の信心と、誠実と、必死の闘争で、
うるわしい団結の組織を築き上げていただきたい。
また、人材育成で大事なことは、
「どんどん励ます」ことである。
いい人を伸ばすことである。
叱つてはいけない。
広布に戦ってくださる同志を、
真心から賞讃し、
ほめていくことである。
そういうリーダーのもとで、
人材は、ぐんぐん育っていく。
学会には、優秀な若い人材が、たくさんいる。
そうした人々を、どんどん育て、どんどん登用し、
力をつけさせていかねばならない。
若い人々を育てるのが、急務の課題である。
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月18日19日
第2162回
一家和楽は
自分が主人公
<家庭は人間が人間らしく
生きられる社会建設の第一歩>
私は、
「成長家族」
「創造家族」という
言葉が大好きだ。
家庭は、
人生の基本となる
「安心」と「希望」の
拠点であり、
「幸福」と「平和」の
基地にほかならない。
日々の生命と活力の
「蘇生」の場であり、
前進と充実を生み出す
「創造」の絆であり、
「和楽」と「成長」の
城である。
家族といっても、
心と心を通い合わせ、
互いを思いやる
気持ちがなければ、
絆を深めることは
できない。
人間の本当の幸せは、
その絆を一生涯、
大切にしながら、
互いの幸福を願い、
それをともに
育んでいく中にある。
良き家庭は
良き人間を創り、
良き人間は
社会のために
良き貢献を
するはずである。
心と心で結ばれた
“人間の家”を
創造しゆく努力は、
それ自体、
人間が人間らしく
生きられる社会の建設の
第一歩になるであろう。
一人が太陽になれば、
その陽光は一家、
一族を照らす。
その福徳は
子々孫々まで包む。
なんの心配もない。
自分が一家和楽の
主人公となれば良いのだ。
自分の境涯を
開いていけば、
必ず和楽は実現できる。
創価の「師弟」という
最極の生命の軌道に則った
「家庭教育」には、
絶対に行き詰まりがない。
その開かれた家庭には、
無限の希望と
和楽と勝利の未来が、
光り輝いていく。
2022年12月18日池田大作先生の写真と言葉「四季の励まし」
2022年12月17日
第2161回
広宣流布は、女性で決まる
<心で決まる>
先日、婦人部の「女性平和委員会」の友が、「世界人権宣言」の起草に貢献した著名な社会運動家エレノア・ルーズベルト女史(アメリカ第三十二代大統領夫人)の貴重な著作を届けてくださった。
その本のタイトルが、まことにすばらしい。『女性で決まる』という本なのである。
エレノア女史は、誇り高く宣言している。
「女性は陰に陽に、世界の命運に偉大な影響力を及ぼしてきました」
「世界の危機を乗り越えられるかどうか。それは、今までにもまして『女性で決まる』のです」(Eleanor Roosevekt, It's Up to the Women, Frederick A.Stokes Company.)
そのとおりである。
戸田先生も、よく、
「広宣流布は、女性で決まる」と言われた。
婦人部、女子部の皆さま方、
一年間、本当にお世話になりました。
明年も、よろしくお願いします。
エレノア女史は、こうも論じている。
「人生において、何を大切にするかによって、女性は、人生を、幸福なものにもできるし、不幸なものにもしてしまう」(同前)
人生で大切なものは何か――セネカはつづっている。
「われわれを富ましめるもの、それは心です」(前掲『道徳論集』)
幸福は、心で決まる。
平和も、心で決まる。
混迷を深めゆく世界にあって、
人類は、
「心」そして「生命」という原点に立ち返る時を迎えている。
心――私たちにとっては、
「信心」が根本である。
日蓮大聖人は「ただ心こそ大切なれ」と仰せである。
これは、大聖人の仏法の一つの結論と言える。
釈尊の法華経も、大聖人の御書も、
「心」がもつ偉大な力を、
あらゆる角度から説いているのである。
日蓮大聖人は、女性門下である日女御前に仰せになられた。
「(法華経の)宝塔品の時には、多宝如来、釈迦如来、十方の諸仏、一切の菩薩が集まっておられます。この宝塔品が今、どこにあられるかと考えてみますと、それは日女御前の胸の間の八葉の心蓮華のなかにあられると日蓮は見ているのです」(御書1249㌻、通解)
全宇宙のあらゆる仏の智慧も、
あらゆる菩薩のカも、
妙法を受持した女性の生命に、
全部、備わっている
――こう、大聖人が断言してくださっているのである。
その智慧と力を無限に引き出せるのが、
信心である。
ゆえに、不幸になるわけがない。
絶対に、縁する人を幸福に導きながら、
今いる場所から世界へ、
「平和の文化」を広げていくことができるのである。
2005.12.8第五十五回本部幹部会、全国青年部幹部会
2022年12月16日
第2160回
正義は必要な力を与えてくれる
<正義に立ったとき、
人間の持つ本当の底力が発揮される>
南米ベネズエラで今も敬愛される独立の指導者に、
フランシスコ・デ・ミランダがいる(1750年〜1816年)。
同国でも、わがSGIの同志は、
女性の理事長を中心に仲良く団結し、
社会貢献の活動を展開している。
ミランダは、
南米解放の先駆者であると同時に、
当時の南米にあって、
きわめて広い世界的視野をもった人物として有名である。
その足跡は、
北・中南米諸国はもとより、
ロシア、トルコ、ギリシャ、北欧・東欧をふくむ欧州各国にまでしるされている。
また、アメリカのワシントン初代大統領や、トマス・ぺイン、イギリスの政治家である小ピット、エドマンド・パーク、思想家のベンサム、さらにはオーストリアの作曲家ハイドンなど、まことに幅広い交友関係を持っていた。
かのナポレオンも、ミランダに注目していたという。
ミランダは南米独立のために、
いち早く自由の旗を掲げて立ち上がった。
人種や階級、年齢、男女などの区別なく、
広く人材を結集して、
指揮を執ったと言われる。
先駆者の彼には、
つねに悪意の中傷や、迫害が絶えなかった。
最後は投獄され、獄中で死去している。
しかし、勇敢に戦いぬいた彼の名は、
歴史に燦然と光り輝いている。
ミランダは言った。
「我々は正しい。
我々は正義である。
正義は、必要な力を与えてくれるであろう。
友よ、すべては我々自身で決まる」(Francisco de Miranda, America Espera, Biblioteca Ayacucho.以下、ミランダの言葉は同書から)
至言である。
正義に立ったとき、
人間の持つ本当の底力が発揮される。
何があろうと、正義を貫き、
正義に一生を捧げゆく覚悟が自分自身にあるか否か。
大事なのは、
肚の据わった人間ほど、強いものはない。
人類を、未来永遠に、
根本的に救いゆく「広宣流布」の活動こそ、
正義のなかの正義である。
ミランダは、こうも言い残している。
「偉大で光輝ある事業であればあるほど、
不正な行為で汚してはならない。
あらゆる犯罪を寄せ付けず、
混乱を招くようなことは避けるよう、
気をつけよ」
醜い利己心や欲望で、
理想を汚してはならない。
また、そうした悪人を、
決して許してはいけない。
責任あるリーダーの皆さんは、
深く心していただきたい。
休む間もない激闘の日々。
迫害の嵐。
ミランダの人生は、波瀾万丈であった。
しかし、彼はこう言っている。
「自由に対する、私の愛が薄れることはない。
正義のための、私のたゆまぬ献身が、やむことはない。
いっそう深まるばかりだ」
どんな烈風も、
ミランダの胸中に燃える″理想の炎″を消すことはできなかった。
否、障害があればあるほど、
その炎は赤々と燃え上がったにちがいない。
私には、彼の気持ちがよくわかる。
本当の信念は、
困難の時にこそ現れる。
御書には
「大難来りなば強盛の信心弥弥いよいよ悦びをなすべし、
火に薪をくわ加へんにさか盛んなる事なかるべしや」(全1448㌻)
と仰せである。
「″正直な人間である″という評判を得ることは、
私にとって、最も栄えある栄誉である」
このミランダの言葉は、
平凡に見えて、
まことに深い含蓄がある。
地位や名声が何だというのか。
富や権力も、はかないものである。
それよりも、一人の人間として、
誠実に、真摯に生きぬく。
嘘偽りなく、正直に、
みずからの信念を貫き通す。
それこそが、最大の誉れの人生である。
その人こそ、勝利者であり、
真の幸福者である。
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月14日15日
第2159回
発明は
「議論」より生ずるものではなくして、
「実行」によって生ずる
<みずからの行動で、道を切り開け>
トヨタ自動車の創業者・豊田喜一郎氏は述べておられる。
「立派な工業も一朝一夕に出来たものではなく、多年の苦心と経営に依つてなり立っているので、裏長屋の様な所で一生研究に没頭して居る幾多の人々の、努力と云う土台の上に築き上げられたものである事に気付いている人は少いのを遺憾と思う」
「屋根の美しさを羨望するあまり土台を築く事を忘れてはならない」
(和田一夫編『豊田喜一郎文書集成』名古屋大学出版会。以下、同書から引用)
いい言葉である。
学会も、陰で黙々と頑張ってくださる方々がいたから、
ここまで発展してきた。
全同志の血のにじむような奮闘のおかげで、
世界的な学会となった。
地道に戦ってくださる会員の皆さまが、一番、尊いのである。
自動車生産を始める以前、
優れた自動織機の製作に取り組んでいた豊田喜一郎氏は、
こうも述べておられる。
「人はなんでもよい、ある一つの点に関しては世界の誰にも負けないものをもつことが大切だ。自分は自動織機に関する限り、世界の誰にも負けない自信がある。この自信があるから、新しい事業をやるときにも、一たん確信がつけば、どこまでも突進していけたのだ」
何か一つでいい。
だれよりも秀でたものを持て
――戸田先生も、このことを言われていた。
さらに豊田氏の言葉を紹介したい。
「吾々の文明を吾々自らが開拓する所に吾々の生命の活路があり、前途の希望が生じ従って人生の快味を感じ、又人間としての生甲斐を感ずるのである」
「発明は議論より生ずるものではなくして、実行によって生ずるのである」
重要なのは行動だ。
みずからの行動で、道を切り開いていくことだ。
どうか全リーダーが先頭に立ち、
新たな大前進への波動を起こしていっていただきたい。
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月13日
第2158回
毎日が人間革命だ
毎日が戦いだ。
毎日が進歩のための闘争である。
改善のための改善ではなく、
勝利のための「改善」である。
価値を生むための「改善」に取り組むことだ。
生きた「改善」を繰り返していくことだ。
それが、勝つための法則である。
今いる環境に安住して、
新たな挑戦の行動を起こさなければ、
その団体はやがて滅びていく。
大切なのは、
つねに自身を変革していくことだ。
私たちでいえば「人間革命」である。
みずからをつねに新たにし、
成長させていくのが、われらの信仰である。
そのための最高の方法が、
唱題であり、学会活動である。
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月12日
第2157回
敢然と反軍国主義を貫いた言論人
「桐生悠々」
<″信念を貫くためには、「一人立つ」以外にない″>
広宣流布の機関紙である、
わが「聖教新聞」の未来のために、
歴史に残る一人の新聞記者について紹介しておきたい。
敢然と反軍国主義を貫いた言論人、桐生悠々である。
桐生悠々は一八七三年、石川県の金沢で生まれた。
長野の「信濃毎日新聞」、
名古屋の「新愛知新聞」の主筆などを務め、
どの地にあっても政治を厳しく監視し、
不正を糾弾する論陣を張った。
「信濃毎日新聞」時代には、
軍部の政策を批判した論説「関東防空大演習を嗤ふ」
(一九三三年〈昭和八年〉)が、軍人たちの逆鱗にふれ、
不買運動をはじめ、さまざまな形で弾圧される。
彼は新聞社を去らざるをえなくなり、名古屋の地で、
個人雑誌「他山の石」の刊行を開始するのである。
″信念を貫くためには、「一人立つ」以外にない″
――その時、彼は六十歳であった。
「他山の石」は、発禁に次ぐ発禁。
生活も苦しくなった。
また、重い病に侵され、健康状態も日に日に悪化していった。
しかし、それでもなお、彼は一歩も引かずに、ペンをとり続けた。
そして、太平洋戦争が開戦する直前の一九四一年九月、生涯を閉じたのである。六十八歳であった。その不屈の歩みは、言論史上の偉業と讃えられている。
彼は、発禁処分を受けた文章で、喝破している。
「威張るものは、大抵弱いものである」(「上層軍部の劣弱性変態」、大田雅夫編『桐生悠々反軍論集』新泉社)
そのとおりである。
本当の実力のない者ほど、威張る。
権威を盾に、正義の人を妨害する。
そして、真実を歪めようとする。
古代ギリシャの哲学者へラクレイトスは、
「傲慢を消すことは火災を消す以上に急務である」(日下部吉信編訳『初期ギリシャ自然哲学者断片集』1、筑摩書房)と述べている。
また桐生悠々は
「国家あっての人民ではなく、人民あっての国家である」(「人民あっての国家」、前掲『桐生悠々反軍論集』)と訴えた。
有名な言葉である。
民衆の幸福を追求する政治を、言論を!
これが彼の信条であった。
ある時は、悪質な一記者の中傷に対して徹底的に反撃し、
紙面を挙げてその悪行を糾弾した。
あまりにも極端ではないか、
との批判に対しても、次のように反論した。
「獅子は一頭の兎を打つにも全力を挙げると聞く。
微々たる一小悪徳記者といえども、
全力をあげて膺懲ようちょう(=こらしめること)せなければ、
生残するおそれがあったからである」(前田雄二『ペンは死なず』時事通信社)
また、
「私たちは『先手を打つ』て、他をリードし、他を引ずらねばならない」(「先手を打つ」、前掲『桐生悠々反軍論集』)と訴え、
ジャーナリストの使命は、
権力の先手を打ち、
警鐘を鳴らすことだと力説した。
私が何度もお会いした中国の文豪・巴金先生は言論人に呼びかけた。
「(=われわれは)ぺンを武器にして、
真理を顕示し、邪悪を糾弾し、
暗黒勢力に打撃をあたえ、
正義を主張する力を結集させることができるのです」
(「核状況下における文字」、「世界」一九八四年八月号所収、岩波書店)
広布に進む私たちもまた、言論の力で勝つ。
「聖教新聞」は、つねにその原動力として、
民衆のための言論戦に先駆していただきたい。
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月10日11日
第2156回
学歴本位なら
組織は分裂し、崩壊する
<学会の役職は信心が根本>
戸田先生は、いつも幹部に明言された。
「上に立つ指導者が、無責任であれば、一切が崩れてしまうぞ!」と。
指導者が大事である。
指導者の責任は大きい。
また、先生は、学会の役職は、
あくまで信心が根本であり、
学歴や社会的立場で決めてはならないと厳命された。
「精神性を重要視する宗教界や思想界が、学歴本位になっていけば、その団体は必ず分裂し、行き詰まり、崩壊するであろう」
これが戸田先生の遺言であった。
若き日、私は、青春の一切を捧げて、戸田先生に、お仕えした。戸田先生の事業が破綻したときも、その再建のために、一人、懸命に働きぬいた。
「私のそばから片時も離れるな。私のそばで生きて生きて生きぬいていけ」――戸田先生の叫びが、今も耳朶に響く。
先生から「君にはすまないが大学もあきらめてくれないか」と言われ、大学に通うことも断念した。その代わり、毎朝のように万般の学問を個人教授してくださった。
世の中には、大学で学びたくても学べない人たちが大勢いる。その人たちの苦しい思いが分かる指導者になっていくのだとの無言の教えであったのかもしれない。
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月9日
第2155回
頭を上げよ! 胸を張れ!
<すべてを前進と成長のエネルギーに>
戸田先生が好きだった言葉の一つが「頭を上げよ、胸を張れ」であった。
会合での話や個人指導の折にも、よく使っておられた。「大作、詩をつくろうよ!」と私を呼ばれ、一緒に詩をつくったときにも、しばしば、口ずさんでおられた。
頭を上げよ! 胸を張れ! ――それでこそ青年である。
何があっても、
毅然と頭を上げて、前へ、前へ!
胸を張って進むのである。
仏法は「変毒為薬」の大法である。
どんな悩みや苦しみに襲われようとも、
信心の力によって、
すべてを前進と成長のエネルギーに変えていける。
それが妙法に生きぬく人生の法則である。
2005.11.25代表幹部協議会
2022年12月8日
第2154回
師匠をお守りすることが、
広宣流布を守り、
創価学会を守り、
愛する同志を守ることになる
<「仏法の師弟」の甚深の法則>
さて、仏の別名に
「(魔軍の攻撃に打ち勝った)勝者」とある。
「絶対に負けない」というのが仏である。
「絶対に勝つ」
「断じて勝ってみせる」――これが仏である。
仏法を持った皆さん方が負けるわけはない。
いかなる障魔も、
醜い陰謀も、
断じて打ち破っていける。
絶対に勝っていけるのである。
戸田先生の時代も苦難の連続であった。
相次ぐ事業の挫折。
獄中闘争で病んだ先生のお体は限界に近かった。
そのなかで、
私は、一人立ち上がり、
戸田先生をお守りした。
全財産、
全青春、
全生命を、
師匠である戸田先生に捧げた。
これが私の永遠の誇りである。
仏法の究極は「師弟」である。
「師弟不二」である。
「仏法を持つ」ということは
「師弟不二」に生きぬくということである。
「師弟、師弟」と口先では何とでも言える。
しかし現実は、そんな簡単なものではない。
私は本当に、全生命を賭して、戸田先生をお守りした。
師匠をお守りすることが、
広宣流布を守り、
創価学会を守り、
愛する同志を守ることになると知っていたからだ。
戸田先生と私は、深き心で結ばれていた。
亡くなられた今も、
そして、来世も、再来世も、
私は戸田先生と一緒である。
それが「仏法の師弟」の甚深の法則である。
2005.12.8第五十五回本部幹部会、全国青年部幹部会
2022年12月5日~7日
第2153回
大事なことは、
「未来はどうなるか」の評論ではなく、
「未来をどうするか」という一念と具体的行動!
<君なら未来をどうするか>
学問探究と人間蘇生の対話で
地球民族の不戦の未来を創れ
全世界の「青年・凱歌」へ、先駆の暁鐘を打ち鳴らしゆく英知の大会、誠におめでとう! 寒い中、全国から本当にご苦労さま。
65年前、法難の嵐の中、民衆の希望を託す学生部を結成された戸田先生も、さぞお喜びでしょう。21世紀とともに誕生した君たちは、1900年生まれの戸田先生と100歳の年齢差がある不思議な宿縁の世代です。
時代の烈風に敢然と挑み、一段と凜々しく逞しdaく、平和の師子吼を轟かせる誇り高き一人一人を、私は命に刻みつける思いで見守り、題目を送っております。
君たちが真摯に研鑽を重ねる「御義口伝」には、「今、日蓮が唱うるところの南無妙法蓮華経は、末法一万年の衆生まで成仏せしむるなり」「妙法の大良薬をもって一切衆生の無明の大病を治せんこと疑いなきなり」(新1004・全720)と仰せです。
百年、千年という範疇さえも超えて、一万年という壮大なるスケールで、人類の宿命を転換し得る生命尊厳の哲理を掲げた幸福と平和の大遠征が、我らの貫く広宣流布であります。
そして、その命運を決する「勝負の世紀」こそ、君たちが元初より誓願して担い立つ、この21世紀にほかなりません。
大事なことは、「未来はどうなるか」という評論ではない。「未来をどうするか」という一念であり、具体的行動であります。
どうか、「一念三千」の極理を体する地涌の君たちは、大宇宙の根本法則たる妙法を唱え弘めながら、学問の探究・革新に、人間蘇生の対話に、民衆厳護の連帯に、そして立正安国への価値創造に、いよいよ勇気凜々と波動を起こし、混迷の21世紀を変え、地球民族の平和・不戦の未来を断固と創り開いてくれ給え!
私は、愛し信ずる君たちが一人ももれなく栄光の青春を、そして凱歌の人生を堂々と飾りゆくことを、祈り抜いてまいります。
結びに今再び、「歴史を創るは この船たしか 我と我が友よ 広布に走れ」と師弟の共戦譜を謳い叫んで、メッセージとします。
2022年12月5日全国学生部大会への池田先生のメッセージ
2022年12月4日
第2152回
心豊かに「幸福の交響曲」を
<「報恩」こそ、人間の証し>
感謝は、
心の豊かさを意味する。
感謝のある人には
喜びがあり、
幸せがある。
恩を知る人は、
謙虚である。
まじめである。
真剣である。
恩を知る人は、
成長がある。
向上がある。
勇気がある。
恩を知る人は、
人を敬うことができる。
心豊かな人は
人を大切にし、
人を育てる。
人も自分も
幸福にしていく。
心貧しき人は
グチや悪口で
人生を暗くする。
人も自分も
不幸にしてしまう。
私たちは心豊かに、
心美しく、
「幸福の交響曲」で
友をつつんでまいりたい。
恩を知る人は、
もっとも偉い人である。
これが、
仏法の骨髄である。
人間の骨髄なのである。
師匠の恩、
衆生の恩に報いることが、
人間の道であり、
仏法の道である。
「報恩」こそ、
人間の証しである。
報恩は、
自分が受けた恩恵を、
次の世代に
贈ることによって
完結する。
要するに、
後継の青年を
大切にし、
励まし、
育てていくことである。
この一年の
広宣流布の大前進、
本当にありがとう!
わが使命の天地に、
希望の旭日を昇らせ、
喜びの花を咲き薫らせた、
一人一人の尊き奮闘を、
私は心から讃嘆し、
感謝申し上げたい。
2022年12月4日池田大作先生の写真と言葉「四季の励まし」
2022年12月1日~3日
第2151回
希望の王子・王女に贈る
題目で心をみがいてピカピカに!
この一年も、よくがんばったね!
正月を前に、家の大そうじを手伝う人もいるでしょう。
部屋をきれいにすると、気持ちも、すがすがしくなるよね。
じつは皆さんは毎日、心をきれいにみがいてるんです。
そう、題目です。
日蓮大聖人は
「ただ南無妙法蓮華経と唱えることが、
最も美しい生命の鏡をみがくことになる」※1と仰せです。
題目を唱えれば、
心が明るく元気になる。
笑顔が光り、
勇気も知恵も出る。
自分らしく良いところを輝かせながら、
家族や友達にも親切にできます。
さあ、ピカピカの心で新年へ出発だ!
※1 新版317㌻ 全集384㌻
2022年12月1日付 少年少女きぼう新聞 KIBOU(12面)
2022年11月29日30日
第2150回
どうしたら皆が安心して広布へ進み、
勝利と幸福をつかんでいけるか
<人の何十倍も苦しみ、題目をあげて、考えぬくこと>
どうしたら、
理想の組織をつくり上げることができるか。
その急所は何か。
それは、リーダーが成長することだ。
手を打つ人間が、
人の何十倍も苦しみ、
題目をあげて、
考えぬくことである。
会合でいい話をすることも大事だ。
だが、それだけでは人は動かない。
一対一で語り、
心がつながってこそ、
徐々に大回転が始まっていく。
改革は必要である。
しかし、安直に進めれば、
かえって、混乱をもたらす場合もある。
だからこそ、現場の声を聞くことだ。
皆が納得して進んでいけるよう、
よく打ち合わせ、
対話を重ねることである。
とくに、若くしてリーダーになったならば、
皆の意見に謙虚に耳をかたむけねばならない。
苦労しなければ、
人の心はわからないものだ。
また、挑戦の心を失えば、
硬直した官僚主義におちいってしまう。
格好はいいが、
血が通わない。
慈愛がない。
思いやりがない
――そういうリーダーであったならば、
皆、がバラバラになってしまう。
「皆、大変ななか、
本当によく戦ってくださっている」
――そう感謝する心があるか、
ともに戦い、
同苦する心があるかどうかである。
どうしたら皆が安心して広布へ進み、
勝利と幸福をつかんでいけるか――その一点を、
私は祈り、全魂を注いできた。
そこに呼吸を合わせなければ師弟は「不二」でなくなる。
決して上から押しつけるのではなく、
皆から「よくやってくれた」と言われる
名指揮を、よろしくお願いしたい。
何でも言える雰囲気が大事である。
そういう組織が伸びる。
立場が上であるほど、
自分から皆の話を聞いて、
一つ一つ応えていかねばならない。
疲れるかもしれないが、そ
れが指導者の責任であるからだ。
何も言えないような雰囲気では、
最低の組織である。
そうならないために、
まずリーダーが真剣に、
一生懸命、戦う。
たゆみなく人間革命していくのだ。
これを心に刻んでいただきたい。
2005.11.11創立七十五周年記念本部・海外最高協議会
2022年11月27日28日
第2149回
創価の人生
<闇が深ければ深いほど、
自分自身の生命を、
太陽のごとく光り輝かせ、
現実の暗閣を明々と照らしていく。>
シードロフ委員長は著名な画家であり、
作家でもあられる。
その自伝的小説には、
委員長のすばらしいおばあさんが登場する。
今、日本も、ますます高齢社会となってきた。
人生の大先輩を尊敬し、
守っていくなかに、
繁栄の道があるといえよう。
小説は描く。真っ赤に燃える荘厳な夕日。
「♪燃えよ、明るく燃えよ、消えることのないように……」
あたりには、鬼ごっこをして遊ぶ子どもたちの歌声が響く。
おばあさんは、夕日に包まれながら、子どもたちに語りかける。
「『燃えよ、明るく燃えよ』っていうのはね、『生きよ、明るく生きよ』と同じことなんだよ」
胸を打つ言葉である。
われわれも生きよう! 明るく!
仏法では「煩悩即菩提」と説く。
悩みがあったとしても、妙法の力用によって、
それをエネルギーに変え、
「智慧の炎」を燃え上がらせていく。
煩悩を悟りへと転じていく。
これが仏法の法理である。
妙法に生きぬく限り、不幸になることは絶対にない。
必ず幸福の道、正義の道を歩んでいけるのである。
闇が深ければ深いほど、
自分自身の生命を、
太陽のごとく光り輝かせ、
現実の暗閣を明々と照らしていく。
これが創価の人生である。
仏法の人生であり、真実の人生である。
2005.11.2 第30回SGI総会、第54回本部幹部会
2022年11月23日~26日
第2148回
激動の乱世こそ、
正義の城が勝ち栄えゆくチャンス
<力ある人材が躍り出る時>
御聖訓には、明確にこう示されている。
「法華経を弘めようと思う心が強盛であったことによって、悪業の衆生に讒言されて、このような(伊豆流罪の)身となったことは、必ず後生のためになるであろう」(御書937㌻、通解)
大聖人は、法華経を弘めようとしたがゆえに、讒言され、迫害されたことを、無上の喜び、永遠の誉れとしておられる。
三代の創価の師弟は、この決心で、「三類の強敵」と大闘争を起こし、勝ち越えてきた。
中国の大指導者・周恩来総理は言われた。
「激動は人民の自覚を高め、社会の発展を早めます」(『周恩来・中国の内外政策』森下修一編訳、中国経済新聞社)と。
激動は望むところだ。
私たちの時代が来る。
私たちが勝つのだ――そういう達観であろう。
激動の乱世こそ、力ある人材が躍り出る時である。
正義の城が厳然と勝ち栄えゆくチャンスである。
そう決めて、私たちは進みたい。
2005.10.13第五十三回本部幹部会、大学会合同総会
2022年11月22日
第2147回
人のつながりが境涯を広げる
大事なのは「人間と人間のつながり」である。
<内外の多くの人々と結び合い、
つき合っていくことである。>
「境涯を広げる」には、どうすればいいか。
それには「人間関係を広げる」ことである。
ゆえに、幹部一人一人は「人間と結合する」ことである。
会員とつながり、人間とつながってこそ本当の幹部である。
大事なのは「人間と人間のつながり」である。
「人間と人間の打ち合い」である。
内外の多くの人々と結び合い、
つき合っていくことである。
その人は、その分だけ生命が広がる。
豊かな人生になる。
トルストイは、臨終の間際に、
かわいがっていた末の娘をそばに呼び、
遺言を伝えた。
その要点の一つは
「生命は他の生命と多く結びつくほど、自我が拡大する」
ということであった。
これを忘れてはいけないと言い残したのである。
私どもで言えば、対話であり、弘教であり、広宣流布である。
ゲーテは言う。
「他人を自分に同調させようなどと望むのは、
そもそも馬鹿げた話だよ」
「性に合わない人たちとつきあってこそ、うまくやって行くために自制しなければならないし、それを通して、われわれの心の中にあるいろいろちがった側面が刺激されて、発展し完成するのであって、やがて、誰とぶつかってもびくともしないようになるわけだ」(エッカーマン『ゲーテとの対話』山下肇訳、岩波文庫)
一人でも多くの人と語った人が勝利者である。
人の面倒をみてあげた分だけ、勝利である。
いろんな人々と、がっちりギアをかみ合わせて、
広宣流布へと向かわせてあげた分だけ、
自分が勝つ。
2022年11月22日
VOD新番組に収録された池田先生の指針
(1997年7月の本部幹部会から)
2022年11月18日~21日
第2146回
学会創立記念92周年
〈池田先生の和歌〉
父母が
不惜の汗で
築きたる
師弟の城に
永久の凱歌を
妙法の
平等大慧の
光彩よ
白ゆり華陽の
スクラム凜と
その囻の
仏法 担いて
若人は
民衆の大力を
不二の師子吼で
2022年11月16日17日
第2145回
ニセの知識人とは断固として戦う
<邪悪と戦う知性こそ真の知性>
牧口初代会長と同世代の、
フランスの詩人に、有名なシャルル・ペギーがいる。
ペギーは、「卑小な哲学とは、かならず、戦うことのない哲学である」(『マギー』第二部、山崎庸一郎訳、『ロマン・ロラン全集』16所収、みすず書房)
とつづった。
現実との格闘なき哲学は、
卑しく、みすぼらしい存在となる。
宗教もまた、同じであろう。
みずから信じる正義を守り貫く戦いにこそ、
その人の哲学の真価は現れる。
そして、邪悪と戦う知性こそ真の知性である。
大聖人は、「佐渡御書」で
「畜生の心は弱きをおどし強きをおそる
当世の学者等は畜生の如し」(全957㌻)と喝破しておられる。
「当世(今の世)の」と仰せだが、現代も同じであろう。
いったん地位や力を得たら、とたんに威張りだし、
″弱きをおどし、強きを恐れる″輩が、いかに多いことか。
こうしたニセの知識階級の傲慢によって、
けなげな庶民が、どれほど侮辱されてきたか。
そしてまた、陰険な邪知によって、
正義の人がどれほど圧迫され、いじめられたか。
悪人に仕立て上げられたか。
それが、今までの歴史の常であったと言わざるをえない。
その流れを転換して、民衆の幸福のために、
すべての哲学と知性を総動員する社会をつくらねばならない。
この″大革命″が、大聖人の慈悲であり、釈尊の慈悲であった。
また、偉大な哲人たちの願望だった。
ゆえに、大聖人の御遺命である広宣流布の前進を阻む、
″畜生″のごとき輩とは、断固として戦い、勝たねばならない。
これが本当の仏法である。
平和と幸福の道であり、真の勝利なのである。
2005.10.13第五十三回本部幹部会
2022年11月15日
第2144回
邪悪と戦わないのは、
無慈悲
また、戸田先生は、峻厳に叫ばれた。
「ひとたび、正義の学会に牙をむき、
仏子の和合を破壊しようとしてきたならば、
その邪悪とは徹底的に戦え。
そうでなければ、創価学会が壊され、
広宣流布が撹乱されてしまう。
一番大事なのは広宣流布だ。
邪悪を放置しておくのは、
慈悲では絶対にない。
悪と戦い、勝ってこそ、
正義であり、慈悲である」
この「戦う心」を、
皆さんは、よく銘記しておいていただきたい。
邪悪と戦わないのは、無慈悲である。
″悪は、静かにして、放っておけばいい″
――その心は、悪に通じてしまうのである。
2005.10.13第五十三回本部幹部会
2022年11月14日
第2143回
人生の勝負は、
途中では決まらない。
最後の数年間で決まる。
<大いなる自負をもって、ますます壮健であれ!>
壮年部の皆さんも、
婦人部に負けじと、
立ち上がってもらいたい。
「壮年部が懸命に働いてきたからこそ、
学会も、日本の国も、
これだけ繁栄したのではないか」と、
大いなる自負をもっていいのである。
″壮年時代″は、もとより、
力なく衰えていく
″人生の黄昏時たそがれどき″ではない。
妙法を護持した人は、
年は若くなり、
福徳をさらに重ねていける
――こう大聖人は仰せである。(御書1135㌻)
創価の壮年は、
年齢を重ね、
経験を重ねるごとに、
ますます壮健であってもらいたい。
人生の勝負は、途中では決まらない。
最後の数年間で決まる。
その時に、
荘厳な夕日のごとく
″黄金の輝き″を放っていくための信仰である。
ともどもに広宣流布に生きぬいて、
王者のごとく、勇敢に、堂々と、自由自在に、
人生の総仕上げを飾ってまいりたい。
壮年部の皆さん、頑張りましょう!
2005.10.13第五十三回本部幹部会
2022年11月13日
第2142回
傲慢から一切が狂っていく
<日本人は少しでも自分が上だと思うと、すぐに威張る>
十九世紀のイタリア統一の英雄マッツィーニは述べている。
「短気と人間の高慢とは、巧妙な悪事よりも、甚しく魂を邪道に導き陥れる」(『人間義務論』大類伸訳、岩波文庫)
これが歴史の教訓である。自分が偉いと思って、傲慢になる。私欲に走る。そこから一切が狂っていく。
これまでの反逆者も、傲慢な人間ばかりであった。
著名な教育者であり、農政学者の新渡戸稲造博士。
国際連盟の事務次長も務め、最後はカナダで亡くなった人物である。博士はつづっている。
「人間の交際上最も邪魔になるもの、且つ日常生活を最も不愉快にするものは、威張る癖である」
「日本人ほど威張りたがるものは類が少いかと思われる」(『人生読本』、『新渡戸稲造全集』10所収、教文館)
鋭い指摘である。かつて日本は中国や韓・朝鮮半島の人々を見下して、侵略し、いじめぬいた。
少しでも自分が上だと思うと、すぐに威張る。
それでは真の友情を結ぶことはできないし、
信頼を勝ち取こともできない。
結局、皆から嫌われてしまう。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年11月12日
第2141回
人類の未来は、
人間主義しか道はない
富山県出身の信念の政治家、松村謙三氏はこう述べている。
「″国民とともにある政治″――これはまことに平凡な言葉かもしれぬ。しかし本当に政治を清潔にし、国民の利害に一致する政治を行なうためにはわれわれ政治家はこの″国民とともにある政治″を片時も忘れてはならないのである」(『花好月圓――松村謙三遺文集』青林書院新社)
国民のために。国民とともに。それを貫かれた氏であった。
松村氏とは、かつて都内で語り合ったことが懐かしい。(1970年三月)
氏は、若い私に「日中友好」という悲願を託してくださった。
日中の国交正常化はもとより、
私は、ソ連と中国の和解、
キューバとアメリカの関係改善にも、
一民間人の立場で、力を尽くしてきた。
冷戦終結の立役者ゴルバチョフ元ソ連大統領、
またアメリカの元国務長官キッシンジャー博士とも何度も語り合った。
世界の指導者と対話を重ねた。
文化で民衆の心を結び、平和の潮流を広げてきた。
ともあれ、
人類の未来は、人間主義しか道はない。
今、創価の哲学を、
世界が求めている。
支持している。
大きな期待を寄せている。
これも、すべてSGIの同志の皆さまの偉大なる奮闘の証である。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年11月11日
第2140回
人間の偉さ
<報恩こそ仏法の魂>
人間の偉さは、どこにあるか。
戸田先生は言われた。
「本当の偉さとは、
たとえ人にしてあげたことは忘れても、
してもらったことは一生涯忘れないで、
その恩を返していこうとすることだ。
そこに仏法の光がある。
また人格の輝きがあり、
人間の深さ、
大きさ、
味わいがある」
人にしてあげたことは忘れても、
してもらったことは一生忘れない!
すごい言葉である。
「それは、えらく損ですね」という人もいるだろう。
たいていの人は、この言葉の反対をやっている(笑い)
しかし、私は、先生の言われることは正しいと思う。
報恩こそ仏法の魂であるからだ。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年11月10日
第2139回
大聖人の仏法は
「無限の向上」の大法
<あらゆる人を活かせ!>
戸田先生はこうも語っておられた。
「南無妙法蓮華経の信仰は、
向上を意味する。
無限の向上である。
朝に今日一日の伸びんことを思い、
勇躍して今日一日を楽しむ。
しかして無限に向上して行く」
「まだまだ、その上へその上へと向上して行く法である」
大聖人の仏法は「無限の向上」の大法である。
飛行機が離陸して、上へ上へと飛んでいくように、
今日より明日へ、明日よりあさってへと、
どこまでも向上していく力が、妙法なのである。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年11月9日
第2138回
学び続ける人生は負けない
<学びは偉大な前進・価値創造>
学ぶことは楽しい。
“知”の発見は
人生の喜びである。
そして喜びが
才能の芽を伸ばす。
人との比較ではなく、
自分なりに
向上していくことである。
学び続ける人、
行動し続ける人は
永遠に若い。
向上しゆく生命は、
たゆみなく流れる
水のように
常に新しく、
清らかさがある。
活字を読むことによって、
頭脳が、精神が、
創造力が
どんどん鍛えられていく。
なかんずく
人類の遺産である
良書によって、
生命そのものを
磨き深めることができる。
読書は、
生命と生命の打ち合いだ。
その積み重ねの中でこそ、
どんな時代の激流にも
動じない生命力をもった、
大いなる自己を
鍛え上げることができる。
仕事の場でも家庭でも、
日常の瑣事の中からでも、
得がたい勉強を
していくことができる。
5分の間に新聞を読む、
本をひもとく、
ニュースに耳を傾ける、
人との出会いからも必ず
何かをつかみとっていく。
忙しそうに見えても、
その人は、
「多忙」そのものを
「学び」に変えていける。
学べば「世界」は広がる。
「学ぶ」こと自体が
「喜び」であり
「幸福」である。
「学ぼうとする決意」は
即「希望の光」であり、
「学び抜こうとする執念」は
即「勝利の光」である。
学び続ける人生は、
決して負けない。
学び抜く生命には、
偉大な前進があり、
価値創造がある。
2022年11月6日〈池田大作先生 四季の励まし〉
2022年11月8日
第2137回
長所を活かせば皆が人材
<あらゆる人を活かせ!>
広宣流布の前進のために、
戸田先生は大切な将軍学を教えてくださった。
「どんな立派な人間でも、短所がある。
また、どんな癖のある人間でも、長所がある。
そこを活かしてあげれば、
みな、人材として活躍できるのだ。
人を見て、その人にあった働き場所を考えることがホシだ」
あらゆる人を活かせ!
――幹部は、この点を絶対に忘れてはならない。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年11月6日7日
第2136回
希望の王子・王女に贈る
(7)
「創価の力」を、世界へ未来へ!
全ての子どもの幸福と平和を願い、
牧口先生と戸田先生は、
1930年の11月8日、
『創価教育学体系』を発刊しました。
これが学会の創立の日です。
「創価」とは、
「価値を創造する力」のことです。
何があっても負けないで、
新たな希望の道を創り開く力です。
この力を、人間の生命から引き出し、
皆を幸福へ、世界を平和へリードしていくのが、
私たちの広宣流布なのです。
どれほど大切な人類の宝の皆さんか。
一人一人に、偉大な使命があります。
自信と誇りに胸を張り、朗らかに学び、
皆さんの「創価の力」を、世界へ未来へ!
2022年11月1日付 少年少女きぼう新聞 KIBOU(12面)
2022年11月2日~5日
第2135回
青年よ
「汝は王者。ただ一人、征け!」
<わが志を、厳然と、そして平然と掲げよ!>
偉大だからこそ中傷される。
正義を貫くからこそ嫉妬され、迫害される。
信念を曲げ、要領よく振る舞えば、
中傷や誹謗は受けないであろう。
しかし、それでは真に偉大な人間とはいえない。
プーシキンが、吹き荒れる誹謗中傷を見おろし、悠然と記した詩がある。その一節を、きょうは青年部に贈りたい。
「詩人よ!」
「愚か者の罵りや嘲笑を耳にするとも、わが志を、厳然と、そして平然と掲げよ!
汝は王者。ただ一人、征け!
自由の大道を、自在なる英知をもって進みゆけ!」(А.С.Пушкин:Собрание счинений. том2, Худсжественная питература)
学会精神、仏法の精神と共鳴する言葉である。
青春時代より、私がずっと胸に秘めてきた一詩である。
また、プーシキンが若い画家を励ました言葉を紹介したい。
その画家とは、名画「第九の怒濤」の作者アイヴァゾフスキーである。この名画は、東京富士美術館などでも展覧された。
プーシキンは呼びかけた。
「働きなさい!
働きなさい!
青年よ!
これが一番、大切なことである」
これもまた、学会の指導に通じる言葉である。
戦いなさい!――青年部の諸君、頼むよ!
2005.11.2第30回SGI総会、第54回本部幹部会
2022年10月29日~11月1日
第2134回
どんな時も弟子として振る舞え
<偉大な人物は恩を決して忘れない>
マルクス・アウレリウスは、
皇帝という最高の権力の座にあっても、
哲学を求め、実践していった。
これは、非常に重要な一点である。
哲学のない闘争は、
野心の闘争にすぎない。
哲学がなければ、
正義はない。
人道もない。
善悪もない。
そのような戦いに明け暮れるのは、
いわば、畜生の世界である。
マルクス・アウレリウスは、
皇帝としての激務に打ち込みながら、
わずかな時間の合間をぬって、
静かに自己と対話し、
みずからの思索の跡を書きつづっていった。
そうした思想の断片は『自省録』としてまとめられ、
今日にいたるまで、多くの人々に読み継がれている。
『自省録』の最初には、
自分をこれまで育ててくれた
親や教師たち一人一人の名を挙げながら、
ことこまかに、感謝の思いがつづられている。
偉大な人物は、
恩を決して忘れないものだ。
恩を知ってこそ、人間として一人前といえるだろう。
とくに彼は、自分の養父であり、
先代の皇帝であり、
ローマの平和と繁栄を築いたアントニヌス・ピウス(在位一三八年〜一六一年)に対して、深い感謝を捧げている。
彼は、この先代皇帝を「師」とも仰いでいた。
「あらゆることにおいてアントーニーヌスの弟子としてふるまえ」(『自省録』神谷美恵子訳、岩波文庫)――こう、彼は記している。
先代を深く敬う彼の姿に、
周囲の人々も、粛然と襟を正したにちがいない。
創価の三代の師弟を貫く精神もまた、
この精神と同様である。
戸田先生は、
いかなるときも牧口先生の弟子として振る舞われた。
私も、どんな迫害の嵐があろうと、
勇敢なる戸田先生の弟子として生きぬいてきた。
それで創価学会は、世界的になった。
あとは皆さんの責任である。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年10月27日28日
第2133回
陰で戦っている人は信頼できる
十六世紀のフランスの思想家モンテニュは、こう言っている。
「人に知られるだろうからというだけで、また、人に知られればいっそう尊敬されるだろうからというだけで善人である人、自分の徳が人に知られるということがなければ善を、おこなわない人、こういう人には大事を託すことはできない」
(『エセー』4、原二郎訳、岩波文庫)
まったく、そのとおりである。
私は、だれが見ていようといまいと、
戸田先生に仕えきった。
学会に尽くしぬいてきた。
陰の戦いに徹してきたがゆえに、
私には、陰で戦っている人の苦労がわかる。
見えないところで真剣に戦っている人こそ、
最も信頼できる。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年10月25日26日
第2132回
何よりも大事なことは
<同志が功徳を受け、
希望と自信と喜びに満ちあふれて前進すること>
大聖人は、この竜の口の法難にあって、お供して殉じようとした誉れの弟子・四条金吾に対して、悠然と言い放たれた。
「これほどの喜びを笑っていきなさい」(御書914㌻、通解)
この大境涯にまっすぐ連なっているのが、わが創価学会である。あらゆる難を不惜身命で勝ち越えてきた。一番、大事なのは、広宣流布のために戦う学会員である。
大聖人は仰せである。
「法華経を持つ人は、男性ならば、どんな身分の低い者であっても、三界の主である大梵天王、帝釈天王、四大天王、転輪聖王、また中国、日本の国主などよりも勝れている。ましてや、日本国の大臣や公卿、源氏や平家の侍、人民などに勝れていることは、いうにおよばない。女性ならば憍尸迦女(帝釈天の妃)、吉祥天女(インドの女性神)、あるいは漢の李夫人(武帝の夫人)、楊貴妃などの無量無辺の一切の女性に勝れている」(御書1378㌻、通解)
まさに、妙法を弘めゆく学会員の皆さまのことである。
いかなる権力の人間も、
学会員の尊貴さにはかなわない。
同志が功徳を受け、
希望と自信と喜びに満ちあふれで前進していく。
それこそが、何よりも大事である。
幸福の連帯を拡大する――これがわれらの勝利であるからだ。
最後に、次の御文を拝したい。
「がうじやう強盛にはがみ切歯をしてたゆ弛む心なかれ、例せば日蓮が平左衛門の尉がもとにて・うちふるまい振舞・いゐしがごとく・すこしも・をづ畏る心なかれ」(御書1084㌻)
たゆむ心なかれ!
恐るる心なかれ!
この御聖訓を深く拝しながら、
さらに勇敢に、正義と勝利の大前進をしゆくことを、
ともどもに朗らかに決意しあって、
私のスピーチとさせていただく。
2005.9.12各部代表協議会
2022年10月23日
第2131回
人を育てるロマンと喜び
人を育てることは、
自分も
大きくなることである。
人に教えることは、
自分も
賢くなることである。
「法」といっても所詮、
弘めるのは「人」である。
ゆえに
人を育てることこそ、
究極の「陰徳」と
いってよい。
その「陽報」は、
まさに計り知れないのだ。
初めて会合に
来てくれた友がいる。
悩みを抱えて、
真剣に題目を
唱え始めた友がいる。
勇気を奮って
対話に挑戦した友がいる。
目立たなくとも、
黙々と動いてくれる
友がいる……。
皆、どれほど尊い
使命の方々か!
誰もが、大切な
広布の人材なのだ!
皆の成長を願い、
胸襟を開いて
語り合うことだ。
一人一人に心を配り、
足を運ぶことだ。
その祈りと
行動があるところ、
どんな心の扉も、
必ず開かれていく。
まず共に実践である。
人のために、
祈り、動き、語る。
この菩薩行の中で、
言い知れぬ充実と
歓喜を味わい、
確信をつかみとる。
これが、人材を育てる
学会の誉れの伝統である。
一回の出会いでも、
一言の激励でも、
それが種となって、
多くの実を結ぶ。
心も躍る、
その結実を見守りながら、
さらに明日へ
希望の種を蒔いていく――
これが、
地道でありながら
ロマンに満ちた
学会の庭の手づくりの
人間教育である。
2022年10月23日池田大作先生の写真と言葉「四季の励まし」
2022年10月21日22日
第2130回
自分が死に物狂いで祈る
<その功徳は全部、家族に通じていく>
皆さんのなかには、
ご両親やご家族が病気の方も、おられると思う。
私は、全同志の健康を、
いつも真剣に祈っている。
題目を送っている。
病気といっても、
さまざまな事情や状況があり、
いちがいに言えない部分もあるかもしれない。
しかし大切なことは、
まず自分が、しっかりと家族の健康を祈っていくことだ。
必ず病気を治すのだと決めて、本気で祈ることだ。
自分が死に物狂いで祈る。
必死になって広布へ戦う。
その功徳は全部、親に通じていく。
家族に伝わっていく。
どこまでも強く、強く進むのだ。
また、たとえば、
病気のお母さんに対しては、
「私が、お母さんのために真剣に祈っているから!
絶対に治るよ!」と声をかけて、励ましていってほしい。
人間は、だれでも病気になる。
大切なのは、病気の人が少しでも元気になるように、
激励していくことだ。
心を砕いていくことである。
どうか、よろしくお伝えください。
2005.9.27創立七十五周年記念各部代表協議会
2022年10月20日
第2129回
苦悩する人々を救う忍辱の人たれ
<″忍辱の心″こそが仏>
ことで御書を拝したい。
大聖人は「南部六郎殿御書」で、
天台大師の師匠である南岳大師の次の言葉を引いておられる。
「もし菩薩がいて、悪人をかばって、
その罪を罰することができないで、
そのために悪を増長させ、
善人を悩乱させて、
正法を破壊させるならば、
この人は実は菩薩ではない」
(新1806㌻、全1374㌻、通解)
仏法は「行動」が魂である。
いくら立派な菩薩といわれる人であっても、
現実に謗法と戦わず、
見て見ぬふりをして、
正法が破られるのを許すのであれば、
その人は菩薩ではない。
それどころか、
「その人は死後、諸の悪人とともに地獄に堕ちるであろう」
(新1806㌻、全1374㌻、通解)と結論しているのである。
悪と戦わなければ、悪を増長させ、
結果的に悪と同じ罪を背負うことになってしまう。
ゆえに徹して悪を責ぬけ!
――これが、牧口初代会長の正義の叫びであった。
悪を滅してこそ、善の世界は広がる。
ゆえに、強い「破折の心」で祈りに祈り、
わが正義を語りきっていくことである。
大聖人は仰せである。
「おのおの日蓮の弟子と名乗る人々は、
一人も臆する心を起こしてはならない」(御書910㌻、通解)
大聖人は「師子」であられた。
弟子の私たちもまた「師子」である。
何ものも恐れない「勇気の信心」で進んでいくことだ。
さらに「御義口伝」には、
「忍辱は寂光土なり
此の忍辱の心を釈迦牟尼仏と云えり」(御書771㌻)と仰せである。
現実の社会の中に飛び込んで、
苦しむ人々を救うために、
いわれなき批判や悪口にあえながら、
生き生きと、妙法を弘め続ける
――この″忍辱の心″こそが仏であるとの御断言である。
この心を心として、
意気揚々と前進している勇者こそ、
わが誉れの同志なのである。
2005.9.12各部代表協議会
2022年10月18日19日
第2128回
勇気をもって語れば、
人の心は変えられる
<核戦争による破滅を防ぐ手だては>
戸田先生とともに旅した仙台に、
かのアインシュタイン博士も訪れた。
博士は関西、東京、愛知、九州にも足を運んでいる。
博士が、第二次世界大戦のころから、
繰り返し、訴えていたことは何であったか。
それは、「人の心を変えなければならない」という一点であった。
核戦争による破滅を防ぐ手だてはあるのか、
との問いに、彼は「ある」と断言する。
「邪悪な心を征服さえできたらね。
科学的手段に頼らず、
われわれ自身が心を入れ替え、
勇気をもって正義を語れば、
人の心を変えられるだろう」(ウィリアム・ヘルマンス『アインンュタイン、神を語る』雑賀紀彦訳、工作舎)
「人間革命」の哲学と深く響き合う。
ゆえに友よ、人間の心に巣くう、邪悪と戦え!
勇気をもって正義と語れ!
平和の道も、
幸福の道も、
その一人一人の戦いから始まるのだ。
2005.8.24創立七十五周年記念協議会
2022年10月17日
第2127回
わが地域の組織を、
もう一つつくる心意気で!
<だからこそ朗々と題目をあげるのだ>
思うようにいかないとこともあるかもしれない。
しかし、人のせいにして愚痴を言うだけ
――そんな消極的な姿勢は、勝利者の生き方ではない。
そういう時こそ、
元気よく、朗々と題目をあげるのだ。
「わが地域を日本一にしよう!」
「わが使命の本陣を、世界一にしよう!」
師子吼するのだ。
猛然と祈るのだ。
「私の祈りで、私の叫びで、皆の心を動かしてみせる!」と。
断固たる決心で進むのだ。
わが地域の組織を、
新しく、もう一つ、つくるくらいの心意気で!
最後の最後まで、
皆を励ましていくのだ。
そして、叫んで叫んで叫びきっていくことである。
2005.8.24創立七十五周年記念協議会
2022年10月14日15日16日
第2126回
師ならどうするか
「師弟不二」こそ「絶対勝利の力」
<偉大な師匠を持つ人生は幸福である>
アメリカの第三代大統領ジェファソンといえば、「アメリカ民主主義の父」として、あまりにも有名である。独立宣言を起草し、信教の自由を打ち立て、大学総長として教育に尽くした。
彼の原点は何か。それは青春時代の恩師との出会いであった。
ジェフアァン青年は、故郷バージニアの大学に入学する。そこで自然科学や数学、倫理学などを教えていたのが、スモール博士であった。
博士の講義のさい、真理の探究に燃える目で、鋭い質問をする学生がいた。ジェファソンだった。ある日、講義の後、博士は彼に声をかけ、散歩しながら話をした。
以来、博士とジェファソンは、毎日のように、科学をはじめ、さまざまなテーマをめぐって語り合った。まさに、「一対一」の人間教育であった。
博士は、ジェファソン青年を、実社会で活躍する識者や指導者にも、どんどん会わせた。師の薫育によって、若き知性は劇的に開花し、めざましい成長を遂げていったのである。
後年、ジェファソンは、スモール博士との出会いが、一生の運命を決定づけたと感謝している。
ほかに影響を受けた人物に、ランドルフ教授やウィズ教授がおり、ジェファソンは孫に、こう書き送っている
「私は大変早い時期に高貴な性格の人と知り合えたこと、そして、彼らのようになりたいと常に願っていたことで、私がいかに幸運であったかを思います。誘惑にあった時、そして困難な状況に面した時、スモール博士、ウィズ氏、ペイトン・ランドルフ氏はどうするであろうと自分自身に問うてみたものです。どうすればこれらの人々の承認を得られるだろうか[と自分に問いました]。このようにして自分の行動を決めたことが、他のどんな理由よりも、正しい方向に自分を導いたと思います」(明石紀雄『モンティチェロのジェファソン』ミネルバァ書房)
偉大な師匠を持つ人生は、幸福である。
偉大な師匠の弟子として生きゆく人生ほど、
強く、深く、美しい劇はない。
ジェファソンの思いが私にはよくわかる。
青春時代、私は全生命をかけて戸田先生にお出えし、訓練を受けた。
今も胸中の先生と対話しながら、
広宣流布の指揮を執っている。
「戸田先生なら、どうするであろうか」と。
「師弟不二」なれば、何ものにも揺るがない。
「師弟不二」なれば、何ものをも恐れない。
「師弟不二」こそ、究極の「絶対勝利の力」なのである。
2005.8.24創立七十五周年記念協議会
2022年10月12日13日
第2125回
徹して戦え!
心晴ればれと勝関をあげられるまで
<なぜ勝つまで戦わないのです?>
人生は、戦いがあるから、おもしろい。
われらの戦いは、
声の力、精神の力で社会を変える戦いだ。
幸福と平和を築く立正安国の戦いである。
戦いは、遠慮したら、だめだ。
臆病であったり、
ひいたりしてはいけない。
ちょっとやって終わり
――それでは、戦いとはいえない。
徹底してやるのだ。
イギリスのシェークスピアの戯曲のせりふに、こうあった。
「なぜ勝つまで戦わないのです?」
(『コリオレーナス』小田島雄志訳、『シェイクスピア全集』3所収、白水社)
あと、もう少し!
もうひと踏ん張りだ!
そうやって、
歯を食いしばって進んでこそ、
心晴ればれと勝関をあげられる。
ともに勝利の喜びを味わうことができるのだ。
2005.8.24 創立七十五周年記念協議会
 日めくり人間革命
日めくり人間革命