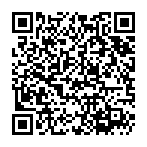新・人間革命に学ぶ
2018年9月15日
第1524回
我らの「人間革命」の挑戦に
終わりはない
<余韻にひたらず、常に新たな前進を!>
今月八日、小説『新・人間革命』の新聞連載が、全三十巻をもって、完結の時を迎えた。
沖縄での前作の起稿からは、五十四年に及ぶ執筆となる。
「命の限り」と覚悟しての挑戦であったが、全同志の真心に包まれ「更賜寿命」の大功徳で、牧口常三郎先生、戸田先生にお誓いした世界広布の大前進の中、連載の区切りをつけることができた。
弟子として感慨は無量であり、感謝は言葉に尽くすことができない。
あの地震直後の北海道では、婦人部をはじめ、同志の祈りと関係者のご尽力で、最終回の載った八日付紙面が印刷・配布されたと伺った。
あらためて、陰に陽に支え続けてくださった、日本中、世界中の全ての皆様に心から御礼を申し上げたい。
ありがたくも、「連載が終わって寂しい」との声も多く頂いている。
しかし、師弟して歩む我らの「人間革命」の挑戦に終わりはない。
私は、可憐な鼓笛隊の演奏会で目に留めた光景を思い出す。それは、舞台の奥で真剣に打楽器を叩く乙女が、演奏の際、楽器にパッと手を添え、余韻が残らないように工夫していた姿である。
「余韻にひたらず、常に新たな前進を!」――日蓮仏法の真髄は「本因妙」だ。一つの「終幕」は、新たな戦いの「開幕」なのである。
まさに「月月・日日につよ(強)り給へ・すこしもたゆ(撓)む心あらば魔たよりをうべし」(御書一一九〇ページ)である。
二十五年前、『新・人間革命』の執筆を始めた直後の九月、私はアメリカの名門ハーバード大学で、「二十一世紀文明と大乗仏教」と題して講演を行った。
そこで訴えた一点は、宗教をもつことが人間を
「強くするのか弱くするのか」
「善くするのか悪くするのか」
「賢くするのか愚かにするのか」――
この指標である。
変化の激流の中を生きることを運命づけられた人間が、より強く、より善く、より賢くなる――どこまでも成長していく原動力となってこそ、「人間のための宗教」なのである。そして、これこそが、我らの「人間革命の宗教」なのである。
この点、アメリカのデューイ協会元会長のガリソン博士も信頼の声を寄せてくださった。
“「人間革命」とは一人ひとりが、かけがえのない可能性を現実の中に開発し、社会全体に貢献していくのである。
ゆえに「人間革命」の理念を掲げるSGIは、「どこまでも成長する宗教」である”と。
誓願の旅は続く
『新・人間革命』に託した私の真情は、「戸田大学」で恩師から一対一の薫陶を受けたように、日本中、世界中の青年たちと、この書を通して命と命の対話を交わしたいということであった。
嬉しいことに、その願いの通り、今、いずこの地でも地涌の若人が「人間革命」の精神を学び、「山本伸一」の心を体して、人生と広布に、栄光の実証を威風堂々と勝ち示してくれている。
小説『人間革命』は、恩師が戦禍の暗闇を破って一人立つ、「黎明」の章で始まり、不二の弟子に受け継がれる「新・黎明」の章で終わった。
『新・人間革命』は、「旭日」の章で始まった。旭日が昇るように、創価の師弟は世界広布へ飛翔を開始したのだ。
恩師の分身として、仏法の慈光を世界へ届けるため、私は走った。
人間の中へ、民衆の中へ飛び込み、対話の渦を巻き起こしていった。そして、最後の章は、「誓願」として結んだ。
御書には、「願くは我が弟子等・大願ををこせ」(一五六一ページ)、「大願とは法華弘通なり」(七三六ページ)と仰せである。
師と同じ大法弘通の大願に立てば、力は無限に湧き出すことができる。それが、誇り高き地涌の菩薩の底力だ。
師弟の誓願の太陽は、母なる地球を照らし、未来永遠を照らす光源として、今、いやまして赫々と輝き始めたのである。
あの国にも、この天地にも、友がいる。民衆が待っている。
さあ、人類が待望してやまぬ「世界広布」即「世界平和」へ、新たな決意で、新たな出発だ。
我は進む。君も進め。
我は戦う。君も戦え。
我は勝つ。君も勝て。
我らは、共々に「人間革命」の大光を放ちながら、新鮮なる創価の師弟の大叙事詩を綴りゆくのだ! 君と我との誓願の旅を、永遠に!
随筆 永遠なれ創価の大城 34「人間革命」の大光 2018年9月15日
小説「新・人間革命」研さんに当たって
2018年10月3日
池田博正主任副会長
「山本伸一」の精神を胸に
池田大作先生の小説『新・人間革命』の連載が9月8日、完結を迎えた。現在、各地では『新・人間革命』の研さん運動が活発に行われている。新連載「世界広布の大道 小説『新・人間革命』に学ぶ」では、各巻を学ぶ上で、参考となる解説や資料を掲載していく。今回は「小説『新・人間革命』研さんに当たって」と題し、池田主任副会長へのインタビューを紹介する。(インタビューの内容は、創価新報の2017年2月1日付と3月1日付で掲載された記事に加筆し、再構成したものです)
池田先生が『新・人間革命』の執筆を開始されたのは65歳の時です。一般的には、“定年”という人生の一区切りの年齢でもあります。その時点で、先生は全30巻での完結という壮大な目標を目指し、新たな挑戦を宣言されました。
『新・人間革命』の「はじめに」には、小説の執筆は「限りある命の時間との、壮絶な闘争となる」と記されています。連載を待ってくれている読者、後継の弟子たちに、何を伝え残していくか。そこに、先生の人生を懸けた戦いがあるのだと感じてなりませんでした。
1993年(平成5年)8月6日の執筆開始から25年。『新・人間革命』の連載が、9月8日に完結を迎えました。振り返れば、『人間革命』の執筆が開始されたのは、1964年(昭和39年)12月2日です。
『新・人間革命』第10巻「言論城」の章には、「移動の車中などで、小説の資料となる文献を読み、構想を練り、早朝や深夜に、原稿用紙に向かう日が続いた」とつづられています。
54年にわたる『人間革命』『新・人間革命』の執筆は、海外訪問などの激務の中でも続けられた、寸暇を惜しんでの「闘争」でした。その激闘に、感謝してもしきれません。
「新」の一字の意義
池田先生が『新・人間革命』の執筆を開始されたのは、軽井沢の長野研修道場です。かつて私が研修道場を訪れた折、先生が記された「全三十冊の予定なり」との直筆原稿が展示されていました。
戸田先生は逝去の8カ月前、軽井沢の地で池田先生に語りました。「牧口先生のことは書けても、自分のことを一から十まで書き表すことなど、恥ずかしさが先に立って、できないということだよ」と。この時、池田先生は、恩師の真実を残すために、“続編”の執筆を固く決意されています。
池田先生の『人間革命』は戸田先生の出獄の場面から始まり、戸田先生が逝去された後、山本伸一が創価学会の会長に就任する場面で終わります。
一方、『新・人間革命』の冒頭は、伸一の会長就任から5カ月後、海外初訪問のシーンから始まっています。
これは、『新・人間革命』が、単に歴史的事実を追うものでなく、「世界広布」を主題としているからではないでしょうか。戸田先生から託された広宣流布の壮大な構想を、弟子がいかに実現していくか。いかに新たな時代に、人間革命の哲学と実践を展開していくか。そこに「新」という一字の意義があると言えるでしょう。
『人間革命』『新・人間革命』には、「一人の偉大な人間革命」が、多くの人々の地涌の生命を呼び覚ますという、人間に対する限りない信頼と尊敬の思想が底流にあります。
『新・人間革命』では、宿命転換を通して人間革命を実現している体験が数多く登場します。この人間革命のドラマの急所が、「誓願」と「願兼於業」の法理です。
「願兼於業」について、池田先生は「仏法における宿命転換論の結論です。端的に言えば、『宿命を使命に変える』生き方です。人生に起きたことには必ず意味がある。また、意味を見いだし、見つけていく。それが仏法者の生き方です」と述べられています。
今、自分が苦難を受けているのは、人を救う「菩薩の誓願」である――そうした学会員の力強い生き方が描かれているのが、『新・人間革命』です。
思いと行動の追体験
池田先生は『新・人間革命』の「はじめに」で、「私の足跡を記せる人はいても、私の心までは描けない。私でなければわからない真実の学会の歴史がある」と書かれています。小説は、人の心を描くには、一番適した形であると思います。
小説だからこそ、読者は、主人公の人生を追体験することができます。「山本伸一」は、あくまで仮名です。もちろん池田先生の生涯そのものですが、弟子の戦いが凝縮されたモデルとも言えます。
つまり、「山本伸一」の人生、心の奥底を追体験し、先生の思いに自分の思いを重ね合わせながら、共戦の道を歩むことができる。誰もが「山本伸一」として生きる可能性を持っているのです。
大発展するインド創価学会のメンバーの合言葉は、「アイ アム シンイチ・ヤマモト(私は山本伸一だ)」です。先生の『新・人間革命』を読み、インド広布に一人立った伸一の思いと行動を追体験しながら、“今こそ、自分が山本伸一の精神で戦おう”と立ち上がっています。
2010年(平成22年)以降、先生が直接、会合に出席されないようになったことで、『新・人間革命』の意義は一層、大きくなりました。先生は小説で、創価学会の精神の正史と、自身の心境をつづられながら、力強いメッセージを発信されてきたのです。
時代が進めば、小説で描かれている当時を知る人は減っていきます。もちろん、その証言は貴重ですが、『新・人間革命』によって、折々の広布史や学会精神が世代から世代へと、“先生の思いと共に”永続的に伝わっていく。ここが、より重要な点です。
言い換えれば、『新・人間革命』は、後世の学会員の依処となる“文証”とも言えるでしょう。だからこそ、私たちが今、しっかりと学んでいくことが大切です。それが、「学会の永遠性」の確立につながっていくのだと確信します。
連載の時期を確認
『新・人間革命』全30巻を、いきなり通して読むのは大変でしょう。その努力をしていくことは大切ですが、まずは、どの巻でも、どの場面でもいいので、自分が身近に感じるシーンや、現在、住んでいる地域・故郷などが描かれている部分を深く読み込んでいくことです。
例えば海外への足跡は、誰も知らないその国の“広布の第一歩”が記されています。日本国内でも、草創期の友の奮闘を通して、先生にしか書くことができない“原点”がとどめられています。その史実を学びながら、前後の背景を読み進めていくとよいでしょう。
また、連載された時期を確認することも大事です。なぜなら、先生は“執筆時”の真情をも記されているからです。
2011年9月1日から連載された「福光」の章は、同年3月11日の東日本大震災で被災した東北を中心に描かれています。先生は苦難に向き合う友へ光を当て、全精魂を込めて励ましを送り続けられました。その一文一文が、どれほど希望となったことでしょうか。
先月の11日から3日間にわたって掲載された「小説『新・人間革命』完結 記念特集」には、全30巻の「主な内容」が載っています。こうした記事を参考に、『新・人間革命』を開くのもいいでしょう。
わが誓願を果たそう
『新・人間革命』第1巻の「あとがき」に、こうつづられています。
「師の偉大な『構想』も、弟子が『実現』していかなければ、すべては幻となってしまう。師の示した『原理』は『応用』『展開』されてこそ価値をもつ」
これからの時代は、『新・人間革命』を、弟子の立場でどう深め、実践していくかが鍵となります。いかに自分たちの血肉とし、後世に正しく伝えていくか。その意味で青年部の皆さんは、使命ある“新・人間革命世代”と言えるでしょう。
8月22日付の「随筆 永遠なれ創価の大城」〈「誓願」の共戦譜〉で、先生は次のように述べられています。
「広宣流布という民衆勝利の大叙事詩たる『人間革命』『新・人間革命』は、わが全宝友と分かち合う黄金の日記文書なり、との思いで、私は綴ってきた。ゆえにそれは、連載の完結をもって終わるものでは決してない」
未来永遠に広布の「誓願」を貫き、自他共の生命を栄え光らせていく。師が託したこの思いに応えていく「使命」が、私たちにはあります。
一人一人が日々、『新・人間革命』の研さんを重ねながら、わが広布の「誓願」を果たし抜いていきましょう。
最終章を脱稿した長野研修道場で
1993年8月6日、池田先生が長野研修道場で執筆を開始した小説『新・人間革命』。起稿25周年の今年8月6日、同じ長野研修道場で、先生は最後の章を脱稿した。
広島原爆忌のこの日、先生は平和への祈りを捧げ、香峯子夫人と共に、研修の役員と出会いを刻んだ。
師は見守り続けている。
弟子の成長を――。
弟子の勝利を――。
「随筆 永遠なれ創価の大城」〈「人間革命」の大光〉に、先生は記した。
「我らは、共々に『人間革命』の大光を放ちながら、新鮮なる創価の師弟の大叙事詩を綴りゆくのだ!」
さあ、きょうも新たな出発だ。師弟の誓願を貫き、“わが黄金の日記文書”を朗らかにつづろう。
2018年10月3日付 聖教新聞 3面
日めくり人間革命
世界広布の大道
小説「新・人間革命」に学ぶ シリーズ
世界広布の大道 小説『新・人間革命』に学ぶII 6巻~10巻
世界広布の大道 小説『新・人間革命』に学ぶIII 11巻~15巻
世界広布の大道 小説『新・人間革命』に学ぶIV 16巻~20巻
 日めくり人間革命
日めくり人間革命