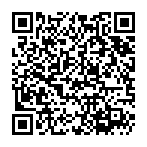私のトップ記事(2/)
2024年7月14日
〈スタートライン〉
希望の歌声を届ける
デュオ Paix²(ぺぺ)
500回を超える刑務所でのコンサート
心のスイッチを押したい
刑務所の受刑者に絶大な人気のある2人組の歌手がいる。北尾真奈美さんと井勝めぐみさんのデュオ「Paix²(ペペ)」だ。全国の矯正施設に足を運び、これまで533回にわたって「プリズンコンサート」を実施してきた。この活動を始めて来年で25周年を迎える2人にインタビューした。
――初めて刑務所で舞台に立った時の印象は?
真奈美 2000年の12月に鳥取の刑務所に行ったのですが、今まで経験したことのない光景に、とにかくびっくりしました。ステージに立つと、目の前に全員同じ服を着た丸刈り頭の受刑者の皆さんが、微動だにせずビシッと並んで座ってて。それを見た瞬間、頭が真っ白になりました(笑)。当時は知りませんでしたが、私語はいけない、よそ見はいけない、手拍子も禁止、などルールがあるんです。
――盛り上がりづらいルールですね。
めぐみ 今では事前に許可を取り、手拍子とかをやってもらって。『元気だせよ』という歌では、受刑者の皆さんと「元気だせよ~」と拳を突き上げて一緒にかけ声をやったりします。これらは私たちの長年の活動を信頼して、許可してくださるようになりました。
真奈美 Paix²のステージは、一冊の小説のように起承転結を意識しています。前半は静かなメッセージ性の強い楽曲、中盤はアップテンポで楽しく、後半は、ある長期受刑者の娘さんから届けられたメッセージを朗読しています。多くの方が涙されるのを見ていると、心がリセットされる瞬間なのかなと思います。
――お二人が刑務所の中で歌い続けるのは、なぜですか。
めぐみ やっぱり、二度と過ちを犯してほしくない、という思いからです。私たちの活動のテーマは「良い心のスイッチを押す」。刑務所の中は、前向きになるにはとても難しい環境です。それでも未来に向けて歩んでほしいなって。
真奈美 初めはとにかく楽しんでもらおうと思っていましたが、受刑者の数だけ外には被害者や遺族の方がいると思ったら、楽しんでもらうだけじゃだめだなと。どうすれば犯罪のない社会にできるだろう? そう考えるうちに、自分たちには、ここで歌う「使命」があるんじゃないかと思えるようになったのです。
めぐみ 私たちは「慰問」という言葉を使いません。慰めに行っているのではなく、「本当の幸せとは何か」というメッセージを携えて行きます。受刑者は加害者であり、被害者を生んでいます。だから、同じ人間として逆の立場になったことも想像してもらい、自分自身としっかり向き合う機会にしてほしいのです。
真奈美 受刑者の中には、犯罪を繰り返してしまう人も多くいます。新しい犯罪の数は減っていますが、再犯率はなかなか減っていません。その一番の理由が、就職の難しさだそうです。前科のある人と働きたいと思う人は少ないと思います。でも、出所した方の中には、自分の罪をしっかり反省して頑張っている方もいるんです。そういう人がいることを、少しでも一般社会の皆さんに知ってもらえるよう、刑務所の中と外をつなげていきたいです。
――印象に残っている出来事はありますか。
真奈美 活動を始めて2年くらいたって、いろいろ悩んでいた時に、プリズンコンサートを聞いて出所された方が、イベントに来てくれたんです。その方は、犯罪を繰り返し、何度も刑務所に入っていました。そんな時、私たちの歌を聴いて「自分も変わらなきゃいけない」と心を入れ替えて頑張れたと。それを聞いた時は、本当にやっててよかったなと思いました。
めぐみ 誰か一人でも、たった一人かもしれないけど、こういう思いをもってくださる方がいるということが、活動の励みになりました。
――悩んでいた時期もあったのですね。
めぐみ やっぱり経済的に大変だった時期があって。今でも、ワンボックスの車に音響設備を積んで、マネジャーと3人で全国を回っていますが、例えば東京から九州まで行っても謝礼が1万円とかだったり……。
真奈美 コンビニに入っても、おにぎり1個ずつと、大きなパックのお茶を分けて飲んだりしていましたね(笑)。ただ、当初から「お金が無いからやめる」ということは絶対にしないという強い思いが共通してありました。
――苦しい中でも続けてこられたのですね。
真奈美 始めた頃は、私たちの活動を知った人から「意味あるの?」と、ばかにされることもありました。でも、ポリシーを貫いたから、世間にも認めてもらえるようになったのかな。活動の内容が変わったわけではありません。だから、自分が正しいと思ったことを貫くのが大切だと思います。
めぐみ 苦しくても続けてきたからこそ、突き抜けられた今があります。頑張っても、すぐに結果になって見えるものばかりではないですよね。自分が苦労している間に、周りではキラキラしている人たちもいる。
でも若い時の苦労って、自分を知る大切な時間になると思う。もし何かに迷って、一歩踏み出せない人がいたら、自分を信じて歩み始めてほしいです。
後記
めぐみさんが、Paix²は本当はマネジャー兼プロデューサーの片山始さんを入れた3人で「ペペペ」だと言っていた。
片山さんは、活動を続けるために、さまざまお金を工面したそうだ。片山さんの「どうせやるなら、人のためになることをやろう」という強い信念が、2人を支え、3人の抜群のチームワークとなって、長く活動を続けてこられたのだろう。
Paixはフランス語で「平和」の意味。2乗し「ぺぺ」と呼ぶ。社会を明るくする運動や応援メッセージソングを発表するなど多彩な活動が評価され、内閣総理大臣賞、法務大臣賞等を受賞している。
北尾真奈美(きたおまなみ)。鳥取県倉吉市出身。前職は岡山大学固体地球研究センター(現・地球物質科学センター)で技術補佐員。
井勝めぐみ(いかつめぐみ)。鳥取県琴浦町出身。前職は看護師。
2024年7月1日
〈連載 三代会長の精神に学ぶ 歴史を創るはこの船たしか〉
第1回 牧口先生「人生地理学」
〈緒論〉(1903年10月)㊤
120年前の先師の叫びを源流に
創価教育が目指す「世界市民」の育成
21世紀に入ってから、まもなく4分の1が経とうとしている。世界が多くの危機に直面する中、すべての人々の生存の権利と尊厳が守られる「生命の世紀」を、どのように築いていけばよいのか。新連載「三代会長の精神に学ぶ――歴史を創るは この船たしか」では、初代会長・牧口常三郎先生、第2代会長・戸田城聖先生、第3代会長・池田大作先生の思想と生涯を通し、時代変革のうねりを民衆の手で巻き起こしていくための要点について学んでいきたい。
牧口先生「人生地理学」〈緒論〉(1903年10月)
私は(新潟県の)荒浜という寒村の出身で、さまざまな場所を転々としながら、人生の半分を衣食を得るために費やし、いまだ世の役に立つようなことはほとんどできていない。しかし、そんな取るに足らない私の身においても、そばにあるものに対してひとたび思いを注いでみる時、(生活を支える)それらのものが(思いも寄らない広大な範囲からの)計り知れない影響を受けて存在していることに、非常な驚きを感じずにはいられない。
私が着ている毛織物の衣服は、平凡なものだが、南米やオーストラリアで生産され、イギリス人の労働力とそこで採掘された鉄や石炭を利用して加工されたものだ。また、私の靴も特別なものではないが、底革はアメリカ合衆国の原産、その他の革は英領インドから来たものである。
◇
これらの原料が(世界各地の人々によって)牧畜されたり、採掘されたり、蒐集され、製造され、運搬されて、売買されることを通じて、ようやく私の身辺に届くまでの労力と時間について想像する時、またこうした有形の物の存在を通じて(世界とのつながりの深さに)気づかされる中で、形には表れない影響についても思いを馳せる時――すなわち、普段は何も気にせずに過ごしてきた単調なこれまでの人生が、こうした広大な(地理的)空間や時間による絶大な影響が重なり合う中で成り立ってきたことについて、思いをいたす時に驚倒しないではおられない。
私に子どもが生まれて、母乳を得られなかった時、粗悪な脱脂粉乳に悩まされたものだったが、医師の薦めでスイス産の乳製品にたどりつくことができ、ことなきを得た。スイスのジュラ山麓で働く牧童に感謝する思いだった。また、乳児が着ている綿着を見ると、インドで綿花栽培のために炎天下で汗を流して働く人の姿が思い浮かぶ。
平凡な一人の乳児であっても、その命は生まれた時から世界につながっていたのである。(『牧口常三郎全集』第1巻、趣意)
本年2月、創価教育の理念を受け継ぐ新しい学校の開校式が、マレーシアで行われた。
首都クアラルンプールの近郊にあるヌグリスンビラン州に開校した学校の名は、創価インターナショナルスクール・マレーシア(SISM)。中等教育と大学予備教育を行う学校で、日本の中高一貫校に当たる。
式典の最後で愛唱歌「共生の輝き」を合唱した1期生の138人の顔には、次代を担う決意があふれていた。
歴史を振り返れば、池田先生が、牧口先生と戸田先生の夢を実現するための第一歩として、東京・小平市に創価学園(創価中学校・高等学校)を創立したのは1967年11月。
以来、創価教育の学舎は、日本のみならず、このマレーシアを含めて、香港、シンガポール、韓国、アメリカ、ブラジルと、地球上に大きく広がっている。そのいずれの場所でも重視されてきたのが、「世界市民」の育成である。
SISMの開校準備が進んでいた2021年に創立者の池田先生が贈った「建学の精神」にも、「世界市民」の文字が重ねて掲げられていた。
一、徹して学ぶ「智慧の世界市民」たれ
一、多様性を成長の糧としゆく「勇気の世界市民」たれ
一、世界に友情を広げる「慈悲の世界市民」たれ
こうした教育の源流をなす思想が打ち出されていたのが、120年以上も前(1903年)に発刊された、牧口先生の『人生地理学』にほかならない。
牧口先生が『人生地理学』を世に問うたのは、32歳の時。
その2年前に北海道から東京に移り住み、妻と3人の幼子に加えて、目を悪くしていた養母との生活を支え、経済的な困窮が続く中で刻苦勉励して書き上げた、実に1000ページにも及ぶ大著であった。
当時、世界では、帝国主義や植民地主義の嵐が吹き荒れていた。その様相は、「国と国、人種と人種が、虎視眈々として、わずかな隙が生じた時に、競って他人の国を奪おうとし、あえて横暴で残虐な行為をすることもはばからない」(趣意)と、牧口先生が指摘していた姿そのものだった。
日本においても、日清戦争の勝利を経て、「富国強兵」の国策をさらに全力を挙げて推し進めようとしていた時代だったのである。
牧口先生は、そのような状況の下で、弱い立場に置かれた国や人々が、容赦なく苦しめられていることに胸を痛めていた。『人生地理学』の主眼は、こうした弱肉強食的な競争からの脱却を促すことにあったのだ。
今回、連載の開始に当たって最初に取り上げたのは、牧口先生がその時代の転換を図るための意識変革の出発点として、“他国の人々に対する眼差し”や“世界との向き合い方”について、自らの経験を通して論じている箇所である。
注目すべきは、世界を生存競争の場ではなく、人類の「共同生活」の舞台として受け止める重要性について論じる上で、牧口先生が焦点を当てていたのは、地理的な知識や経済的なつながりへの認識を深めることだけではなかったという点だ。(㊦に続く)
〈語句解説〉
ジュラ山麓 フランスとスイスにまたがり、ライン川とローヌ川の間を南西から北東に走る山脈のふもと。古くから、牧畜やチーズ製造が盛んに行われてきた。
帝国主義 政治・経済・軍事などの面で、他国の犠牲によって自国の利益や領土を拡大しようとする思想や政策。19世紀後半から、その動きが本格的に強まった。
富国強兵 明治政府のスローガン。殖産興業による経済的な発展と、近代的な軍事力の創設と増強が目指された。
※次回(第2回)は7月2日付に掲載予定
2024年6月14日
〈危機の時代を生きる 創価学会ドクター部編〉
第20回
命を守る土台となるもの
社会医療法人若竹会
つくばセントラル病院理事長
金子洋子さん
人類の進化と密接に関わる腎臓
体内の環境を整え活動を陰で支える沈黙の臓器
腎臓は、握りこぶしぐらいの大きさで、そら豆のような形をしている。
自覚症状が出にくい臓器だからこそ、定期的に健康診断を受けることが大切となる
長寿社会の現代。医療は多くの人々を支える重要な役割を果たしている。その最前線で働く友は、これからの時代を健康で生き生きと暮らすために必要なことを、仏法の健康の智慧から、どう見ているのか。「危機の時代を生きる 希望の哲学――創価学会ドクター部編」の第20回のテーマは「命を守る土台となるもの」。腎臓内科が専門で、社会医療法人若竹会「つくばセントラル病院」の理事長を務める金子洋子さんの寄稿を紹介する。
紅こうじのサプリメントを摂取した人に腎臓の障害が起こったことを巡り、厚生労働省は5月28日、この製造過程で青カビが混入し、健康被害を引き起こす「プベルル酸」などの化合物が作られた可能性があることを公表しました。
この問題が表面化した今春以降、私が所属する日本腎臓学会でも会員医師を対象にアンケート調査を行い、事態を注視してきましたが、多くの人は摂取をやめることで腎機能は改善するようです。適切な対応を行った上で、心配な方は医師に相談していただきたいと思います。
その上で、一般に腎臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、疾患の初期には自覚症状がほとんどないことが知られています。
特に日本では、成人の約8人に1人が「CKD」と呼ばれる慢性腎臓病を患っているといわれ、気付かない間に腎機能が低下し、進行すると透析や腎移植に至ることもあります。腎機能の低下は血液や尿の検査で分かりますので、健康診断を定期的に受け、異常を指摘されたら、早めに医療機関を受診してください。
血液の成分を調整
腎臓と聞いて、尿を作る臓器と思う人は多いかもしれません。それも正しいのですが、腎臓の機能はただ尿を作っているだけではありません。
血液をろ過して尿を作る腎臓は、その過程で、体内の水分量や体液の成分が一定になるようにコントロールしています。
具体的には、私たちが大量の水分を摂取した場合は、排出する尿の量を多くし、逆に汗をかいて体内の水分量が減った場合は、尿の量を少なくするといったことです。それとあわせ、体液に含まれるナトリウムやカリウムなどの成分、体液の酸とアルカリのバランスも一定になるように調整しています。
また腎臓は、各臓器に酸素を届けるために赤血球を増やしたり、血圧を調節する指令を出したりしています。
ちなみに腎臓でろ過される血液の量は、健常な人で1日当たり約150リットル、およそドラム缶1本分にもなります。ですが、全身を巡る血液の量は5リットル程度。つまり血液は1日に何度も腎臓に流れ込み、ろ過されて、常にきれいな状態に保たれているのです。また、実際に尿として排出されるのは1・5リットル程度なので、実に99%を再利用し、極力、無駄な老廃物だけを排出するようにしています。
腎臓がこのような役割を持つ臓器になったのは、進化の過程で私たちの祖先が海から陸へと生活の場を移してきたことと、密接な関わりがあると考えられています。
陸上で生活するためには、体内で水分や塩分などを保持しながら、体内にたまった老廃物を排せつする必要があります。その調節を担うのが腎臓なのです。事実、体液の組成は、太古の海に近いといわれます。腎臓の働きによって、その環境が陰で保持されているからこそ、私たちは生きていくことができます。いわば、腎臓は生命の恒常性を維持する「命を守る土台」と言えます。
減塩の工夫が肝腎
腎臓は“命の土台”だからこそ、異常が起きると、その影響は他の臓器にも及び、健康の維持が難しくなります。まさに、人体のネットワークを円滑に調整する要の役割を果たしているのです。
この腎臓とともに、人体にとって有害な物質を分解する肝臓の役割は、生命活動の源となることから、中国の伝統医学でも重要視されており、「肝腎(=大切な)」という言葉が生まれました。
仏典に見える病気予防の智慧
他者に尽くして身心共に健やか
生命を触発する利他の行動
健康の世紀開く鍵はここに
腎臓の役割は、仏法でも着目され、天台大師は「摩訶止観」で「体に気力がないのは腎臓が病む症状」と記しています。
「気力がない」とは疲れが残り、だるさを感じることから生じるものだと考えられますが、こうしただるさや疲れやすさは、腎臓病の症状の一つです。その意味で、天台大師の洞察は、腎臓の症状を正しく捉えたものと感じます。
では、腎臓を悪くしないために、どのようなことに気を付けたら良いのでしょうか。
基本的には、日々の生活習慣の改善が大切です。
睡眠不足や不規則な生活は、腎臓に負担がかかります。疲れを感じた時は、無理をせず、身体を休めるように心がけてください。
食事に関して、注意していただきたいのは、塩分の取り過ぎです。腎臓は、食事で摂取した塩分を尿として排出する働きをしていますが、塩分を取り過ぎると腎臓に負担がかかってしまうからです。
厚生労働省は、日本人の1日当たりの塩分摂取量の目標を、成人男性で7・5グラム未満、成人女性で6・5グラム未満としていますが、実際の摂取量は、成人男性が10・9グラム、成人女性が9・3グラム。多くの人が取り過ぎている状態です。塩分が過剰になると、高血圧や動脈硬化などにつながり、心臓や脳の病気を引き起こすリスクも高まります。しょうゆをかける量を少し減らす、麺類の汁は控えめにするなど、実行できるところから摂取量を減らす工夫をしていただきたいと思います。
また腎臓の健康維持には、運動も効果的です。慢性腎臓病のある人が1日5000歩ほど歩くと、腎機能の維持・向上がみられたという報告があります。日々、黙々と働く腎臓への思いやりの心を持って、少しずつでも運動習慣を身に付けてください。
「人のために火を」
腎臓は一度悪くなってしまうと、なかなか改善が見込めない臓器です。ですので、早期発見・早期治療のために定期的に健診を受けること、何より普段の心がけで悪化させないように予防していく大切さを感じています。
それらは、医学全体の流れでもあります。医学の進歩によって、病状が早期であるほど、治療できる可能性が高まっていますし、日々の生活習慣はもちろん、その人の考え方や心の持ち方が病気と密接につながっていることが明らかになってきたことで、予防も重要であるとの認識が広がってきたからです。
そうしたことは、仏法でも教えています。
例えば、「天台小止観」には、“病気にかかった時、すぐに治療することに努めよ。時間がたつと完全に病気になってしまい、治りにくくなる”と説かれています。これは早期発見・早期治療の大切さを教えていると感じます。
また仏法の思想には、病気にかからないようにするための、予防の智慧がちりばめられています。
一例を挙げれば、「四分律」という仏典では、歩くことの効用として「病気が少ない」「消化がよい」「よく思索できる」等とあり、これは現代医学の見解とも一致します。
その上で私が健康という観点で仏法の哲学が大事だと思うのは、周囲の人に尽くす大切さを教えていることです。
実は、利他の行動が健康に良いことを証明するような興味深い研究があります。高齢夫婦を5年にわたり追跡し、「支援する生き方」と「支援される生き方」という違いによって、死亡率がどう変わるのかを調べたものです。
その結果、他者に対して精神的な支えとなる生き方を貫いた人は、そうしなかった人に比べて長生きで、調査期間中の死亡率が2分の1となっていたことが分かりました。
また現代はストレス社会といわれますが、周囲のために動いたり、優しくしたりするといった利他の行動で、脳内ではオキシトシンというホルモンが分泌されます。このオキシトシンには、ストレスの軽減に大きな効果を持つことが分かっています。
まさに、利他の行動こそ、身体も心も健康にするものであり、日蓮大聖人が「人のために火をともせば、我がまえあきらかなるがごとし」(新2156・全1598)と仰せの通り、他者に尽くすことは、自分のためにもなっているのです。
病と向き合った母
私自身、母の闘病の姿を通して、利他の心に生き抜くことが、どれほどの力になるのかを身近に実感したことがあります。
母は9年前、多発性骨髄腫の宣告を受けました。完治が難しい血液のがんで、一般に診断から5年間で約50%の人が亡くなるといわれています。薬で進行を抑えてきましたが、7年を越し、ついに従来薬は全て使用し尽くし、効果が得られない状態になっていました。
そのような中でも母は、前を向いて強く祈り抜いていました。そして弱まるどころか逆に私たちを励まし、精神的な支えとなっていたのです。
そんな母を身近で見ていると、周りを励ます中で母自身が励まされ、それが生きる力となっているのだと感じてきました。また、母が気丈な心で病と向き合えたのは、池田大作先生の折々の言葉はもちろん、同志から励ましを受ける中で、胸の中に「絶対に治してみせる」との揺るぎない誓いが燃えていたからだと思います。
そして家族で祈りを深める中、母は幸運にも新薬による治験に参加することができ、それが功を奏して昨年6月に完全寛解となりました。
闘病を経験した母は今、これまで支えてくださった同志への感謝を胸に、ますますはつらつと、周囲の人が幸福をつかんでいけるよう、励ましを送っています。
信念を貫いた輝き
病気が回復する方がいる一方、誰しも生老病死から逃れることはできませんので、いつかは死を覚悟しなければならない時も来ます。そうした時にあってなお、最期まで人々のために尽くす信念を貫き、命を燃焼させた人には、その生き方に自らも続きたいと周囲に思わせる荘厳な輝きがあるというのが、これまで多くの臨終の場に立ち会ってきた私の実感です。
私がよく知る方は、病床にあっても見舞いに訪れる方々に励ましを送り、最期まで毅然とし、安祥として霊山へと旅立たれました。その臨終に触れ、悲しみが込み上げながらも、安らかな顔を見て、“私もその方に恥じないよう、目の前の一人の人に尽くしていこう”という思いが湧き上がってきました。
他者のために最期まで生き抜く学会員の姿は、一人から一人、また一人へと利他に生きる心を周囲に広げていく力になっていると確信します。
周囲の励ましは力
かつて池田先生は「利他という行動に触発されて、あらゆる生をはぐくむ、生命本源の力が、慈悲や英知のエネルギーとなって、絶え間なくわきあがってくるのです」と指導されました。
皆さんも、周囲の励ましに触れて心が前向きになり、生きる力が湧いてきた経験があると思います。他者のために心を砕き、他者に勇気と歓喜を与える行動には、自分だけでなく、周囲も健康にする力があるのです。
まさに他者に尽くす行動こそ「命を守る土台」であり、その心が広がっていくことこそ「健康の世紀」を開く鍵であると思えてなりません。
私自身、創価高校に通っていた時代、創立者である池田先生が目の前の一人一人の成長のために心を砕く振る舞いを目の当たりにし、利他の心の大切さと素晴らしさを学んだことが生涯の財産となっています。そして、その出会いが、人々の健康を守る医師を志す原点となりました。
自他共の幸福の道を開く最高の生き方を教えていただいた師への感謝を胸に、どこまでも苦悩を抱える方々に寄り添い、真心の励ましを送りながら、地域の同志と共に利他の心を広げていく決意です。
かねこ・ようこ 医学博士。専門は腎臓内科。創価高校卒業。筑波大学医学専門学群卒業。信州大学大学院博士課程医学研究科修了。社会医療法人若竹会「つくばセントラル病院」で腎臓内科部長、副院長などを経て現職。日本内科学会認定内科医・総合内科専門医。日本腎臓学会腎臓専門医・指導医。日本透析医学会透析専門医・指導医。創価学会関東ドクター部女性部長、女性部副本部長。
2024年3月23日
〈危機の時代を生きる 希望の哲学 創価学会学術部編〉
第26回
共生社会を築く言葉の力
差異を多様性の源にする鍵は「内省力」働かせる対話に
国際教養大学
専門職大学院教授
左治木敦子さん
在留外国人数は過去最多を更新している(共同)
互いを尊重し支え合う共生社会を築く上で、「言葉」によるコミュニケーションは大切な要素である。多様な人々との交流を輝かせる言葉の使い方とは何か。「危機の時代を生きる 希望の哲学――創価学会学術部編」の第26回のテーマは「共生社会を築く言葉の力」。日本語教育が専門で、国際教養大学専門職大学院教授の左治木敦子さんの寄稿を紹介する。
テレビやSNS等で「若者言葉」を時折、見かけます。中には年長者にとって、意味不明な言葉もあります。それもそのはずで、若者にしか通じない言葉で会話するからこそ、そこに一種の連帯感が生まれるのです。一方、理解できない人にとっては、その言葉が会話を阻む壁になります。
若者言葉だけでなく、職場や趣味の集まりなど、特定の人同士で共有される専門用語も同様です。言葉は使い方によって、連帯感を生む基になる一方、周囲に疎外感を抱かせる壁にもなります。
私たちが日頃、何げなく使っている日本語に、壁を感じる人たちがいます。例えば、日本語を母語としない非母語話者の在留外国人(日本に暮らす外国人)です。私はこれまで日本語教育、日本語教師養成に携わり、多くの非母語話者と関わってきました。
在留外国人数は過去最多の約322万人です。現在、その数は増加し続けています。在留外国人が多く居住する集住地域では、近隣や職場等で在留外国人に接したり、見かけたりする機会も多いのではないでしょうか。
オノマトペと敬語
外国人とのコミュニケーションというと、長い間、英語教育を受けてきた人は「英語を使わなくては……」と思いがちです。ですが、実は在留外国人で英語ができる人は、そんなに多くはありません。
今、国内での日本人と外国籍の人とのコミュニケーションには、日本語を使う時代になっているのです。そうした背景もあり、2019年(令和元年)に日本語教育推進法が施行され、日本語の学習支援の充実が図られています。
非母語話者の外国人が日本語を学ぶ場合、どのような難しさがあるのでしょうか。オノマトペといわれる擬音語・擬態語、外国語から日本語の語彙に入ってきた外来語、話し手の属性や相手との関係性により変わる敬語などが難しい例として挙げられます。
例えば、痛みを表す「キリキリ」「シクシク」「ズキズキ」「ドーン」といったオノマトペは、感覚的な表現のため、非母語話者には理解しにくいとされています。
次に敬語の使い方です。
「明日、東京に行く?」という質問を上司にするときは「明日、東京にいらっしゃいますか」となります。「行く」が「いらっしゃる」になる。敬語の表現も日本語の難しさの一つです。
非母語話者の外国籍の人にとっては、ごみの出し方、銀行口座の開き方などの公的情報は、入手、理解が困難なものです。多言語対応している情報もありますが、あまり多くありません。
特に災害時の情報が届かない場合、受け取れない場合は致命的な事態を引き起こしかねません。
先入観の“ラベル”を貼らず一対一の積極的な交流を
相手に伝わる言葉とは思いやる心から生じる
言語的弱者を置き去りにしないようにするには、どうしたらいいのでしょうか。
ここで紹介したい取り組みが、「やさしい日本語」です。1995年(平成7年)の阪神・淡路大震災を契機に考案され、東日本大震災などでも活用されました。日本語非母語話者でも理解しやすいよう、次のような工夫が施されています。
①一文を短くする。
「明日は雨なので、傘を持ってきてください」
→「明日は雨です。傘を持ってきてください」
②主語を省略しない。
「田中です」
→「私は田中です」
③敬語(尊敬語、謙譲語)を使わない。
「看護師をしております」
→「看護師です」
④分かりにくい語を言い換える。
「右折してください」
→「右に曲がってください」
これらのコツをまとめた「はっきり言う」「さいごまで言う」「みじかく言う」の最初の文字を取り、「ハサミの法則」ともいわれています。
これらの工夫を施すと、次のような表現になります。
「明日の懇談会は自由参加です」
→「明日、先生や他の保護者といろいろ話します。行っても行かなくてもいいです」
「やさしい日本語」は、日本語能力試験(JLPT)のN4からN5を想定しています。小学校2、3年で学習する程度の文字(漢字、ひらがな、カタカナ)により表現されています。「やさしい日本語」を用いた場合、情報の理解度が高くなったという調査結果も出ており、各自治体や、団体、マスコミなどでも導入する試みが始まりました。
言語的調節とは
ここまで、在留外国人が理解しやすい日本語の発信例を紹介しました。このように相手が理解しやすいよう言葉を配慮するのを「言語的調節」といいます。
実は私たちも普段、何げない会話の中で、話す相手により、難しい言葉を言い直したり、言い換えをしたりして調節をしています。「言語的調節」は、ただ内容を分かりやすく伝える技術ではなく、その背後には相手への気遣いの心があります。
私は、この「言語的調節」をしてもらった個人的な経験があります。私の住む秋田県には、方言があります。この方言は県外出身の私にはなかなか分かりづらい部分があります。ある日、私が地元の温泉に行った時のことです。浴槽では二人の女性が秋田弁で仲良く話をしていました。
やがて一人の女性が去り、私ともう一人の女性が浴槽に残りました。私は少し気まずい思いをしていました。というのも、私は少し前に脱衣場で、その女性から秋田弁で話しかけられていたにもかかわらず、彼女の言葉が全く分からなかったので、生返事をして通り過ぎていたのです。
二人だけになると、彼女は、くるりと私の方を向き、こう聞いてきました。「今の私たちの話、分かった?」。私にも分かる言葉でした。
私が小さく「いいえ」と首を振ると、その人は“なるほど”というようにうなずきました。そして、そのままの言葉で「冬の温泉は温まっていいね」と言い、浴槽を出て行きました。彼女は、私が秋田弁を分からないことに気づき(認識)、瞬時に自分の伝え方を変え(内省)、再度話しかけてくれたのです。
私は脱衣場で生返事をし、彼女とのコミュニケーションをやり過ごした自分の態度を深く反省しました。とともに、彼女が、私の理解できる言葉に言い直してくれた思いやりに心が温まる思いでした。
何よりも私への関わりを途中で放棄せず、最後まで「冬の温泉は温まっていいね」とコミュニケーションを取り続けてくださった積極性に心から感謝しました。
共生社会を築くためには、彼女のように、対話をする際に「自分の言葉は伝わっているだろうか」と相手の反応を確かめつつ、自分の言葉や伝え方を振り返る「内省力」が大切になってきます。
言葉というツール(道具)は、内省力がある人には、心と心をつなぐ「架け橋」になります。多少時間がかかっても意思疎通可能なツールを探り当てることができることでしょう。苦労をして心がつながった瞬間の喜びは忘れがたい経験となります。
因陀羅網の比喩
そんな「架け橋」にもなる言葉ですが、内省力を阻む危険な機能も含まれています。それは言葉の持つ「ラベルを貼る」という機能です。例えば相手に「外国人」というラベルを貼ることにより、知らず知らずのうちに世間の「外国人」のステレオタイプ(先入観)のラベルまでも貼ってしまうことがあります。
「外国人」=「日本語が伝わらない人」という先入観が働くと、コミュニケーションを取ろうという気持ちは途絶え、この内省力は働きにくくなります。心がラベルにとらわれてしまうからです。
そうした既成のラベルを貼ることなく、「可燃ごみの出し方が分からずに、困っている隣人のリーさん」「PTAの活動に不安を感じているパクさん」のように、自分の言葉で相手を認識したとき、「どうすれば分かりやすく伝えられるだろう」と内省力が働くのです。
そして、言葉の持つ壁を乗り越え、言葉の力を発揮させていく不断の努力が相手に伝わり、自らの成長にもつながるのではないでしょうか。
キルギスの作家アイトマートフ氏は、池田大作先生との対談集の序文で、「言葉はつねに我々の人格を、まるで写真で写したかのように、刻印している」とつづっています。言葉は使い手の人間性そのものといえましょう。
この言葉の力を見事に発揮しているのが、「言葉を自在に使う人」(ヤスパース著『佛陀と龍樹』峰島旭雄訳、理想社)と称された釈尊です。
釈尊は一部の特権階級が使う高尚な言語ではなく、当時の民衆語であったマガダ語を使い、巧みな比喩や明快な道理で、分かりやすく法を説きました。
共生社会を目指す上で、自分と他者との差異を対立の火種ではなく、多様性の輝きと捉えていく視点として紹介したいのが、仏典に説かれる「因陀羅網」の比喩です。
帝釈天の宮殿には、結び目一つ一つに美しい「宝石」が取りつけられた「宝の網」がかかっています。どの宝石も他のすべての宝石を相互に映し出すゆえに、輝きを増しているというものです。私の大好きな比喩です。
この比喩の深さは、ただ宝石が輝くという静止画的なものではありません。他の宝石の輝きを自らに映し出し、自らの輝きを増すということではないでしょうか。他を認めるだけという消極性を脱却し、相手との差異を自らに取り入れて輝くという能動的な相互作用を感じさせます。
ラベルを貼った先入観で相手を見るのではなく、自分とは異なる光を放つ相手に対し内省力を使い、内包していく。その中で、多様性が輝く共生社会が築かれていくのではないかと信じます。
精神の鍛えの中で
御書に「言と云うは、心の思いを響かして声を顕すを云うなり」(新713・全563)とあります。まさに相手を思いやる心から、相手に伝わる言葉が生み出されていくのだと思います。
私たちは仏法対話をするとき、相手に分かってほしいとの思いから、仏法の精神をなるべくかみ砕き、相手にも分かる言葉で語ろうとします。
日蓮大聖人が庶民に寄り添い、かな文字を使って手紙をしたためられたのも、そのような心遣いからではないでしょうか。都に上り、気取った言葉を使う弟子に対し、「言をば、ただいなかことばにてあるべし」(新1657・全1268)と、飾らない言葉を使うよう、厳しく教えられている箇所も見受けられます。
共生社会では、まず相手に配慮する、そして自分が歩み寄るという内省力が大事です。在留外国人といっても、滞在日数や出身国などの状況によって日本語の理解度は違うものです。
また、外国人(非母語話者)だけでなく、聴覚障がいや言語障がいがある人など、自分が話す言葉を受け取る相手の状況は千差万別です。
そうした一人一人に対し、すぐに完璧な「相手に伝わる言葉」を話せるわけではありません。「どうすれば伝わるか」と内省し、言い直しや言い換えを繰り返す中で、次第に相手に伝わる言葉が生まれるのです。大切なのは理解してくれると相手を信じ、自らの言葉を柔軟に変えていく粘り強さではないでしょうか。
池田先生は言葉を自分らしく使いこなすことの難しさについて、“言葉を使っているようでも、使われていることが想像以上に多い”と指摘されています。
そして「人間であろうとするかぎり、言葉という道具を自在に使いこなせるよう、精神を鍛え上げる以外にないのです。換言すれば、人間はそのままで人間であるのではなく、“言葉の海”の中で鍛えられてこそ、人間になるのです」とまで語られています。日々何げなく口にしている言葉を、精神の鍛えの中で使いこなそうとする中で、私たちは成長していけるのです。
私が言葉の教育者を目指したとき、その原点としたのは、池田先生の「言葉には翼がある」との指針です。
言葉の「壁」がある世界をつなげられるのは言葉を「翼」に変えた者ではないでしょうか。これからも自らの言葉を「翼」に変える鍛えを続け、生命尊厳の哲学を語り抜いていく決意です。
さじき・あつこ 博士(言語教育)。米インディアナ大学大学院博士課程修了。現在は国際教養大学専門職大学院教授。創価学会総秋田副学術部長。支部副女性部長。
2024年3月15日
〈危機の時代を生きる 創価学会ドクター部編〉
第19回
「薬」と向き合う
薬剤師 宮崎信一さん
多彩な物質を作って健康を守る 人体は“一大製薬工場”
長寿社会を支える医療。その最前線で働く友は、これからの時代を健康で生き生きと暮らすために必要なことを、仏法の健康の智慧から、どう見ているのか。「危機の時代を生きる 希望の哲学――創価学会ドクター部編」の第19回のテーマは「『薬』と向き合う」。調剤薬局を事業展開する会社に勤務する薬剤師の宮崎信一さんの寄稿を紹介する。
現行の健康保険証は12月に廃止され、マイナンバーカードと一体化したマイナ保険証に移行される見通しです。
マイナ保険証には一人一人の健康診断の結果や病院での受診情報、薬剤の処方歴といったデータが蓄積されていくので、医師がそうした情報をもとに、適切な治療につなげていくことが期待できます。
また災害時の避難で処方薬を置き忘れたとしても、マイナ保険証を確認することで、被災地で適切な薬を改めて処方できるようになります。
もちろん、そうした情報を管理することは情報漏洩のリスクとも隣り合わせで、不安を感じる人もいるでしょう。そうした問題が起こらないような対策や、持たない人への柔軟な対応を進めていくことは当然とした上で、私たち薬剤師の立場からは、このマイナ保険証の導入によって一人一人の健康が守られるメリットの方を感じています。
例えば、さまざまな疾患を抱え、複数の病院で受診しているような患者さんの場合、これまでは各病院や診療所でどんな薬が処方され、何種類の薬を飲んでいるのかは、お薬手帳の提示といった本人の情報提供がなければ分かりませんでした。実は、ここにリスクが潜んでいます。薬の中には相互作用を起こすものがあり、結果として人体に悪影響を及ぼすことがあるからです。御書にも「病人に薬をあたえるには、前に服用した薬のことを知らなければならない。薬と薬が(体内で)ぶつかって、争い、人の体をこわすことがある」(新1829・全1496、通解)とある通りです。
研究では、高齢者は薬の種類が増えるほど身体に異常が起こりやすく、6種類を超えると、そのリスクがより高まることが分かっています。そこでマイナ保険証で処方歴を知ることができれば、医師または医師への薬剤師の提案などで薬の種類を減らしたり、副作用のリスクを低減する方法を考えたりすることができるようになります。
その上で今は花粉症の季節ですが、処方された薬との相互作用は市販の花粉症の薬でも起こり得ますし、健康食品として扱われるサプリメントでも薬との飲み合わせの悪いものがあり、副作用のリスクが高まる可能性があります。
そうした情報は、マイナ保険証では分かりませんので、医療機関にかかる際は、飲んでいるサプリメントなどの情報についても積極的に提供していただければと思います。このほか、薬の服用について悩んだ時は、医師や薬剤師に相談してください。
食事 睡眠 運動 心の持ち方 全て病を乗り越える“薬”に
生命の次元から人間を蘇生 妙法こそ「第一の良薬」
そもそも、創薬の歴史を振り返ると、毒から生まれた薬は数多くあります。
その一つが抗がん剤で、第2次世界大戦で使われたマスタードガスという毒ガスが開発のきっかけとなりました。マスタードガスを浴びた人は白血球が減少してしまうのですが、これを応用すれば、白血病やリンパ腫といった血液のがんの治療に使えるのではないかと考え、類似構造の化合物を作ったことが抗がん剤の開発につながりました。
また、トカゲの持つ猛毒が糖尿病の薬に、植物の毒が心臓病の薬の開発につながったこともあります。
このように、薬と毒は紙一重だからこそ、用量を守ることが大切なのです。また飲むタイミングで効き方に差が生じ、場合によっては副作用として出ることもあるので、用法を守ることも大切です。
薬の中には、食前(食事の20~30分前)、食後(食事の20~30分後)など、飲む時間を指定しているものもありますが、その時間は食事によって変化する胃の状態や体内への吸収の度合いを踏まえて決められていますので、可能な限り、守っていただきたいと思います。
加えて、薬は水よりもお湯で飲んだ方が、吸収が早いことも分かっていますので、ぬるま湯で飲んでいただくことをお勧めします。
さまざまな食材を
ここまで述べてきた薬は私たち薬剤師が扱う「医薬品」のことで、用法・用量が文書で定められているものですが、もともと薬は自然界にある植物や鉱物などから、さまざまな病気や痛みなどの治療に役立つものを経験的に見つけ出したのが始まりです。ここからは、そうした“広義の薬”という観点で話を進めます。
まずは「食事」です。
第2代会長・戸田城聖先生が人体のことを「一大製薬工場」と言われた通り、体内では、さまざまな病気と闘うために、薬の働きをする多彩な物質を作り出していますが、それも原料となる物質がなければ作られません。その原料の多くが私たちが摂取する食物であることから、日々の食生活を健康につなげる意味でも、魚や野菜、キノコ、発酵食品など、「多彩な食材をバランス良く食べること」が大切です。
とりわけ、日本では魚を食べなくなってきているので、日々の食事の中で意識的に取り入れていただきたいと思います。魚に含まれるドコサヘキサエン酸(DHA)やエイコサペンタエン酸(EPA)といった脂肪酸には、血液をサラサラにして動脈硬化を抑える働きのほか、体内の炎症やアレルギーを抑える作用があることが知られています。
加えて野菜を食べることも必要です。緑や黄色、赤、オレンジ、紫、白と、色とりどりの野菜がありますが、そうした野菜にはビタミン、ミネラル、食物繊維が含まれ、老化予防や美肌効果などが期待できますので、さまざまな色の野菜を組み合わせて摂取することを心がけてください。
仏教が教える「食」
仏教でも「食」を「薬」と捉え、食事の重要性を教えてきました。例えば「九横経」という仏典では、人間が寿命を全うできない理由を九つの点から明らかにしていますが、そのうち四つが食事に関することです。
一つ目は「食物としてはならないものを食物とすること」。毒キノコなどを思い浮かべるかもしれませんが、今日では人体に悪い食品添加物なども分かってきているので、そうしたものを控え、過剰に摂取しないようにすることも含まれるでしょう。
二つ目は「食べる量を測らないこと」。食事の分量のことで、暴飲暴食への戒めです。食べ過ぎは、肥満や生活習慣病を助長するので注意が必要です。
三つ目は「慣習に従わないで食事をする」。気候や風土に従わないことへの注意です。
それぞれの地域には、その地ならではの食材や季節に応じた恵みがあります。現在は保存技術や流通の発達で、年間を通して多彩な食材を手に入れることができるようになりましたが、それぞれの食材には旬の時期があり、その時期に栄養価が高いことが知られています。また、例えば夏に旬を迎えるキュウリには、身体の熱を冷まし、喉の渇きを潤す効果がありますが、冬に食べてしまうと、逆に身体を冷やしてしまうことになります。このように、旬の時期に食べるということは栄養面のみならず、身体の調子を整える作用もあるのです。
四つ目は「消化しないのに食すること」。十分かまずに飲み込んだり、不規則な時間に食べたりすれば、胃腸に負荷がかかります。
最近では、食べたものが消化され、空腹を感じるくらい時間を置いた方が身体に良いことが明らかになってきました。空腹の時、体内では「オートファジー(自食作用)」といって、細胞内にたまった古い酵素や不要なタンパク質などを掃除しているのですが、時間を置かずに食べてしまうと、不要なものが体内に残ってしまい、細胞の機能を保てなくなってしまうのです。
年齢を重ねると消化機能も衰えてきますので、おなかがすいていなければ、1食抜いたり、軽めの食事にしたりするといったことも意識していただきたいと思います。
こうした四つの食事の注意点は、現代科学に照らしても説得力があります。
プラセボ効果
“広義の薬”という観点では、食事だけでなく、運動や睡眠も大切です。運動には動脈硬化や心筋梗塞などの予防に効果があることが知られていますし、睡眠には疲労回復はもちろん、認知症のリスクを抑えるなどの効果があります。まさに、生活習慣が薬のようになるのです。
加えて、心の持ち方も薬となります。この点について、科学でよく指摘されるのは「プラセボ効果」です。プラセボとは「偽薬」のことで、例えばデンプンや乳糖でも、患者が効くと思って服用すれば、本物の薬を飲んだかのように痛みが止まったり、体調が良くなったりと臨床的に良い効果が出ることです。
このプラセボ効果を最初に調査結果として発表したとされる麻酔実験学者のヘンリー・ビーチャーによれば、約1000人のうち35%、実に3人に1人の割合で、そうした効果があったとしています。
心の持ち方が健康に影響を与えるということは、さまざまな角度で研究が進んでいます。例えば、カナダの大学の研究では、がんの自然寛解、つまり治療を行っていないのに、がんが消滅した患者について調べ、その患者の行動パターンなどから、「信じる気持ち」が寛解と関係すると結論づけています。
またアメリカの研究者は、心と身体のつながりを示す実験を行っています。
それは被験者を三つのグループに分け、第1グループには指などを動かす運動を3カ月間、実際にやってもらい、第2グループには頭の中だけでやってもらい、何もしない第3グループとの間で、どのような差が生まれるのかを調べたものです。その結果、実際に運動を行った第1グループは、第3グループと比べて指の強さが向上したのは当然のこととして、頭の中で思い浮かべた第2グループの人でも、指の強さが35%も向上したというのです。
強い気持ちさえあれば、全ての病気を乗り越えられるとは思いませんが、少なくとも心の持ち方が身体に変化をもたらし、病に立ち向かう上での力になるということは言えるのではないでしょうか。
唱題を重ねる中で
御書の中にも、「薬」という字が多く登場します。その一つが「諸薬の中には南無妙法蓮華経は第一の良薬なり」(新155・全335)です。
妙法は、生命という根本の次元から人間をよみがえらせ、救っていく良薬である。この日蓮大聖人の確信の言葉に触れ、私自身も病を克服することができました。それは20歳の時に突如として起こったパニック障害です。
いつ発作が出るのか分からないという恐怖と、この先、どう生きていけばいいかという不安……。先ほどの御文に触れたのは、そんな時です。
そこから御本尊への向かい方が変わり、やがて最良の医師に巡り合い、私にとって最適な処方をしてもらう中で、体調も安定していきました。
その後も唱題を重ね、同志から励ましを受ける中で、自分の心が前向きに変わっていくことを実感しました。
発作が出たとしても、少しの間だけ我慢すれば治まるじゃないか。薬で症状も落ち着くのだし、この病気と上手に付き合っていけばいいじゃないか、と。
振り返ると、そう思えたことが薬になったのかもしれません。それまで病気の苦しみから目を背けてばかりでしたが、病気と真正面から向き合えるようになり、自分の力を信じられるようになったからです。その中で、いつの間にか不安がすっと消え、病を乗り越えることができました。
なぜ、大聖人は「第一の良薬」と仰せなのか。私の経験から言えば、それは題目によって最適な薬と出あい、題目によって心が薬のような役割を果たしたように、妙法には全ての“薬”の働きを自然と伸ばし、結果として最高の効果を引き出す力があるからだと思えてなりません。
かつて池田大作先生は、ドクター部のことを「二十一世紀の薬王菩薩」と呼びかけ、「医学で人を救う。そして、仏法で人を根本的に救う。これこそ世界の誰人もなし得ぬ、生命尊重の究極の道であります」と最大の期待を寄せてくださいました。
この限りない使命を胸に、人々が健康で生き生きと暮らしていける社会を目指して、力強く歩んでまいります。
みやざき・しんいち 1962年生まれ。明治薬科大学薬学部卒業。調剤薬局を事業展開する会社に勤務。創価学会ドクター部薬学部会委員長。総埼玉副ドクター部長。圏長。
2024年2月9日
クローズアップ ~未来への挑戦~
インド㊤
持続可能な時代を実現する鍵とは?
人類の境涯を高める哲学
アヌラダ・シャルマさん
人類の未来を左右するいくつもの危機に直面する現代にあって、世界の創価学会員は、そうした地球的課題や社会問題にどう向き合っているのか。新企画「クローズアップ 未来への挑戦」では、同志や識者らへの取材を通し、創価の哲学と運動の価値を考えます。第1回はインド㊤。(記事=小野顕一、写真=笹山泰弘)
取材でインドを訪れたのは昨年5月。首都ニューデリーの気温は連日の42度超え。危険な暑さを考慮し、移動先も制限された。
仏教発祥の時代から猛暑は変わらないのだろう。仏典に、悩みを「熱悩」、悟りの境地を「清涼」と例えるのもうなずける。
「前の年よりは、まだ涼しいですよ」と現地の人が教えてくれた。特に一昨年は、過去100年で最も厳しい酷暑だった。エアコン普及率はまだ低く、熱波の影響で犠牲者は数百人に上った。
取材でも、近年の異常気象への不安を多く耳にした。昨年は、雨が降らないはずの乾期に大雨が降り続いた一方、8月が今世紀で最も乾燥した月となった。その後、「地球沸騰化」との警告が発せられたが、取材で知り合った人は「これからどれだけ暑くなるか、想像したくもない。近い将来、本当に住めなくなる」と漏らしていた。
隣国のパキスタンは、一昨年の大洪水で国土の3分の1が水没した。雨量の増加や氷河の融解に、気候変動の影響が指摘されている。
国連のIPCC(気候変動に関する政府間パネル)が、地球温暖化の原因は人間の活動にあると明言したのが2021年。経済活動やライフスタイルにおける価値観の変革が迫られる中、インド創価学会(BSG)は「BSG FOR SDG」と銘打った社会貢献活動を同年に始めている。
SDGs(持続可能な開発目標)の周知とともに、一人一人が地球を守る「変革の担い手」となることを目指すもので、BSGの友はSDGsの17項目と自分の生活を照らし合わせながら、おのおのができる挑戦に取り組んでいる。
例えば、デリー在住のアヌラダ・シャルマさん(地区婦人部長)。
――ゴミの分別を呼びかける一方、生ゴミから堆肥をつくるコンポストを活用し、家庭から出るゴミを60%削減。近隣住民も輪に加わり、120人が自主的にゴミを分別するように。約50世帯のゴミ排出量を月当たり300キロ減らすことができた。この取り組みは、直接にはSDGsの目標12「つくる責任 つかう責任」に該当することから、「12」のタグを付けて、「BSG FOR SDG」のアプリに写真を投稿。さらにはゴミの運搬や燃焼を減らすという意味で気候変動対策にもつながっている。
BSGが開発した同アプリからは、インド各地でのアクションをスマホなどから確認することができ、互いに励まされるという。
昨年、インドの人口は、中国を抜いて世界一に。人口比率や経済規模、CO2排出量の割合から、インドは世界全体のSDGs推進の鍵を握る主役ともいわれる。
2015年に採択されたSDGsの達成期限は2030年。創価学会創立100周年の節目でもある。今年は、折り返しのスタートでもあり、活動に拍車がかかる。
あらゆるものが
この活動に深い関心を寄せるのが、医師のルビー・マキジャ博士。プラスチックゴミ問題に警鐘を鳴らし、多彩な活動を広げている。
気候変動と並んで懸念される環境汚染。インドの状況はとりわけ深刻で、各都市の大気汚染指数は軒並み高く、世界最悪の水準ともいわれる。人口増によって粉塵や排ガス、焼却灰が急増し、生活や健康への影響が危惧される。
インドでは毎日、十数万トンのゴミが排出され、その3分の2は収集・処理されるが、残りの3分の1は川や海、埋立地に廃棄され、水質汚濁や大気汚染の原因になっている。「リデュース(ごみの減量)・リユース(再使用)・リサイクル(再生利用)」といった行動は始まったばかり。残念ながら不法投棄や“ポイ捨て”は、まだなくならない――とマキジャ博士。
たしかにインドの路上には多種多様なゴミが散乱している。一方で不思議なのは、街中に比べて、家やお店の中はきれいな点だ。
そこには文化的要因も大きい。ゴミを路上に捨てることで、それを拾う仕事が行き渡るという考え方もある。だが適切に処理されなければ、やがては地球を汚してしまう。特にプラスチックゴミは海で魚の体内に蓄積したのち、食物連鎖をたどって人体に影響を与えかねない。博士が懸念するのも、この点だ。急速な経済発展に伴い、廃棄物は増加する一方である。
長年、診療を続け、がんやアレルギーの増加に心を痛めてきた博士は、その原因としてクレジットカード1枚分――5グラムものマイクロプラスチックが毎週、人体に蓄積されていること等を指摘する。
そんな博士が注目する創価学会の哲学がある。「自然環境とそこに暮らす人々が一体という生き方――仏法に説かれる『依正不二』に基づくライフスタイルです」
プラスチックゴミの問題を依正不二の原理に当てはめるならば、自分の見えないところにゴミを投げ捨てているつもりが、実は、自分の体内に入れているに等しい。
かつて日本を訪れた博士は、人目のない所でタバコを吸った男性が、携帯灰皿を取り出して吸い殻を処分したことに驚き感心したと話してくれた。「持続可能な社会の基礎は、自分の行動に責任を持つこと」が持論の博士にとって、「人は変われる」と勇気をもらった経験でもあったという。
衆生と環境・国土の相互連関を説く依正不二の生命哲学からいえば、「他者を利すること(利他)」は同時に「自分を利すること(自利)」につながる。その考え方は、自然環境との関係にも応用できる。
「あらゆるものが互いに支え合っているという視点があるから、創価学会員は環境汚染に無関心ではいられない。周囲や社会にも働きかける。その責任ある生き方を可能にしているのは、自分の心の変革から、人生も、環境も、やがては世界も変えていけるという『人間革命』の哲学なのだと思います」
なぜダメなの?
「BSG FOR SDG」をはじめとする創価学会の運動は、単なる社会貢献活動ではない。博士が指摘した通り、そのプロセスの中に、「自他の変革」を含んでいる。
例えば、先のシャルマさんは、同活動が始まるずっと以前、BSGに入会する前から、“自然を大切にしたい”と、節電や節水等の工夫を重ね、資源の節約を呼びかけてきた。しかし、“なぜ従来の方法ではダメなのか”と、家族からでさえ嫌な顔をされた。「私は正しいことを勧めているのに、どうして誰も理解してくれないの?」
シャルマさんは2012年、幼馴染みに誘われてBSGに入会。いつも人の目を気にしていたが、次第に自信が持てるようになったと述懐する。「印象的だったのは、周りの人のために祈ること。それも時に、普段なら気に留めないような他人のために祈る。人として、とても美しいことだと思います」
実践を続けるうち、いつしか、100人以上が行動を共にするように。「今、振り返ると、以前は“なぜ、あの人は分かってくれないのか”という気持ちしかなかった」。自分本位に行動を押し付けるのではなく、まず自分が変わることで変化が広まったという。
「無駄なことをするな」と反発していた人が、今では率先して声をかけてくれると笑顔を見せた。
青年世代の関心
地球温暖化の議論は、今に始まった話ではない。
半世紀以上も前、世界的シンクタンクであるローマクラブは、人口増大と工業投資が続けば、人類は100年以内に成長の限界に達し、生存条件が脅かされると警告した(1972年)。池田先生が歴史学者トインビー博士と対談を開始した年である。
博士との対談集『21世紀への対話』では、70年にインドを襲った熱風等の異変が取り上げられ、世界の気候が重大な変化に直面していることに言及されている。
博士は言う。「われわれが当面する人為的な諸悪は、人間の貪欲性と侵略性に起因するものであり、いずれも自己中心性から発するものです。したがって、これらの諸悪を退治する道は、自己中心性を克服していくなかに見いだせるはず」と。一方で「自已中心性の克服は、困難で苦痛をともなう課題」と、その難しさを指摘している。
未来を開く鍵として両者の意見が一致したのは、人間の自己中心性を克服し、行動の変革を促す「自己超克の哲学」の必要性だった。
「若い世代ほど、社会に貢献したいという願いを持っていると感じます」と語るのは、「BSG FOR SDG」を主導するシュルティ・ナンギアBSG女子部長。
BSGでは持続可能な社会へのヒントを伝える「希望と行動の種子」展(SGI等が制作)を100以上の教育機関で開催。展示を解説するのは各学校の生徒である。皆が自信をもって話せるように、青年部で研修を担当。生徒たちの成長も地域に波動を広げている。
コロナ禍で大切な人を亡くすなど、失意の底にある同志もいた。それでも、今こそ自身の変革から時代を開く弟子になろうと、BSGでは「アイ アム シンイチ・ヤマモト!(私は山本伸一だ!)」の精神を確立してきた。
池田先生がトインビー博士と対談した当時、数えるほどしかいなかったインドの創価学会員は、今や約30万人に。半数が青年世代で、その割合は年々高まっている。
2024年1月6日
〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
デューイ協会元会長
ラリー・ヒックマン博士
地球的規模の問題解決へ
未来開く価値創造の実践
本年は、創価教育の父である牧口常三郎先生の殉教から80年(11月18日)。牧口先生が敬愛した人物の一人が、同時代を生きたアメリカの教育哲学者ジョン・デューイであった。ジョン・デューイ協会元会長のラリー・ヒックマン博士に、デューイと牧口先生の教育哲学などを巡りインタビューした。(聞き手=萩本秀樹)
ヒックマン博士 新年のごあいさつを申し上げます。この一年の始まりは、皆さまにとって、池田第3代会長の業績への感謝を深め、会長が示した道に続く決意を新たにする機会であることと思います。
――私たちは今、ウクライナや中東の情勢、気候変動をはじめ、地球規模の危機に向き合っています。ジョン・デューイ(1859~1952年)が生きた時代のアメリカも、分断と対立が深まっていました。
博士 おっしゃる通り、デューイは混迷の時代を生きました。南北戦争と2度の世界大戦、さらに朝鮮戦争を見て、亡くなったのは「核時代」の始まりとも言える時です。アメリカ社会には、構造的な人種差別、社会の周縁に追いやられた民族や文化集団への迫害が横行していました。
その中でデューイは、誰もが敬意を払われ、成功と幸福への方途を提供されるべきであると考えました。例えば彼は、アフリカ系アメリカ人(African-Americans)やイタリア系アメリカ人(Italian-Americans)など、アメリカ国外に民族性のルーツを持つ人々について、このハイフン(-)はアメリカ社会を隔てるのではなく、つなぐものであると述べました。
彼は、「アメリカは国や民族の“るつぼ”である」という、一人一人の個性を消すような考えを嫌いました。むしろ、それぞれの楽器が固有の音色を奏でて調和をなす、「交響曲」のような国であらねばならないと信じていたのです。
2050年には、アメリカ人口の約4分の1を中南米系の移民が占めるという調査を、最近、目にしました。私が生まれ育ったテキサス州にも、ヨーロッパやアジアからの移民が多くいて、豊かで多様な文化の形成に貢献しています。気候変動とともに人口移動が加速する今、移民の人たちの存在はますます大きくなるでしょう。
経済的また政治的なストレスの増大や現下の国際情勢の影響で、難民の数も増え続けており、多くの国で移民政策の見直しが議論されています。創造的かつ人道主義の観点から、早急に解決されなければならない問題です。
デューイと牧口
――池田先生とのてい談(『人間教育への新しき潮流』)では、同時代を生きたデューイと牧口常三郎先生について、さまざまな点から語り合われています。
博士 二人には非常に多くの共通点がありました。
まずは二人の違いに着目してみると、第一に、牧口会長は日本社会の伝統に収まらない革新性を持ち合わせ、それ故に多くの批判を受けた一方で、デューイは、哲学や教育学の分野ですでに広く尊敬を集めており、その意味で、アメリカ社会の伝統の“内側”にいた人物であったと言えます。実際に、デューイは、アメリカ心理学会とアメリカ哲学会の会長を務め、ニューヨークタイムズは彼を、「アメリカの哲学者」と呼んでたたえています。
第二に、牧口会長が、教育改革を推し進める中で日蓮仏法に帰依したのとは対照的に、デューイは、キリスト教の原理主義者であった母を見ていたことで、キリスト教は哲学や教育の改革に不向きな偏狭なものであると捉えました。
もっとも、デューイは信仰それ自体に否定的であったのではなく、科学や人文科学が進歩する中で変わることができない、形骸化する宗教組織や制度に批判的であったということです。
身近な観察から視野を広げ
「世界市民」を育む創価教育
次に、デューイと牧口会長の共通点についてですが、まず、教育に対する革新的なアプローチと、環境意識の高さが挙げられます。二人とも、ダーウィンの進化論などの科学的な世界観、そして恐らく最も重要な点として、機械論的ではない有機的な世界観に影響を受けていました。
心と体を対立するものとして区別せず、人間を全体として捉えていた点も共通しています。デューイは著書『経験と自然』の中で、「身体―精神(Body-Mind)」とハイフンを使った言葉を用いています。ここでも、彼にとってハイフンは、「つなぐもの」を意味していました。
また、デューイも牧口会長も、自由な探究を妨げるものとは戦い、学校を地域生活に密着した場として捉えていました。さらに、コンテクスト(脈絡)を考慮する重要性も一致しています。学習者の過去の経験や文化的規範、そして地理的要因や歴史的要因などを考慮することが重要であるという主張であり、牧口会長が、地理学を基礎として他の学問領域にわたって多くの著作を残したことにもつながるものです。
オープンエンド
――昨年行われた日本デューイ協会の第66回研究大会で、博士は、デューイの「成長」と牧口先生の「価値創造」という概念の共通性について語られました。
博士 牧口会長の「価値創造」と、デューイが個人やコミュニティーの「成長」として表現したものは、程度の差こそあれ同じであったと考えます。
当時、「成長」の概念は曖昧すぎると批判を受けましたし、同様のことは「価値創造」にも当てはまったのかもしれません。しかし私はむしろ、それらの概念は曖昧なのではなく、結論が固定されていないがゆえの「オープンエンド」(途中で変更や修正が可能であること)な性質を帯びたものであると思うのです。
成長も、価値創造も、実験的なものであり、多分に進化論的な考えです。環境条件が変われば、適応し、生存するための戦略も変わるものですが、それは教育についても同様であるべきなのです。
思い起こすのは、アメリカ創価大学(SUA)で開催された創価教育会議で、「創価教育とは何か」を巡る問いと議論が飛び交っていたことです。この問いに対し、私たちは明確な答えを知りません。創価教育を定義する作業は、今なお進行中であるからです。
デューイは、人間の可能性への信頼によってのみ民主主義の創出は可能になると言いましたが、その意味で、価値創造も、成長も、挑戦的な目標であり、多くの作業を伴うものです。
――「オープンエンド」な方法が開かれた対話を促す一方で、結論が決まっている「クローズエンド」のアプローチは、広がりに欠ける側面もあります。
博士 その意味で、教育者は変化を恐れてはなりません。イギリスの経済学者であるケインズは、かつて自分の立場を変えたと非難されたとき、「状況が変われば私は意見を変える」と答えています。
では、曖昧であることとオープンエンドであることの違いをどう見極めるのでしょうか。曖昧さは、多くの場合、ただ問題を回避するための逃げ道となりますが、オープンエンドであることは、変化を受け入れ、新たな経験がもたらす価値を歓迎します。ゆえに、具体的に問題解決を進めていく方法たり得るのです。
探究心と創造性
――デューイと牧口先生の教育哲学と実践は、どのように共鳴していたとお考えですか。
博士 デイル・ベセル氏(米インタナショナル大学元教授)は、牧口会長の哲学をいくつかの主要なテーマに立て分けていますが、その一つ一つが、デューイの教育論においても重要であると言えるでしょう。
第一に、教育の目的は実生活のニーズの中で生まれなければならないということです。デューイもまた、子どもたちのニーズと関心が教育の中心にあらねばならないと考えました。
第二に、幸福は社会で共有された意識の中で育まれるという点です。デューイは、社会性を身に付けることそれ自体は、犯罪集団の間でも起こりうるものだと考えていました。ゆえに重要なのは、社会の意識を良い方向へと導き、人々がより幸せになる方法を見つけることです。
第三に、子どもは生まれながらにして探究心と創造性に富んでいるということです。ゆえに教育は、創造的で貢献的な人生を生きるための目標とツールを開花させゆくものです。
4点目に、牧口会長は、教育の目的は情報や価値の単なる伝達ではないと考えましたが、デューイも同様です。丸暗記や詰め込み教育、テストのための教育といった、従来の教育モデルの克服を目指しました。
5点目は、教育の科学の重要性です。牧口会長の実証主義に通ずる点として、デューイもまた、教育には科学的な根拠が必要であると考えました。
そして6点目に、フィールドワークの大切さです。デューイの教育哲学は①テーマ中心型の学習、②ピアラーニング(注1)、③サービスラーニング(注2)、④共同研究者としての教師という柱で表現されますが、これらは、SUAをはじめとする創価教育の柱でもあると私は考えています。
注1 学習者同士が協力しながら学び合う方法
注2 社会活動を通した学習
自分の事として
――池田先生は世界市民を育成する事業として、創価教育の学びやを国内外に創立しました。世界へと開かれた視野も、デューイと牧口先生の共通点でした。
博士 私の知る限り、世界市民という言葉は、デューイの時代には存在していませんでした。それでもデューイは、自国以外の文化や生活様式へと認識と理解を広げることを志向していましたし、彼自身、世界を広く旅しており、人類が進歩するためには、国家や文化の対立、偏見、競争心を克服しなければならないと考えていました。
「世界市民」と、通常言うところの「コスモポリタン」の間には、区別があります。コスモポリタンは縦横無尽な市民のことを指します。彼らは上昇志向を持ち、文化を超えて移動し、働きます。食べ物、音楽、芸術など、他の文化を高く評価しつつ、世界の宗教的多様性をよく理解した人たちです。
その意味で、コスモポリタンは世界市民の一部ではありますが、全体ではないのです。世界市民とは、地球規模での経済的な視点を、不公正も含めて正しく認識している人たちのことであるからです。そしてまた、生態系の実情を理解し、地球環境保護の重要性や環境正義に意識を向けていなければなりません。
経済正義やエコロジー、多様性、平和教育などの地球規模の問題に対して、自分の事として関心を持つ中で、コスモポリタニズムを超えた世界市民への道があると考えます。
――博士は長年、SUAの理事も務められました。創価教育のどのような側面に、デューイの精神が生きていると考えますか。
博士 例えば、SUAでは学生と教員の比率が約7対1であり、少人数の学習環境で両者が共同研究者となっているという意味で、デューイの教育の柱の一つが体現されています。
また、「ラーニングクラスター」のような学際的な授業を通じて、物事の相関関係を深く知ることができます。デューイが重んじた実証的な経験を、教育の中心に置いている実例です。
全ての学生が経験する留学も、異なる文化に身を置くことで、「教育ツーリズム」にとどまることのない世界市民教育の重要な一部となっています。また、ビジネスや産業界、NGO、教育など多様な分野で通用するリーダーシップを磨く経験や、平和研究に力を入れていることも重要です。
こうした創価教育の魅力は大学にとどまりません。今も思い出すのは、関西創価学園を訪問した時のことです。ある生徒たちは、環境衛生の指標としてホタルの個体数を調査しており、一方である生徒たちは、NASA(アメリカ航空宇宙局)とのプロジェクトに携わっていると知りました。
身近なホタルの観察を通して、より広い環境問題へと関心を向けながら、一方で、壮大な宇宙についての研究もある。素晴らしい教育だと実感しました。
そしてこれらは、池田会長が構想し、発展させた、世界市民教育のほんの一例にすぎません。こうした世界市民の育成が、創価教育のあらゆる場所、あらゆる学びやで、大きく花開いているのです。
Larry Hickman 1942年、アメリカ・テキサス州生まれ。アメリカ哲学振興協会会長、ジョン・デューイ協会会長などを歴任。南イリノイ大学カーボンデール校名誉教授。『ジョン・デューイのプラグマティック・テクノロジー』など著作・編著多数。池田先生と同協会元会長のジム・ガリソン博士と、てい談集『人間教育への新しき潮流』を発刊している。
2023年11月17日
〈11・18「創価学会創立の日」記念インタビュー〉
インド 創価池田女子大学
セトゥ・クマナン議長
三代の師弟に貫かれる 人間の可能性への信頼
池田大作先生を師と仰ぎ、インド・チェンナイに「創価池田女子大学」を設立したセトゥ・クマナン議長。師との出会いから四半世紀を経て、創価の教育哲学や師弟の精神の広がりを、どう見つめているのか。同大学を訪ね、インタビューしました。(聞き手=小野顕一)
――2000年に創価池田女子大学が開学し、24年目を迎えました。チェンナイを代表する名門マドラス大学のカレッジとして18学部を有し、卒業生は6000人を超えたそうですね。
海外で市民権を得て活躍する人もいれば、パイロットの夢をかなえた人もいます。1期生からは大学教授も誕生しました。彼女は学費の捻出が難しく、無償で教育を受けた一人です。
インド出身の若者が名だたるIT企業でグローバルに活躍する様子が取り上げられ、国中に教育が行き届いている印象も抱かれがちですが、児童の義務教育が制定されたのは2009年のことで、現在の大学進学率は28%ほど。特に農村地域で女子教育への偏見は依然として根強く、女性は家の手伝いをして、早く子を産み、家族に尽くすべきだとの考えが残っています。
ある学生の父親が、高等教育は女性に悪影響を及ぼすと主張し、娘の大学進学をやめさせようと訴訟を起こしたこともありました。
何度も対話を重ねて、納得してもらうことができました。卒業後、彼女は有名な歌手となり、テレビにもよく登場しています。育児に励みながら、音楽研究の博士課程にも在籍し、今では彼女の選択を父親も祝福してくれています。
こんな人生を誰が想像できたでしょうか。「教育」によって彼女の未来は開かれたのです。教育は、この一生の可能性を最大限に引き出すためにあるのです。
「母」の詩
――なぜ大学名に「創価池田」と掲げたのですか?
私が池田先生を知ったきっかけは「母」の詩でした。
世界詩歌協会創立者であるクリシュナ・スリニバス博士から頂いた書籍で「母」を読み、雷光を目にしたような衝撃を受けたのです。
母の姿が浮かびました。家畜の乳搾りをして学費を工面してくれた母です。
私は詩人です。各国で詩人の集いに参加してきましたが、これほど感銘を受けた詩は初めてでした。“この詩人にいつか会いたい”と願うようになりました。
1996年に日本での世界詩人会議に出席した折、創価大学を訪問することができ、そこで初めて、池田先生が詩人だけでなく、いくつもの教育機関を創立した教育者であることを知ったのです。仏法指導者、平和運動家としても著名であると伺い、「創価」が「価値創造」の意味であり、SGIが仏法を基調とした団体であることを知りました。
創価女子短期大学の見学を終えた時、空には大きな虹が懸かっていました。この時、インドの地に池田先生の名を冠した女子大学をつくろうと決めたのです。
「教育は私の最後の事業」「21世紀を女性の世紀に」との先生の精神に基づき、私は「創価」と「池田」の二つの名を大学に冠することを願い出て、快諾していただくことができました。
女性が教育を受けることで、家庭にも地域にも、そして次世代にも良い影響が広がります。ただ貧しい地域では、女性が高等教育を受ける機会が限られます。学校に通うため都会に出ることも難しい。ですので、あえて都市部から離れた地域に大学を設立しました。
チェンナイは1961年に池田先生がインドを初訪問された際、その第一歩を印された地です。この地に建設した意義が時と共に高まると信じています。
――大学の設立に当たって、苦労されたことは何でしょうか。
まず資金が十分ではありませんでした。自宅を抵当に入れて資金集めに奔走しました。
さらに、親戚や友人から設立を反対されました。なぜ日本人の名を掲げる必要があるのか。やめた方がいいと忠告されたのです。
「創価」の意味や「池田大作」という人物について、設立の認可を申請した当局や学位授与の提携を要請した大学から繰り返し質問を受けました。
今、振り返っても、本当に苦しい時でした。でも、ひるみませんでした。できることは限られていますが、私は教育の分野で先生との誓いを果たす。自らの行動で先生の偉大さを証明してみせると決意していたのです。
当時、私が抱き締めていた先生の指針があります。
“一人決然と立つ時、その胸中の思いは普遍の真実となって全世界に伝わっていく”という言葉です。
私は関係者一人一人に会い、「なぜ今、池田先生という人物が必要とされているのか」を、忍耐と誠実をもって訴えました。
徐々に支援者が増え、ようやく資金の目途がつきました。土地を取得することもできました。レンガを無償で提供してくれる人、後払いでいいからと資材を手配してくれる人、破格の工賃で建設作業を請け負ってくれる人……。中には「いつか、この創価池田女子大学が必ず有名になるよ」と、励まし続けてくれた人もいました。忘れられません。
大勢の方々の協力を得て、2000年8月に大学を開学することができ、翌年度から学生を校舎に迎えることができたのです。
この時、私は知りました。師匠とは、弟子が一番苦しんでいる時に「力」と「幸福」を与えてくれる存在なのだと。大学の設立は、私が池田先生を心から尊敬している証しであると同時に、次々に直面する困難に師と共に打ち勝った証しでもあるのです。
行動する詩人
――クマナン議長と池田先生は国籍も言語も異なります。なぜ先生を師匠と定めたのですか。
創価学会員ではない私が、なぜ池田先生を師匠と決め、力を尽くしているのか。その理由は、私が先生に“生きる光明”を見いだしたからです。
実は以前、私は「師匠」を探し求めて、世界中を旅していました。100を超える国を巡りました。友人はたくさん見つかりましたが、師といえる存在には巡りあえなかったのです。
池田先生を師匠と決めたのは、先生の「詩」を読んだ瞬間です。
詩人と詩人は、すぐに共鳴するものです。詩は、世界に隠されている美しさを明らかにするものです。魂を高揚させ、若返らせます。先生の詩は、どんな人にも分け隔てなく力を与えています。
美しい詩を作る人は、世界に数え切れないほどいます。しかし、詩の創作はしても、実践の伴わない人が大半です。ですが、先生は理想のために「行動する詩人」でした。
著名な詩人であったアブドル・カラム大統領(当時)を官邸に訪ね、先生の「母」の詩を紹介したこともありました。大統領は「これこそが詩のあるべき姿だ」と、「母」を3度、詠唱されたのです。「人々に幸福をもたらす、本当の詩人がここにいる」と語っていました。
創価の三代の師弟は、いずれもが卓越した教育者です。初代会長の牧口常三郎先生は、経済的に苦しい中、女子教育の普及に多大な尽力を果たされました。第2代会長の戸田城聖先生は、牧口先生の教育理論を実践する私塾を開いています。
その師と弟子の契りは、激動のさなかで受け継がれていきました。
牧口先生と戸田先生は軍国主義に抵抗して投獄されました。牢獄で殉教された牧口先生の遺志を継ぎ、戸田先生は創価学会の再建に孤軍奮闘されます。学会を支える戸田先生の事業が苦境に陥った時、池田先生は夜学に通うのを断念してまで師を守りました。そして「戸田大学」で万般の学問を教授されながら、師弟のあり方を示されたのです。
絶体絶命の窮地にあって師弟の究極の姿を示されたからこそ、創価の師弟は時代や国境を超越し、老若男女あらゆる人の“人生の模範”と輝いているのです。
イケディアン
――ガンジーの思想を実践する人を「ガンディアン」と呼ぶように、創価池田女子大学の学生は、池田先生の思想を実践する「イケディアン」を自称しています。
イケディアンであるということは、「幸福である」ということです。状況に支配されるのではなく、池田先生のように積極果敢に立ち向かい、他の人をも勇気づけながら自身の問題を解決していく。これは人生の一つの真髄です。
だから私も問題に直面した時、先生のことを思ってきました。自分の悩みが小さく感じられ、行動する勇気が湧きました。
創価池田女子大学に入学したばかりの学生にとっては、「創価」という言葉や池田先生の存在は耳慣れないものです。なので、先生の著書を通して、その精神を学びます。
1年生は『香峯子抄』(英語版)が必読書です。あれだけの世界的偉業を達成された池田先生を、どのように香峯子夫人が支えられたのか。問題をどう乗り越えるのかを、ディスカッションを通して深めるのです。地域や社会の問題を解決していくためには、その根本となる家庭が平和で価値的でなければなりません。
『若き日の日記』(同)も反響が多くあります。若き日の池田先生は何を思い、何をされていたのかを学ぶ。苦境にありながらも師を守り抜くことで、人生の価値を何倍にも開いていける師弟の原理を知るのです。
私は幼稚園から高校までの一貫教育を実施するセトゥ・バスカラ学園の理事長も務めています。ここでは8000人が学んでいて、「ドクター・イケダ・ブロック(池田博士校舎)」という校舎があります。
学園では視覚障がいのある30人の子たちも学んでいますが、先日、その一人が、何と州で一番の成績を収めたのです。原動力は、池田先生から教わった無限の可能性を信じる心です。その思いに応えようとした時、計り知れない力が発揮されることを実感するのです。
池田先生と同じように、私も全ての時間を学生の可能性を広げるために使いたいと考えています。
ですので、創価池田女子大学に私の部屋や椅子はありません。学生や生徒の元にとにかく足を運び、対話をします。師匠の間断のない行動に少しでも近づければ、弟子として本望です。
今、振り返ると、大学の開学には多くの困難がありました。しかし、思い返してみれば、わずか6カ月で校舎の完成にこぎ着けました。全て、師匠にお応えしようとする中で達成したことです。先生の心に即座に反応しようとすれば、必ずことは成就するのです。
目覚めるたび
私は、教育を通じて、自分にできるベストを尽くしていこうと考えています。
創価池田女子大学と同じ州内に約30万坪の土地を取得し、2015年に「セトゥ・バスカラ農業大学」を創立しました。これまで5万本以上の木を植樹し、敷地内には「池田博士森林公園」が広がっています。
この地域は私の故郷でもあります。教育の力で地域の生活を豊かにするとともに、環境に配慮した先進的な農法を研究し、地球環境に貢献する人材を育成していきたいと考えています。
これは、先生が折々に発表してこられた“環境提言”から着想を得たもので、私なりの気候変動問題への挑戦です。そうして行動を積み重ねた結果、気温がほんのわずかでも下がるかもしれない。理想を描いて行動し続けるのが本物の詩人であり、弟子です。
――池田先生を師匠に抱かれ、四半世紀が経ちます。
私はうれしいんです。師のおっしゃる通りに結果を示せることが。今日も師に付いていけることが。
毎朝、目が覚めるたびに先生は希望と幸せを与えてくれます。先生の一言一言から活力をもらいます。
池田先生の心を携えて学生に会えば、それが伝わって、みんなが心を弾ませるんです。「師匠にお応えしたい。今日も何かを成し遂げたい」と。
先生は世界の師匠です。先生を師と仰ぐ世界の数百万人の一人であることが、私の人生の誇りなのです。
Sethu Kumanan 1961年、インドのタミル・ナードゥ州生まれ。詩人。マドゥライ・カーマラージャル大学卒業。セトゥ・バスカラ学園の理事長。創価池田女子大学の設立に尽力。同大学の議長を務める。
2023年11月15日
「創価学会教学要綱」発刊
「御書根本」「大聖人直結」で
「実践の教学」を
池田先生が監修
「11・18」を記念して発刊される『創価学会教学要綱』
11・18「創価学会創立の日」を記念して、池田大作先生監修による『創価学会教学要綱』が発刊される。
「仏法の人間主義の系譜」「日蓮大聖人と『南無妙法蓮華経』」「一生成仏と広宣流布・立正安国」「万人に開かれた仏法」の4章立てで、創価学会が実践する日蓮仏法の骨格・核心について論じられている。
広宣流布大誓堂の完成から10年。「会則」の教義条項の改正や、「勤行要典」「会憲」「社会憲章」の制定、『日蓮大聖人御書全集 新版』の刊行など、創価学会は世界宗教としての基盤を着実に整備してきた。
教学要綱は、独善的・差別的な日蓮正宗(日顕宗)の教義と完全に決別し、「御書根本」「大聖人直結」で「実践の教学」を貫く創価学会こそ、日蓮仏法の唯一の正統な教団であることを明確に示すとともに、創価学会の教義を、各国の仏教団体をはじめとした宗教界、社会全体に向け、教学的な見解を踏まえて客観的に説明することに力点を置いた一書である。
2800円(税込み)。11月16日発売。
全国の書店で購入・注文できます。聖教ブックストアのウェブサイト、または電話での注文も受け付け中。電話(0120)983563(午前9時~午後5時、土・日・祝日を除く)。※電話の場合、支払いは代金引換のみ。FAXでの注文はできません。
コンビニ通販サイト「セブンネットショッピング」「HMV&BOOKS online」での注文、受け取りも可能です。
2023年11月9日
〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
インタビュー
インド 医師・社会活動家
ルビー・マキジャ博士
持続可能な世界の実現へ!
自分が変わり社会を変える
自分自身の行動の変化をもって
周囲の人々を啓発
あなたが変わろうとすれば、
世界も宇宙も変わらないわけがない。
地球環境に深刻な被害をもたらす「プラスチックごみ問題」。世界各国で対策がとられるものの、プラスチックごみは今後も増え続けると指摘される。持続可能な未来を実現するために、私たちはプラスチックとどう付き合っていけばよいのか。インド・デリーでレジ袋の代わりに布製の袋を使用する運動を広げる、医師のルビー・マキジャ博士にインタビューした。(聞き手=小野顕一)
1週間に5グラム
――医師であるマキジャ博士が、なぜ布袋の使用を訴える活動を始めたのですか。
私は20年以上、眼科を専門に診療を続けてきました。20年前と今を比べると、がんやアレルギーに苦しむ人が非常に増えています。重い症状に落胆する患者や家族を目にするたび、胸が張り裂けそうな思いをしてきました。
何かできることはないかと自問していた時、環境汚染――なかんずくプラスチックごみの処理について疑問を抱いたのです。
私たちの生活は
プラスチック製品であふれており、
使い捨てられたプラスチックは
最終的に焼却処分場か海、
埋め立て地のいずれかに行き着きます。
特に直径5ミリ以下の
マイクロプラスチックは、
海で魚の体内に蓄積し、
食物連鎖を通じて
人体に影響を与える可能性が
懸念されています。
今、どれだけの量のプラスチックが
体内に取り込まれているかご存じですか。
1週間に5グラム、
およそクレジットカード1枚分もの
プラスチックが体内に入っているんです。
昨年に発表された研究結果では、
マイクロプラスチックが
血液から検出されて話題となりましたが、
その後、母乳や心臓などからも見つかり、
さらなる衝撃が走りました。
人体への影響が
解明されたわけではありませんが、
マイクロプラスチックは
化学物質と相性がよいといわれます。
発がん性のある有害物質が吸着し、
体内に取り込まれた結果、
健康に悪影響を及ぼす可能性は少なくありません。
――そこで運動に立ち上がられたのですね。
私たちが考えたのは、
買い物で使い捨てにされるレジ袋の代わりに、
繰り返し使える布袋を使用することでした。
そうすれば1人当たり
約2万枚から4万枚のビニール袋を
生涯で削減できるのです。
インドでは、
日本で普及するエコバッグのように、
家にある袋を買い物に持っていく
習慣がありません。
なので、布袋を自宅ではなく
お店に置くことを思いつきました。
それを、ごく少額の保証金で
借りてもらうのです。
布袋は、買ったお店以外でも返せます。
袋に二次元コードが付いていて、
返却できるお店が分かります。
返却先を検索する際に、
プラスチックごみ問題の深刻さや
影響について知ることができます。
リデュース(ごみの減量)・
リユース(再使用)・
リサイクル(再生利用)等の
行動が始まったばかりで、
まだまだ長い道のりです。
残念ながら不法投棄や
“ポイ捨て”もあります。
だからこそ、
環境への配慮をこうした
運動を通して学ぶことが大切なのです。
現在、
布袋を置く店はデリー市内の
1000店舗近くに広がり、
袋の製作作業は
困窮世帯や女性の
雇用創出にもつながっています。
実践の「可視化」
――近年、インドでは廃棄物の管理規則が相次いで規定され、昨年7月には一部の使い捨てプラスチックの使用が禁止となりました。
ファストフード店等のコップやストローが紙製に変わるなど、デリーの街中では変化も見られますが、全国的な浸透には長い時間が必要です。
デリーだけで毎日1・1万トンの廃棄物があり、そのうち10%がプラスチックです。しかし、そのプラスチックの50%は、一度使っただけで捨てられてしまうものなのです。
ビニール袋の平均使用時間は、
わずか12分とも指摘されています。
そんな短時間の使用にもかかわらず、
プラスチックは自然に分解されないため、
1000年以上も地球に残ってしまうのです。
私はある意味で、
プラスチックは“奇跡”ともいえる
素材だと思っています。
少なくとも、私が生きているうちには、
プラスチックに匹敵するような、
安価かつ軽量で、
耐久性があり、
成形しやすく、
断熱性にまで優れた素材は
実現しないでしょう。
特に医療において衛生を保つ上で、
私たちはプラスチックから
多大な恩恵を受けています。
プラスチックを使わないことが理想ですが、
近い将来に実現するのは難しいと思います。
だからこそ、
プラスチックの存在自体が
問題なのではなく、
どう使用するかという
私たちの側の行動が
問われているのではないでしょうか。
数年前に日本を訪れた時、
私はたくさんのインスピレーションを得ました。
ホテルから向かいのビルのバルコニーが見え、
そこにタバコを吸う男性がいました。
吸い終えると、
彼は誰も見ていないのに、
ポケットから灰皿を取り出し、
そこにタバコを捨てたのです。
多くの国で放り捨てられるのを
目にしてきたので、驚きました。
だからこそ日本は
清潔さが保たれているのだと
感嘆するのと同時に、
日本人の意識と行動に感銘を覚えました。
自分の行動に責任を持つことが
持続可能な社会の基礎だ
と思っていた私にとって、
必ず人は変わっていけると
背中を押されたような経験でした。
――BSG(インド創価学会)では社会貢献の一環として、2021年から「BSG FOR SDG」と掲げ、行動しています。SDGs(持続可能な開発目標)に関する取り組みをスマホやパソコンで共有し、先月は「BSG 25トンプラスチック回収活動」も実施されました。
BSGの活動がユニークだと思うのは、測定可能な手段を取り入れていることです。私もいくつかのアクションを目にしてきましたが、実践を「可視化」したことで努力や進歩が具体的に分かり、次回の目標を決める際の励みになっていると感じます。
「あの地域ではこんな取り組みをしているんだ」と体験をシェアできますし、「それなら私にもできる」と挑戦を後押しすることもできます。
BSGの取り組みの根本には「平和・文化・教育・持続可能性(サステナビリティー)」の各次元で社会に貢献するとの理念があります。自分の行動に責任を持ち、実践を共にする中で自信と意欲を育み、持続可能な方法を広げていく。だからこそ確実で長期的な変化をもたらしていけるのだと思います。
サステナビリティーへの貢献を
上から押し付けるのではなく、
自分自身の行動の変化をもって
周囲の人々を啓発する。
このような教育のアプローチは、
私自身の活動とも共通するものです。
山をも動かせる
――最も関心を持つ創価学会の哲学は何でしょうか?
特に注目しているのは、
自然環境とそこに暮らす人々が
一体であるという生き方
――仏法に説かれる「依正不二」に
基づくライフスタイルです。
ありとあらゆるものが
相互につながっていて、
互いに深く支え合っている
という視点があるからこそ、
環境汚染に無関心ではいられない。
周囲や社会にも働きかけようとする。
その責任ある生き方を可能にしているのは、
自分の心の変革から、
人生も、環境も、
やがては世界も変えていけるという
「人間革命」の哲学なのだと思います。
私は今、人間が人間であることが、
とても難しい時代に入っていると感じます。
地球に生きる一員として、
社会に生きる一人として、
どう責任を果たしていくべきなのか。
人間革命という言葉には、
その答えへと導くような、
人間としてあるべき姿を
引き出すイメージを持っています。
私たちは世間的な地位や肩書、立場
といった“見え”にとらわれがちです。
そうした自分を飾っているものを
一つ一つ取り除き、
人間らしくある大切さを、
BSGの方々と接していて感じるのです。
また環境への関わり方は
人それぞれですが、
生活に困窮していたり、
人生に満足できていなかったりすると、
とても環境のことまで
考えられないといったことも
当然あるでしょう。
一方で人間革命は、
今この場所から
幸福をつくり出していく哲学です。
自分自身が幸福感に満ちている、
あるいは、幸せになれるという
希望があれば、
環境や社会の課題に対しても
前向きに取り組んでいけるように感じます。
幸福な人が環境活動に取り組む姿は、
自分もこうなりたいと感じさせるものです。
私はよく
「自身の体験を5人に伝えてください。
その5人が、さらに5人に伝えてくれれば
25人が変わります。
相乗効果で必ず問題は解決できます」
と訴えています。
BSGの飛躍的な発展は、まさしく、
豊かな生き方の広がりを
象徴するものともいえるでしょう。
――創価学会の池田会長はインドで「ガンジス川の流れも、一滴の水から始まる」と語りました。BSGの若い世代にも、「私の一歩から全てを変革する」との実感が広がっているように感じます。
その「一滴」が重要です。
どんなに些細なことでも、
一つの行動が次につながり、
やがては大きなインパクトにつながるのです。
決して、自分一人に何ができるというのか
とは思わないでください。
私もあなたも、
宇宙そのものであり、
世界そのものです。
あなたが変わろうとすれば、
世界も宇宙も変わらないわけがない。
変化をもたらすと決意すれば、
それは必ず起こります。
後は、どれだけ本気になって
運動を継続するかにかかっています。
私は、信仰を基盤とする団体が果たす役割に着目しています。信仰を持つ人は「山をも動かせる」エネルギーがあると感じます。そして、信仰やスピリチュアリティー(精神性)といったものは、人の「生き方」そのものであり、社会から切り離すことができないものです。
信仰は内面の世界にとどまるものではありません。人々や社会と関係して、初めて価値をもたらします。信仰が現実の生活から離れてしまえば、それは観念や抽象の域を出ません。重要なのは、自身の信仰や実践を社会に生かしていこうというあり方です。
BSGの問題解決へのプロセスと価値創造の信念が、インド社会において、さらに重要な役割を果たしていくと確信しています。それは、サステナビリティーの取り組みを何倍にも加速させ、人類が待ち望む新しい文明を指し示すに違いありません。
Ruby Makhija インド・デリー市の眼科医。使い捨てプラスチックを削減するキャンペーン「Why Waste Wednesdays Foundation」を2021年に創設。レジ袋の代わりに布袋の使用を奨励する「Project Vikalp」を主導する。デリーにおけるプラスチック廃棄物管理に関するタスクフォース(特定任務に当たるチーム)の一員。
2023年11月7日
管楽合奏コンテスト全国大会
関西高が最優秀賞
関西小は優秀賞
第29回「日本管楽合奏コンテスト」(主催=公益財団法人日本音楽教育文化振興会)の全国大会が東京・文京シビックホールで行われ、関西創価高校(大阪・交野市)の吹奏楽部が「最優秀賞」に輝いた(5日)。関西創価小学校(大阪・枚方市)のアンジェリック・ブラスバンドは、「優秀賞」を受賞した(3日)。
関西高は高校生A部門に出場し、伊藤昌教諭の指揮で「ルイ・ブルジョワの賛歌による変奏曲」(C・T・スミス作曲)を熱演。
講評者から「躍動感あふれる感動的な音色でした」「全体のバランスが良く、とてもダイナミックな素晴らしい演奏でした」等と高く評価された。
辻谷智恵部長(3年)は「皆で一丸となって、感謝と歓喜の演奏をすることができました」と語った。
一方、関西小は、堀夢夏教諭の指揮で「ロベルト・シューマンの主題による変奏曲」(R・ジェイガー作曲)を披露。「一音一音を大切にしている演奏」「聴き手に伝わる美しい調和」等の講評が寄せられた。
山下優子バンド長(6年)は感謝の言葉を述べつつ、「ここまで励まし合って頑張り切れたことに胸を張りたい」と瞳を輝かせた。
2023年10月27日
会長選出委員会行う
原田会長を再任
創価学会の会長選出委員会(議長=山本武総務会議長)が26日午後2時から東京・信濃町の学会本部別館で開かれ、全員の賛同で原田稔会長を再任した(5期目)。
同委員会は原田会長の任期(4年)が11月17日をもって満了となることから、創価学会会則に基づき次期会長選出のため行われた。
2023年10月21日
〈識者が見つめるSOKAの現場〉
寄稿 「世界への広がり」を巡って
東京大学大学院
開沼博 准教授
学会員の「価値創造の挑戦」を追う連載「SOKAの現場」では、「世界への広がり」をテーマに、取材ルポを9月9日と15日に掲載。「東京インタナショナル・グループ(TIG)」で活動するメンバーと、SGI(創価学会インタナショナル)青年研修会に参加した海外のメンバーを紹介した。それに連動して、社会学者の開沼博氏が、ルポに登場したメンバーを8月下旬と9月上旬に取材した。世界に広がるSOKAの魅力に迫った、開沼氏の「寄稿」を掲載する。
「近代化」の帰結
個人化、都市化、情報化など、私たちの日常を取り巻くさまざまな側面は、社会が「近代化」した帰結として言い表すことができます。そうした近代化のプロセスが、戦後日本で加速度的に進む中、創価学会には、社会からこぼれ落ちそうになる人々を包摂し、生きる希望を与える機能があった。
これまでこの連載を通して、全国で100人以上の創価学会員に会い、重ねてきた取材は、すでに先行研究によって広く知られていたこうした学会の社会的機能を、フィールドワークの中で再確認する作業であったともいえます。
翻って、世界を見てみると、どうなのか。創価学会の会員は192カ国・地域に広がっています。近代化それ自体は、スピードの違いこそあれ、地球上の至る所で相当程度、進んでいます。どこにいても、地球の裏側にいる人と、スマートフォンでオンライン会議ができる。
であるならば、「近代化における創価学会」は、日本のみならず海外でも、共通して見られる事象であるのか。この連載を進める中で、確認しておきたいテーマでもありました。
一つの“セット”
首都圏に在住する英語話者の海外メンバーで構成されるTIGと、4年ぶりのSGI青年研修会で来日した海外メンバー。どちらのグループの取材からも見えてきたのは、日本各地の取材で見てきたものの「再現可能性」でした。
具体的には、日々の勤行・唱題や、座談会をはじめとする会合、何でも語り合える人間のつながり。あるいは、折伏や社会貢献活動といった、外へと開かれた活動。これまでもその価値を考察してきた、こうした日々の習慣が、世界各国で同じように再現され、実践されていました。
もっとも、同じ信仰を持った創価学会員の皆さんからすれば、当たり前のように映るかもしれません。しかし、文化も伝統も異なる国々で、こうした実践が一つの“セット”となって広がっていることは、特筆されるべき事実です。
人の幸福を願っての祈りや実践、社会のしがらみから離れて対等に語り合えるコミュニケーションの場など、創価学会は、あらゆる人が普遍的に求めてやまない価値を、社会に提供することを可能にしてきた。これが、世界に広がった理由の一つであることを改めて理解できました。
国籍や民族の違いがさまざまな葛藤を生む現代にあって、創価学会員という一点において、国を超えても違和感なく、変わらぬ活動が成立している。TIGで活動するアメリカ出身のケニー・コハギザワさんは、日本で文化の違いに戸惑ったといいます。その中で、地域の男子部やTIGの先輩の励ましに触れ、改めて祈ることの大切さを実感した。祈りが深まると、仕事の姿勢も変わっていった。転職を経て、今、世界有数の金融企業に勤務します。
異国の地での新たな人間関係や葛藤の中で、もともと持っていた創価学会の信仰に、再び立ち返っていった。グローバル化する現代社会にあって、至る所で生ずるであろう摩擦や葛藤を乗り越えるための術を、信仰と実践の中に見いだした。こうした例を、取材した多くの方々から伺うことができました。
現実生活の中で
改めて驚いたのは、海外でも、創価学会の“2世”“3世”が多く、世代間継承も進んでいるという事実です。今回取材したメンバーの出身国は、アメリカ、ドイツ、インド、シンガポール、マレーシア、ベネズエラの6カ国ですが、それぞれに異なる個別の宗教事情がありました。キリスト教やイスラム教など特定の宗教の習慣が伝統的に残っている上で、近年は、どの国でも「世俗化」が相当進み、宗教から離れる人が増えているのも事実です。
その中で、あえて自ら選び取るだけの魅力を、創価学会の信仰に見いだし、子や孫の世代も継承している。特に多くの若者にとっては、宗教が“非日常”である世俗化の時代に、熱心に学会の信仰に励む、強い動機と誇りが必要です。
インド出身のギータンジャリ・ダンカールさんは、TIGの活動を通して、「信仰と現実生活は、別物ではない」ことを学んだといいます。人の幸福に尽くす信仰の目的は、彼女自身の現実生活や研究活動の目的そのものでもある、と。
現代は、宗教が“根付いているけれど、身近ではない”ものとして形骸化し、信仰と現実生活は別物となってしまった。インドで生まれ育った彼女にとっても、宗教はそういうものだったといいます。日本で生まれ育った人々と似た感覚が、そこにはあるわけです。
その点、ダンカールさんの言葉からは、創価学会が海外でも一貫して“信仰即生活”の実践を人々に広めてきたことがうかがえました。生まれ育った環境だからではなく、現実に自分自身を高め、課題を解決してくれるものだから信仰をしている。学会員にとって、信仰は、仕事や生活に直結した“日常”なのでしょう。自然体のまま、生き生きと信仰に励む理由がそこにあるのだと思いました。
誰にも開かれた実践で
誰もが変革の主体者に
地域に根差した活動が日常的に行われ、そこに新しい世代・属性の人々が多く参加している創価学会の現場から見えてくるのは、常にそのあり方をアップデートし続けようとする挑戦です。冠婚葬祭の時だけ顔を見せる宗教ではなく、とにかく意識の中でも、行動でも、個人的にも集団的にも「プラクティス(実践)」をすることが前提になっている。外部が言う「宗教」と、内部で捉えられる宗教とは全く別物です。
取材した方々は皆、そうした実践に意義を見いだしていました。SGI青年研修会に、ベネズエラから来日したオマイラ・サルダ・ナランホさんが、一日に数時間も唱題をしていたことに、友人が驚いたと語っていたのは印象的です。その驚きには、僧侶のような“読経のプロ”ではない彼女にも再現可能な、実践のシンプルさに対する新鮮さがあるようにも思います。
誰にも開かれた実践を通して、誰もが社会に変革を起こす存在になれる。自分は無力ではないし、日常こそが大切だ。そうした創価学会の哲理が、ハイパーインフレをはじめ過酷な社会状況に立ち向かうベネズエラで、確かな希望となっているのが分かりました。
メンバーが語る、信仰の功力の現れ方は多種多様でした。仕事で高い評価を得たといったものもあれば、会いたいと願っていた人と街中で本当に会えた、といったものもある。多種多様であるということは、一部の願いや一部の人に限られるのではなく、全ての人に信仰の結果は出るという、信仰の体系のもつ柔軟性の現れでもあります。
「必ず結果が出る」ことを強く確信して、信仰の実践に励む中で、現実に身の回りに変化が起こる。それを功力だと捉えて、さらに実践に熱が入る――。こうした循環が成り立つことが、多くの人を引きつけているのだと実感します。
共通していたのは、良いことも悪いことも、周囲ではなく自分自身に、その原因を求める姿勢です。この連載でも、心理学の「ローカス・オブ・コントロール(統制の所在)」――あらゆる行動や評価の原因を、内(自己)に求めるのか、外(他者)に求めるのかを分類する考え方に触れましたが、日本でも海外でも、創価学会員は、身の回りの出来事を“自分事”として捉えようとします。
だからこそ、行動の結果が思い通りにならないときは、環境のせいにするのではなく、自分の行動を見直してみたり、人間関係の中での振る舞いを変えてみたりする。徹底的に自分自身を変革していく姿勢が、挑戦することを促し、良いトライアル・アンド・エラー(試行錯誤)を継続させ、先の好循環を生む原動力となるのでしょう。
幸福の姿で示す信仰の証し
私自身、昨年、任用試験の受験に際して、「随方毘尼」(※)という教えを知りましたが、取材では、それが海外でどう具体化されているのかを理解できました。全ての国に共通する実践がありながらも、それ以外の点については、その国や地域、相手に応じて柔軟に変化させていく。「共通性」と「特殊性」の両方を強みとしてきたのが創価学会なのではないか、と。
そして、改めて創価学会が「人間革命」と呼ぶ基盤の上に、四つの実践が、世界共通の「柱」となっている。①自分を見つめる「勤行・唱題」、②他者と生活・信心を分かち合う「座談会」、③それらを社会に開いていく「折伏」、④伸び縮みするような柔軟な「師弟」の関係性、という四つです。これらが、日本の外でも成立している。「創価学会のグローバル化」の鍵がここにあるのでしょう。
もちろん、グローバルに広がる過程において、さまざまな障壁があったことは想像に難くありません。今回、話を聞いた中でも、マレーシアやシンガポールはかつて日本軍が侵略した国であり、“日本の宗教”に対してさまざまな目が向けられた。あるいはドイツでは、戦時中のナチスドイツの教訓から、一つの信念で結び付く凝縮性の高い組織そのものに、忌避感を持つ人も多いと聞きました。
ただ、そうした個別の事情、お国柄をよく理解し、受け入れつつ変化していったが故に、創価学会のグローバルなネットワークが、今も維持されている。
当然、日本で広がるのとは比べ物にならない葛藤があったはずです。キリスト教・イスラム教が強固に根付いている国に、創価学会が入っていくのは、逆の立場になって考えれば、全く入る余地も見えないところからのスタートだったでしょう。ただ、そういう国においても、そもそも世俗化が進み、既存の宗教自体が日常生活の中から消えていっている。そこにおいて、自らの成長を常に急き立てられ、個人主義的であると同時に常に孤独・孤立にさらされる現代人にフィットする信仰として、創価学会が広がっていった。
信仰の証しが人間としての成長・幸福に直結していて、そういう姿を周囲の人に見せることが折伏になっていく。そういう連鎖の中で信仰が生き残ってきたことが理解できました。
※仏法の根本の法理に違わない限り、各国・各地域の風俗や習慣、時代ごとの風習を尊重し、随うべきであるとする教え。
計算可能な社会
かつては自然が人間への恵みでありつつも、脅威でした。それを、科学的合理性の中でコントロールしたり、何が起こるかが予想できるようになってきた。これは、「計算可能性」が高まってきたと表現されたりもします。
私たちは、計算可能性の高い社会に生きていると、無意識に信じ切っています。例えば、私たちが、スマートフォンの充電を始めれば、何時間後に充電が完了するかを知っているように。それは、電力の供給が安定しているとか、充電池がすぐには劣化しないといった、さまざまな条件によって成り立っているにもかかわらず、充電が必ずなされることを当然だと思ってしまう。
でも現実に、世界を見渡せば、計算不可能なことであふれています。先進国は移民や安全保障、新興国は経済危機や政情不安と向き合う。そして現代の戦争・災害・感染症は、私たちの計算可能性を乗り越えてくる、厄介で計算不可能なものです。「リスク社会」と呼ばれる現代社会には、そうした不安や矛盾が常に横たわっています。
社会や経済、そして個人の生活も揺らぐ現実の中で、環境ではなく自分の内側に幸福の基準を置く創価学会の信仰が、日本のみならず海外でも、生き方の指針となり、それ故に多くの人を引きつけていることを、改めて感じる取材となりました。
かいぬま・ひろし 1984年、福島県生まれ。東京大学大学院准教授。専門は社会学。『漂白される社会』『日本の盲点』など著書多数。
2023年10月16日
〈社説〉
18日は「民音創立記念日」
争いを食い止め、
民衆の心を平和の方向へと
昇華させゆく偉大な潮流は、
文化
1963年(昭和38年)10月18日に誕生した民主音楽協会(民音)。創立60周年の佳節を記念する企画展示「『平和構築の音楽』展」が、今月13日から始まった(民音音楽博物館、明年6月30日まで)。「音楽を通じ国際間の文化交流を推進し、世界の民衆と友誼を結ぶ」と掲げる民音にとって、一つの集大成とも言うべき展示だ。
民音創立者の池田先生が、その設立を構想したのは、61年(同36年)2月、初のアジア歴訪の中でのこと。長兄が戦死したビルマ(現ミャンマー)を訪れ、戦争の悲惨さに思いを巡らせた。世界平和実現のために、何が必要か、思索を重ね、文化交流を目的とした団体の設立を提案した。
その時の思いが、小説『新・人間革命』第3巻「平和の光」の章に描かれている。
「広宣流布というのは、仏法をもって人間の生命を開拓し、平和と文化の花を咲かせていく運動です。つまり、平和、文化にどれだけ貢献し、寄与できるかが、実は極めて重要な問題になってくる」
平和貢献への挑戦こそ、民音60年の歩みだ。
創立から3年後の66年(同41年)には、「世界バレエ・シリーズ」の第1回として、ソ連(当時)のノボシビルスク・バレエ団を招へいしている。政治対立の激しい東西冷戦の時代にあって、人間と人間との友好の花を咲かせた。
85年(同60年)には、当時、公式には同席することのなかった中国とソ連の音楽家が、画期的な企画「シルクロード音楽の旅」にて、“世界初共演”を果たす。
民音の国際的な文化活動を紹介し、「民音は、ある意味で、音楽分野での国連と言ってよいだろう」と、フィリピンの日刊紙が評したこともある。
これまで結んできた文化交流は、112カ国・地域に広がっている。世界最高峰のオペラ、アルゼンチン・タンゴ、中国の京劇など五大陸の芸術を堪能できる、多彩な公演を重ねてきた。
また、「学校コンサート」の取り組みも、今年で50年の節目を刻む。未来を担う世代へ、民音は、音楽の魅力を伝え続けてきた。
「結論を言えば、争いを食い止め、民衆の心を平和の方向へと昇華させゆく偉大な潮流は、文化しかないのです」(『青春対話1』)
あらゆる智慧と努力を注いだ、さらなる名企画に期待したい。
2023年10月16日聖教新聞5面
2023年10月8日
〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
インタビュー㊦
日本大学文理学部 末冨芳教授
「安心」して生きるために
自他共の「幸せ」に焦点(フォーカス)を
「こどもまんなか社会」を築くために必要なことは、いったい何か。7日付の㊤に続き、日本大学文理学部教授で子ども政策が専門の末冨芳さんに聞きました。(聞き手=大宮将之、村上進)
人権を守ると平和を創れる
――インタビューの前半では、子どもの権利意識を育むため、子どもが意見を表明する機会を奪ってきた「沈黙の文化」から、子どもの意見に耳を傾ける「対話の文化」への転換が重要であると伺いました。そもそも子どもの権利は全ての子どもが“無条件”に持っているものです。「義務」や「責任」を果たさないからといって奪われるものでも、果たしたからといって与えられるものでもありません。
まず改めて考えたいのが、「なぜ人権を大切にするのか」という点です。権利について学び合う場などでこうした質問を学校の先生方にすると、答えに困ってしまう方々も少なくありません。私は一言、「『平和』を創れるからです」とお伝えしています。
「世界人権宣言」(1948年採択)の前文に、そう書いてあるのです。正確に言うと“すべての人間の尊厳と権利を承認することは、世界における自由、正義及び平和の基礎である”とうたわれているのですが、ただ「自由」「正義」「平和」の三つを一遍に伝えても、みんな忘れちゃうので(笑)。私は「人権を守ると『平和』を創れる」と、シンプルに伝えています。
創価学会の池田名誉会長がこれまで、「対話」の目的を「平和」という一語をもって繰り返し強調されてきた理由についても、私なりに考えてみました。それは「平和」という一語の中に、「自由」も「正義」も含まれているからではないか――と。
人としての基本的な自由が制限されている状態を「平和」とは呼べません。人権侵害の不正義が放置されている状態も「平和」とは呼べません。
ケアする人をケアして
――池田先生も次のように語っています。「『平和』とは『戦争がない』というだけの状態ではない。『平和』とは『人間一人一人が輝いている』『人権が大切にされている』社会のことです」と。
自分の権利や尊厳が侵害された時、つらい時、苦しい時には、遠慮なく声を上げていい。それを受け止め、助けてくれる人が必ずいる。仕組みがある。だから安心して――そんなメッセージを、子どもたちに伝えられる社会にしていかなければなりません。
「こどもまんなか社会」の実現を目指す上で、私自身は「安心」こそがキーワードだと感じています。
その参考として、一つのアンケート結果を紹介させてください。神奈川・川崎市が、2020年に実施したものです。同市は全国に先駆けて、「子どもの権利に関する条例」を施行しています(2001年)。子どもと大人が一緒になって考え、何度も話し合いをしてできた条例でした。
条例には「ありのままの自分でいる権利」や「自分で決める権利」など七つの権利がうたわれているのですが、その中で「どの権利が大切だと思うか」との問いに対し、アンケートに回答した604人の子どもたちのうち半数以上が選び、最も多かったものが「安心して生きる権利」だったんですね。私自身も、各地の講演会などで子どもたちと語り合う際に、同様の実感を得ています。
子どもたちは誰もが、「今を安心して生きたい」と願っている。虐待があったり、心身が疲れた時にゆっくり休ませてもらえなかったりする家庭には、安心がありません。いじめがあったり、教師から怒鳴られたり、理不尽なルールがあったりする学校にも、安心がありません。
どうすれば、家庭を、学校を、子どもたちにとって安心の居場所にできるのか――。「こどもまんなか社会」を築くため、私たち大人がみんなで考え、取り組んでいく必要があります。
とはいえ、子育て中の保護者は何かと忙しく、「わが家を“安心の居場所”にと言われても、負担が大きい」と感じるご家庭も、少なくないでしょう。
だからこそ、地域で安心・安全の居場所をつくっていくことが大事になります。児童館であったり、子ども食堂であったり。近年はユースセンター(中・高生向けの放課後施設)にも注目が集まっています。
自らそうした「居場所」をつくることは難しくても、すでにある「子どもの支援団体」への寄付などを通し、間接的に子どもを支えていく方法もあります。子どもを支援する団体にとって、現実的に一番助かるのが「経済的な支援」です。もちろん、できることから実際に「お手伝い」をすることも、喜ばれます。どこも人手不足ですから。地域・社会全体で、物心両面において「子どもをケアする人たち」のことを「ケア」していかなければなりません。
大人も子どもも一緒の居場所に
――創価学会も、親御さんたちが子育ての悩みや苦労を安心して話し、ホッとできる「家庭教育懇談会」という取り組みを各地で実施しているほか、小中高世代のメンバーと日常的に関わり、支え励まし合う「未来部」という組織があります。今夏は全国各地で、この未来部を「真ん中」に置いた集い「“未来”座談会」を開催しました。
素晴らしい取り組みです。特に「“未来”座談会」は、大人の皆さんが子どもたちの意見に耳を傾け、それを取り入れる内容だったと伺いました。事前と事後に、代表の地域で子どもたちにアンケートを取ったのもいいですね。
事前の声で「(いつもの座談会は)大人向けの内容で堅いから、あまり楽しくない」という率直な意見を聖教新聞に載せたことも、事後に「楽しかった」「まあまあ楽しかった」という声が約9割ある一方で、ちゃんと「あまり楽しくなかった」「楽しくなかった」という声が掲載されていたことも、どちらも忖度がなくていい(笑)。子どもたちが安心して意見を表明できている証拠です。
“地域の居場所が大切だ”といっても、望ましいのは、「大人だけ」「子どもだけ」の居場所ではなく、「子どもと大人が一緒にいられる、一緒につくる、一緒に学べる」居場所だと、私は思います。そんな居場所をつくるには、大人が子どものことを決して下に見ず、子どもたちの力を信じることが第一歩です。
もちろん大人だけで物事を進めたほうが早いし、楽かもしれません。けれど大変だからこそ、新しい発見があり、新しい学びがあり、新しい楽しさもあるんです。
大人が「子ども目線」に立つということは、子どもを対等なパートナーとして見るということでもあります。
「子どもの幸せ」を第一に考えて、「子どもを信じる。一緒に学ぶ」――この信念や哲学を、私たち大人が持てるかどうか。それが問われているともいえるでしょう。
自分もあなたも大切にする哲学
――小学校の校長も務めたことのある創価学会初代会長の牧口常三郎先生は「教育は子どもの幸福のためにある」と叫び抜き、太平洋戦争中に軍国主義教育を進める軍部政府と対峙して、投獄されています。子どもを信じ、どんな時も子どもと共に歩んだ教育者でした。その信念を強めたものが「人間の無限の可能性」「自他共の幸福」を説いた日蓮仏法の信仰でした。
牧口会長は、困難な状況にあった多くの子どもを前にして、「この子らを何としても幸せにしなければならない」と思い、「そのために自分は何をすべきか」と問い続けた方であると理解しています。「子どもの権利」や「人権」といった概念などなく、「国家のための教育」が推し進められていた時代に、「子どもの幸福のため」と叫ぶことが、どれほど大変なことだったか。
ひるがえって現在、「こどもまんなか社会」を実現しなければならない理由として、「少子化による人口減少や、労働力の減少を抑えるため」「年金制度を維持するため」など経済的な理由を挙げる声も少なくありません。もちろん、そのことを否定する必要はありませんが――しかし、やはり、それは「国の目線」「大人まんなか」の発想です。
「こどもまんなか社会」を目指す今こそ、もっともっと一人一人の「幸せ」にフォーカス(焦点)を当てる社会に変化できるチャンスだと、私は思っています。
「国の未来のため」だとか「お金のため」だとか、そうしたものばかりに焦点を当てていると、「人間の幸せ」にフォーカスする力が、だんだんと弱まってしまいます。実際、私たち日本の大人は、子どもの幸せを実現する強い願いを持てなくなってしまっているのではないでしょうか。
「人間の幸せ」にフォーカスする力を支えるものこそ、人権に対する「哲学」です。「自分の権利」だけでなく、「あなたの権利」も大切にする。大切にしなければならない――と。何が正解なのか分かりづらい時代だと言われますが、「人間としてこれだけは譲れない」という正解は、必ずあるのです。
その哲学こそが、「こどもまんなか社会」を築く原動力となるに違いありません。
2023年10月7日
〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
インタビュー㊤
日本大学文理学部 末冨芳教授
「こどもまんなか社会」とは?
「今を生きる私」から始める未来
「こども基本法」の施行、「こども家庭庁」の発足から半年がたちました。目指すべき社会像は「こどもまんなか社会」です。それは具体的にどんな社会? 自分にも関係ある? 上下2回にわたり、日本大学文理学部教授で子ども政策が専門の末冨芳さんに聞きました。(聞き手=大宮将之、村上進)
子どものことをどう捉えるか?
<「こども基本法」が施行された意義とは改めて何でしょうか?>
それは二つの側面から語れます。「理念法」としての面と「政策の規定(プログラム)法」としての面です。まず理念としては「子どもは権利の主体である」と位置付けられたことが非常に大きい。子どもを「大人が保護すべき対象」として捉えるだけではなく、「大人と同じように、一人の人間として権利を持った主体」だと定義されたわけです。
<見方を変えれば、これまでの日本は、子どものことを“大人と等しく権利を持った主体”と認めず、“未熟な存在”と見て、その意見を尊重しない社会だったとも言えるでしょうか>
ええ。ご自身が子どもだった頃を振り返ってみてください。例えば学校や自治体において、自分たち子どもに関わるルールや政策が検討されている時に、「どうせ子どもだから分からないだろう」と理由を付けられ、自分たち(子どもたち)の意見を全く聞いてもらえず、大人たちだけで勝手に決められたり。自分たち子どもが何らかの意見を述べても、「子どものくせに」と思われ、その意見を抑え付けられたり……。思い当たるフシは、ありませんか?(苦笑)
1989年に国連で採択された「子どもの権利条約」には、“最も大切な「四つの権利」”として、「自分の意見を伝え、参画する権利」をはじめ、「子どもにとって最も良いことが実現される権利」「差別されない権利」「安全安心に成長する権利」が掲げられています。
「こども基本法」の意義のもう一つの側面についてはまさに、この「子どもの権利条約」を「誠実に遵守」するための政策が充実し始めてきている点を挙げられるでしょう。
「からだ」「心」「社会」の全て
<先月末、こども家庭庁は、子ども・若者政策の指針となる「こども大綱」の中間整理案を示しました>
評価できるポイントはいくつかあるのですが、「こどもまんなか社会」の定義がとても素晴らしい。
「全てのこども・若者」にとって幸せな社会とは、具体的には、「①身体的」「②精神的」「③社会的」に、将来にわたって幸せな状態(ウェルビーイング)で生活を送ることができる社会である――と定義しているのです。
幸せとは何かを考える上で「からだ」「心」「社会」という三つの側面から、子どもや若者たちの状態を捉えること、その三つの全てが良好な状態となるようにアプローチすることが、絶対に欠かせません。
一方、「こども大綱」の中間整理案には、まだまだ課題もあります。私自身、こども家庭審議会の「こどもの貧困対策・ひとり親家庭支援部会」で委員を務めているのですが、「子どもの貧困」に関する記述が十分ではなかったと感じています。「子どもの貧困」の解消なしに「子どもの権利」の保障と「最善の利益」の追求など、ありえません。もちろん今後、大綱案が改善されていくことを期待しています。
(こども家庭庁では「こども大綱」の策定に向けて、子どもや若者、子育て・孫育て中の方々、また貧困や虐待、社会的養護の当事者、さらに子ども・若者支援団体などから意見を募集しています。詳しくはこちらから)
受付期間:2023年9月29日(金)~10月22日(日)
子どもの貧困 視点を変えて
<7月に行われた創価学会女性平和委員会主催の「平和の文化講演会」で、末冨さんは「子どもの貧困」の定義を巡って、多くの場合、“低所得世帯の問題”として限定的に捉えられてしまっている実情に、警鐘を鳴らしていました>
世帯の所得が「高い」か「低い」かだけで「貧困」を捉えてしまうと、家庭内における子どもたち一人一人の状況が“見えなく”なってしまいます。
「子どもの貧困」とは親の所得の高低にかかわらず、「子どもらしく生きる権利や安心・安全に育つ権利、幸せな生活が奪われている状況」である――との視点の転換が必要です。
今、社会科学の分野では「家族内貧困」という概念が注目されています。例えば世帯の稼ぎ手である父親が、配偶者である母親、子どもの生活資金を不当に制限・管理する「経済的虐待」をしている場合、世帯の収入が安定していたとしても、子どもの状況は「貧困」です。これでは、子どもに「安心・安全」があるとはいえません。
また他にも、例えば2人きょうだいのうち上の子だけが習い事をさせてもらったり、学習塾に通わせてもらったりしているのに、下の子はそれを一切させてもらえないといったケースもあります。
現代は地域のつながりの希薄化や核家族化が一段と進み、子どもたち一人一人の置かれている状況が周囲から“見えなくなっている”社会ともいえるでしょう。今までは「家庭内の方針」として見過ごされてしまっていたようなケースについても、「こども基本法」に基づいて“子ども一人一人の権利”を擁護する視点から、地域・社会全体でアプローチし、解決していかなければなりません。
その意味でも、行政から独立した立場で子どもの権利が守られているかを監視し、権利の擁護に努める専門機関「子どもコミッショナー」の創設や、子どもたちが安心して何でも相談したり、助けてもらえたりする自治体の第三者機関「子どもオンブズマン」等の拡充が一層、求められます。
こうした「子どもの権利」を守る仕組みづくりとともに、絶対に外してはならないことは、子どもたち自身が「自分たちは権利の主体なんだ」という意識や自覚を育める「学びの場」を、積極的につくることです。
「沈黙の文化」を「対話の文化」に
子どもの意見を聞ける大人に
<子どもたちの人権意識の向上を阻むものがあるとすれば、それは何だと思われますか>
一言でいえば「沈黙の文化」です。「“子どもなんだから”我慢しなさい」とか、「“子どもなんだから”黙って大人の言うことを聞きなさい」とか、そういった理由だけで沈黙を強いられ、意見を表明する権利を奪われ、人権とは何かを学ぶ機会すらも奪われてきたのが、これまでの日本社会だともいえます。
<近年、問題となっている学校の「ブラック校則」(必要性や合理性が見当たらない校則)も、「沈黙の文化」を象徴するケースの一つかもしれません。例えば「生徒は登下校時にコンビニに入ってはいけない」と指導されているのに、大人である教員は出退勤時、普通に入っている。その矛盾に生徒が「おかしい」と声を上げても、「子どもだから」という理由で一方的に制限されてしまう……>
そもそも登下校の際の責任は、学校ではなく保護者にあります。民法上に定められる親の責任(監護権)の範囲なのです。だからそもそも、登下校の際にコンビニに入ってはいけないとか、学校から指示される理由はないのですが……。
ただ学校側としても、コンビニに自分の学校の生徒が集団でたむろしているのが常態化している場合、学校にクレームを入れられることが多いため、「安全管理」の名のもとに、コンビニへの出入りを制限してしまうのでしょう。
では、こうしたケースの場合、「権利」の視点からどのように対応すればよいのでしょうか。小・中学生が「子どもだから」という理由だけでコンビニの出入りを制限されること自体、権利の侵害です。
一方でコンビニ側の視点に立って考えてみた場合、お店の入り口に集団でたむろされると、他のお客が入りづらくなるため、お店にとっては「利益を上げる権利」が侵害されている状態だといえるわけです。
もしも学校教育の現場でこうしたケースを取り上げるとしたら、生徒とコンビニの双方にそれぞれ権利があることを学び、それをどうすれば侵害せずに尊重できるか――子どもたちを主体とした「対話」を通して共に考えていく方法が挙げられるでしょう。
「沈黙の文化」の対義語があるとすれば、それは、「対話の文化」です。しかし、この「対話の文化」「対話の作法」が日本社会に十分に育っていないことこそ、課題なのです。
どんな人生がいいですか?
<自分も相手も、大人も子どもも、どうすれば「互いの権利」を守り、「共に幸せ」な状況をつくれるか。その道筋を見いだすために「対話」が必要なのですね。
「自分も相手も幸せに」という目的を踏まえた上で「こどもまんなか社会」の実現を大人たちに呼びかけると、「子どもも大変だろうけれど、大人だって大変だよ」「子どもを大切にと言われても、自分たち大人の負担(物理的・経済的)が増えるのは嫌だ」という声が聞かれることも少なくありません。末冨さんであれば、そうした方々と、どのような対話をされますか>
ちょっと厳しい言い方になるかもしれないのですけれど……。こう問いかけるようにしています。「あなたは、誰かを傷つけて不幸にしたいですか」と。それでよいというのであれば、仕方がありません。けれどそう問いかけた時、ほぼ全ての人が「いや、それは違う」「そんなことは思っていない」とお答えになるんですよね。
それはなぜかといえば、誰もが自分の心の中に「誰かを望んで不幸にはしたくない。できれば誰かを幸せにして、自分も幸せでありたい」という本然的な願いがあるからだと、私は思っています。
であるなら!――その願いに正直になりましょう。そしてその優しさを真っ先に向けるべきは、子どもたちをはじめ、高齢者や障がい者など、社会的に弱い立場に置かれている人ではないでしょうか。そうした人たちに優しい気持ちを向けてこそ、社会は初めて明るくなり始めるからです。
社会福祉学には「バルネラビリティ」(社会的脆弱性)という概念があるのですが、社会で一番置き去りにされがちな人の幸せに対して目を向けてこそ、あらゆる人々が幸せになれるという認識が共有されているのです。
「誰かを置き去りにして、誰かを傷つけて、誰かを不幸にする人生でもいいですか」という問いを立てることで気づきが生まれる――人権について学ぶ大切さも、そこにあるんです。誰かの権利の侵害を放置するということは「誰かを不幸にして傷つける」ということと同じ意味ですから。
<私たちが信奉する日蓮仏法も「自他共の幸福」を追求します。創価学会名誉会長の池田大作先生も「自分だけの幸福もなければ、他人だけの不幸もない」と一貫して訴えてきました>
人権を大切にすることは「自分も相手も幸せになるため」であり、究極は「平和」のためだと、私は思っています。この点、池田名誉会長が「対話」の目的を「平和」という一語をもって繰り返し強調されてきたことに、「なんて優れたセンスだろう!」と尊敬の念を抱いているのです。
(インタビュー㊦は、あす8日付に掲載予定。「対話と人権」「安心できる居場所づくり」、さらには学会が今夏に実施した「“未来”座談会」や、牧口先生の教育哲学などを巡っても話を伺いました)
すえとみ・かおり 山口県生まれ。京都大学教育学部卒。同大学院教育学研究科博士課程単位取得退学。学術博士(神戸大学大学院)。専門は教育行政学、教育財政学。大学院修了後、福岡教育大学准教授などを経て2016年から現職。内閣府子供の貧困対策に関する有識者会議構成員、文部科学省中央教育審議会委員等を歴任。著作に『教育費の政治経済学』(勁草書房)、『子育て罰 「親子に冷たい日本」を変えるには』(共著、光文社新書)などがある。
2023年10月7日〈危機の時代を生きる 希望の哲学〉
2023年9月20日
〈創価インターナショナルスクール・マレーシア(SISM)〉
教職員にインタビュー
9カ国・地域から1期生を迎え、8月24日に第1回入学式を行った
「創価インターナショナルスクール・マレーシア(SISM)」
ヌグリスンビラン州の州都スレンバンに立つ「創価インターナショナルスクール・マレーシア」。クアラルンプールの国際空港から車で約45分。豊かな自然に恵まれた地で、治安も良い。
国際水準のカリキュラムと生徒第一の充実の学習環境が整い、若き世界市民の育成がスタートした。今月から首都クアラルンプール近郊にある校舎で授業が始まっている。具体的な教育プログラムや理念などについて余美婷校長、郭福安学園長ら教職員に聞いた。
◆余美婷 校長「時代に合わせた最良の教育法を導入」
――SISMの特徴を教えてください。
生徒が主体的に学ぶ、人間主義の教育プログラムが一番の特徴です。
また学力向上はもちろん、総合的な「ウェルビーイング」(心身と社会的な健康)の土台を築くことが大切だと考えます。
優秀で献身的な教職員も魅力の一つだと自負しています。
マレーシアはもとより、アメリカ、カナダ、韓国、日本、インド、イギリスなどから、創立者・池田大作先生の教育思想に共鳴し、創価の名を冠した初のインターナショナルスクールの設立のために集ったメンバーです。創価教育同窓の友もいて、一緒に歩めることを心強く思います。
9カ国・地域から1期生を迎えた 創価インターナショナルスクール・マレーシア
地元マレーシアの生徒を中心に、今月から対面の授業が始まった。ビザなどの関係で、海外の生徒にはオンラインの授業も。新入生全員が校舎に集って授業を受けるのは明年1月からの予定
――世界市民教育の具体的な取り組みは?
7~11年生(日本の中学1年~高校2年に相当)では、世界的に高く評価されている英国中等教育プログラムの国際版「IGCSE」を採用します。
その後の大学予備教育に当たる12、13年生(日本の高校3年以降に相当)では、一人一人が自身の進路に合わせ、国際バカロレア(IB)機構の「ディプロマ・プログラム」、またはケンブリッジインターナショナルの「Aレベル」プログラムから選択。
それぞれ所定の成績を収めると、欧米をはじめ世界の大学への入学に有利になります。
またSISM独自の「グローバル・シティズン・プログラム」に沿って、
自他共の幸福に寄与する意欲や能力を、7年生から13年生まで段階的に育成します。具体的には、
7年生では「友情」をテーマに、キャンプなどの課外活動で絆を結ぶ大切さを学び、
8年生では「環境」への理解を進めるために、野外活動を行い、人間と自然の関連性を学びます。
9、10年生は、「自分とコミュニティー」をテーマに、ボランティア活動を通して地域との関わりを学習。
11年生では、海外渡航の機会をもつ予定で、世界市民としての視野を培っていきます。
12年生では、「自分と社会問題」への考えを深め、プレゼンテーションに挑戦。
最高学年の13年生では、大学教授らを招待してフォーラムを主催し、
対等な立場に立って議論することを目指します。
このように、まずは身近な友情を育むことから始まり、徐々に視野を広げつつ、最後は、社会にいかに貢献していけるのかを考え、行動に移せるようにプログラムを進めていく予定です。
さらに「ソーシャル・エモーショナル・ラーニング」も取り入れています。これは、社会性と情動(感情)の学習とも呼ばれており、毎朝のホームルームで、生徒一人一人が今日一日をどのような気持ちで臨むのかを考え、感情を自分自身でコントロールしながら目標を立てます。
最近の研究では、新型コロナウイルスの世界的大流行の後、子どもたちが高いレベルの緊張感にある実態が明らかになってきました。
子どもたち、さらには教員自身が心を平穏に保つことが、非常に重要になっています。
「パーパス・ベースド・ラーニング」にも力を入れます。
これは、生徒自らが問いや目標を設定し、探究する中で学ぶ意味も考えていく、教科横断型の学びになっています。
――多角的で最先端の教育法を取り入れながら、生徒を育んでいくのですね。余校長ご自身、これまで青年の育成について研究されてきたと伺いました。
はい。マレーシアの国立プトラ大学の大学院で学び、青少年の社会性と情動の学習等を研究する「ユース・デベロップメント・スタディーズ」の分野で博士号を取得しました。
その後は、同大学と国立マラヤ大学で教壇に立ってきました。
SISMでは、最新の教育学の成果を取り入れていくことはもちろんですが、その根底には、創立者が示された創価の人間主義教育があることを強調したいと思います。
私たちの目的は、どこまでも生徒一人一人の幸福です。
だから、その時々に合わせて最良の教育法を導入していきたいと考えています。
時代が変われば、本校の教育プログラムも変化していくことでしょう。
しかし、創価教育の思想を根本に、生徒の幸せのために力を尽くす教職員の姿勢が変わることはありません。
――最後に改めて、SISMに携わる決意をお聞かせください。
SISMの校長の話をいただいた時、創価教育の父・牧口常三郎先生、戸田城聖先生、そして池田先生へと継承された精神を継ぐ挑戦ができることに、感謝と決意で胸がいっぱいになりました。
子どもたちには無限の可能性があります。一人一人が、より良い人生を歩めるよう全力でサポートしていくとともに、社会貢献の精神と一生涯の友情を築いていけるように尽力していきます。
ここには、誰もが平等に世界市民になれる教育環境が整っています。
「地球文明の平和の未来へ、智慧と勇気と慈悲の『世界市民』を育む」学園として、創立者が大きな期待を寄せるSISMの歩みは始まったばかりです。ここから旅立つ鳳雛たちが、21世紀、そして22世紀に、世界中で活躍する人材になっていくことを強く確信しています。
◆郭福安 学園長「多くの支援者に感謝」
8月に第1回入学式を迎えるまでの道は、困難の連続でした。2021年2月にSISMの建設開始が発表されましたが、それと前後してウクライナ危機やコロナ禍による資材の高騰、労働者不足などに見舞われたのです。
それらを乗り越えて「8・24」に晴れの式典を迎えることができました。工事関係者をはじめ、建設に携わった人々の尽力に感謝でいっぱいです。
そして何より、教育を「人生の総仕上げの事業」と定められた創立者・池田先生の心を、わが心として、支えてくださった多くの寄付者、支援者の皆さまに厚く御礼申し上げます。
生徒の幸福を第一に考えたカリキュラム、学習施設等をそろえることができました。
また今後も、一人一人が伸び伸びと学べるような環境づくりに全力で取り組んでいきます。
創立者の構想を実現する新たな創価の学びやとして、教職員一同が団結して、SISMを発展させていく決意です。
◆カーティ・パンカジ 教諭「学び続ける姿勢を培う」
私はカナダで約20年間、国際バカロレア(IB)機構の認定校で働いてきました。SISMでも採用するバカロレアは、“多様な文化を尊重する精神をもち、より良い、より平和な世界を築くことに貢献する若者を育成すること”を目的としています。
これは、世界に寄与する価値創造の人材を育むSISMの教育と共鳴するものだと思います。
「生徒主体」の理念も共通しています。SISMでは、教員との対話を通して生徒自らが課題を見つけ、解決していく教育法や、大きな困難に対して、仲間たちと協力して乗り越えていく環境等を提供し、人生を向上させるための「学ぶ力」を培っていきます。
どんな環境でも学び続けていく姿勢を身に付けることは、卒業後も生徒の未来を切り開いていくと信じています。
池田先生の掲げる「生徒の幸福を第一とする教育」の現場で、自分自身の経験を生かせる喜びを胸に、持てる力を全て発揮していきます。
◆リヤナ・アヒラ 図書館司書「創立者の思想を生徒に」
国立マラ工科大学を卒業後、図書館司書として、政府関係の施設や、マレーシアで最も長い歴史のある英国式教育のインターナショナルスクールで勤務してきました。
私は創価学会のメンバーではありませんが、偶然にも自宅近くにSISMができるに当たり、人間主義の思想に基づく創価の教育理念を初めて聞いて共感し、図書館司書に応募しました。また、創立者が池田大作先生であることを知り、驚くとともに、ある記憶がよみがえりました。
中学生の頃、クアラルンプールでの「自然との対話――池田大作写真展」を見学したことがあったのです。当時、両親が離婚し、気持ちが沈んでいましたが、美しい写真を見ると不思議と心が落ち着きました。写真のポストカードをたくさん買い求めたことを覚えています。
“学校の心臓部”ともいえる図書館で、多くの生徒が創立者の平和思想を学びつつ、万般の知識を吸収していけるように環境を整備していきます。
2023年9月14日
地球環境は人間を映し出す鏡
世界最高峰の賞に輝いた自然写真家に聞く
自然写真家
高砂淳二さん
海の生き物をはじめ地球の神秘を撮影してきた自然写真家の高砂淳二さん。昨年、自然写真の世界最高峰といわれる「ワイルドライフ・フォトグラファー・オブ・ザ・イヤー」の“自然芸術性”部門で、日本人初の最優秀賞を受賞しました。約40年にわたり、世界中の海を見つめてきた高砂さんに、SDGsの目標14「海の豊かさを守ろう」を巡ってインタビューしました。(取材=樹下智、澤田清美)
――高砂さんはダイビング専門誌の専属カメラマンを経て、1989年に独立されました。自然写真家になろうと思ったきっかけは何だったのでしょうか。
大学時代に1年間休学して、オーストラリアを旅した時、ダイビングのライセンスを取りました。海の中で“ぷかー”っと浮く浮遊感がたまらなく好きになり、水上から差し込む光がきれいで、「うわぁ、これはとんでもないものを見てしまった」と思ったんですよ。
ダイビング仲間に水中で写真を撮っている人がいて、「自分の写真が売れた」って言うんですよね。「なに!? そんな仕事があるのか」と思いまして。それから、プロの水中写真家を目指すようになりました。
――水中の撮影から、自然全体へと被写体を移していったのはなぜですか。
専属カメラマンの時代から、とにかく気になったものは撮らなきゃと思って、カメラを向けていました。普通、雑誌のカメラマンだったら、全体の構成を考えながら撮影するのですが、クマノミ(海水魚)が気になって、そればっかり撮って、編集長に怒られた時もありました(笑)。
でも、徐々にいい作品も撮れるようになって、だんだん自然全体に意識が向くようになりました。独立した後、動物や植物も撮り続ける中で、「どうして、こんなにいろんな生き物がいて、しかもその中で、なぜ人間という不思議な生き物がいるんだろう」っていう疑問で、僕の頭の中はパンパンになっていきました。
――そこで、ハワイに行って、人間と自然について探求されたんですね。
はい。先住民族の方のもとに毎日通って、いろいろなことを教わりました。「世の中が成り立つように、全ての生き物にそれぞれの役目があるんだよ」って。人間には二つの役割があって、一つは、全体のバランスが崩れないように自然を看ること。もう一つは、一生かけてアロハ(愛)を学ぶことだ――そう言われたんです。
――環境を破壊する人類は、真逆のことをしているように思いますが……。
ええ。それを考えると、人間はいない方がいいんじゃないかって感じる人も多いと思います。でも、相手の立場に立って考えて、相手を思いやれる力というのは、人間が圧倒的に強いと思うんです。「人間にも役割があるんだ」って、先住民の方の話を聞いて、ふに落ちました。だからこそ、環境問題を解決して、バランスを戻していく必要があると、強く感じます。
――約40年間、自然と向き合い続けてきて、特に感じる変化は何でしょうか。
やっぱり、暑さですよね。例えば、カナダのセントローレンス湾で北方から移動してくる流氷の上で生まれるアザラシを撮影してきたんですけど、年々暖かくなってきて、氷が薄くて撮影の際にヘリコプターで降りられない年が増えました。
4年前は、まだ氷が厚い方で、無事にアザラシの赤ちゃんの撮影ができたのですが、その約2週間後に、氷が全部解けてしまったことが分かりました。アザラシの赤ちゃんが独り立ちするには、氷上で4週間は生活する必要があるので、僕が撮影した子たちは、おそらく全員死んじゃったんだと思います……。
――とても悲しい話ですね。
その翌年は、氷が全くなくて、アザラシのお母さんはやむなく陸地に上がって出産したらしいです。それは、赤ちゃんが敵に狙われやすい危険な環境です。
人間は暑くても冷房を使えば、変わりなく暮らしていけますけど、こうした動物たちは、少し気温が上がるだけで生きていけなくなる。地球温暖化による海水温の上昇や海洋酸性化で、海で暮らす動物や海洋生物の生態系は危機にさらされています。サンゴの白化現象もたくさん見てきましたが、サンゴ礁は40年で半分以下になったといわれています。
――海洋プラスチックごみの問題も深刻です。
ええ。僕も1990年代から、その影響を見てきました。太平洋のど真ん中に浮かぶミッドウェー島に、アホウドリを撮影しに行った時のことです。ハワイから2000キロも離れていて、ほとんど誰も住んでいないような島で、プラスチックごみを食べて死んだアホウドリがたくさんいたんです。
海流の影響で流れ着いたプラスチックごみを、アホウドリのお母さんが餌だと勘違いして、子どもたちにあげるんですね。それがおなかにたまって、他のものを食べられなくなって、栄養失調になって死んでしまう。死骸を見ると、胃の形になってプラスチックごみが固まっているんです。そういった死骸が、ごろごろ転がっていました。
――90年代で、既にそうした状況だったんですね。
今はもっと多くのプラスチックごみが、海にあふれていると思います。9割以上の海鳥の胃に、プラスチックごみが入っているとまでいわれています。また、ウミガメの半数が、ビニール袋などを飲み込んでいるともいわれていますね。
――プラスチックごみが海で細かく分解されたマイクロプラスチックも問題視されています。
海に浮かんで目を凝らすと、水面に細かいプラスチックが見えることがあります。先日も、日本の海の調査船に乗せてもらったんですけど、5分くらい網を海中で引っ張ると、いっぱいプラスチックごみが入っていて。海水を実験室に持って帰って、目に見えるごみを全部取り除いても、顕微鏡で見るとまだまだいっぱいあるんですよね。2050年には、魚よりプラスチックごみの量の方が多くなるって予測されていますが、本当にそうなるような気がします。
――高砂さんは自身の撮影活動の経験から、“自然や生き物に心を開いて敬意をもって接していけば、自然や生き物も心を開いてくれる”と言われています。
ハワイの先住民の方から、環境は自分を映す鏡だから、自分と環境の関係を正しくするには、アロハの心、敬意や感謝の心をもって接していかないといけないと教わりました。海に一緒に入った時に、「どうだった?」と聞かれて、「いやー、気持ちよかったですよ」って答えたら、「それなら海も喜んでるな」って言われたんです。
――仏法では「依正不二」といって、人間(=正報)と、その人間を取り巻く環境(=依報)は分かちがたく関連していると説いています。
日本でも西洋文化が入ってくる前は、人間と自然は一体だという感覚が、もっと当たり前だったっていいますよね。そういった心持ちで被写体に向き合うと、やっぱり向こうの反応が違うんです。
森に入る時も、“撮ってやるぞ!”ってズカズカ入るんじゃなくて、“お邪魔します”って静かに入っていく。生き物の様子をよく見て、気にしてるなと思ったら少し下がって、安心してるなと思ったら少し近づく。遊びたそうにしていたら、面白いことをしてあげる。子守歌を歌いながら撮影する時もあります。そうすると、向こうも自然と緩むんですよね。
――そうした撮影を続けてこられ、昨年、自然写真の世界最高峰の賞に輝かれました。93カ国から16部門に3万8000以上の応募があった中での快挙です。
ありがとうございます。受賞作品となった「Heavenly flamingos」は、南米ボリビアにあるウユニ塩湖に降り立ったフラミンゴを撮影したものです。
この時も、究極の自然のハーモニー(調和)を織りなすフラミンゴたちにカメラを向けるため、2時間近くかけて、しゃがみながらゆっくり近づいていきました。標高3700メートルにある湖なので、酸素が薄くて、もう頭が痛くて(笑)。
でも、捕食の瞬間とか、あっと驚くような生態を捉えた写真が評価されやすい欧米のコンテストで、自然に溶け込むように努力して、自然のハーモニーを撮影しようと頑張った作品が最優秀賞を受賞できたのは、率直にうれしいです。
――高砂さんは環境NPOの副代表理事も務めています。最後に、環境問題に向き合う上で大事にしていることを教えてください。
二酸化炭素の排出量をどう削減しようとか、プラスチックごみをどう減らそうとか、いろんな施策や方法を考えるのも重要です。でもその前に、感謝や愛情をもって地球に接していくという“気持ち”を大切にする必要があると思います。
この数十年間、人間は地球に甘えてばっかりで、取りたいものは取り放題で、使い終わったら海に全部流せば大丈夫って思ってきた。今、その付けが回ってきている。人間と地球は一体ですから、そういう感謝も愛情もない態度で接していけば、自分たちの首を絞めることになります。
感謝や愛情があれば、例えば、大地にダメージを与えないよう、無造作に除草剤をまくことをやめるとか、具体的な行動につながっていくと思います。
人間も壮大な自然のハーモニーの一部として、人間にしかない役割があるはずです。愛、感謝、敬意といった心を、僕たちの周囲や自然環境に広げていきたいですね。
2023年8月12日
〈危機の時代を生きる 希望の哲学 創価学会ドクター部編〉
第16回
「健康」を勝ち取るために
健病不二が仏法の視座
前向きに病と闘う心を
しゅくみね内科・院長
祝嶺千明さん
長寿社会の現代。医療は多くの人々を支える重要な役割を果たしている。その最前線で働く友は、これからの時代を健康で生き生きと暮らすために必要なことを、仏法の健康の智慧から、どう見ているのか。「危機の時代を生きる 希望の哲学――創価学会ドクター部編」の第16回のテーマは「『健康』を勝ち取るために」。沖縄県の「しゅくみね内科」で院長を務める祝嶺千明さんの寄稿を紹介する。
生活習慣の影響
有数の長寿県として名をはせた沖縄も、現在は「沖縄クライシス」という言葉が聞かれて久しい状況にあります。
厚生労働省は5年に1度、都道府県ごとの平均寿命を発表しており、沖縄は1985年まで男女とも全国1位でしたが、徐々に順位を落とし、2020年時点では、女性が16位、男性が43位になったことが明らかになりました。
沖縄の方言では、食べ物のことを「くすいむん」と言います。これは“薬になるもの”という意味で、“食事は病を治す薬になる”との考えのもとで、多くの人々が野菜を中心に魚介類や、適度に豚肉などをバランスよく食してきました。こうした食事も、戦後、長らくアメリカの統治下に置かれたことなどが影響し、脂質や糖質の多い食事に変わりました。
また、車社会で運動の機会が少なく、アルコールを多く摂取する社会風土であることも、平均寿命が低下した原因と分析されています。
私は、特に健康問題が多いといわれる沖縄の中部圏で内科クリニックを構えていますが、患者さんと接する中、こうした生活習慣が健康に悪影響を及ぼしていると強く感じます。加えて健康診断の受診率が低く、病気の発見が遅れ、治療につながらないことにも問題があると考えています。
複雑で曖昧な境目
以前、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病といった生活習慣病は、加齢とともに発症・進行するものとされ、成人病と呼ばれていました。しかし、実際には運動不足や飲酒、喫煙、不規則な生活など、長い間の生活習慣が原因となって発症することが分かり、生活習慣病と改められました。
将来、こうした病気で苦しまないためにも、バランスの良い食事や十分な睡眠、適度な運動といった習慣を取り入れるのが大切であることは、言うまでもありません。
しかし、いくら健康的な生活を心がけても病気になることはあります。それは生活習慣のほか、ストレスや加齢、遺伝的なものなど、病気は複数の原因が複雑に絡み合って発症するものだからです。逆に、私たちの健康は、そうした複雑な状況に対し、体内の器官が複雑に連携しながら、全体として調和を保つ中で支えられているのです。
このような複雑性の結果として、ある時は病気となり、健康となることから、その境目は曖昧で、病気とはどのような状態を指すのかは簡単なようで、実は非常に難しい問題なのです。
例えば、病気でも生き生きと暮らしている人がいる一方、身体は健康でも病気になったような浮かない顔をしている人もいます。これは見た目の話ですが、見た目では分からない場合もあります。
がんに関して言えば、「体内にがん細胞ができた時、がんという病気になる」と思うかもしれませんが、実際、私たちの体内では、毎日、数千個の単位でがん細胞が発生していると考えられています。しかし問題にならないのは、がん細胞が増殖する前に、体内の免疫細胞によって排除されるからです。
がん細胞が増殖しても、命に危険を及ぼさない場合もあります。例えば、前立腺がんの中には、進行が極めて緩やかなものがあり、寿命で亡くなった方の身体を解剖した結果、80歳以上の6割の方に前立腺がんが見つかったとの研究もあります。その状況が生前に分かっていれば、がんと診断されていたでしょう。
もちろん、これは一部の事例であり、がんはあくまで早期発見・早期治療が大切ですが、がんになっても健康な人はいるということです。
同じようなことは、認知症でも言えます。物忘れが出てもおかしくない脳の萎縮が見られても症状が見られず、記憶が鮮明な方がいます。
また、病気になることが、後の健康につながることもあります。
例えば、体内の免疫細胞には、感染した際に病原体の特徴を記憶し、その病原体が再び体内に侵入した時、病原体を効率的に排除して身体を守ってくれる働きがあります。
といっても、命の危険にさらされる可能性もあり、病気にはなりたくないでしょう。そこで開発されたのがワクチンです。ワクチンには、病原体の一部だけを体内に送り、あたかも病原体そのものの感染があったような反応を起こして、免疫細胞に記憶させる仕組みがあります。
このように見ると、病気と健康の捉え方も変わるのではないでしょうか。
道理を重んじる
これまで病気と健康が密接な関係にあることを見てきましたが、それは仏法の視座では“健病不二”と捉えます。
病気と健康は、見かけは異なりますが、本質的には分かちがたく一体であり、ある時は健康な状態として表れ、ある時は病気の状態となって表れるということです。
そして病気と健康は関連し合っているからこそ、仏法では、病気になったとしても希望を失わず、病気と闘い、その中で心身の健康を確立していく大切さを教えています。
御書を拝すると、日蓮大聖人は、そうした強い心で病と向き合うよう、門下を激励されています。
長患いで気も沈みがちだった富木尼には「どうして病が癒えず、寿命が延びないことがあろうかと強い思いをもって、御身を大切にし、心の中であれこれ嘆かないことです」(新1317・全975、通解)と仰せです。
夫が病床に伏していた妙心尼には、お手紙で次のようにつづられました。「このやまいは仏の御はからいか。そのゆえは、浄名経・涅槃経には、病ある人仏になるべきよしとかれて候。病によりて道心はおこり候なり」(新1963・全1480)
病気になって落ち込むのではなく、むしろ仏の境涯を開くチャンスと捉え、信心で乗り越えてみせると覚悟を決めることを教えられています。
私は、こうした捉え方は病気に立ち向かう上で、とても重要であると思います。というのは、心の持ち方が健康を勝ち取る力となるからです。
例えば、病気であっても「自分は健康である」と思える人の方が、病気の経過が良く、身体の衰えも緩やかという興味深い報告があります。
また、大きなストレスがかかると、副腎という臓器からホルモンが分泌され、血圧や血糖などが調節されることが分かっていますが、そのストレスが長期間にわたると、人体の各所で機能障害を起こしてしまうことが知られています。
一方、笑うことは、NK(ナチュラルキラー)細胞を活性化させ、免疫機能を高めることが知られています。
その上で仏法は、気合と根性があれば病は治ると言っているわけではなく、あくまで道理を重んじ、病になった時の注意点も教えています。
例えば、「摩訶僧祇律」には、病人としての心構えが記されています。
①それぞれの病気に適した食事や薬を服用する。
②治療する人・看病する人の言葉にしたがう。
③自分の病気が重いか、軽いかを認識する。
④苦痛を耐え忍ぶ。
⑤努力を怠らず、聡明な智慧をもつ。
こうした点は、複雑な要因で発症する病気に対し、生活習慣や周囲の協力など、あらゆるものの“総合力”で立ち向かっていくという発想であり、現代医学に照らしても説得力があります。
学会員の温かさ
私はこれまで、医師として、またドクター部員として、多くの方の病の悩みと向き合ってきました。その中で実感するのは、学会員には病を前向きに捉える人が多いということです。それは、まさに、先に挙げた仏法の哲学を心肝に染めているからでしょう。
実は、私自身も国指定の難病を患っており、そうした同志と似た体験をしました。
7年前のことですが、突然の倦怠感と吐き気に襲われ、入院して検査を受けると「急速進行性糸球体腎炎」との診断を受けました。数ある腎臓病の中でも、たちの悪いタイプの一つです。病名を聞いた瞬間、“このままいくと透析治療かもしれない”と頭をよぎりましたが不思議と動揺も不安もなく、「絶対に意味がある」と受け止めることができました。そう思えたのは、多くの同志が病に勇敢に立ち向かう姿を目の当たりにしてきたことはもちろん、これまで幾度も学会員の温かさに触れてきたからです。
妻が病になり、不安を抱えていた時には、ある女性部の先輩から「心配しなくていいよ。大丈夫だよ。私が題目を送っているからね」と声をかけてもらったことが忘れられません。こうした同志の温かさに包まれる中、妻は病を乗り越えることができました。
学会には、周囲の人の病を自分のことのように捉え、皆で祈り合う中で乗り越えていこうとする心があります。こうした団結も“総合力”の一つであり、そうした心に普段から触れているからこそ、病になった時に孤独にならず、前向きに捉えることができるのだと思います。
私自身はステロイドと免疫抑制剤の大量投与を受け、副作用で苦しむ日々が続きましたが、体調は次第に良くなり、ここ3年間は症状もなく、発症時に4分の1まで落ち込んだ腎機能も、約2分の1まで回復しました。
今では、日頃の診療の中、病に悩まれている方に、自らの闘病体験を伝えることがあり、その話で表情が和らぐ患者さんを見るたびに、私が病気になった意味があったとの思いを強くしています。
「仏は少病少悩」
現代は長寿社会であり、長生きをすれば、病気になるリスクも当然、高まります。そうした時代を反映してか、今では「無病息災」ではなく「一病息災」「二病息災」といわれ、何らかの病気があるのは当たり前との考え方が主流になりつつあります。
仏法でも「仏は少病少悩」と説かれています。たとえ自分自身に病気があっても、失望せずに雄々しく立ち向かっていく。そうした姿を周囲に見せることは、これからを生きる人々にとっての希望となると感じます。また、そうした強い心で立ち向かうからこそ、健康も勝ち取っていけるのだと思います。
健康の智慧に満ちあふれた仏法を学び、実践する一人として、これからも満々たる生命力で地域の方に寄り添い、一人でも多くの方が健康で生き生きと暮らしていけるよう心を尽くしてまいります。
しゅくみね・ちあき 1961年生まれ。群馬大学医学部を卒業。出身地の沖縄で研修を受けた後、南大東診療所の所長として離島医療に従事。中頭病院消化器内科を経て、2003年に「しゅくみね内科」を開院。創価学会沖縄ドクター部長。副総県長。
2023年8月5日
小説『新・人間革命』起稿から30周年
記念インタビュー
インド・ガンジー研究評議会議長
N・ラダクリシュナン博士
21世紀は、
池田先生の価値創造のリーダーシップと
その思想を受け継ぐ弟子たちによって、
混迷の危機の時を
人道の時代へと転換した世紀とする!
平和こそ人類の根本の第一歩
あす8月6日、池田大作先生が小説『新・人間革命』の執筆を開始してから30周年を迎える。起稿の日(1993年8月6日)、先生はガンジー研究の第一人者であるニーラカンタ・ラダクリシュナン博士と長野研修道場で会見している。インド南部・ケララ州のガンジー記念館で、平和活動家・教育者としてガンジー研究を主導する博士を訪ね、会見当時の印象や現代における創価学会の役割などをインタビューした。(聞き手=小野顕一)
――30年前、池田先生が小説『新・人間革命』を執筆開始された、まさにその日、ラダクリシュナン博士は先生と会見されています。
あの時のことは、鮮明に覚えています。
私は、広島に原子爆弾が投下された8月6日を、「人類の歴史における一番の暗黒の日」と認識していました。池田先生との会見では、そのことについて、何か大切なお話をいただけるのではないかと期待していたのです。
まず思い出されるのは、お会いした瞬間から、先生が私を事細かに気遣い、緊張を解きほぐそうとされたことです。
日本へのフライトは快適でしたか?
昨日はよく眠れましたか?
朝食はおいしく食べられましたか?
車窓からの景色はどうでしたか?
ご家族と連絡はとられましたか?
――質問に答えるうち、池田先生のことが、まるで実の父のように感じられ、とても安心した気持ちになりました。
そうしたやり取りを重ねながら、ガンジーの戦争観や平和の信念などについて、意見を交換していったのです。
ふと、先生は一枚の原稿用紙を手に取り、私に尋ねました。
「博士、私が何を書いたか、お分かりになりますか」
通訳の方が、内容を翻訳して教えてくれました。
そこには「平和ほど、尊きものはない。平和ほど、幸福なものはない。平和こそ、人類の進むべき、根本の第一歩であらねばならない」と――。
そうです。それは、小説『新・人間革命』の冒頭の一節だったのです。
先生は、
この小説が、全何巻・何章で、
どういった構成になるのか、
具体的な考えを話してくださいました。
驚いたのは、
創価学会の歴史や登場人物の詳細を、
あたかもコンピューターがデータを読み出すように、
明瞭によどみなく記憶されていたことです。
私が「人類の暗黒の日」と考えていた、
この8月6日に、いわば、
民衆一人一人の人生の軌跡をもって、
創価学会の真実の歴史をとどめようとされていることに
深い感動を覚えました。
非暴力の覚醒
――この日、
博士は、ガンジーの“「魂の力」は原子爆弾よりも強い”との信念に触れ、語られています。
「誰もが持つ『魂の力』を引き出し、
平和を生み出していく
――これこそ池田先生が世界に広げている運動です」と。
創価学会三代の会長は、信仰を人生変革への希望の力とし、民衆を勇気づけてきました。一人一人が「生きる喜び」を得て、人生はより良く変えられるという実感を持ちながら、正義と平等の価値を周囲に広げていく――。そこに、持続可能な平和への道筋が、人間絵巻のモザイクアートのように現れているのです。
ガンジーが亡くなって、
今年で75年がたちました。
インドも世界も劇的な変化を続けています。
ですが、人間の基本的な性質は変わっていません。
もし、ガンジーが2023年という今日に生きていたとしたら、
全ての戦争や不平等に反対し、
人間の尊厳を掲げて、
あらゆる腐敗に挑んだに違いありません。
もちろん、
権威主義的なアプローチではなく、
どんな他者からも学び、
人と人との間に調和をもたらしながら、です。
「創価の師弟」は全人類の希望
自他共の変革で人道の時代を
ガンジーの非暴力・不服従の信念は、
南アフリカやインドで、
人々と苦しみを共にする中で不動のものとなりました。
直接会って苦労を知り、
自らの実感を元に、
癒やしの手を差し伸べたのです。
長きにわたる人権闘争で挫折しかけた時にも、
後悔と戦い、
分析を怠らず、
発想や手法を変え、
行動を起こし続けました。
それが地球的規模での非暴力の覚醒へとつながっていったのです。
平等、公平、尊厳、平和といった理念は、
自らが変わる中でしか伝わらないことを、
ガンジーは知悉していました。
民衆一人一人の成長が積み重なることで、
初めて変革の波紋は広がり、
社会のあるべき変化が成し遂げられていく。
そうした点においても、
「私の人生そのものが、私のメッセージだ」
「あなたが望ましいと思い描く変革の主体者たれ」
とのガンジーの信念は、
まさしく創価学会員の歩みと深く響き合っているのです。
人間の宗教
――かつて博士は「創価学会は、まさに『混迷の時代』の全人類の希望なのです」と語られました。
そう強く感じたのは20年以上も前のことです。
しかし、その直感は正しかったのだと断言できます。
創価学会は今、
世界平和のイニシアチブ(主導権)を遺憾なく発揮しています。
想像してみてください。
192もの国や地域で、
老若男女、
あらゆる立場の人が、
価値創造の担い手となり、
人々の憎しみや悲しみを生きる力へと転換し、
地域や社会の責任ある一員として、
地球の平和を願い、
希望のビジョンを示している。
「価値創造者」は、
世界の平和を祈る一方で、
草の根からの挑戦を続けるものです。
その柱こそ、「創価」の哲学であり、
「人間革命」の思想です。
軍部政府の弾圧によって壊滅状態になった創価学会は、
牧口先生と戸田先生の師弟の誓いによって、
戦後の灰の中からよみがえり、
再び「広宣流布」の旅を開始しました。
そして、人が人を殺してきた「戦争の世紀」において、
創価学会は一貫して平和の人を育ててきたのです。
言うなれば、
創価学会は、
“一人の人間がどれほど偉大な力を持っているのか”を学ぶ、
校舎なき学舎であり、
その規模は世界全体にわたっています。
教育者であった牧口先生の主眼は、
子どもたちの未来を信じ、
将来の可能性を広げ、
生きる自信をつけさせることでした。
教育は、
記憶力のテストなどであってはならない。
将来、子どもたちが何になりたいのか、
そのために身に付けるべき力とは何かを共に考え、
真実の人生を得るためのものでした。
学習と生活の一体化を目指した
「半日学校制度」の提唱なども、
そうした価値観の表れでしょう。
本来、学習と生活は、
一生涯、並行して行われるものです。
価値を創造する「創価」の思想を、
戸田先生は「人間革命」という理念で示しました。
そして人間革命の実践と連帯は、
池田先生の哲学と行動によって、
「人間の宗教」として世界へと広がっていったのです。
人生には多くの苦難があります。
しかし、
困難に立ち向かう覚悟を持ち、
人間革命に挑戦する中で、
「今までの経験は、このためにあった」
「私は、この道を生きていく」という
「人生の真実」を得ることができるのです。
この人間革命の理念は、
生活する国や、
生まれた境遇、
あるいは、
扱う言語、
経済状況など、
一切の違いに関係なく、
私たち自身の人間性を求め、深め、広げゆく、
“普遍的な呼びかけ”なのです。
不惜身命の精神
――インドでも多くの学会員が生まれています。
池田先生と言葉を交わしたり、
会合などで空間を共にしたりして、
先生を師と定める人が多くいます。
その一方で、
先生に直接、接する機会はなくても、
先生を自身の師匠と決めて、
自らの人生を開いていく人が、
世界には数えきれないほどいます。
インドの若い世代の人たちもそうです。
一度も会ったことのない人の存在を、
常にそばで見守ってくれているように感じ、
心を奮い立たせ、
現実の課題に立ち向かう力としていく――。
この師弟の力の淵源は何なのかと、
私は時に自問自答するのです。
世界中の人々に対して、
池田先生の存在が、
これほどまでに希望と感動をもたらすのは、
先生が人間革命について語るだけでなく、
古今東西の誰よりも、
先生自らが人間革命を実践されてきたからとも
言えるのではないでしょうか。
今、私が持ち歩く一冊に、
池田先生の『若き日の日記』(英語版)があります。
そこには、
若き先生が直面した困難が、
赤裸々につづられています。
苦しみながらも戦い、
決して諦めない。
絶対に勝利し、
師に応えてみせるという一念が描かれている。
私は、これこそ「人間の真実」なのだと思います。
師を行動の根本に据えることが、
人生を、いかに強く、豊かに、
大きく転じていくことになるか。
インドの創価学会員もまた、
小説『新・人間革命』を学び、
実践する中で、
その師弟不二の精神に迫っているのでしょう。
創価の三代に貫かれた、
不惜身命の精神は、
時代や世界を超越して、
尽きることのない人類の希望となっているのです。
人類を結ぶ象徴
――今、学会が果たすべき役割とは何でしょうか。
私が、よく受ける質問があります。
“なぜガンジーは、武器を持つことなく、
インドの独立を果たすことができたのか”との問いです。
私は、
ガンジーが“人間の共通項”を見いだし、
ヒューマニズムの連帯を呼びかけたこととともに、
ガンジーが世界中に友人を持っていたことが
重要だと考えています。
ガンジーを応援する友人は、
国外にも多くいました。
また、ガンジーの優れた伝記は、
いずれもアメリカやイギリス、ドイツといった、
欧米の著者によって書かれています。
池田先生も海外の友人が多く、
世界での評価が、
むしろ本質を突いていることも多分にあると感じます。
私のように、信仰や立場は異なろうとも、
先生を師匠と仰ぎ、
評価する人は世界に大勢います。
先生の思想は、
今や世界中で研究される、
定評のある学問領域です。
先生の存在は、
一人の可能性を無限に信じ、
最大に鼓舞する師匠であると同時に、
「人類を結ぶ象徴」なのです。
創価学会が民衆を本当に幸福にするために、
現実の社会や政治にも関わり続けることで、
「平和の擁護者」という宗教本来の使命が果たされ、
宗教の価値が活気づいています。
大きなものは、
目の前にあると全容が見えない。
大きな山は、
遠くからしか視界に入れることはできないのです。
池田先生という存在は、
そういう目で見なければいけません。
改めて強調しますが、
先生ほど、
青年や女性を信頼し、
力を与え、
「未来の指導者」と信じて激励し続けた人を、
私はガンジー以外に知りません。
だからこそ、
私は、先生のことを「生きているガンジー」と呼ぶのです。
私は創価学会員ではありませんが、
マハトマ(偉大なる魂)の研究を重ねてきたからこそ、
ガンジーと池田先生、
両方の大山を視界に入れることができるのです。
ガンジーの思想は、
絶えず価値を創造しながら、
後世の人々の心に生き続けていく。
池田先生の思想もまた、
悲哀や絶望にも人生を諦めない人、
分断や不平等と勇敢に戦う人、
他者に対する責任ある生き方を貫く人
――そうした無名の民衆の行動の中に、
厳然と生き続けていくのです。
先生の本を読んでください。
先生の偉大さを、
今以上に知ってください。
それが人類に変革をもたらします。
1年や2年の戦いではないのです。
先生という存在を知って以来、
私にとって、先生を学ぶことそのものが、
人生の大きな喜びとなっています。
それは、
「人生とは何か」に迫りつつ、
「人生とは、かけがえのない贈り物」であることを発見する、
師弟の旅路です。
私たちは、
この21世紀が、
戦争や暴力がなく、
人類が一つになり、
地球が平和と希望にあふれる世紀になると思ってきました。
しかし、
その最初の四半世紀は、
世界が未知の不安に襲われた時代であったと
歴史書には書かれざるを得ない。
ですが、
私たちは全てを「変毒為薬」していけるに違いありません。
そして、
将来の歴史書には、こう描かれるはずです。
21世紀は、
池田先生の価値創造のリーダーシップと
その思想を受け継ぐ弟子たちによって、
混迷の危機の時を
人道の時代へと転換した世紀であった、と。
誰一人も置き去りにしない、
人間主義の時代の到来には、
一人一人の変革が不可欠です。
それが人間革命の希望のメッセージです。
自他共の変革に挑み続けましょう。
池田先生の弟子であるために。
持続可能な平和のために。
そして、人類の未来のために。
 日めくり人間革命
日めくり人間革命